どんな質問にもとても親切に、丁寧に対応して下さいました。
本当に助かりました。ありがとう御座います。
もらい事故とは?泣き寝入りせず得する方法を事故後の対応・保険・賠償金から解説

もらい事故に巻き込まれ、泣き寝入りせずに、適切な損害賠償金を受け取りたい方へ。
もらい事故とは、過失割合が0対10、つまり被害者に一切の過失がない交通事故のことです。
もらい事故では過失による減額がないため、被害者は慰謝料や治療費などの損害賠償金を満額受け取れます。
しかし、もらい事故は、過失による減額がない分、加害者側がシビアな態度で示談交渉に臨んでくること、被害者は保険会社に示談交渉を代行してもらえないこと等から、被害者が泣き寝入りしてしまうこともあるのです。
そこでこの記事では、もらい事故で損せず得する方法を、事故後の対応や保険、賠償金の観点から解説していきます。新車でもらい事故にあった場合の補償についても触れているので、ぜひご覧ください。
目次
もらい事故とは?定義と例えを解説
まずは、もらい事故とはどういう事故なのか、具体的にどのようなケースが該当するのか解説します。
もらい事故とは?
もらい事故とは、被害者に一切の過失がない交通事故のことです。
交通事故では多くの場合、被害者側にも何らかの過失があるとされます。例えば信号無視や速度違反などのわかりやすい過失のほか、「被害者側にも相手車両との衝突を避ける余地があったはず」といった理由で過失がつくこともあります。
こうした過失が加害者側・被害者側それぞれにどの程度あるのかを示したものが「過失割合」です。被害者でも過失割合がつけば、その割合の分だけ受け取れる賠償金が減額されます。(過失相殺)
しかし中には、被害者側には一切の落ち度も事故を回避する余地もなかったというケースがあります。
こうした場合、被害者側の過失割合は0とされ、一方的に巻き込まれたという意味で「もらい事故」と呼ばれるのです。
もらい事故とは例えば?
もらい事故の例えとして代表的なのが、赤信号で停車中に追突されたケースや、青信号で適切に横断歩道を渡っていた歩行者に信号無視の自動車が突っ込んだケースです。
適切に走行していたのに対向車がセンターラインを越えて突っ込んできた事故も、もらい事故の1つです。

もらい事故の例え
- 交差点で信号待ち中、正面から車が突っ込んできた
- 路肩に適切に停車中、自転車にぶつけられた
- 青信号で横断歩道を渡っていた歩行者に、赤信号を無視したバイクが衝突した
ただし、一見もらい事故に見えるケースでも、被害者側に過失が付くことがあります。
例えば直進車と対向右折車が衝突した事故は、対向車との衝突という点で、もらい事故である「対向車がセンターラインを越えて突っ込んできた事故」と似ています。
しかしこの場合は、過失割合1対9なのでもらい事故ではありません。

また、追突事故でも、被害者側の急ブレーキなどで事故が起きた場合は被害者側にも過失があるとされ、もらい事故にはなりません。
過失の有無は各事故の細かい状況まで考慮して決められます。そのため、似たような事故がもらい事故だからといって、ご自身の事故ももらい事故といえるとは限りません。
もらい事故が泣き寝入りになりやすい理由
もらい事故では、被害者に非がなく過失相殺による減額もないにもかかわらず、十分な賠償金を得られず泣き寝入りしてしまうケースがあります。
その理由は次のとおりです。
- 自分の保険会社に示談代行してもらえない
- 加害者側が通常よりシビアな態度で交渉してくる
- ひき逃げ・当て逃げのもらい事故だと賠償請求が難しい
この3点について、詳しくみていきましょう。
自分の保険会社に示談を代行してもらえない
もらい事故では自身の保険の示談代行サービスが使えません。過失が0の被保険者に代わって保険会社が示談交渉することは、弁護士法72条で禁じられている「非弁行為」にあたるからです。
被害者は自力で示談交渉することになりますが、加害者側は示談代行サービスを使うことが多いでしょう。
交渉のプロである保険担当者を相手にすることになるため、以下の点で不利な立場に追いやられやすいのです。
- 妥当な損害賠償金の金額がわからず、本来より低い金額で合意してしまいやすい
- 交渉経験も知識も加害者側の方が豊富であり、被害者側の主張は受け入れてもらいにくい
- 加害者側の保険担当者に高圧的な態度をとられ、疲弊してしまう
- 保険会社に専門用語を多用され、納得がいかないまま強引に交渉を進められてしまう
こうした事情から加害者側に有利な内容で示談が成立してしまい、泣き寝入りとなるおそれがあるのです。
示談交渉でよくあるトラブルについては『交通事故の示談でもめる8ケースと保険会社とのトラブル対策・解決法』でより詳しく紹介しています。
加害者側は通常よりシビアな態度で交渉してくることがある
もらい事故の場合、加害者側は通常よりも低めの損害賠償金を提示してきたり、増額交渉を拒むような態度を見せたりすることが多くなります。
もらい事故では、過失相殺による賠償金の減額がないことがその理由です。
加害者側の任意保険会社はなんとかして少しでも損害賠償金を低く抑えたいと考えています。そのため、過失相殺ができないなら損害賠償金自体を低額にしようと、厳しい態度で交渉してくる傾向にあるのです。
示談代行サービスが使えないだけでも被害者側にとっては難しい状況なのに、さらに加害者側の保険担当者の態度が頑なだと、被害者は太刀打ちできずに泣き寝入りしてしまいかねません。
ひき逃げ・当て逃げのもらい事故だと賠償請求が難しい
もらい事故の中でも、加害者がその場から逃げた「ひき逃げ」や「当て逃げ」は、特に賠償請求が難しく泣き寝入りが発生しやすいケースです。
加害者が分からないため損害賠償請求ができず、損害の補償を自己負担するか、自分の保険で賄うかすることになるからです。
もらい事故でひき逃げ・当て逃げとなる例えとしては、「駐車場に停めていた車が当て逃げされ、相手の車がそのまま走り去った」「すれ違いざまに擦られたが、そのまま相手の車が行ってしまった」などが挙げられます。
警察に届け出たとしても、人身被害のない当て逃げの場合は特に、それほど本格的な捜査が期待できないことも多く、加害者が分からないまま泣き寝入りとなることがあります。
関連記事
ひき逃げなら:ひき逃げされた時の対処法
当て逃げなら:当て逃げされた場合の対処法
もらい事故で泣き寝入りしない!得するための【事故直後の対応】8選
もらい事故の被害者が泣き寝入りせずに得するためには、事故後の対応をしっかりしておくことも非常に重要となります。
もらい事故の被害者が得をする具体的な方法は以下の通りです。
もらい事故の被害者が得をする方法
- もらい事故直後に示談をしない
- 警察への届け出を適切にする
- もらい事故の証拠を収集・保全する
- 自身の保険会社にも連絡する
- 軽いケガでも早く病院へ行き、適切に通院する
- 後遺症が残ったら後遺障害認定を受ける
- 車の修理では、先に見積書を加害者側に送る
- 弁護士に本当にもらい事故か確認を取る
それぞれの対応について、具体的に見ていきましょう。
(1)もらい事故直後に示談をしない
事故直後に示談を求めてくる加害者もいますが、絶対に示談しないでください。
物損(車の修理費など)や人損(ケガの治療費、慰謝料など)などの損害額は、事故直後では分かりません。
その場で示談してしまうと、保険が使えなくなったり、追加で示談金を請求したりできなくなります。
もらい事故の示談交渉のタイミング
交通事故による損害がすべて確定したら、加害者側と示談交渉を行い、損害賠償金の金額を決めることになります。
損害が確定するタイミングは以下のとおりです。
| 事故の種類 | 損害確定のタイミング |
|---|---|
| 後遺障害なしの人身事故 | ケガが完治した |
| 後遺障害ありの人身事故 | 後遺障害等級認定の結果が出た |
| 死亡事故 | 四十九日などの法要が終わった |
| 物損事故 | 修理費用の見積もりが出た |
なお、人身事故の場合、物損部分の示談交渉を人身部分に先立って行うことも多いです。
交通事故の示談をくわしく解説した記事『交通事故の示談とは?示談交渉の流れや示談をうまく進めるための注意点』では、示談の意味や示談交渉する時の注意点を紹介しています。
(2)警察への届け出を適切にする
もらい事故にあったら、必ず警察に通報しましょう。これは、道路交通法で定められた義務です。
もらい事故の被害者であっても、警察への通報を怠ると拘禁刑3ヶ月または5万円以下の罰金刑が科せられる可能性があります。
また、警察に通報しなかった場合、交通事故証明書が発行できず、適切な損害賠償を受けられなかったり、自分の保険が使えなかったりする恐れもあるのです。
届出の際には、ケガをしているなら軽微なものであっても人身事故として届け出ることも重要です。
病院で診断書を発行してもらったら、警察に人身事故として届け出をしましょう。
人身事故ではなく物損事故として届け出た場合、慰謝料や治療費を適切に受け取れない可能性があります。
ケガをしたにも関わらず物損事故として届け出ていた場合は、すみやかに人身事故に切り替えましょう。可能な限り、事故発生から10日以内に切り替えるのが望ましいです。
(3)もらい事故の証拠を収集・保全する
もらい事故のあとは、事故現場の様子を写真に撮るなどの証拠保全も重要です。
例えばもらい事故が人身事故だった場合は、警察による実況見分という捜査にて、事故現場の確認が行われます。
しかし、警察が到着するまでの間に安全確保のために車両を動かしたり、天候が変わったり、日が暮れて現場の見通しが変わったりすると、正確に事故時の状況を確認できない可能性があります。
その結果、示談交渉などで事故時の状況について、加害者側の虚偽の主張が通ってしまい、被害者側が¥泣き寝入りせざるを得ない状況になる可能性も否定できません。
そのため、事故を通報して警察の到着を待つ間に、事故現場や事故車両を写真や動画に収めるなど、できるだけ証拠保全をしておきましょう。
交通事故の証拠については『交通事故で集めるべき証拠は?保全の重要性と立証に必要な書類・証明資料』の記事でも詳しく解説しているので、ご確認ください。
(4)自身の保険会社にも連絡する
事故直後の一連の対応が終わった後は、自身が加入している保険会社に連絡を入れておきましょう。
もらい事故では、保険担当者に示談を代行してもらうことはできませんが、損害内容に応じて「人身傷害補償保険」「車両保険」「弁護士費用特約」といった保険を利用することは可能です。
そのため、自身の保険会社にも連絡して使える保険の案内を受けておくと、加害者から十分な賠償金を受け取れず、泣き寝入りするような状況になったとしても安心です。
保険会社とのやり取りについてもっと知りたい方は『交通事故の保険会社対応と流れ|相手方とのやりとりに困ったときは?』の関連記事もご覧ください。
加害者が無保険の場合は特に、自身の保険の利用が重要
もらい事故の加害者が無保険である場合には、被害者が泣き寝入りになるおそれが高いといえます。
通常、交通事故の賠償金は、加害者側の自賠責保険や任意保険から支払われます。だからこそ、加害者の資力に関係なく、賠償金をきちんと受け取れるのです。
しかし、加害者が無保険の場合は、加害者本人に賠償金を支払ってもらわなければなりません。
自賠責保険は強制加入なので加入している人が多いですが、自賠責保険はあくまでも最低限の補償をするにすぎません。
そのため、足りない分は加害者本人の負担になりますが、資力の問題で速やかに全額回収できるとは限らないのです。

そうした場合は特に、被害者自身の保険の利用が重要となるでしょう。交通事故で使える被害者自身の保険については、本記事内で後ほどくわしく解説します。
また、加害者が無保険の場合は、政府保証事業を利用するのも一つの手です。詳しくは『政府保障事業を利用するには?請求方法・慰謝料計算・支払いまでの期間』をご覧ください。
加害者が無保険であるケースの問題点や、その対処法について知りたい方はこちらもおすすめ:交通事故の相手が無保険でお金もない?泣き寝入りしないための賠償請求・対策法
(5)軽いケガでも早く病院へ行き、適切に通院する
もらい事故によるケガが軽いものであったとしても、ケガをした場合はできるだけ早く通院を始めることが大切です。
事故後すぐに通院を始めないと、「被害者が主張するケガは、事故後に別の要因で生じたもの」と保険会社から反論される可能性があるからです。
交通事故の直後は、興奮状態になっていて痛みに気づかないことも多いです。また、むちうちのように後日に症状が出てくる傾向にあるケガもあります。
そのため、「軽いケガだ」「痛い気がするけれど気のせいかもしれない」と思っても、念のため速やかに病院へ行きましょう。
なお、整骨院や接骨院に通いたい場合でも、まずは病院に行き、医師の許可を得たうえで整骨院・接骨院に通いましょう。
ワンポイントアドバイス
もらい事故でケガをして治療する場合は、健康保険を使うと負担額が減ります。ただし、交通事故で健康保険を使う場合は通常とは違う手続きが必要です。
詳しくは『交通事故で健康保険は使える!切り替え手続きや医療保険の併用まで弁護士が解説』をご覧ください。
関連記事
(6)後遺症が残ったら後遺障害認定を受ける
治療の結果、ケガが完治せず、症状固定と判断され後遺症が残ったら、後遺障害の申請をしましょう。
後遺障害等級認定の審査を受け、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害残存に対する補償を受けられるからです。

症状固定と診断された後の対応については『症状固定とは?時期や症状固定と言われたらすべき後遺障害認定と示談』の記事をご覧ください。症状固定の判断時期や後遺障害認定の申請方法について要点をおさえることができます。
(7)車の修理では、先に見積書を加害者側に送る
もらい事故で損傷した車を修理する場合は、実際に修理する前に加害者側に見積書を提出するなどして、修理内容を伝えておきましょう。
修理をしてから、「その損傷は今回の事故によるものではない」「その修理は必要不可欠とは言えない」などと反論されるのを防ぐためです。
もらい事故で車を修理する流れは、次のとおりです。
- 警察による事故状況の聴取が終われば、車を修理工場に移動させる
- 加害者側の任意保険会社に修理工場を連絡する
- 保険会社の調査員が損傷の状態・妥当な修理方法・費用などを調査する
- 保険会社と修理内容について合意できれば、修理を開始する
なお、修理の見積もりだけ取り、実際には修理しないことも可能です。
その場合も修理費を受け取れますが、その金銭をどのように使うかは被害者の自由となります。
実際に修理しない場合、工場によっては見積もりの手数料を請求されることがあるので、その点はあらかじめ留意しておきましょう。
(8)弁護士に本当にもらい事故か確認を取る
交通事故にあい、「もらい事故かな」と思った場合、念のため事前に弁護士に確認しておくことをおすすめします。
交通事故では事故時の細かい状況まで考慮して過失割合を判断するため、一見もらい事故のように思える事故でも、実はもらい事故ではないといったケースも珍しくありません。
そのことを利用し、本当はもらい事故なのに、「被害者側にも過失がある」と加害者側が主張してくることもあるでしょう。
こうした場合に備え、「本当にもらい事故といえるか」「なぜもらい事故といえるか」を専門家である弁護士に確認しておくと安心です。
弁護士への相談は無料でできることも多いので、気軽に相談してみましょう。
もらい事故で泣き寝入りしないために知っておくべき注意点
もらい事故は被害者側に過失がないため、「被害者側に有利に示談交渉を進められる」「賠償金を全額もらえてお得」と考える方も多いです。
しかし、もらい事故だからこその注意点・落とし穴もあるので、確認しておきましょう。
もらい事故でも賠償金が減額されることはある
もらい事故では、過失相殺による減額はありません。しかし、素因減額によって損害賠償金が減額される可能性はあります。
素因減額とは、被害者にもともと備わっている素因によって事故の損害が拡大した場合、その影響分を、賠償金から差し引くことです。
例えば以下のような場合、交通事故による損害はすべてが加害者のせいだとは言えません。
- 本来なら後遺障害が残るほどの負傷ではないが、被害者の既往症の影響で後遺障害が残った
- 被害者が治療に消極的だったせいで、治療期間が延びて入通院慰謝料が高額化した
それなのに、損害のすべてを加害者が補償するのは公平ではないため、素因の影響分だけ賠償金が減額されるのです。
ただし、どのような素因でどの程度賠償金が減額されるかについて明確な決まりはなく、交渉次第です。
また、加害者側は素因減額の対象ではない点について、素因減額を主張してくることもあるため、素因減額の正当性は慎重に判断すべきです。
- その他、もらい事故にあたる事故は?:交通事故で過失割合が10対0になる場合とは?過失割合を減らす方法も解説
- 素因減額とは?:素因減額とは?該当するケースや対処法を解説【判例つき】
もらい事故の賠償請求には時効がある
もらい事故の被害者は「自分に過失がないのだから、いつでも賠償請求できる」と思いがちですが、損害賠償請求にも時効があるため、放置すると権利を失うおそれがあります。
交通事故の時効期間(民法724条の2)
| 請求の種類 | 時効期間 |
|---|---|
| ケガに関する費目 | 事故翌日から5年 |
| 後遺障害に関する費目 | 症状固定翌日から5年 |
| 加害者が死亡した場合の遺族による請求 | 死亡翌日から5年 |
| 物損事故(車・物の損害) | 事故翌日から3年 |
多くの場合、時効までに示談が成立しますが、以下のような場合は時効に間に合わない可能性があります。
- 加害者側の保険会社との交渉が長引いている
- 後遺障害認定に時間がかかっている
時効の成立は遅らせることもできるので、時効が迫ってくる前に一度弁護士に相談してみましょう。
弁護士特約で弁護士費用の負担を0にできることが多い
もらい事故の場合、被害者側に非がないとはいえ、泣き寝入りせずに適正な賠償金額を得るには弁護士への相談・依頼が重要です。
本当にもらい事故なのか判断するにしても、適正な賠償金額を算定するにしても、加害者側からの素因減額の主張に対抗するにしても、専門的な知識や交渉力が必要になってくるからです。
弁護士に依頼をすると費用が発生しますが、ご自身や家族の保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
実質的に費用をかけずに弁護士を立て、後遺障害認定や示談交渉において専門的なサポートを受けられるので、弁護士費用特約の有無について確認してみてください。
もらい事故で請求できる損害賠償金

もらい事故で請求できる損害賠償金は、物損事故か人身事故かによって異なります。
なお、物損事故とは「人の身体には被害がなく、車や持ち物が壊れただけの事故」のことを言い、人身事故とは「人の身体に被害があった事故」のことを言います。
それぞれのケースにおける損害賠償金を詳しく見ていきましょう。
物損被害の賠償金|車の修理費など
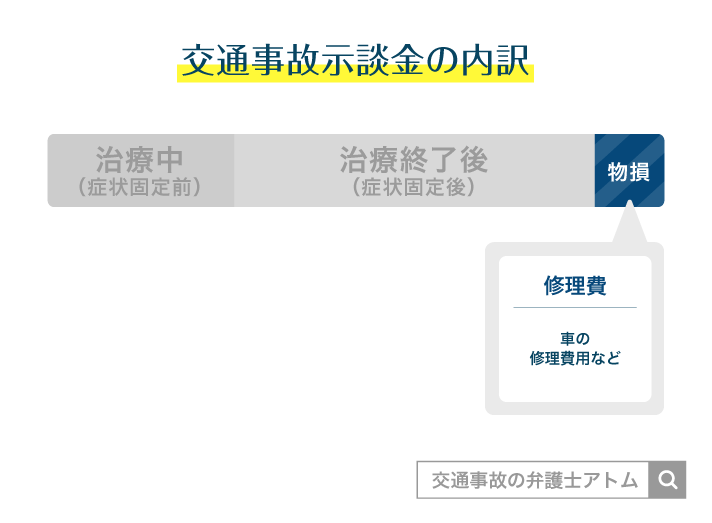
物損事故で加害者側に請求できる主な損害賠償金は、次のとおりです。
物損事故の主な損害賠償金
- 車の修理費用
事故当時における車両価格の金額を上限として、基本的に全額請求できる。
また、以下のような場合は、修理費ではなく買い替え費用を請求できる。- 車の修理費が事故当時の車両価格を上回る場合(経済的全損)
- 車が物質的に修理不可能な場合(物理的全損)
- 評価損
車に事故歴・修理歴が残ったり、修復できない傷跡や欠陥が残ったりしたことで車の価値が下がった場合に請求できる場合がある。
修理費の10%~30%にあたる金額になることが多い。 - 代車料
車の修理中に代車を使った場合に請求できる。
ただし、公共交通機関で代用できると判断される場合などは請求できない。 - 休車損害
営業車の修理により休業せざるを得ない場合に請求できる。
ただし、他の営業車で代用できる場合などは請求できない。 - レッカー代
車を修理工場に運ぶ際にレッカーを使った場合に請求できる。 - 持ち物や積載物の修理費用や弁償代
ペットの治療費などもここに含まれる。
なお、物損事故では原則的に慰謝料を請求できません。
これは、慰謝料が「人の身体が被害を受けたことによる精神的苦痛を補償するお金」であるためです。物が壊れたことによる精神的苦痛は、修理費用や弁償代といったお金を受け取れば慰撫されると考えられています。
これまでの裁判では、墓石の倒壊やペットの死亡などで慰謝料が認められたケースもあります。
しかし、基本的には物損事故で慰謝料が認められる可能性は極めて低いと考えておいた方がよいでしょう。
物損事故で慰謝料がもらえる可能性については、『物損事故で慰謝料がもらえた事例|原則もらえない理由と獲得を目指す方法』の記事で詳しく解説しています。
人身被害の賠償金|慰謝料、治療費など

人身事故で加害者側に請求できる主な損害賠償金は、次のとおりです。
物損事故の損害賠償金の費目は実費に基づいて計算されることが多いのに対し、人身事故の費目は示談交渉で金額が左右されるものが多いです。
示談交渉で加害者側の任意保険会社が提示してくる金額は、被害者が本来もらえるはずの金額よりかなり低い可能性が高いため注意してください。
費目ごとの相場額の計算方法については『交通人身事故の賠償金・慰謝料の相場と計算方法!物損事故との違いは何?』の記事もご覧ください。
また、以下の計算機では、損害賠償金のうち、慰謝料と逸失利益の金額を計算できます。加害者側から提示された金額が妥当か知りたい場合は、ぜひお役立てください。
もらい事故で新車が壊れたら賠償は?泣き寝入りするしかない?
もらい事故の中でも、特に車が新車だった場合は、車を傷つけられたことによる損害や精神的苦痛が大きくなりがちです。
こうした場合、十分な賠償は受けられるのか、解説していきます。
基本的には修理費と評価損の請求になる
新車でもらい事故に合った場合、新車そのもので返してもらうことは難しいですが、「評価損」を加害者側に請求できる可能性があります。
評価損とは、車に事故歴や修理歴などが付くことで、市場での取引価格が低下してしまうことに対する補償です。
判例では、事故車が登録から間もない新車であり、価格の高い外国産車や人気の国産車であると評価損が認められる傾向にあります。
新車に買い替える費用を請求できるケースについて詳しくは『過失割合10対0の事故で新車が損壊…買い替え費用や修理代はどうなる?』の記事をご確認ください。
また、『納車前の新車事故、評価損は?―裁判所が認めた「新車の価値」 #裁判例解説』では、実際の裁判例をモデルに、裁判所の判断のポイントなどを解説しています。あわせてご覧ください。
新車の買替費用が認められるケース
もらい事故にあい新車が損傷した場合、以下に該当し「全損」と判断されれば、新車の買い替え費用を加害者側に請求できることがあります。
- 自動車が物理的に修理不可能な状態
- 修理可能であるものの、修理費が時価額等より高額になる状態
なお、新車の買い替え費用を請求できるといっても、実際に請求できる金額は、「車両の時価額+買い替え諸費用(登録費用、車庫証明費用など)-事故車の売却金額(スクラップ金額)」」となるのが基本です。
また、新車の買い替えにあたっては付随して様々な費用がかかりますが、そのすべてを加害者側に請求できるとは限らない点には注意しましょう。
詳しくは、『事故で全損に…相手の保険や車両保険からいくらもらえる?車を買い替える流れ』をご覧ください。
もらい事故では自分の保険なども有効活用しよう
もらい事故で活用できる被害者側の保険の中で、主なものは以下の通りです。
- 人身傷害保険(ケガをした場合に利用)
- 車両保険(車両の損害に利用)
- 弁護士費用特約(保険に付帯する特約。弁護士費用をまかなえる)
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 人身傷害保険 | ケガの治療費や逸失利益等の補償が受けられる自分の保険。 <保険金の目安> ・傷害:120万円 ・死亡・後遺障害:3000万円~無制限 |
| 車両保険 | 車両の修理費等の補償が受けられる自分の保険。 <保険金の目安> ・新車:購入時の時価額+オプション費用+消費税 ・中古車:時価額 |
| 弁護士費用特約 | 自分や家族の自動車保険等に付帯する特約。弁護士費用が補償される。 <保険金の目安> ・法律相談:10万円 ・弁護費用:300万円 |
ここでは、人身傷害保険と車両保険について、詳しく確認していきます。弁護士費用特約については、後ほど本記事内「(3)弁護士費用特約でお得に弁護士へ依頼」の項目で詳しく解説します。
なお、もらい事故で使える自分の保険は『もらい事故で保険会社が示談交渉できない理由は?交渉の注意点や使える自分の保険について解説』の記事でも詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
人身傷害保険
人身傷害保険とは、保険加入者や搭乗者の治療費・慰謝料などを保険金として受け取れるものです。
以下のような場合では、人身傷害保険の利用を検討するとよいでしょう。
- 加害者が無保険(任意保険未加入)であり、分割払いや踏み倒しになりそう
- 示談交渉が長引き、損害賠償金の受け取りまで時間がかかっている
人身傷害保険の詳細や、加害者が無保険の場合の対応法については、以下の関連記事で詳しく解説しています。
車両保険
車両保険は、交通事故で損傷した車両の修理費や買い替えの補助を受けられる保険です。
人身傷害保険と同様に、車両保険も加害者が任意保険未加入の場合に役立ちます。
車の修理費など、物損に関わる費目は加害者側の自賠責保険から支払われないので、加害者が任意保険未加入だと全額加害者本人からの支払いを待つことになるためです。
なお、車両保険には以下のような特約がついていることがあるので、利用の際にはあわせて確認してみるとよいでしょう。
- 全損時諸費用特約:車が全損した場合の買い替え費用の一部をカバーする特約
- 新車特約:車が全損した場合、新車を買った時の購入金額が全額補償される特約
- 車両無過失事故に関する特約:車両保険の利用で保険の等級が低下せず、保険料が増加しない旨の特約
加害者が無保険のもらい事故の場合は自身の保険を利用すべき
加害者が任意保険に入っていないもらい事故では、被害者自身の保険を利用すべきといえます。
自賠責保険からは最低限の損害賠償金しか受け取れず、不足分についても加害者によっては支払いを踏み倒す恐れがあるため、自身の保険を利用して損害を補てんすべき必要性が高いといえるでしょう。
もらい事故で泣き寝入りしない!得するための【交渉術】3選
もらい事故では被害者側の任意保険会社に示談代行してもらえず、加害者側もシビアな態度で交渉しくるケースが多くあります。
加害者側の提案を簡単に受け入れると、泣き寝入りの結果となるおそれがあるでしょう。
もらい事故で泣き寝入りせずに得する方法として、加害者側からの提案に安易に同意しない、弁護士に依頼して慰謝料を増額させる、弁護士費用特約でお得に弁護士を立てるという3点が重要です。
(1)加害者側からの提案に安易に同意しない
加害者側は少しでも自身が支払う損害賠償金を抑えるため、基本的に相場より低い金額の支払いを提案してきます。
この際、提案額が相場額のように主張してくる可能性が高いので、加害者側からの提案に安易に同意してはいけません。
少しでも疑問が残る場合には、その場で返答せずに保留し、加害者側からの提案が正しいのかどうかについて検討を行いましょう。
請求できる損害賠償金の費目と相場額を知っておく
自身がどのような損害について請求できるのか、損害賠償金額の相場がいくらなのかを把握しておけば、相場より低額な提案額で示談することを防ぐことができます。
交通事故の被害にあった場合には、治療費や慰謝料などさまざまな費目を請求することが可能なため、費目ごとの相場額について知っておくことが大切です。
| 相場・目安 | |
|---|---|
| 治療関係費 | 必要かつ相当な実費 |
| 休業損害 | 1日あたりの基礎収入×休業日数 |
| 入通院慰謝料 | 慰謝料算定表の相場による ※通院3か月の場合 ・軽症:53万円 ・重症:73万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級ごとに相場がある ・1級:2,800万円 ・14級:110万円 |
| 後遺障害逸失利益 | 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 ※喪失率の相場 ・1級:100% ・14級:5% |
過失割合が「10対0」の事故の示談金相場は『10対0事故の示談金相場はいくら?むちうちの慰謝料や計算方法がわかる』で詳しく解説しています。
慰謝料の相場額については、以下の計算機から簡単に確認できます。ご自身が受け取るべき妥当な金額はいくらなのか、確認してみてください。
(2)弁護士に相談して慰謝料増額を目指す

もらい事故の被害者が示談交渉を自身のみで行うことは簡単ではありません。
やはり、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士なら、被害者が請求できる費目や相場額の計算を正確に行うことが可能であり、加害者の提案が正当であるかどうかも判断することができるでしょう。
弁護士基準の慰謝料相場を目指せる!
もらい事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、弁護士基準での示談交渉が可能となります。

結果として、被害者にとって得になる結果が生じます。
なかには、保険会社の提示額の2倍近くまで増額した事例もあります。こちらは、過失割合について、被害者:加害者=0:100のもらい事故の解決事例です。
骨折の増額事例
弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。

弁護活動の成果
提示額の354万円から、最終的な受取金額が750万円まで増額された。
年齢、職業
40~50代、自営業
傷病名
肩骨折、左膝骨折
後遺障害等級
12級13号
任意保険会社がシビアな態度をとっている場合でも、弁護士が示談交渉をすれば、被害者は得する可能性が高いです。
弁護士が示談に強い理由
- 専門知識を持つ弁護士の主張であれば、任意保険会社も無下にできない
- 弁護士が出てくると、任意保険会社は裁判への発展を警戒し、態度を軟化させる
- 任意保険会社の内部で「弁護士が出てくれば増額を認める」といった取り決めをしている場合がある
もらい事故による慰謝料の請求に関しては、関連記事『もらい事故の慰謝料はいくら?相場や請求の流れ・注意点を解説』も参考になりますので、あわせてご覧ください。
アトム法律事務所の弁護士による慰謝料増額の実例については『交通事故の解決事例』のページにて一部を紹介しています。
また、アトム法律事務所は、交通事故の被害に遭われた方を対象に弁護士による無料相談を実施中です。気軽に利用ください。
慰謝料の増額以外にもメリットがある
交通事故で弁護士に相談・依頼するメリットは慰謝料の増額だけではありません。
他にも、煩雑な手続きを一任できる、治療中の保険会社とのトラブルに対処してもらえるといったサポートを得られます。
弁護士への相談・依頼を検討する際は、『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事も参考にしてみてください。
(3)弁護士費用特約でお得に弁護士へ依頼
弁護士に相談・依頼をする際には費用がかかりますが、加入する保険に付帯している「弁護士費用特約」を使うと、基本的に弁護士費用300万円、法律相談料10万円を限度として、保険会社に支払ってもらえます。
すべての弁護士費用を弁護士費用特約でまかなえることは珍しくありません。
そのため、多くのケースで金銭的な負担をすることなく弁護士に相談・依頼ができるのです。
弁護士費用特約を利用すれば、慰謝料の増額分について弁護士費用を差し引くことなく得られるので、非常にお得といえます。

もらい事故における弁護士費用特約のポイントは『もらい事故こそ弁護士特約を使って慰謝料増額!特約のメリットや使い方』の記事が参考になります。
なお、たとえ弁護士費用特約がなく、弁護士費用を自己負担することになったとしても、弁護士に依頼した方が多くの金額が手元に残ることは珍しくありません。
弁護士への無料相談を利用し、損害賠償金の増額幅と弁護士費用の見積もりをとってみるとよいでしょう。
弁護士への相談は、病院での初診後~示談締結前であればいつでも可能です。早く相談した方が受けられるサポートの幅が広いので、まずは気軽に無料相談を利用してみてください。
参考になる記事
もらい事故で泣き寝入りをせずに済んだ事例(アトムの解決事例)
アトム法律事務所が実際に扱ったもらい事故で、泣き寝入りにせず済んだ事例を紹介します。
赤信号停車直後のもらい事故で約124万円の増額に成功した事例
弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があり、弁護士による交渉の結果、約124万円の増額に成功した事例を紹介します。
頚椎ヘルニアの増額事例
赤信号で停車した直後に後方より加害者の車両が追突してきたもらい事故
過失割合
被害者0:加害者100
弁護活動の成果
提示額の約152万円から、最終的な受取金額が276万円まで増額された。
傷病名
頚椎ヘルニア
後遺障害等級
14級
走行中のもらい事故で約147万円の増額に成功した事例
弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があり、弁護士による交渉の結果、約147万円の増額に成功した事例を紹介します。
右肩神経のしびれの増額事例
片側三車線の幹線道路で一番右の車線を走行中、前の車のスピードに合わせて少し減速した際に、後ろからかなりのスピードで迫ってきている後方車を確認したため、少し右に避けたが追突されたもらい事故
過失割合
被害者0:加害者100
弁護活動の成果
提示額の約276万円から、最終的な受取金額が約423万円まで増額された。
年齢、職業
46歳、自営業
後遺障害等級
14級
もらい事故に関するよくある質問
ここからは、もらい事故での保険の利用や示談交渉に関してよくある質問にお答えします。
Q.もらい事故で保険は使える?等級は下がる?
もらい事故の被害者は、自身の人身傷害保険や車両保険、弁護士費用特約などを使えます。
弁護士費用特約や人身傷害保険は、それだけを利用しても保険の等級は下がりません。一方、車両保険は利用により等級が下がり、翌年からの保険料が上がることが多いです。
ただし、実際の契約内容は保険によっても異なるため、事前に確認してみてください。
Q.もらい事故で得する方法は?
弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼すると、実質的に費用をかけずに弁護士を立て、効果的な示談交渉ができるので得につながります。
実際の増額事例では2倍以上の増額に成功するケースもあります。
もらい事故の増額事例(むちうち症)
信号待ちをしていたところ、追突されるもらい事故に遭い、むちうち症を負った。弁護士相談の段階で、保険会社からの提示があったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。
弁護活動の成果
保険会社の提示額の約43万円から、弁護士の示談交渉により2倍以上増額し、最終的な受取金額が約94万円となった。
過失割合
被害者0:加害者100(もらい事故)
年齢、職業
30~40代、自営業
傷病名
むちうち
Q.もらい事故の示談交渉は自分でできる?
もらい事故の示談交渉は被害者自身でも可能です。
ただし、被害者自身で交渉を有利に進めることは、難しいでしょう。
加害者側は交渉のプロである保険担当者を出してくることが多い点、もらい事故で過失相殺ができないからこそ相手の態度がシビアになりやすい点が理由です。
そのため、弁護士を立てて示談交渉することがお勧めです。
もらい事故について電話・LINEで無料相談ができる窓口
もらい事故のまとめ
もらい事故とは、被害者の過失割合が0%の交通事故のことです。
もらい事故の場合、被害者は、示談代行サービスを使えないため、自分で加害者側と交渉をしなければなりません。
ですが、加害者側の交渉窓口は通常、任意保険の担当者です。相手は、交渉のプロです。被害者は圧倒的に不利な立場に置かれ、泣き寝入りになることも少なくありません。
もらい事故で泣き寝入りしないためには、適切な損害賠償を受けるために知識が必要です。
もらい事故の証拠収集、早期の通院開始、過失割合の検討、弁護士基準による請求額の算定など、賠償請求で重要なことは多岐にわたります。
まずは、交通事故に詳しい弁護士に相談してみて、今後の方針を立ててみてください。
もらい事故の弁護士相談:24時間受付中
弁護士への相談・依頼を検討されている方は、ぜひアトム法律事務所の無料相談もご利用ください。
アトム法律事務所の無料相談の特徴は、電話・LINEで気軽に相談できることです。
無料相談にあたっては弁護士費用特約の有無は関係ありません。もらい事故でケガをされた方はお気軽に活用してください。
無料相談のポイント
- 自宅や職場などから、スキマ時間を活用できる
- 仕事や子育て、治療で忙しい人にも最適
- 依頼後の弁護士費用についても気兼ねなく聞ける
- 弁護士費用特約あり:保険会社が弁護士費用を負担してくれる
- 弁護士費用特約なし:着手金は基本ゼロ、報酬は後払制で安心
- セカンドオピニオンとしても利用いただけます
- 無料相談のみの利用でも全く問題なし
無料相談の予約は24時間365日受け付けています。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

どうなるのかの説明が明快で分かりやすかった為とても安心できました。
また難しいことは難しいとちゃんと伝えてくれたことも信頼できると感じました。

弁護士さんに相談することは初めてで、最初はとても勇気が要りましたが、優しい対応で安心できました。ありがとうございます。
今後深い話をさせていただく事になると思いますが、是非宜しくお願い致します。

遠方にいて、わずかな情報しかなく、心細かったのですが、丁寧な対応で安心して頼ることができました。本当にありがとうございました。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了




