政府保障事業を利用するには?請求方法・慰謝料計算・支払いまでの期間
更新日:
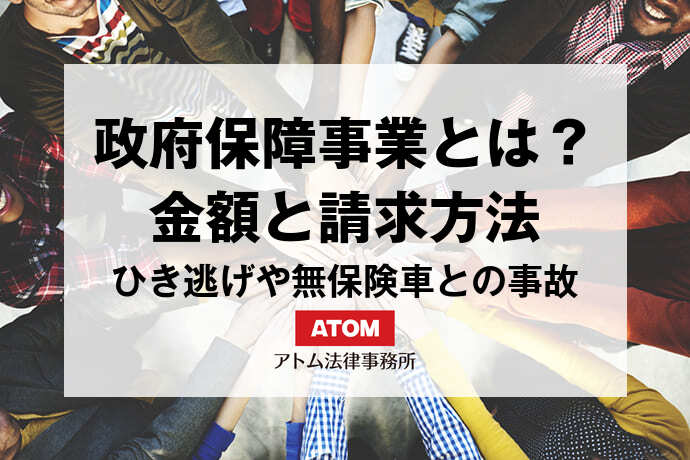
政府保障事業は、ひき逃げや無保険車による交通事故で自賠責保険から補償を受けられない被害者を救済する国の制度です。
本来、交通事故の損害賠償金は加害者が加入する自賠責保険や任意保険から支払われます。
しかし、加害者が不明な「ひき逃げ」や、相手が自賠責保険にすら加入していない「無保険車」との事故は、被害者が十分な補償を受けられないリスクがあります。こういったリスクから救済するために、政府保障事業があるのです。
本記事では、政府保障事業を利用できるケースと受け取れる金額、請求から支払いまでの流れを解説します。
目次
政府保障事業とは?しくみと対象となる事故
政府保障事業は、自動車損害賠償保障法に基づく制度で、自賠責保険では補償されない特定の事故の被害者を救済します。被害者の救済制度であるため、加害者は請求はできません。
無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、政府保障事業によって、国が自賠責保険・共済と同等の損害を塡補する救済が行われています。
政府保障事業|国土交通省
物損事故では政府保障事業の対象とならず、補償されるのは人身損害に限られます。政府保障事業の制度を利用できるのは、主に以下のようなケースです。
- ひき逃げ事故で加害者が不明
- 自賠責保険に未加入や期限切れの無保険車による事故
- 盗難車や無断運転等で自動車保有者に責任が生じない
こうした状況で、健康保険や労災保険などの社会保険を利用してもなお残る損害がある場合に、政府(国土交通省)が被害者へ立て替え払いをします。
政府保障事業で受け取れる金額は?
政府保障事業の補償内容は、自賠責保険に準じています。支払われる金額の上限と補償対象となる費目について、詳しく見ていきましょう。
政府保障事業の支払限度額と補償内容
政府保障事業では、損害の種類ごとに支払限度額が定められています。
| 損害の種類 | 法定限度額 |
|---|---|
| 傷害(ケガ)による損害 | 120万円 |
| 後遺障害による損害 | 75万~4,000万円 ※後遺障害等級による |
| 死亡による損害 | 3,000万円 |
この範囲内で、実費や基準に基づいた金額が支払われます。
補償の対象となるのは、治療費・休業損害・慰謝料などの人身被害に関する費目です。修理費など物損に関する費目は補償されません。
傷害事故の費目
- 治療関係費
診察料、入院料、投薬料、手術料、通院交通費、診断書の発行手数料など - 文書料
交通事故証明書や印鑑登録証明書、住民票などの発行手数料 - 休業損害
事故によるケガや入通院で仕事ができず減少した収入の補償 - 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
事故による精神的・肉体的苦痛に対する補償
後遺障害の認定を受けると、後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われます。
後遺障害を残した事故の費目
- 後遺障害慰謝料
後遺障害が残ったことで生じる精神的・肉体的苦痛に対する補償 - 後遺障害逸失利益
後遺障害によって将来得られるはずだった収入が減ったことへの補償
交通事故で死亡した場合は、死亡慰謝料や逸失利益、葬儀費用が補償されます。
死亡事故の費目
- 死亡慰謝料
交通事故によって死亡した被害者と、その遺族の精神的苦痛に対する補償 - 死亡逸失利益
死亡によって得られなくなった、将来の収入に対する補償 - 葬儀費
通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などの費用
慰謝料はいくら?目安の計算方法
政府保障事業に請求できる慰謝料には入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料があり、「自賠責基準」と呼ばれる国が定めた基準に沿って計算されます。
入通院慰謝料
原則として、4,300円×対象日数で計算されます。対象日数は、「治療期間」と「実際に通院した日数×2」のいずれか短い方が用いられます。
例えば、治療期間90日で実際に通院したのが40日だった場合、対象日数は80日(40日×2)となり、入通院慰謝料は4,300円×80日=344,000円となります。
後遺障害慰謝料
認定された後遺障害等級と被扶養者の有無に応じて金額が定められています。最も重い1級で1,850万円(扶養ありの場合)、最も軽い14級で32万円と幅があります。
なお、後遺障害慰謝料は、医師から症状固定(これ以上治療しても症状が改善しない状態)の診断を受けた症状が後遺障害等級に認定されなければ、原則的に請求できません。
後遺障害認定を受ける方法は、『後遺障害等級が認定されるには?後遺症との違いや認定の仕組みを解説』をご覧ください。
死亡慰謝料
自賠責基準の死亡慰謝料は、本人分が400万円、遺族分が550万円〜950万円です。
死亡慰謝料は、交通事故で亡くなった被害者本人だけでなく、その遺族に対しても支払われます。遺族とは、原則として被害者の配偶者と子、父母・養父母を指します。
遺族の人数によって金額が異なり、1人であれば550万円、2人は650万円、3人以上は750万円です。被害者に被扶養者がいる場合は200万円が加算されます。
政府保障事業からの支払いが差し引かれるケース
すでに他の制度や保険から補償を受けている場合は、その分が差し引かれます。ひとつの損害に対して二重に補償を受けることはできません。
例えば、ご自身の人身傷害保険から保険金が支払われた場合や、加害者から損害賠償金を受け取った場合が該当します。
また、7割以上の重大な過失が被害者にあるときは、過失割合に応じて減額されることがあります。
政府保障事業への請求方法と必要書類
政府保障事業の請求は、治療を終えた後に行います。
手続きは原則として被害者本人(死亡事故の場合は遺族)が請求します。いずれも損害保険会社や共済組合を通じて進める流れになります。
請求の流れと必要書類を、4つのステップに分けて解説します。
(1)警察に人身事故の届出をする
交通事故でケガをしたら、必ず警察に人身事故の届出をしてください。
人身事故として届出をしていない場合や、物損事故扱いのままでは、政府保障事業の支払対象外となる可能性があるためです。
物損事故で届け出た後に人身事故に変える方法は、『物損から人身への切り替え方法と手続き期限』で解説しています。
(2)請求先の窓口に連絡する
病院での治療を終えたら、損害保険会社や共済組合の窓口に連絡し、政府保障事業の請求に必要な書類をもらいましょう。
どの損保会社や組合が請求を受け付けているかは国土交通省の自賠責保険・共済ポータルサイトで確認できます。
(3)請求に必要な書類を揃える
政府保障事業に請求するには、事故の状況や損害を証明できる書類を提出しなければなりません。
ここでは代表的な書類を紹介します。
政府保障事業の請求に必要な書類
- 政府保障事業への支払請求書
- 交通事故証明書(人身事故扱いのもの)
- 事故発生状況報告書
- 診断書、診療報酬明細書など治療内容を証明する資料
- 本人確認書類
請求内容によっては、通院交通費明細書や休業損害証明書、後遺障害診断書、死亡診断書などの提出も求められます。
どの書類が必要かは、事前に請求先の損害保険会社や共済組合に確認しておきましょう。
(4)請求先の窓口に書類を提出する
すべての書類が揃ったら、請求先の損害保険会社や共済組合の窓口に提出します。
提出した書類は、損害保険料率算出機構という専門機関に送られ、事故状況や損害額の調査が行われます。
書類に不備があった場合は、内容の確認や追加提出を求められることがあります。
いつ支払われる?請求から支払いまでの期間
請求書類を提出してから、実際に保障金が支払われるまでには時間を要します。
損害の調査や審査に手間がかかるため、自賠責保険よりも支払いまでに時間がかかることが多く、数か月で終わる場合もあれば、1年以上かかるケースもあります。
特に、以下のような場合は審査が長引くことがあります。
- 後遺障害の等級認定が複雑な場合
- 事故の状況について、目撃者などへの確認が必要な場合
- 提出された書類に不備がある場合
支払いまでに時間がかかることを踏まえ、必要書類や手続きの準備をしっかり確認しておきましょう。
政府保障事業の請求前に確認しておきたい3つの注意点
政府保障事業は被害者を救済する大切な制度ですが、利用にあたっては知っておくべきポイントがあります。請求前に必ず確認しておきたい3つの注意点をみていきましょう。
自分の任意保険の補償内容を確認する
まずは、ご自身の保険契約に人身傷害保険や無保険車傷害保険などの補償が付いていないか確認しましょう。
- 人身傷害保険
交通事故で被保険者やその家族が死傷した場合に、治療費や休業損害などの損害を補償する保険です。保険加入時に設定した金額を上限として、治療費・休業損害・慰謝料など実際の損害額が支払われます。 - 無保険車傷害保険
加害者の車が無保険で十分な賠償を受けられない時に使える保険です。ひき逃げで加害者がわからないときにも使えます。被害者が死亡、もしくは後遺障害が生じた場合に補償を受けられます。
契約内容によっては、政府保障事業よりも補償が広く、手厚い救済を受けられることがあります。ご自身の保険証券を確認するか、契約先の保険会社に「今回の事故で利用できる補償はないか」と問い合わせてみましょう。
なお、任意保険から受け取った保険金は、政府保障事業から支払われる金額から差し引かれます。二重に受け取ることはできません。
請求できる期間には時効がある
政府保障事業には請求できる期限(時効)があります。この期間を過ぎると請求できなくなるので注意が必要です。
| 傷害(ケガ)による損害 | 事故発生日から3年 |
| 後遺障害による損害 | 症状固定日(これ以上治療しても改善しないと判断された日)から3年 |
| 死亡による損害 | 死亡日から3年 |
ひき逃げ事故で後から加害者が判明した場合は、その時点から3年です。
政府保障事業は原則として治療が終了してから請求しますが、時効が迫っている場合は例外的に受け付けてもらえます。迷わず、早めに損害保険会社や共済組合の窓口に相談しましょう。
健康保険や労災保険を優先して利用する
交通事故によるケガの治療でも、健康保険や労災保険などの社会保険を利用できます。
健康保険や労災保険から支払われるべき分は、政府保障事業の補償から差し引かれます。
自由診療で治療を受けて費用が高額になったとしても、本来健康保険等で支払われるべき部分については、政府保障事業からは補償されません。社会保険を使わずに治療を受けてしまうと、自己負担が大きくなるリスクがあります。
政府保障事業の対象となる事故であれば、例えば「ひき逃げ事故で自賠責保険を使えないので健康保険で治療したい」と医療機関に伝えてください。
政府保障事業を正しく理解して活用しよう
ひき逃げや無保険車との事故は、加害者への怒りや将来への不安で、被害者やご家族に大きな精神的負担をもたらします。そんな状況を救済するための制度が政府保障事業です。
この記事のポイントをもう一度整理しましょう。
- 政府保障事業は、ひき逃げや無保険車による事故の被害者を救済するための国の制度
- 保障内容は自賠責保険に準じており、補償額には上限がある。
- 請求窓口の損害保険会社や共済組合に相談し、必要書類を集めることから始める。
- 請求には時効があるため、早めの行動が大切。
ご自身での手続きに不安がある場合や、損害額の計算が難しいと感じる場合は、交通事故に詳しい弁護士など専門家へ相談するのも有効です。安心して補償を受けるための一歩につながります。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了


