交通事故の過失割合の判例集|事故状況別にわかる事例一覧
更新日:
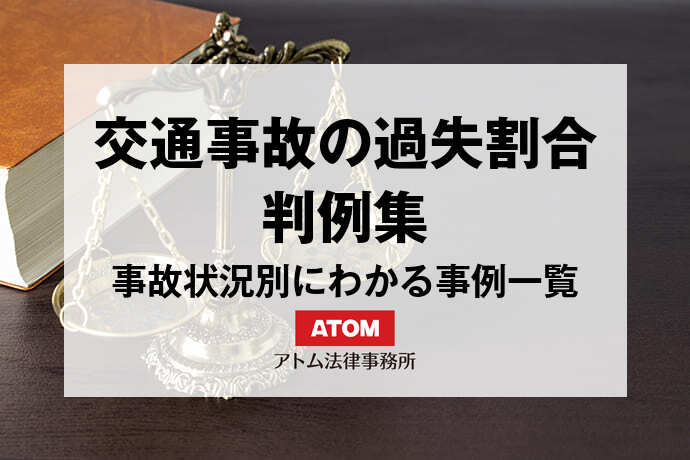
交通事故の損害賠償額を左右する大きな要素が「過失割合」です。これは、事故に対する当事者それぞれの責任の重さを「8対2」などの比率で示すもので、受け取れる賠償金額に直接影響します。
たとえば、500万円の損害があっても、被害者に2割の過失があると認定されれば、受け取れる賠償金は400万円に減ってしまいます。
では、過失割合はどうやって決められるのでしょうか?
実はその判断は、これまでに積み重ねられてきた数多くの裁判例(判例)をもとに、事故の種類ごとに基準が決まっています。
本記事では、実際の判例を事故類型別に紹介し、わかりやすく解説します。各事故類型についてはより詳しく解説したページへの案内もありますので、ご自身のケースと照らし合わせる際の参考にしてください。
目次
判例タイムズとは|判例の基準が詰まった過失割合の集大成
交通事故の過失割合を決める際、裁判官や弁護士、保険会社が共通の判断基準として使っている、もっとも信頼性の高い資料が「別冊判例タイムズ38号」です。
これは東京地裁の交通専門部の裁判官が編集したもので、正式名称は『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』といいます。
この書籍の特徴は、過去の膨大な裁判例をもとに、交通事故をパターン別に分類し、それぞれに「基本となる過失割合」と「修正すべき要素」を体系的にまとめている点です。
たとえば、車同士の事故、歩行者と車の事故など、事故の組み合わせごとに7つの大きな分類があり、さらに交差点の有無、信号の有無、車の動きなど、より細かい分類がされています。
実務では、この判例タイムズが“事実上のルールブック”として使われており、裁判だけでなく保険会社との示談交渉でも基準になります。
車の事故の過失割合の判例
①交差点事故の過失割合の判例
信号機が設置されていない交差点では、優先道路を直進する車と、非優先道路(劣後道路)から進入してきた車のあいだで事故が起きることがあります。
このようなケースでの基本の過失割合は優先道路の車:非優先道路の車=10:90です。
信号なし交差点での過失割合
名古屋地判平28・2・26(平成26年(ワ)2747号)
信号機のない交差点で、優先道路を時速40kmで走行していた被害車と、非優先道路から一時停止後に進行した加害車が衝突。
被害者は、交差点手前24m地点で一時停止中の加害車を認め、「運転者がこちらを見ていない様子」に気付いたが、「当然こちらも確認するもの」とみて減速せずに進行。
加害者は一時停止後に安全確認したつもりで再発進したが、右方の安全確認が不十分で被害車に気づかなかった。
裁判所の判断
「(加害車は)優先道路である交差道路を通行する車両の通行を妨害してはならなかったにもかかわらず、右方の安全確認不十分のまま漫然と本件交差点内に進入した」
名古屋地判平28・2・26(平成26年(ワ)2747号)
- 加害者の過失:右方安全確認不十分での交差点進入は「過失の程度は大きい」
- 被害者の過失:相手が自分を見ていないことに気づきながら減速しなかった注意義務違反は「軽微」
過失割合
被害者(優先道路):10%・加害者(非優先道路):90%
この判例では被害者側にも「相手が自分を見ていないことに気づきながら減速しなかった」過失が認定されています。しかし、道路交通法上の優先関係が明確に考慮され、被害者の過失は「軽微」とされています。
被害者の過失が著しい不注意や重過失とまで言えない限り、基本の過失割合(10:90)から大きく修正されることはありません。
関連記事
・交差点事故の過失割合|信号や車の種類で変わる?事故の類型別に図解
②追突事故の過失割合の判例
追突事故では基本的に後続車に100%の過失が認められますが、前車の急ブレーキや不適切な運転行為があった場合は過失相殺される可能性があります。
黄信号の停止は過失なしとされた裁判例
東京地判令2・1・10(平成31年(ワ)第2356号)
交差点で右折のため停止線で停止していた男性の車に、後続車が時速約20キロで追突。
被告側は「原告が黄色信号でいきなり急ブレーキをかけたため避けられずに追突した」として、原告に3割の過失があると主張。
原告は「約50メートル手前で黄信号を認識し、安全に減速して停止した」と反論。
黄信号での停止行為の適法性が争点となった。
裁判所の判断
「原告が停止線で原告車を停止させるためにブレーキをかけたことが、理由のない急ブレーキであったと認めることはできない」
東京地判令2・1・10(平成31年(ワ)第2356号)
- 時速約20キロの低速走行で車間距離も約8メートルあった
- 黄色信号での安全な停止は適切な運転行為
- 右折完了は危険な状況であり停止が正しい判断
過失割合
被害者0%:加害者100%
本件では被告側が「理由のない急ブレーキ」を主張しましたが、裁判所は適切な速度と車間距離での走行、黄信号での安全な停止という事実を重視し、原告の過失を完全に否定しました。
黄信号で迷った際は、安全に停止できる状況であれば停止することが交通法規に適った行為であり、それによって追突されても過失は問われないことを示した重要な判例です。
関連記事
・追突事故の過失割合は10:0が原則!急ブレーキの過失や判例も紹介
③車線変更事故の過失割合の判例
一般道路で、前を走る車が車線変更をした際に、後ろから来た車とぶつかってしまった場合、基本の過失割合は「車線変更した車:後方車=70:30」となっています。
もっとも、その場所が進路変更禁止の区域(たとえば交差点付近など)だった場合、過失割合が修正されて車線変更した側の責任がより重くなります。
進路変更禁止区域での車線変更
さいたま地判平28・7・7(平成26年(ワ)第2595号)
雨天の夜間に青果運送会社の4トン冷凍車が国道の第1車線を時速60km程度で走行中、第2車線から左折のため車線変更してきた普通乗用車と衝突した事故。
普通車は交差点手前の進路変更禁止区域(黄色線区間)内で車線変更を行い、後方から直進してきた冷凍車の右側面に左側面を接触させた。
裁判所の判断
「双方の過失割合について、原告車が10、被告車が90とするのが相当である」
さいたま地判平28・7・7(平成26年(ワ)第2595号)
過失割合
過失割合:普通車90%、運送会社10%
進路変更禁止区域での車線変更は道路交通法の明確な違反行為であり、基本的に車線変更した側の過失が重く認定されます。本判例では普通車側に90%という高い過失割合が認定されました。
ただし、後続車両にも一定の注意義務があります。前方車両が方向指示器を出して進路変更の意思を示している場合、たとえ違法な車線変更であっても、可能な範囲で減速や回避措置を講じる義務があるとされています。
関連記事
・車線変更事故の過失割合|合流地点の事故は?よくあるケースや判例を解説
④道路外出入車と直進車の事故の過失割合の判例
直進車の過失なしとされた裁判例
名古屋地判平22・2・19(平成20年(ワ)6066号)
原付運転者が歩道を走行した後、駐車場出入口付近から一時停止も安全確認もせずに道路へ進入し、直進中の高級外車(アウディ)と衝突した事例。
被害者は左前方4.2メートルで原付を発見しブレーキをかけたが間に合わなかった。
裁判所の判断
「…路外から被告車が進入してくることを想定して衝突を回避するために一旦停止するなどの措置をとる義務までは認められない」
名古屋地判平22・2・19(平成20年(ワ)6066号)
- 直進車には、路外進入車の違法行為まで予見する義務はない
過失割合
原付100%、直進車0%
この判例では、原付運転者が歩道走行という交通違反を犯した上で安全確認を怠ったという悪質性が影響し、路外進入車(原付)に10割の過失が認定され、直進車には一切の過失なしとされました。
関連記事
・路肩発進や路外出入り時の事故の過失割合はどうなる?頭出し待機の影響も解説
⑤対向車同士の事故の過失割合の判例
科学的鑑定で決着した正面衝突事故
東京地判平19・3・30(平成15年(ワ)20769号)
片側1車線の左カーブで普通乗用車(A車・青色)と軽貨物車(B車・白色)が正面衝突。
A車運転手は「B車がスピンしながらセンターラインオーバーしてきた」と主張し、B車側は「A車が制限速度超過でセンターラインを越えてきた」と真っ向対立。合計4人の自動車工学専門家による鑑定書が提出される異例の展開に。現場には長さわずか1.4メートルのスリップ痕が2条残され、車両の破損状況との整合性が争点となった。
裁判所の判断
「本件事故は、B車が約30度の角度でセンターラインオーバーをし、A車走行車線上で衝突したものである」
東京地判平19・3・30(平成15年(ワ)20769号)
- B車の左サイドメンバーに前方からの力による3箇所の座屈を認定
- B車の左ランプレンズにA車の青色塗料付着を重視
- 物的証拠と整合性のない相手方鑑定書の信用性を否定
- A車の過失相殺を否定(回避不能性を考慮)
過失相殺
過失割合:A車0%、B車100%
鑑定の信用性は専門家の肩書きや鑑定書の分量ではなく、現場の物的証拠との論理的整合性で判断されます。
特に重要なのは、車両の微細な破損状況(塗料の付着、座屈の方向)が決定的な証拠となった点です。わずか1.4メートルのスリップ痕の詳細な分析により、車両の走行角度まで特定されています。
また、A車が「センターラインギリギリを走行」していたにもかかわらず過失相殺が否定された点も実務上重要です。裁判所は回避可能性の有無を重視し、「相手方の直前でのセンターラインオーバーは回避不能」と判断しました。
関連記事
・対向車が突っ込んできた事故の過失割合。センターオーバーによる正面衝突の対処法
⑥駐車場事故の過失割合の判例
立体駐車場で起きた事故の判例
東京地判平25・10・30(平成25年(ワ)第3244号)
立体駐車場3階で、バック駐車をしていた原告車に被告車が衝突。
被告は「停車していた」と主張したが、警察の物件事故報告書には「駐車するのを待たず、後ろにいた車が接触」と記載されていた。また、被告車は駐車区画をまたぐ位置にあり、通常の進行経路から逸脱していた。修理費26万円の負担割合が争点となった。
裁判所の判断
「駐車区画に進入しようとする車両の動静を注視して、その安全を確認すべき注意義務」に違反した
東京地判平25・10・30(平成25年(ワ)第3244号)
過失割合
原告0%:被告100%
決定的だったのは、警察が作成した物件事故報告書の記載内容です。この報告書は事故直後に当事者双方から聴取した内容をまとめた公文書であり、高い証拠価値が認められます。
交通事故では当事者の記憶や主張が時間とともに変化することがありますが、事故直後に作成された警察の報告書は、最も現場の状況に近い客観的証拠として極めて重要な価値を持つことを示した判例です。
関連記事
・駐車場事故の対処法!警察呼ばなかった時のリスクやコンビニ・スーパー等の事故判例
バイクの事故の過失割合の判例
①すり抜け事故の過失割合の判例
バイクの追い抜き事故における過失認定で車両の損傷状況が決定的な証拠となった判例です。
バイク追い抜き事故の過失認定
東京地判平31・1・30(平成29年(ワ)7064号)
信号待ちから発進した乗用車(トヨタ・アクア)とバイク(ハーレーダビッドソン)が接触。
乗用車は第1車線を直進、バイクは第2車線から追い抜こうとして接触したと主張。
一方、バイク側は「乗用車がウインカーなしで車線変更してきた」と反論。
バイク運転手(33歳美容師)は右手関節捻挫等で約5か月通院し、428万円の賠償を請求した。
裁判所の判断
「被告車が、原告車の右後方から原告車よりも高速で進行してきて、その右側を通過する際に接触して発生した」
東京地判平31・1・30(平成29年(ワ)7064号)
- 乗用車の右サイドミラーが前方に折れ曲がった損傷状況から後方からの衝撃と認定
- バイク側の車線変更説は車両損傷と整合しないとして否定
- 直進車には後方からの追い抜き車両への注意義務なし
過失割合
バイク100%:乗用車0%
裁判所は、乗用車の右サイドミラーが「正常な状態であれば曲がることのない前側に折れ曲がった」状況から、後方からの衝撃であることを科学的に判断しました。
追い抜きを行うバイクには、前方車両の動静に注意して安全に追い抜く義務があります。本件では信号発進直後という状況でしたが、直進車両には後方から追い抜く車両に対する特別な注意義務はないとして、乗用車側の過失を完全に否定しました。
関連記事
・バイクのすり抜け事故|過失割合や損害賠償請求の流れ、違反になるケースもわかる
②右直事故の過失割合の判例
右直事故で過失割合5:5となった裁判例
大阪地判平14・3・29(平成12年(ワ)13391号)
信号機のない見通しの悪い交差点で、普通乗用車が右折しようとした際、直進してきた原付(時速15キロ)が急ブレーキをかけて転倒した事故。
右折車は一時停止をしていたが「右方の安全確認が不十分」、直進原付は13メートル手前で相手車を発見したが「制動操作を誤った」として、双方の過失が争点となった。
裁判所の判断
「見通しの悪い交差点における双方の注意義務違反を認定」
大阪地判平14・3・29(平成12年(ワ)13391号)
- 右折車:右側安全確認不十分による過失を認定
- 直進原付:注意不足と制動操作ミスによる過失を認定
- 損害賠償:447万円(過失相殺後)
過失割合
右折車50%:直進バイク50%
一般的に右直事故では右折車の過失が重く見られがちですが、本件では5:5という対等な過失割合が認定されています。
信号機のない交差点での右直事故では、右折車の徐行・安全確認義務だけでなく、直進車両も見通しの悪い交差点への進入時には十分な注意義務があることがわかります。
関連記事
・右直事故の過失割合は?早回り右折など修正要素や10対0のケースも解説
③巻き込み事故の過失割合の判例
典型的な左折四輪車と直進二輪車の巻き込み事故における過失割合の認定基準を示す判例をご紹介します。
左折巻き込み事故の裁判例
東京地判平15・8・28(平成14年(レ)481号)
丁字路交差点で、会社代表者運転の普通乗用車が左折しようとした際、後方から直進してきた原付バイクと衝突した左折巻き込み事故。
四輪車側は交差点30メートル手前でウインカーを出したものの、左折動作開始前に二輪車を見失い安全確認を怠った。二輪車側も前方不注視で四輪車の左折合図を見落とし適切な回避行動を取らなかった。
裁判所の判断
「左折車両と直進車両との接触事故では左折車両の側に、四輪と二輪との接触事故では四輪の側に、それぞれより重い注意義務が課せられる」
東京地判平15・8・28(平成14年(レ)481号)
- 左折車は後続車の動静確認義務を最後まで怠ってはならない
- 直進二輪車にも前方注視義務と適切な回避義務がある
- 四輪車と二輪車の事故では四輪車により重い注意義務あり
過失割合
四輪車(左折車)60%、二輪車(直進車)40%
左折車には単にウインカーを出すだけでなく、左折動作完了まで継続して後続車の動静を確認する義務があります。一方で、直進二輪車側にも前方不注視の過失が認められており、四輪車側に重い責任があるとはいえ、二輪車側も一定の注意義務を負うことが示されています。
この6:4という過失割合は、類似の巻き込み事故における過失認定の重要な指標となっています。
関連記事
・巻き込み事故は内輪差が原因?事故の過失割合は?巻き込み事故の弁護士解説
歩行者の事故の過失割合の判例
①信号のある横断歩道での事故の判例
酩酊状態での横断歩道事故
大阪高判平26・8・29(平成26年(ネ)383号)
会社員女性(25歳)が深夜の懇親会後、血中アルコール濃度0.229%の酩酊状態で幅32.8メートルの6車線道路を横断中、時速60~65キロで走行してきたタクシーと車道東端から15.6メートルの地点で衝突。
女性は青信号で横断を開始したが、途中で赤信号に変わったにもかかわらず横断を続けており、歩行者と運転者双方の過失割合が争点となった。
裁判所の判断
「長距離横断歩道では青色表示で渡り始めても横断途中で赤色表示になることが容易に想定できる」
大阪高判平26・8・29(平成26年(ネ)383号)
- 運転者の過失:制限速度超過での漫然運転、手前30メートルで横断者を認識したのに減速せず
- 歩行者の過失:信号無視での横断継続、車両動静への注意義務違反、酩酊状態による判断力低下
過失割合
歩行者60%、タクシー40%
この判例では、途中で赤信号に変わった後の継続横断と酩酊状態という要素が重視され、歩行者に6割という高い過失割合が認定されました。
幅32.8メートルという長距離横断歩道では、青信号で開始しても途中で赤信号に変わることが容易に想定されるため、歩行者にはより高度な注意義務が課されることを示しています。
一方で運転者にも、通常の横断歩道以上に歩行者の有無を注意深く確認し、適宜減速する義務があることが確認されました。
関連記事
・横断歩道の事故の過失割合と慰謝料|歩行者と車の状況別に過失を解説
②信号のない横断歩道での事故の判例
信号機のない横断歩道やその付近で歩行者と車の事故が起きた場合、実務や判例では基本的に歩行者の過失は「0」と判断されます。
これは、車の運転者には「横断歩道に近づくときの徐行義務」や「歩行者がいる場合の一時停止義務」があるためです(道路交通法第38条1項)。このようなルールは、「横断歩道上の歩行者は優先的に保護されるべき存在である」という考え方に基づいています。
信号なし横断歩道で過失相殺0%
大阪地判平17・11・25(平成16年(ワ)13282号)
商店街の生活道路で夜間、12歳の少女が信号のない横断歩道を横断中、渋滞車両の左側を時速30kmで走行してきた原付バイクと衝突。
少女は頭部外傷で42日間入院し、事故後は記憶力低下や注意力散漫により一人で通学できない状態となった。
原付運転者は前照灯を点灯していたが、横断歩道を見落とし減速せずに進行、少女は渋滞車両の間を小走りで横断していた。原付運転者は歩行者の夜間横断や小走りを理由に過失相殺を主張した。
裁判所の判断
「被告の過失は著しく、夜間であることや原告が渋滞により停車している自動車の間を小走りに横断していたことを考慮しても、過失相殺をすることは相当ではない」
大阪地判平17・11・25(平成16年(ワ)13282号)
- 横断歩道の見落としと減速義務違反を重視
- 12歳という年齢と商店街という立地を考慮
過失割合
歩行者0%、原付運転者100%
一般的に歩行者側の過失として考慮される要因には、①夜間の横断、②急な飛び出し、③斜め横断、④横断禁止場所での横断などがあります。本件でも夜間であり、少女が小走りで横断していましたが、裁判所はこれらの事情を考慮してもなお過失相殺を否定しました。
重要な判断要因は、①車両側が横断歩道を見落とした重大な過失、②渋滞で見通しが悪い状況での減速義務違反、③被害者が12歳の児童であること、④現場が商店街の生活道路であることです。
特に児童の事故では、大人と同程度の注意義務を期待できないため、過失相殺が制限される傾向にあります。
過失割合の裁判例の調べ方について
裁判例は、実際の交渉や訴訟において重要な参考資料となります。より多くの、あるいはご自身の事故状況に近い裁判例をお探しの場合は、以下の方法があります 。
- 裁判所ウェブサイトの「裁判例検索」
一部ですが最高裁判所や下級裁判所の判決を検索できます 。 - 専門の判例集
「交通事故民事裁判例集」や「判例タイムズ」といった書籍には、実務上重要な裁判例が多数掲載されています。大きな図書館などで閲覧できる場合があります 。 - 法律専門家向けデータベース
弁護士などが利用する有料のデータベース(D1-Law.com、Westlaw Japanなど)では、より網羅的な判例検索が可能です 。
裁判例の調査は専門的な作業。弁護士に任せるのが安心です
実は自分に合った裁判例を見つけるのは専門的な知識と経験が必要な作業です。一般の方がインターネットや書籍だけで適切な判例を探し出すのは、かなり難しいのが実情です。
一見すると「自分のケースと似ている」と思える裁判例でも、細かい事実関係や争点が違えば、まったく参考にならないこともあります。事故の状況、過失の割合、ケガの程度、通院の頻度など、どれか一つが違うだけで結果が大きく変わることも珍しくありません。
こうした理由から、過失割合に納得がいかない場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
関連記事
・過失割合は弁護士の介入で変わる?理由や正しくない過失割合のリスク
保険会社の過失割合に納得できないときは
判例を基準に過失割合の交渉をする際のポイント
保険会社から提示された過失割合に納得できない場合、感情的に反論するだけでは話が進みません。判例タイムズという客観的な基準を元に、冷静に交渉を進めましょう。
【交渉の3ステップ】
- 保険会社の根拠を確認する
まず、「なぜこの過失割合になるのか、その根拠を教えてください」と具体的に質問しましょう。どの判例(事故類型)を参考にしているのかを確認します。 - 自分の主張と証拠を整理する
ご自身の事故に最も近い判例(基本割合)と、有利になる「修正要素」を整理します。ドライブレコーダーの映像、事故現場の写真、目撃者の証言など、客観的な証拠があればさらに強力です。 - 客観的な基準を元に交渉する
「判例タイムズの〇番の図によれば、基本割合はこうなっています。さらに、相手には脇見運転という著しい過失があったため、10%の修正がされるべきではないでしょうか」というように、具体的な根拠を示して交渉します。
関連記事
・交通事故の過失割合が納得いかない!おかしいと感じたら弁護士を通じて交渉を
交通事故に強い弁護士にお任せください
交通事故の過失割合について押さえておくべきポイントは、以下のとおりです。
過失割合のポイント
- 過失割合は「判例タイムズ」を基準に判断される
- 事故の類型ごとにおおよその「基本割合」が存在する
- 個別の事情(修正要素)によって割合は変動する
- 交渉は感情的にならず、客観的な根拠に基づいて行う
ご自身で過失割合を調べたり、保険会社とやり取りをすることも大切です。ですが、適切な裁判例を見つけたり、正確な過失割合を判断したりするには、専門的な知識と経験が必要です。ほんの少しの判断ミスが、最終的な賠償金額に大きく影響することもあります。
もし、保険会社から提示された過失割合に納得できない場合や、交渉がうまくいかないと感じる場合には、無理にご自身で対応しようとせず、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
経験豊富な弁護士であれば、あなたのケースに合った適切な裁判例を選び、保険会社との交渉も代わりに行ってくれます。多くの法律事務所では初回無料相談を実施しているため、まずは専門家の意見を聞いてみるのも一つの手です。
アトム法律事務所では、日本全国の交通事故の相談受付を24時間365日体制で行っています。交通事故でお困りの方はまずは一度お電話ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了


