赤信号停止中に追突され腰部挫傷14級を負った事例
弁護士に依頼後...
増額
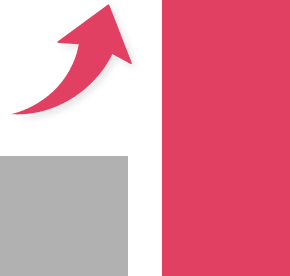
更新日:

交通事故の慰謝料は、原則として示談成立後から約2週間以内に振り込まれます。
事故発生から慰謝料振込までの流れと目安期間は、次の通りです。
ただし、事故の内容や治療の長期化、後遺障害の有無などによっても慰謝料をいつもらえるかは変わってきます。
「いつ支払われるのか」「今すぐ受け取る方法はないのか」と不安な方のために、本記事では慰謝料が支払われるまでの流れ・期間・対処法をわかりやすく解説します。
交通事故の慰謝料は、原則として示談成立後から約2週間以内に振り込まれます。
事故発生から慰謝料振込までの流れと目安期間は、次の通りです。
ただし、事故の内容や治療の長期化、後遺障害の有無などによっても慰謝料をいつもらえるかは変わってきます。
「いつ支払われるのか」「今すぐ受け取る方法はないのか」と不安な方のために、本記事では慰謝料が支払われるまでの流れ・期間・対処法をわかりやすく解説します。
目次
まずは、交通事故の慰謝料はいつもらえるのか、タイミングともらえるまでの期間について解説します。
交通事故示談から、慰謝料支払いまでの期間は一般的に約1~2週間程度が目安です。
交通事故の慰謝料がもらえるのは、示談が成立して示談書に署名・捺印をしたあと、加害者側の保険会社での手続きが完了したタイミングです。
具体的な支払いのタイミングは、示談成立から約2週間後が一般的で、早ければ1週間以内に振り込まれることもあります。
交通事故で慰謝料がもらえるのは示談成立から1~2週間後ですが、事故発生から考えたときに慰謝料振込までどれくらいの期間がかかるのかは、実際の通院期間などによっても異なります。
傾向として、通院期間が長いほど慰謝料や賠償金は高額化しやすく、示談交渉で揉める可能性が高くなります。その分、示談交渉にかかる期間が長くなり、慰謝料振込が遅くなりやすいでしょう。
通院期間から予想される、事故から慰謝料支払いまでの大まかな期間は次の通りです。
| 通院期間 | |
|---|---|
| 1ヶ月程度 | 事故から示談成立、慰謝料振込まで約2〜3か月なることが多い 【想定されるケース】打撲などの軽傷 |
| 2〜3ヶ月程度 | 事故から示談成立までは約3〜5か月、支払い完了まで含めると6か月程度が目安 【想定されるケース】むちうちなど |
| 通院半年以上 | 事故発生から示談成立・慰謝料の振込まで、1年超かかるケースもある 【想定されるケース】骨折や、手術が必要なケガ。後遺障害が残る症状など |
【コラム】死亡事故の場合、慰謝料の支払い時期は?
死亡事故では慰謝料の金額が高額になりやすいため、示談成立までに時間がかかる傾向があり、事故から支払いまで半年〜1年ほど要するケースもあります。
示談が成立したあとから数えると、通常と同様に1〜2週間以内に指定口座へ振り込まれるのが一般的です。
なお、死亡事故の場合、示談交渉は遺族と保険会社の間で行われます。多くの場合、葬儀や四十九日法要を終えてから交渉が始まります。
交通事故の発生から慰謝料支払いまでの基本的な流れは以下のとおりです。
それぞれのフェーズについて解説します。
目安期間
事故発生直後〜当日中に対応。
交通事故が起きたら、まずは警察への届け出が必要です。
警察は「交通事故証明書」を発行しますが、これは後の保険請求や慰謝料請求に欠かせない書類となります。
警察への連絡は道路交通法上の義務でもあるため、もしまだ警察に届け出ていないなら、後日になっていてもよいので届け出ましょう。
関連記事
交通事故後は警察への報告義務あり|報告・届け出をしないデメリット
目安期間
症状により、通院期間は1ヶ月〜1年超まで幅がある。
打撲・むちうち・骨折の目安は以下の通り。
事故後は、医療機関で診察を受け、必要な治療を継続することになります。
目安は上記表のとおりですが、あくまでも目安なので、実際には医師と相談しながら治療を進めましょう。
なお、通院回数や治療期間は、慰謝料の金額に大きく影響する重要な要素です。
途中で治療をやめると慰謝料が減額される可能性があるので、必ず医師から治癒(完治)または症状固定(後遺症が残った)と診断されるまで通院しましょう。
症状固定の定義やタイミングについては『症状固定とは?時期や症状固定と言われたらすべき後遺障害認定と示談』
慰謝料の1つ、入通院慰謝料の金額は、通院期間に大きく影響されます。
例えば軽傷で通院1ヶ月なら慰謝料は19万円ですが、3ヶ月なら53万円です(弁護士基準)。
通院期間が短くなれば、その分入通院慰謝料が少なくなります。
また、後遺症が残ったとしても、通院を途中でやめていると、後遺障害認定されない可能性が高くなります。その結果、後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できないリスクがあるでしょう。
こうした点でも、時間がかかっても治療は最後まで継続することが重要です。
ただし、通院頻度が低すぎたり、無理に通院を長引かせたりした場合は慰謝料が減額されることがあります。あくまでも医師の指示に従い、医学的根拠のある頻度・期間で通院しましょう。
関連記事
交通事故の被害者は毎日通院した方がいい?通院頻度や期間と慰謝料の関係
目安期間
申請準備に約1ヶ月、審査から承認まで1〜2ヶ月程度。
全体ではおおよそ3ヶ月ほどかかるのが一般的。
ケガが完治せずに症状固定となり後遺症が残ったら、後遺障害認定を受けます。後遺障害認定は、「後遺障害慰謝料」「逸失利益」を請求するために必要です。
後遺障害認定では、申請準備に1ヶ月程度、審査に1〜2ヶ月程度かかります。つまり、トータルでは3ヶ月程度かかるということです。
後遺障害認定の審査にかかる期間(2023年度統計)
| 期間 | 割合 |
|---|---|
| 30日以内 | 72.2% |
| 31日~60日 | 14.7% |
| 61日~90日 | 7.0% |
| 90日超 | 6.1% |
参考:損害保険料率算出機構「2024年度 自動車保険の概況」より
ただし、高次脳機能障害など重い後遺症では経過観察などを挟むこともあり、審査結果が出るまでに数ヶ月〜数年かかることもあります。
関連記事
後遺障害認定の通知書はいつ届く?非該当への対応や等級認定後の流れ
目安期間
事実関係に争いがなく、金額のみを調整する場合は2〜3ヶ月程度で示談が成立することが多い。
ただし、過失割合などで争いがある場合は、さらに長期化する可能性がある。
示談交渉は、ケガが完治した場合は治療終了後、後遺症が残ったときには後遺障害等級認定の結果を受けてから、開始します。死亡事故の場合は四十九日を過ぎた頃に示談を開始しましょう。
示談成立までにかかる期間は、事実関係に争いがなく、金額のみを争うケースであれば2~3ヶ月程度となるケースが多いです。
一方、事実関係に争いがあり、過失割合も争点になるケースでは、示談交渉の期間が長引く可能性が高くなるでしょう。
示談は一度成立すると、原則として撤回や再交渉、追加の賠償請求ができません。
たとえ時間がかかったとしても、納得のいく結果になるよう交渉することが重要です。交渉をスムーズに進めつつ、納得のいく結果にしたい場合は、弁護士を立てることも検討してみてください。
関連記事
目安期間
示談成立から慰謝料振込までは、以下の流れでトータル2週間ほど
交通事故の慰謝料は、法的には相手ドライバーが支払うことになります。
しかし、ドライバーの多くは保険に加入していることから、実質的には相手の加入する保険会社が慰謝料を支払うことになるのが一般的です。
交通事故の示談金は、通常、示談成立・書類提出(免責証書への署名・捺印)から、約1~2週間後(3営業日~2週間程度)で、保険会社から指定口座へ振り込まれます。
慰謝料・賠償金が高額になったとしても、基本的には示談成立から1~2週間ほどで振り込まれます。ただし、振込み手続きの都合により、一括入金ではなく2件に分けて入金される場合もあります。
保険会社に示談書を返送してから1週間が経過しても慰謝料が支払われない場合、保険会社の支払い手続きが遅れている可能性があります。
保険会社に連絡をして支払い日を確認するようにしましょう。
まれに口座情報の記入ミスや名義の不一致などが原因で振込が保留になることもあるため、提出書類も念のため見直しておくと安心です。
なお、相手方が保険会社ではなく加害者側の弁護士だった場合、加害者本人・保険会社・弁護士の間で連携が必要になること等の理由から遅くなりがちです。このような場合、示談成立から慰謝料・賠償金の支払いまでの期間が、約3週間から1か月以内が目途になるでしょう。
交通事故の発生から慰謝料の支払いを受けるまでには、後遺障害等級認定の申請をする場合なら1年以上かかることも珍しくありません。
しかし、示談成立前でも慰謝料などまとまったお金を受け取ることは可能です。具体的には以下の方法があるので、それぞれ見ていきましょう。
| 方法 | 入金までの目安 | 申請のしやすさ |
|---|---|---|
| 仮渡金の請求 | 約1週間 | 条件に合えば支払いが早い |
| 被害者請求 | 約1ヶ月 | 書類がやや多め |
| 内払い | 数日~数週間 | 加害者側の保険会社との交渉次第 |
| 任意一括対応 | 即日以降* | 対応してもらえないケースもある |
| 人身傷害保険 | 2~4週間 | 自身の保険なのでスムーズ |
| 搭乗者傷害保険 | 1~2週間 | 自身の保険なのでスムーズ |
*加害者側の任意保険会社が治療費を病院に直接支払ってくれるサービスで、被害者の口座に直接入金があるわけではない。
自賠責保険から慰謝料を受け取る方法は、「仮渡金の支払いを請求する」「被害者請求する」の2つです。
仮渡金(かりわたしきん)とは、傷害の程度に応じた金額を、示談成立前に受け取れる制度です。
| 仮渡金の金額 | 傷害の程度 |
|---|---|
| 40万円 | ・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの ・上腕または前腕の骨折で、合併症を有するもの ・大腿または下腿の骨折 ・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの ・14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの |
| 20万円 | ・脊柱の骨折 ・上腕または前腕の骨折 ・内臓の破裂 ・病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの ・14日以上病院に入院することを要する傷害 |
| 5万円 | ・11日以上医師の治療を要する傷害を受けたもの |
* 参考:自動車損害賠償保障法施行令第五条
* 死亡事故の場合は290万円
仮渡金を受け取ると、示談成立後にはその金額を差し引いた金額が支払われます。示談金より仮渡金が高額だった場合は、差額を返さなければなりません。
なお、仮渡金を請求すれば、およそ1週間程度で支払いを受けられます。仮渡金は1回しか請求できません。
被害者請求とは、交通事故の慰謝料・賠償金のうち、加害者側の自賠責保険分の金額を請求する方法です。
通常、自賠責保険分の金額は示談成立後、任意保険分の金額とともに加害者側の任意保険会社からまとめて支払われます。
しかし、自賠責保険に直接請求すれば、自賠責保険分のみ先に受け取れるのです。
被害者請求では、以下の金額を上限として「自賠責基準」に基づいて計算される金額を請求できます。上限に達するまでなら何度でも請求可能です。
| 上限 | |
|---|---|
| 傷害分 (入通院慰謝料・治療費など) | 120万円 |
| 後遺障害分 (後遺障害慰謝料など) | 75万円~4,000万円* |
| 死亡分 (死亡慰謝料など) | 3,000万円 |
*後遺障害等級による
たとえば、入通院慰謝料は以下のうち少ない方の金額を請求できます。
※2020年3月31日までに起きた事故については1日あたり4,200円で計算します。
※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。
被害者請求の申請から支払いまでの期間は、およそ1ヶ月程度です。
ただし、この後解説する任意保険会社の一括対応中に被害者請求をすると、一括対応をしてもらえなくなる点には注意する必要があります。
被害者請求で支払われる金額や手続きの方法は、『交通事故慰謝料が120万を超えたらどうなる?自賠責保険の限度額や請求方法を解説』の記事をご確認ください。
加害者側の任意保険から受け取る方法としては、「損害賠償金の内払いをしてもらう」「治療費を一括対応してもらう」の2つです。
任意保険会社との交渉次第では、示談成立前に一部の慰謝料や損害賠償金を支払ってもらえる可能性があります。
この任意保険会社の対応を「損害賠償金の内払い」といいます。
特に、通院交通費や休業損害などは示談成立前の生活にも関わる費目なので、内払いに応じてもらえる可能性が比較的高いです。
一方、精神的損害に対する補償である慰謝料の内払いは、すぐ対応してもらえない可能性が高いです。
慰謝料の内払いを受けたい場合は、なぜそのお金が必要かを丁寧に任意保険会社に説明する必要があります。
注意点
加害者側に内払い請求をすると、相手に金銭的な余裕がないことを知られてしまいます。
そうすると、加害者側は「被害者側は早くまとまったお金が必要だから、低い慰謝料額でも示談成立を優先させるだろう」と考える可能性があります。
その結果、示談交渉の際、加害者側は低い提示額で強気の交渉をしてくることがあるのです。
そのため、示談成立前の時点で必要以上に加害者側へ請求することは控えるべきでしょう。
任意一括対応とは、治療の際、加害者側の任意保険会社が病院に直接治療費を支払ってくれるサービスです。
これにより被害者は治療費を立て替える必要がなくなります。本来なら示談交渉時に請求する治療費を、示談成立前に補償してもらえると考えてください。
治療費を一括対応してもらうための手続きは以下のとおりです。
一括対応の手続き
ただし、任意保険会社の一括対応は、あくまで任意保険会社のサービスの一つです。以下のような場合には治療費の一括対応を受けられません。
また、治療中であっても任意一括対応を打ち切られてしまう(治療費打ち切り)ことがあります。この場合は、治療費を立て替えつつ最後まで治療を継続しましょう。
治療費打ち切りへの詳しい対処法については『交通事故で治療費打ち切りの連絡が保険会社から来た!阻止するための対応方法』の記事をご覧ください。
被害者側の任意保険を使い、示談成立前に慰謝料同等の保険金を得ることもできます。それが、人身傷害保険です。
また、搭乗者傷害保険も役に立つので合わせて解説していきます。
人身傷害保険とは、示談成立前でも治療費や慰謝料などを保険金として受け取れる保険です。
ただし、支払われるのはあくまでも、自身の保険会社が自社基準に従い算定した金額です。
また、あとで加害者側から受け取る慰謝料・示談金と相殺される点にご注意ください。
交通事故では被害者側にも過失がある場合、その過失分、受け取れる慰謝料や示談金が減額されます。これを過失相殺と言います。
しかし、人身傷害保険金として受け取る慰謝料などには過失相殺は適用されません。自身の過失が大きい場合にも活用することがおすすめです。
過失相殺については『過失相殺とは?計算方法や交通事故の判例でわかりやすく解説』の記事が参考になります。
被害者やその家族が加入している自動車保険に搭乗者傷害保険が付いている場合、より早期に保険金を受け取れる可能性があります。
搭乗者傷害保険とは、あらかじめ契約で定められた症状や部位に応じて、定額の金額が支払われる保険です。
搭乗者傷害保険は損害賠償額の計算が不要なため、人身傷害保険よりも素早く支払いを受けられるのがポイントになります。
保険会社によっても異なりますが、治療期間(入通院の合計日数)が5日以上を経過した時点で、症状や部位に応じて搭乗者傷害保険の保険金を請求できるケースが多いです。
人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いをもっと詳しく知りたい場合は、『人身傷害補償特約は必要?いらない?補償内容や他の保険との違いとは』の関連記事をご覧ください。
以下のようなケースでは、慰謝料の支払いが遅くなる可能性があります。
こうしたケースにおける対策や対処法を確認していきましょう。
示談交渉で加害者側と揉めた場合、示談成立が遅くなるため慰謝料の振り込みも遅れます。
示談交渉で揉めやすいケースは、以下のようなものです。
示談をスムーズに進めるための対策としては、弁護士を立てることがおすすめです。
自力で示談交渉すると、示談成立が遅くなるだけでなく、加害者側が提示する低い慰謝料額・示談金額で合意せざるを得なくなることが多いです。
被害者側の立場が不利になる前に弁護士に相談することをおすすめします。
関連記事『交通事故の示談が長引く原因5つ&対処法』では、示談が長引く理由やその対処法について、より深く掘り下げて解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
交通事故の示談には時効はありません。しかし、加害者側に損害賠償請求できる期間には時効があります。
損害賠償請求権の消滅時効
(2017年4月1日以降に発生した交通事故の場合)
| 損害の種類 | 時効期間 |
|---|---|
| 物損に関する損害 | 事故発生日の翌日から3年 |
| 人身に関する損害 (後遺障害による損害以外) | 事故発生日の翌日から5年 |
| 人身に関する損害 (後遺障害による損害) | 症状固定日の翌日から5年 |
| 人身に関する損害 (死亡による損害) | 死亡した日の翌日から5年 |
| 加害者不明の損害※ | 事故発生日の翌日から20年 |
※2017年3月31日以前に発生した交通事故にも適用される場合がある。
※※加害者が判明した場合は、判明した日の翌日を起算日とし、物損部分は3年、人身部分は5年で時効となる。
なお、自身の任意保険や加害者の自賠責保険に対する請求は、上記の表にかかわらず起算日から3年で時効となります。
特に大きな問題もなく治療や示談交渉が進んだのであれば、時効はそれほど気にするものではありません。
ただし、状況によっては時効が近づいていることもあり、時効を延長すべきケースもあるでしょう。時効の延長方法については、関連記事『交通事故の示談に期限はある?時効期間と時効の延長方法』をご覧ください。
加害者が任意保険に入っていない場合、本来なら任意保険から支払われる金額は加害者本人に請求しなければなりません。
この場合、加害者本人からの支払いが分割になったり、踏み倒されたりして回収が遅れる可能性があります。
自身の保険を活用して対応したり、示談書を公正証書にして踏み倒しに備えたりすることが必要です。
詳しくは『交通事故の相手が無保険でお金もない?泣き寝入りしないための賠償請求・対策法』の記事をご覧ください。
示談交渉で合意ができず決裂してしまった場合、解決による慰謝料振込までの期間には、裁判に要する期間がさらに加わります。
裁判所の公表資料によると、交通損害賠償の平均審理期間は13.3ヶ月です。
つまり、裁判になってしまうと、裁判だけでも1年以上、交通事故の発生から慰謝料の支払いまでをカウントすると2年以上の期間を要する可能性が高いといえます。
交通事故裁判の審理期間(第一審)
| 期間 | 割合 |
|---|---|
| 6月以内 | 21.2% |
| 6月超1年以内 | 41.9% |
| 1年超2年以内 | 30.3% |
| 2年超3年以内 | 5.0% |
| 3年超5年以内 | 1.4% |
| 5年を超える | 0.2% |
参考:「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」(最高裁判所・令和6年)【資料2-1-2】より
裁判による長期化を防ぐためには、示談交渉により解決を図る必要があります。
適切な示談交渉を行うためには、弁護士に依頼して示談交渉を行ってもらうことをおすすめします。
交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害関連の慰謝料を受け取るためには後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
後遺障害認定の結果が出るまで、交通事故の損害賠償金額を把握できないため、示談交渉を始められません。
そのため、慰謝料の支払いが遅くなるのです。
『2022年度自動車保険の概況』(損害保険料率算出機構)によると、後遺障害認定の審査にかかる期間は「60日以内」が約88%です。
しかし、高次脳機能障害のような経過観察が必要な症状であるケースや、認定結果に納得がいかず異議申し立てをするケースでは、後遺障害認定に時間がかかりやすいでしょう。
続いて、交通事故の慰謝料の支払いに関してよくある、以下の質問にお答えします。
原則として、慰謝料は被害者本人名義の銀行口座に振込まれます。
ただし、未成年者や高齢者などの事情がある場合は、家族名義など本人以外の口座に振り込まれるケースもあります。
また、弁護士を立てて示談交渉した場合は、まず法律事務所の口座に慰謝料が振り込まれ、そこから弁護士費用を差し引いた金額が被害者の口座に振り込まれることが多いです。
基本的に、交通事故の慰謝料は示談成立後に一括で支払われるのが一般的です。
保険会社が対応する場合は、示談書に記載された金額がまとめて指定口座に振り込まれます。
ただし、加害者が任意保険に未加入で、自己負担で支払う場合などには、被害者との合意のうえで分割払いが選ばれることもあります。
その場合でも、分割回数・金額・支払日を明確に記載した示談書の作成が必要です。
支払いが滞った場合に備えて、弁護士に相談しておくと安心です。
基本的には、示談が成立して慰謝料が支払われた後に追加で請求はできません。
示談書には「これ以上請求しない」旨の条項(清算条項)が盛り込まれるのが一般的なためです。
ただし、示談時に含まれていなかった損害が後から判明した場合など、例外的に追加請求できる可能性もあります。
加害者本人に支払い能力がない場合でも、基本的には加害者が加入する任意保険や自賠責保険から慰謝料が支払われます。
特に自賠責保険は強制加入であるため、少なくとも自賠責保険からは、一定額の慰謝料を受け取れることが多いでしょう。
一方、任意保険への加入は強制ではないため、加害者が任意保険に入っていない可能性はあります。
この場合、自賠責保険からの支払いだけでは足りない分は加害者本人に請求します。加害者に支払い能力がない場合は、支払いが分割になったり踏み倒されたりするリスクがあるでしょう。
自身の保険を活用したり、弁護士に相談したりといった対応が必要です。
弁護士に相談・依頼すると、慰謝料の早期の支払いや慰謝料額の増額などのメリットが生じます。
しかし、弁護士費用が気になる、弁護士に依頼する決め手にかけると考えている人もいるのではないでしょうか。
そこで最後に、弁護士に依頼するメリットや弁護士費用の負担を軽減する方法について紹介します。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットが生じます。
それぞれのメリットについて解説していきます。
弁護士に相談・依頼をすることで、示談交渉がスムーズに進み、慰謝料等を早期に支払ってもらいやすくなるのです。
弁護士に依頼すると示談交渉を弁護士が行ってくれます。
弁護士が専門知識に基づいて、適切な主張をもとに示談交渉を行ってくれるので、交渉自体がスムーズに進みやすくなるでしょう。
また、弁護士からの主張であることから、加害者側も受け入れる可能性が高いので、早期に示談交渉が終了し、慰謝料等が示談金として支払われることになりやすいのです。
弁護士に相談・依頼を行うことで相場に近い慰謝料額で示談できる可能性が高まります。
慰謝料相場は、以下の3種類の計算基準のうちどれを適用するかにより大きく異なります。
任意保険会社は少しでも支払う金額を抑えようと示談交渉を行います。
そのため、任意保険基準で計算した慰謝料額は、相場額より低額であることが大半です。
弁護士基準は過去の裁判例を基に作成された基準であり、弁護士基準で計算した慰謝料相場は最も高額かつ相場の金額となります。
示談交渉において、被害者自身が弁護士基準によって計算された額について慰謝料請求を行っても、加害者側は根拠に欠けるなどとして、簡単には請求に応じてくれません。
しかし、弁護士に依頼すれば、法的根拠のある請求であるとして弁護士基準で計算した高額の請求に加害者側も応じてくれやすくなります。
その結果、支払いを受けられる金額を大幅に増やすことができるのです。
慰謝料の相場は治療期間やケガの程度によって異なるので、一人ずつ異なります。もっとも、他の人が実際どのくらいもらったのか参考にすることも大事です。詳しくは『交通事故で慰謝料はいくらもらった?事例や相場から増額のポイントまで解説』の記事をご覧ください。
また、ご自分のケースで弁護士基準の慰謝料相場がいくらになるかを知りたい方は、以下の慰謝料計算機をご利用ください。
慰謝料相場や増額ポイントの記事
弁護士に依頼すれば、認定に有利に働く証拠や意見書などを添付して後遺障害等級認定の申請手続きをすることができます。
その結果、適切な後遺障害等級に認定される可能性が高まるのです。
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級によって慰謝料相場が決まります。
適切な後遺障害等級に認定されることは、慰謝料の増額につながるのです。
過失割合の知識が豊富な弁護士に依頼すれば、妥当な過失割合で示談できます。
交通事故で被害者が支払いを受けられる金額は、過失割合によっても大きく違いがあります。
被害者が支払いを受けられる金額は、損害額から被害者の過失割合分を減額した金額だからです。
加害者側の任意保険会社は、支払う慰謝料などを減額するために、被害者側に不利な過失割合を提示してくることが少なくありません。
弁護士に依頼すれば、妥当な過失割合になるよう示談交渉を行ってもらえます。
その結果、支払いを受けられる金額が増える可能性があるのです。
「弁護士に相談・依頼して相場の慰謝料を受け取りたいけれど、費用が心配」という方は、弁護士費用特約が使えるか確認してみましょう。
自分や家族の保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を自分で負担しなくてよい可能性があります。
弁護士費用特約
交通事故で相手方に損害賠償請求するため弁護士に相談・依頼した対価として支払う費用を保険会社が負担してくれる保険の一内容
弁護士費用特約を使えば、多くのケースで相談料は10万円、依頼による費用は300万円まで保険会社に負担してもらえます。
相談料や依頼による費用が上限額を超えることは、最終的な慰謝料などが数千万円を超えない限り非常に少ないです。
弁護士費用特約を使うことで、弁護士費用の自己負担をなしにできる可能性が非常に高いといえるでしょう。
弁護士費用特約がなかったとしても、無料相談を実施していたり着手金を無料としていたりする法律事務所であれば費用の負担を軽減できます。
また、弁護士を立てると、慰謝料・賠償金の増額が期待できます。たとえ弁護士費用特約が使えなくても、弁護士を立てた方が結果的に手元に入るお金が多くなることは珍しくありません。
交通事故による怪我の治療を受けながら、いつ慰謝料や損害賠償金を受け取れるのか分からず不安な日々を過ごしているのなら、弁護士に今すぐ相談しましょう。
早めに弁護士に相談しておけば、当面の生活に困らないように慰謝料を早めに受け取る方法などのアドバイスがもらえます。
いつ慰謝料が支払われるのか知りたいなら、アトム法律事務所の弁護士による無料の法律相談を受けてみましょう。
無料相談の予約受付は24時間365日いつでも対応中です。
お問い合わせいただくと、まずは専属スタッフが事故内容をヒアリングさせていただいています。気軽にお問い合わせください。
ここからは、アトム法律事務所が取り扱った解決事例の一部を、プライバシーに配慮したかたちで、ご紹介します。
交通事故により腰部挫傷等の傷害を負い、後遺障害14級9号が認定された事案です。
総治療期間は、271日間(約9ヶ月)でした。
弁護士の示談交渉により、相手方の提示額から約98円増額し、最終的に300万円の支払いを受けることができました。
交通事故により左肩骨折等の傷害を負い、4ヶ月間の入院を余儀なくされた事案です。
総治療日数は514日でした。
弁護士が「被害者請求」をおこない、後遺障害12級13号の認定を獲得しました。自賠責保険金224万円の支払いを受けることができました。
また、保険会社との粘り強い示談で、1,400万円の賠償金の支払いを受けることもできました。保険会社の提示額から約978万円の大幅増額となりました。
交通事故により頸椎脱臼骨折で92日間入院し、頚部の手術を2回、カテーテル手術を1回受け、頭蓋骨にハローベストを3ヶ月装着した事案です。
被害者は、後遺障害併合7級の認定を受けました。
弁護士の粘り強い交渉により、保険会社の提示額から約1,409万円増額し、最終的に3,600万円の賠償金の支払いを受けることができました。
アトム法律事務所では、これまで数多くの交通事故事案を解決に導いてきました。
交通事故の慰謝料がもらえるのは、軽傷なら事故から最短1ヶ月、重症なら1年半以上かかることも多いです。この長い期間、ご自身だけで保険会社とやり取りを続けるのは、精神的にも大きな負担となります。
「自分の場合はいつ頃もらえるのか?」と不安に思われたら、まずは無料相談で現在の状況をお聞かせください。
【まとめ】交通事故の慰謝料はいつもらえる?
| 状況 | 振込までの期間(目安) |
|---|---|
| 示談成立から | 1〜2週間以内 |
| 事故から(打撲) | 約2〜3ヶ月程度 |
| 事故から(むちうち) | 約6ヶ月程度 |
| 事故から(重傷) | 1年以上 |
| 最短でほしい時 | 仮渡金請求(最短1週間) |
納得のいく金額を、適切なタイミングで受け取るためには、早めの準備と専門的な知識が欠かせません。一人で悩まず、アトム法律事務所の無料法律相談をぜひご活用ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。




