追突事故の慰謝料はいくらが相場?示談金の計算方法と損しないポイント

「信号待ちをしていたら、後ろから追突されてしまった」
このような追突事故では、「過失がないから十分な慰謝料や示談金を受け取れるだろう」と考えるのが普通です。
実際、追突事故で多いむちうちの場合、入通院慰謝料の目安は通院3ヶ月で約53万円、6ヶ月で約89万円になります。
さらに後遺障害14級9号が認定されれば後遺障害慰謝料は約110万円、12級13号なら約290万円が目安です。
ところが、保険会社が最初に提示する金額は、相場の金額より低いことがほとんどです。
慰謝料は計算方法によって大きく差が出る上、通院期間や症状の経過、後遺障害の有無でも金額が増減するため、何も知らずに示談すると相場より低い金額でまとまってしまうことがあります。
この記事では、追突事故で請求できる慰謝料の種類や計算方法、相場の考え方、示談で損をしないためのポイントをわかりやすく解説します。
▼すぐに大まかな慰謝料相場が知りたい場合は、計算機をご活用ください。
目次
追突事故で請求できる3種類の慰謝料
追突事故で請求できる慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。

追突事故はむちうちなどで通院のみとなるケースが多いため、3つのうち「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2つを中心に見ていきましょう。
(1)入通院慰謝料
入通院慰謝料は、治療のために入院・通院したことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。
金額は通院期間や実通院日数などをもとに算定されます。
追突事故では入院を伴わず通院のみとなることが多く、例えばむちうちで3ヶ月通院なら約53万円、6ヶ月通院なら約89万円がひとつの目安です。
関連記事
交通事故の慰謝料は通院1日いくら?8600円より増額する方法と通院6ヶ月の相場
(2)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、治療を続けても完治せず後遺症が残り、後遺障害に認定された場合に請求できる慰謝料です。
後遺症の内容に応じて認定された後遺障害等級(1級〜14級)ごとの金額が受け取れます。
追突事故では、むちうちによる神経症状として14級9号または12級13号が認定されるケースも見られ、14級で約110万円、12級で約290万円が目安になります。
後遺障害慰謝料は入通院慰謝料とは別に請求できるため、認定の有無で慰謝料総額が大きく変わります。
関連記事
後遺障害慰謝料の相場はいくら?いつ支払い?後遺障害等級認定と賠償金額のすべて
(3)死亡慰謝料
死亡慰謝料は、被害者が死亡した場合に遺族(配偶者・子・父母など)が請求できる慰謝料で、目安は2,000万円〜2,800万円程度です。
追突事故で死亡に至るケースは多くありませんが、高速道路での追突や玉突き事故など重大事故では起こり得ます。
死亡慰謝料についての詳細は『死亡事故の慰謝料・賠償金の相場や平均は?示談の流れや保険金も解説』をご確認ください。
【注目】物損事故(ケガ無し)の場合は原則として慰謝料請求できない
慰謝料は、事故によって生じた精神的苦痛に対する補償です。
そのため、ケガがない物損事故の場合は、精神的苦痛が「壊れた物の賠償(修理・買替えなど)」によって回復されるという考え方から、原則として慰謝料は請求できません。
ただし、事故による車の修理費用や代車費用などの実費は請求できることがあります。ケガがない物損事故の補償については、以下の記事も参考にしてください。
関連記事
物損事故の賠償金とは?請求できるものや金額の決め方・交渉ポイントを解説
追突事故における慰謝料の計算方法|金額はどう変わる?
追突事故の慰謝料は、状況に応じて受け取れる金額が大きく変わることがあります。
受け取れる慰謝料の金額に影響するのは、主に次の3つです。
- 計算方法(自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準)
- 過失割合
- ケガの程度(通院期間・後遺障害の有無)
保険会社から提示された金額が妥当か判断するためにも、どの要素で増減するのかを押さえておきましょう。
追突事故の慰謝料には3つの計算方法がある
追突事故に限らず、交通事故の慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの金額基準があり、それぞれで計算方法が異なります。
慰謝料の3種類の算定基準
| 自賠責基準 | 交通事故の被害者に補償される、最低限の金額を算定する基準 自動車損害賠償保障法によって定められている (関連記事:自賠責保険の補償内容や慰謝料計算) |
| 任意保険基準 | 加害者側の任意保険会社が用いる算定基準 各任意保険会社が独自で定めており、公開されていないが、一般的に自賠責基準と同程度〜やや高い金額帯 |
| 弁護士基準 | 弁護士や裁判所が用いる算定基準 裁判基準とも呼ばれ、過去の判例をもとにしている (関連記事:交通事故慰謝料の弁護士基準(裁判基準)とは?) |

3つの基準の中でもっとも高額かつ法的に正当と言えるのは、過去の判例をもとにした「弁護士基準」の金額です。
一方、最低限の金額を算定する自賠責基準では、入通院慰謝料は「日額4,300円×対象日数」で算定され、対象日数は以下のうち少ない方が採用されます。
- 治療期間(初診~完治または症状固定まで)
- 実通院日数×2
加害者側の任意保険会社は「自賠責基準」や「任意保険基準」で計算した慰謝料額を提示してくることが多く、弁護士基準の半分~3分の1程度になっているケースもあります。
むちうちで通院3ヶ月した場合の慰謝料差(例)
追突事故で多い「むちうち」を例に、通院3ヶ月(90日)の入通院慰謝料を比べると、次のように金額差が出ます。
| 計算基準 | 入通院慰謝料(通院3ヶ月の目安) |
|---|---|
| 自賠責基準 | 最大38万7000円 |
| 弁護士基準 | 約53万円 |
このように、同じ通院期間でも基準が違うだけで10万円以上の差が出ることがあります。
保険会社の提示額が妥当か判断するためにも、まずは「どの基準で計算されているのか」を意識して確認することが大切です。
過失割合によって慰謝料金額が大きく変わる
加害者との示談交渉では、過失割合が争点になりやすいポイントのひとつです。
追突事故は基本的に被害者の過失がつきにくく「10:0」になりやすい一方で、状況によっては被害者側にも一定の過失があると判断されるケースがあります。
過失割合が「10:0」から「9:1」「8:2」などに変わると、慰謝料を含む損害賠償金はその割合に応じて減額(過失相殺)されます。
つまり、過失割合が不利になるほど、受け取れる金額は目減りしてしまうということです。
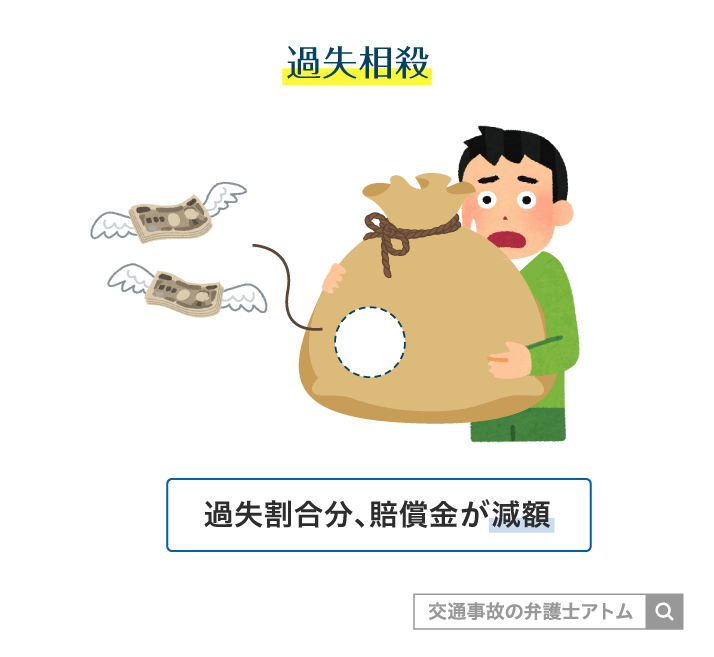
保険会社の提示に納得できない場合は、事故状況(ドラレコ映像・現場写真・衝突態様など)も踏まえて慎重に確認しましょう。
追突事故の過失割合について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
ケガの程度や後遺障害の有無によって慰謝料金額が大きく変わる
追突事故の入通院慰謝料は、通院した期間や実通院日数によって増減します。
さらに治療を続けても症状が残り、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も請求できます。
この慰謝料は入通院慰謝料とは別に請求できるため、受け取れる金額が大きく変わる可能性があります。
「自分の状況だとどのくらいの慰謝料が見込めるのか知りたい」という方は、以下の計算機で簡単に目安をシミュレーションできます。
追突事故における慰謝料相場
追突事故の慰謝料は、ケガの程度や通院期間、後遺障害の有無によって大きく変わります。
特に追突事故では、むちうちなどで通院のみとなるケースが多いため、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の相場感を把握しておくとよいでしょう。
入通院慰謝料の相場|通院3ヶ月で約53万円、6ヶ月で約89万円
追突事故で多いむちうち(軽傷)の場合、弁護士基準の入通院慰謝料は通院期間に応じて次のような相場が目安になります。
- 通院3ヶ月:約53万円(弁護士基準)
- 通院6ヶ月:約89万円(弁護士基準)
一方、自賠責基準は「日額×対象日数」で計算されるため、実通院日数によって金額が変動する点に注意が必要です。
通院3ヶ月・6ヶ月の目安を基準別に比較すると、次のとおりです。
| 計算基準 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 通院3ヶ月 | 最大38万7000円 | 約53万円 |
| 通院6ヶ月 | 約77万4000円 | 約89万円 |
※自賠責基準は実通院日数によって変動する場合があります。
弁護士基準の相場は、通院期間に応じた算定表(軽傷・重傷)を用いて確認します。
追突事故ではむちうちなど比較的軽いケガが多いため、基本的には「軽傷」の算定表が参照されます。
弁護士基準の算定表(軽傷)

弁護士基準の算定表(重傷)

入院月数・通院月数が交わる部分が、入通院慰謝料の相場です。
なお、「1月」は1ヶ月ではなく30日を意味します。入院日数・通院日数を30日で割り切れず端数が生じる場合は、日割計算を行います。
たとえば、追突事故で治療期間90日のケガをした場合、軽傷なら53万円、重傷なら73万円が相場となります。
弁護士基準では、自賠責基準のように実通院日数は基本的に考慮されません。ただし、通院の頻度があまりに低いと、慰謝料が減額される可能性があるので注意しましょう。
後遺障害慰謝料の相場|むちうちは14級で約110万円、12級で約290万円
追突事故では、むちうちによる神経症状として14級9号や12級13号が認定されるケースが見られます。
弁護士基準の後遺障害慰謝料の目安は、次のとおりです。
- 14級:約110万円
- 12級:約290万円
後遺障害慰謝料の金額は、認定される等級に応じて以下のように定められています。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級・要介護 | 1,650万円 | 2,800万円 |
| 2級・要介護 | 1,203万円 | 2,370万円 |
| 1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |
| 2級 | 998万円 | 2,370万円 |
| 3級 | 861万円 | 1,990万円 |
| 4級 | 737万円 | 1,670万円 |
| 5級 | 618万円 | 1,400万円 |
| 6級 | 512万円 | 1,180万円 |
| 7級 | 419万円 | 1,000万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 9級 | 249万円 | 690万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 11級 | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
※2020年4月1日以降に発生した事故の場合
等級によって受け取れる金額は大きく変わるため、まずは自分の症状がどの等級に該当し得るのかを意識して確認することが大切です。
関連記事
【後遺障害等級表】認定される後遺症・症状の一覧と等級認定の仕組み
【コラム】慰謝料・示談金・保険金の違い
追突事故で保険会社とやり取りをしていると、「慰謝料」「示談金」「保険金」といった言葉が出てきます。
これらは似ているようで意味が異なるため、違いを整理しておくと示談交渉で混乱しにくくなります。
- 慰謝料
事故による精神的苦痛への補償(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料など) - 示談金
示談で支払われるお金の総称で、慰謝料のほか治療費・休業損害なども含む - 保険金
自賠責保険や任意保険など、示談金の支払いに充てられる「保険から出るお金」を指すことが多い

示談交渉では、提示された金額が「慰謝料なのか」「示談金総額なのか」、内訳を確認した上で妥当性を判断することが大切です。
追突事故の慰謝料が低額になりやすい3つの理由
追突事故は被害者側に過失がないケースも多く、「慰謝料は十分に受け取れるはず」と考えがちです。
しかし実際には、追突事故には慰謝料が低額になりやすい落とし穴があり、保険会社の提示額が相場より低くなることも珍しくありません。
ここでは、追突事故で慰謝料が低くなりやすい代表的な理由を3つ解説します。
(1)治療費を早期に打ち切られやすい
交通事故の治療費は、加害者側の任意保険会社が支払うことが多いですが、治療中でも「そろそろ治療を終了してください」と、治療費の支払いを早期に打ち切られることがあります。
追突事故で多いむちうちは、外見上は軽傷に見えやすく、事故から3ヶ月前後で治療費打ち切りを打診されるケースも珍しくありません。
治療費の支払いが早期に打ち切られ、治療を途中でやめてしまうと、慰謝料や示談金に次のような影響が出るおそれがあります。
- 治療期間が短くなる分、入通院慰謝料が低額になりやすい
- 後遺症が残っても、十分な治療経過がないとして後遺障害認定されず、後遺障害関連の慰謝料・示談金を受け取れない恐れがある
治療費打ち切りの連絡を受けたときの具体的な対応は、『交通事故で治療費打ち切りの連絡が保険会社から来た!阻止するための対応方法』で詳しく解説しています。
治療費が打ち切られた場合の対処法
治療費打ち切りを打診されても、すぐに治療を中断するのではなく、次の対応を検討しましょう。
- 医師に相談し、まだ治療が必要であれば意見書などをもらって、保険会社に打ち切り延長を求める
- それでも打ち切られた場合は、治療費を一時的に立て替えて通院を継続し、示談交渉で後日加害者側に請求する
治療費を立て替える際は、健康保険を使うと負担を軽減できます。
交通事故における健康保険の使い方については、関連記事『交通事故で健康保険は使える!切り替え手続きや医療保険の併用まで弁護士が解説』をご覧ください。
(2)後遺障害等級が認定されにくい
追突事故で治療を続けても完治せず後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。
しかし追突事故に多いむちうちは、レントゲンやMRIなどの画像上から判断することが難しいため、後遺障害の認定を受けることが難しいのが現状です。
認定を目指す場合は、次のような点を意識して準備を進めることが大切です。
- 弁護士に専門的なアドバイスを求める
- 事故直後から適切な通院と治療を行う
- 有利な検査結果を用意する
- 適切な後遺障害診断書への記載
認定の有無で受け取れる金額は大きく変わるため、手続きに不安がある場合は交通事故に強い弁護士へ相談することも検討しましょう。
関連記事
後遺障害認定されない理由と厳しい認定率…非該当から異議申し立てで逆転を目指す方法
(3)被害者自身の対応になるため不利になりやすい
追突事故は、被害者側の過失割合が10:0となるのが原則です。
しかし過失割合が10:0の場合、被害者側の任意保険会社による示談代行サービスは原則として利用できません。
そのため、相手方(加害者側の任意保険会社)との示談交渉を、被害者自身で進める必要が出てきます。
追突事故は「被害者に過失がない=安心」と思われがちですが、交渉面では不利になりやすい点に注意が必要です。
関連記事
交通事故で過失割合が10対0になる場合とは?示談交渉の注意点も解説
追突事故の慰謝料に関する判例
追突事故では「過失がない=慰謝料も満額もらえる」と思われがちですが、実際は通院状況や後遺障害認定などによって慰謝料や示談金が増減することがあります。
ここでは、どのような事情が慰謝料の減額・増額に影響するか、参考となる判例を3つ紹介します。
通院頻度が少なく慰謝料が減額された判例
通院頻度が少なく慰謝料が減額された判例
神戸地判平5・8・10(平成4(ワ)877号)
前方渋滞のためトンネル内で停車していたところ、走行車線上の落下物を回避しようとした後続車両に追突され、頸部捻挫を負った。通院治療の必要性・相当性(治療期間の妥当性)が争点となった。
裁判所の判断
「…通院治療は、…同人の本件受傷の具体的内容に照らすと、過剰といわざるを得ない。」
神戸地判平5・8・10(平成4(ワ)877号)
- 通院回数が多くても「必要性」が薄いと削られる
- 因果関係が認められない期間は、慰謝料も評価されない
最終受取額
213万8,584円(内慰謝料100万円)
むちうちで後遺障害等級が認められた判例
むちうちで後遺障害等級が認められた判例
名古屋地判令2・6・17(平成29年(ワ)2349号)
前方車両の減速・停止に合わせて停止したところ後続車に追突され、頸部挫傷・背部挫傷などの診断を受けたほか、右肩の痛みや右環指・小指のしびれが残った。これらの症状が後遺障害として認められるかが問題となった。
裁判所の判断
「…全体として後遺障害等級併合12級と認めるのが相当である。」
名古屋地判令2・6・17(平成29年(ワ)2349号)
- 検査で裏付けがある症状は認められやすい
- 画像が弱くても「一貫した症状+所見」で評価される
最終受取額
750万8,118円(内慰謝料300万円)
過失割合10:0でも示談金が下がった判例
過失割合10:0でも示談金が下がった判例
名古屋地判令2・7・17(平成29年(ワ)694号)
赤信号で停止していたところ後続車に追突され、頚椎捻挫・左膝関節捻挫・両肩挫傷を負った事案。入院28日・通院約6ヶ月半(実通院92日)の治療を受けたが、長期の治療や別の通院が事故と関係するか、さらに既往症の影響を理由に減額すべきかが争点となった。
裁判所の判断
「…本件事故のみによって、入院や長期の通院を要するような傷害を負うとはにわかに考え難い…これらの事情は素因減額において考慮するのが相当である」
名古屋地判令2・7・17(平成29年(ワ)694号)
- 10:0の追突事故でも、通院の長期化がそのまま認められるとは限らない
- 事故と関係ある治療はどこまでかを区切られることがある
- 既往症などが影響すると、素因減額で示談金が目減りする
最終受取額
308万2,374円
追突事故の慰謝料で損しないための注意点
追突事故で適正な慰謝料・示談金を得るには、示談交渉を成功させ、加害者側からの提示額を増額させなければなりません。
追突事故での示談交渉での注意点は、次のとおりです。
追突事故の注意点
- 過失割合10対0だと保険会社に示談を頼めない
- 不適切な通院頻度や整骨院の利用は慰謝料減額のおそれがある
- 後遺症が残ったなら後遺障害認定をうける
- 慰謝料以外の示談金も請求する
それぞれのポイントを確認していきましょう。
(1)過失割合10対0だと保険会社に示談を頼めない
追突事故で被害者側の過失割合が0だと、被害者が加入している任意保険会社による示談代行サービスを利用できません。よって、被害者自身で交渉にあたる必要があります。
この場合、被害者は以下の2点から示談交渉で不利になりがちです。
- 加害者側は、交渉のプロである任意保険会社の担当者が示談交渉にあたることがほとんど
- 過失割合10:0で過失相殺ができない分、加害者側の姿勢がシビアになりやすい
追突事故で被害者側の過失割合がない場合、過失割合に応じて示談金を減額する「過失相殺」が適用されません。
そのため、加害者側は示談金そのものを低額に抑えようという意識が強くなり、より厳しい態度で示談交渉に臨んでくることが多いです。
このような状況で、被害者だけの力で十分な示談金を受け取ろうと交渉しても、納得できる結果とすることは難しいでしょう。
また、被害者が交通事故の損害賠償問題に疎いことが伝わると、さらに強気な態度で交渉を進められることもあります。
示談金の増額が認められなかったり、加害者側の任意保険会社の交渉態度にストレスを感じていたりする場合は、交通事故に詳しい弁護士への相談・依頼を検討するとよいでしょう。
弁護士は法律のプロであり、過去の裁判例や法的に認められる請求の範囲も熟知しています。弁護士が出てくれば裁判への発展も現実的になるため、加害者側の任意保険会社は示談金の増額を認めることが多いです。
追突事故の被害者となった場合にはどう対応すべきか、過失割合の決まり方などの関連記事を読んでおくことをおすすめします。
(2)不適切な通院頻度や整骨院の利用は慰謝料減額のおそれ
治療中の通院頻度が低かったり、整骨院の利用方法が不適切だったりすると、入通院慰謝料が減額される可能性があります。
通院頻度や整骨院への通院を理由に慰謝料を減額されないためには、以下の点に注意しましょう。
- 通院頻度は月10回程度を目安とし、医師と相談しながら決める
- 整骨院への通院は医師の許可を得てからにする
通院頻度は月10回程度を目安とする
治療中の通院頻度は、月に10回程度を目安としましょう。
通院頻度が低いと、加害者側の任意保険会社に「すでにケガは治っているのに通院期間を引き延ばしているのではないか」「通院期間が長くなったのは被害者が治療に消極的だったからではないか」と疑われる可能性があります。
その結果、「治療期間が長引いた原因は被害者にもある」として、入通院慰謝料が減額されたり、治療費の一部が補償されなかったりするリスクがあるのです。
ケガの完治が近づいて通院頻度が下がった場合でも、最低でも月に1回以上は通院するようにしてください。
過剰通院や漫然治療にも要注意
医師の指示なしで毎日通院している場合、過剰通院を疑われ、「通院日数を多くして慰謝料を不正に多く受け取ろうとしているのではないか」として慰謝料が減らされるおそれがあります。
また、通院頻度が適正でも、薬や湿布を処方してもらうだけといった「漫然治療」を受けている場合も、慰謝料が減額されるおそれがあるので注意が必要です。
整骨院への通院は医師の許可を得てからにする
交通事故では基本的に、まずは整形外科などの病院に通ってください。
整骨院(接骨院)に通う場合は、以下の点をおさえるようにしましょう。
- 病院の医師から許可を得たうえで通う
- 保険会社にもあらかじめ連絡しておく
- 整骨院への通院と並行して、病院にも月に1回以上通う
整骨院での施術は、交通事故のケガを治すために必要なものと認められづらいです。そのため、整骨院に通院した分の治療費・入通院慰謝料は、認められなかったり減額されたりする可能性があります。
ただし、医師の許可を受けたうえで整骨院に通うなら、交通事故のケガを治すために必要なものと認められやすくなります。整骨院に通うことをあらかじめ保険会社に連絡しておけば、治療費などが減らされる可能性をさらに低くできるでしょう。
整骨院を利用する際の注意点について詳しく知りたい方は『交通事故で整骨院に通院するには?慰謝料・治療費などへの影響は?』の記事をご覧ください。
(3)後遺症が残ったなら後遺障害認定をうける
交通事故で後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定を受けましょう。
後遺障害認定の結果次第で、後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できるか、金額はいくらになるかが変わるからです。
後遺障害認定を受ける際は、以下の点を意識した対策をしましょう。
- 後遺障害認定は基本的に書類審査である
- 後遺障害等級の認定基準や過去の認定事例を参考に、個々の症状に合った対策をする
具体的な認定対策は具体的な症状により異なるため、個別に判断しなければなりませんが、基本的には弁護士によるサポートのもと、「被害者請求」という方法で後遺障害申請することがポイントです。
詳しくは『後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由』をご覧ください。
(4)慰謝料以外の示談金も請求する
追突事故で請求できる慰謝料以外の費目についても、忘れずに請求することで示談金を増額させることができます。
人身事故の示談金
追突事故によって被害者がケガをした場合、主に以下のような費目を請求できます。
傷害分の主な費目
- 治療費
- 器具・装具費
松葉づえや車いすなどの器具・装具の費用 - 入院雑費
入院中に必要な消耗品費・通信費などの補償 - 通院交通費
通院にかかった交通費
(関連記事:交通事故の通院交通費|請求できる条件や慰謝料との違い) - 付き添い看護費
家族や職業看護人が入通院に付き添った場合の補償
(関連記事:交通事故の付添費|付き添いに認められる範囲と相場は?) - 休業損害
交通事故により仕事を休んだため発生した減収の補償
追突事故によって後遺障害等級に認定された場合は、後遺障害慰謝料のほか、以下のような費目も請求可能です。
後遺障害分の主な費目
- 後遺障害逸失利益
後遺障害の影響で減る将来的な収入の補償 - 将来介護費
将来にわたる介護で必要な費用の補償
(関連記事:交通事故で介護費用が請求できる2ケース)
死亡事故の示談金
追突事故で被害者が死亡した場合は、死亡慰謝料のほか、以下のような費目も請求可能です。
死亡事故の主な費目
- 死亡逸失利益
死亡したため得られなくなった将来的な収入の補償
(関連記事:死亡逸失利益を正当に受け取るために) - 葬儀費用
(関連記事:交通事故の葬儀費用はいくら請求できる?葬儀費用の範囲と請求のポイント)
なお、交通事故にあってから亡くなるまでの間に一定期間の入通院をしていれば、上で紹介した「傷害分の費目」も請求可能です。
物損事故の示談金
車などの物品に損害が生じた場合、以下のような費目も請求可能です。
物損事故の主な費目
- 車の修理費用
- 代車代
- 買い替え諸費用
- 評価損
車に修復歴が残ったことで低下した市場価格の補償
(関連記事:事故車の評価損とは?請求のポイントと新車やもらい事故で格落ちを勝ち取る方法)
なお、物損のみが生じている物損事故では基本的に慰謝料を請求できません。
物損事故の示談金について詳しく知りたい方は、『物損事故の示談の流れと示談金相場|交渉時の注意点』の記事をご参照ください。
追突事故の慰謝料・示談金についてよくある質問
続いて、追突事故の慰謝料・示談金についてよくある以下の質問にお答えします。
Q1.追突事故の慰謝料・示談金を受け取るまでの流れは?
追突事故の発生から慰謝料・示談金を受け取るまでの流れは、以下のとおりです。
追突事故の流れ
- 追突事故が発生する
- ケガをしている場合、病院で治療を行う(完治したら示談交渉へ)
- 後遺症が残った場合、症状固定後に後遺障害認定の申請を行う
- 示談交渉を行う
- 示談が成立したら慰謝料・示談金を受け取り
- 示談が不成立ならADRや裁判で解決を目指す

なお、示談交渉は、以下の流れで進められます。
示談交渉の流れ
- 加害者側の任意保険会社から、示談金額や過失割合の提示を受ける
- 提示された内容について、交渉する
- 示談が成立したら、加害者側の任意保険会社から示談書が送られてくる
- 示談書に署名・捺印をして返送すると、2週間程度で示談金が振り込まれる
関連記事『交通事故の示談とは?示談交渉の流れや示談をうまく進めるための注意点』では、示談をスムーズに進めるための注意点を紹介しています。あわせてご一読ください。
示談成立前にお金を受け取る方法もある
示談金は基本的に示談成立後に振り込まれます。よって、治療や示談交渉が長引いた場合、経済的な不安を抱えてしまう被害者の方も多いと思われます。
もし、示談成立前に一定の金額を受け取りたいなら、加害者側の自賠責保険に示談金の一部を請求しましょう。
このような請求を被害者請求といいます。
被害者請求の方法や請求できる範囲について知りたい方は『交通事故の被害者請求|自賠責保険に請求するには?やり方とデメリット』の記事をご覧ください。
Q2.追突事故でも過失割合が10:0にならないことがある?
過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるのか、割合で示したものです。
後ろから追突された事故の場合、基本的に被害者側の過失は0ですが、場合によっては被害者側にも過失割合がつく可能性があります。
被害者側にも過失割合がつく可能性があるのは、具体的には以下のような場合です。
- 完全には停車していない状態だった
- 被害車両の急ブレーキにより追突事故が起きた
- 被害車両が灯火義務を怠って停車したことで追突事故が起きた
- 被害車両が正しい場所・方法で駐停車していなかったために追突事故が起きた
被害者にも過失割合が付くと、その分示談金が減らされてしまうので注意が必要です。
過失割合の決まり方や、追突事故の過失割合については、以下の関連記事をご覧ください。
納得いかない過失割合を提示されたら?
追突事故の過失割合は、基本的に示談交渉で決められます。
もし、加害者側の任意保険会社から納得いかない過失割合を提示されたら、事故状況を証明する資料を用意して反論しましょう。資料の例としては、以下のものがあげられます。
- ドライブレコーダーや現場周辺の防犯カメラ映像
- 警察が作成した実況見分調書
- 目撃者の証言
そもそも加害者側の提示する過失割合が不当なのか確認しておきたい、他にどのような証拠が有効なのか知りたいといった場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
Q3.追突事故でむちうちになった、後遺障害認定対策は?
追突事故でむちうちになり、後遺症が残った場合の後遺障害認定対策としては、以下が挙げられます。
- 神経学的検査などで、症状の有無・程度を客観的に証明する
- 自覚症状とともに、その症状による生活や仕事への影響もアピールする
- 症状の一貫性・継続性を伝える
- 6ヶ月以上治療を続ける
むちうちの場合、認定される可能性がある後遺障害等級は12級13号または14級9号です。
12級13号に認定されるには画像検査の結果から神経症状が生じていることを医学的に明らかにする必要があり、14級9号に認定されるには事故の状況や症状の一貫性などから神経症状が生じていることを医学的に説明できる必要があります。
そのために、上記のポイントを押さえた対策を行いましょう。詳しくは、後遺障害認定に精通した弁護士に相談することがおすすめです。
過去の認定事例や専門知識をもとに、的確なアドバイスを受けられます。
関連記事
むちうちの後遺症で後遺障害認定は難しい?認定対策や完治しない時の賠償金は?
Q4.友人や家族の運転する車に同乗中に追突されたら?
友人や家族の運転する車両に同乗していたとき、追突事故の被害者になってしまった場合も慰謝料や治療費などの請求は通常どおり可能です。
同乗者だからといって請求できる示談金が減ることはありません。
なお、被害車両の運転手にも過失がある場合は、損害賠償請求の相手は加害者と運転手である友人・家族になります。
運転手が友人であり、損害賠償を請求しづらいなら、事故の加害者に全額請求するとよいでしょう。加害者からの支払い後、加害者と友人の間で損害賠償に関する調整がされます。
運転手が家族の場合は、同じ家計となるため損害賠償を請求するメリットは少ないです。また、家族の加入する任意保険からは支払いを受けられません。
なお、以下のような場合では、同乗者の過失が問われたり賠償責任が生じたりする可能性があるので注意してください。
- 安全運転の妨害をした
- 事故車の所有者だった
- 好意同乗とみなされた
(好意により無償で自動車に同乗させることを言うが、一般的には好意同乗が原因の減額は行われない)
同乗者の慰謝料請求について詳しく知りたい方や、好意同乗による慰謝料減額をせまられている方は、以下の関連記事を参考にしてください。
【アトム解決事例】追突事故の慰謝料・示談金を受け取った事例
追突事故の慰謝料・示談金は、通院状況や後遺障害の有無などによって金額が大きく変わります。
ここでは、アトム法律事務所が対応し、適正な賠償につながった解決事例を紹介します。
後遺障害等級が認定され、示談金345万円超を受け取った事例
人身事故に切り替え、示談金345万円超を獲得した事例
物損事故扱いから人身事故への切替え、後遺障害申請を含めて弁護士に相談したケース。
弁護活動の成果
併合14級の後遺障害認定、345万円超の示談金を獲得。
年齢、職業
40~50代、自営業
傷病名
頸椎捻挫
後遺障害等級
併合14級
最終受取金額
345万9,246円
治療費打ち切り通告後の示談交渉で、後遺障害認定を得た事例
治療費打ち切り通告後の示談交渉で示談金約323万円を獲得した事例
痛みやしびれが残る中で保険会社から治療費打ち切りを通告され、治療や手続きの進め方について弁護士に相談したケース。
弁護活動の成果
治療継続の必要性について相手方保険会社と交渉を行い、併合14級の認定と示談金約323万円を獲得。
年齢、職業
20~30代、主婦・主夫
傷病名
頸椎捻挫
後遺障害等級
併合14級
最終受取金額
323万5,780円
慰謝料以外の損害も含め、示談金約370万円を受け取った事例
自営業での休業損害等も含め示談金約370万円を獲得した事例
自営業で休業が発生しており、慰謝料だけでなく休業損害や実損(食材費)も含めて補償を求めたいとして弁護士に相談したケース。
弁護活動の成果
休業損害・食材費などの損害を整理して請求し、後遺障害併合14級認定。総合的に交渉を進め、約370万円を獲得。
年齢、職業
40~50代、自営業
傷病名
頚椎捻挫
後遺障害等級
併合14級
最終受取金額
370万8,820円
追突事故の慰謝料・示談金については弁護士相談も検討しよう
追突事故について弁護士へ相談・依頼するメリット
追突事故の示談金を請求する際は、弁護士への相談・依頼もご検討ください。
弁護士に相談・依頼をすると、次の3つのメリットが得られます。
- 慰謝料・示談金の増額
- 加害者側とのやりとりからの解放
- 適切な後遺障害等級認定が受けられるようサポート
示談交渉で加害者側は相場よりも低い示談金を提案してきます。十分な金額まで引き上げるためには、弁護士から適切な主張を行ってもらうことが欠かせません。
また、弁護士に示談交渉を任せれば、自分で加害者側とやりとりをする必要がなくなります。加害者側から高圧的な言動をとられる、強引に交渉を進められるといったストレスから解放され、日常生活への復帰に集中できるようになるのです。
この他にも、追突事故によるむちうちなどのケガが完治せず、後遺障害等級認定が必要となった場合には、弁護士に依頼して申請手続きのサポートを受けることで、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まります。
後遺障害等級認定を受けることで請求できる損害賠償金額は大きく異なることからも、弁護士に相談・依頼するメリットは大きいといえるでしょう。
弁護士の検討に役立つ記事
- 示談金をいくら増額できる見込みがあるかわかる
- 弁護士に相談・依頼するメリットがわかる
追突事故こそ弁護士費用特約を使うべき
弁護士費用特約とは、弁護士に依頼したときにかかる弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約のことです。通常、弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを負担してもらえます。

被害者の過失なしとなりやすい追突事故こそ、弁護士費用特約の使いどころと言えます。
被害者の過失がない事故では保険会社の示談代行サービスを使えず、被害者自身で示談交渉を進めなければなりません。そのうえに、被害者側にとって不利な条件を提示され、なかなか増額を認められないことが多いのです。
このような場合、弁護士費用特約を使って弁護士を味方につけることが効果的に働きます。
法律の専門家である弁護士の主張なら、加害者側の任意保険会社もないがしろにはできません。また、弁護士が出てくると任意保険会社は裁判への発展をおそれ、被害者側の主張を受け入れる傾向があります。
なお、弁護士費用特約を使う場合も、保険会社に紹介された弁護士に依頼する必要はありません。
むしろ、保険会社に紹介された弁護士は加害者側のサポートの方を得意としていることも多いため、被害者自身でも交通事故に強い弁護士を探すことをおすすめします。
追突事故のようなもらい事故で弁護士費用特約を使うべき理由は、関連記事『もらい事故こそ弁護士特約を使って慰謝料増額!特約のメリットや使い方』で詳しく解説しています。
弁護士への相談は示談成立前に|無料の法律相談案内
示談が一度成立すると、原則的に撤回することはできないため、弁護士に相談・依頼は示談成立前に行いましょう。
加害者側の任意保険会社と合意する前に、法律の専門家である弁護士に相談し、示談金が妥当か確認するべきといえます。
アトム法律事務所は、電話・LINEによる弁護士への無料相談を実施しています。
事務所までお越しいただかなくても、自宅から弁護士に相談していただけるのがアトムの無料相談の特徴です。加害者側からの提示額が妥当か知りたい場合や、加害者側とのやりとりでトラブルが生じている場合に、ぜひ気軽にご利用ください。
もちろん、無料相談のみの利用でも問題ありません。依頼を強要するようなことはありませんのでご安心ください。
相談の予約は、24時間年中無休で受け付けています。
まずは電話やLINEで、お気軽にお問い合わせください。





高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了



