渋滞停車中に後方から追突され首のむちうちを負った事例
弁護士に依頼後...
回収
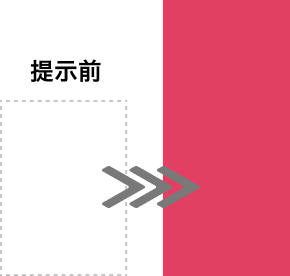
計算機の慰謝料は弁護士基準・過失0の場合を基準に計算しています。弁護士基準まで慰謝料を増額するためには弁護士に相談するのが最短・最適の方法です。
計算ソフト利用上の注意点
・主婦の方は、「年収」の欄で「301~400」を選択してください。
・逸失利益は、失業中の方、大学生の方について計算の対象外としています。
・本計算機は、個別事情を考慮せず、一般的な計算方法に基づいて慰謝料等を計算しています。正確な慰謝料額を知りたい重傷の被害者やご家族の方は、当事務所の電話無料相談サービス(0120-434-911)をご利用ください。
交通事故に遭ったとき、示談の前に「慰謝料の相場」を把握しておくことは非常に重要です。
しかし、加害者側の任意保険会社から提示される慰謝料は、本来受け取れる金額よりも低く抑えられていることがほとんどです。
記事冒頭の「慰謝料計算機」を使えば、入通院・後遺障害・死亡事故など、ケースに応じた慰謝料の目安額を簡単にシミュレーションできます。
まずはこの慰謝料計算機というツールで相場を把握し、そのうえで「提示された金額が妥当かどうか」を判断していくことが大切です。
本記事では、慰謝料の金額を左右する3つの基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)の違いや、具体的な計算方法・計算例をわかりやすく解説しています。保険会社の提示額に納得がいかない方や、正しい慰謝料を知って損をしたくない方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次
交通事故に遭ったとき、気になることとして「慰謝料はいくらもらえるのか」という点が大部分を占めるかもしれません。
しかし、保険会社から提示される金額が適正なのか、示談前に自分で判断するのは簡単ではありません。そこで活用したいのが、誰でも無料で使える「慰謝料計算機」です。
冒頭にある慰謝料計算機を使えば、事故状況や通院期間などの情報を入力するだけで、弁護士基準(裁判基準)による慰謝料の目安をその場で自動計算できます。
まずは、示談前に適正な慰謝料の金額を把握することから始めましょう。
交通事故で受け取れる慰謝料は、入通院の期間や後遺障害の有無、死亡事故かどうかによって金額が大きく異なります。また、計算方法も複数の基準があるため、被害者が自力で正確な金額を算出するのは非常に困難です。
そこで役立つのが、示談前に利用できる自動計算ツール「慰謝料計算機」です。
慰謝料計算機に必要な情報を入力すれば、被害者が受け取るべき「弁護士基準」での慰謝料額の目安がすぐにわかります。
主な入力内容
保険会社から提示された金額と比較することで、「この慰謝料は本当に適正なのか」を客観的に判断する手がかりになるのです。
慰謝料計算機を使うことで、慰謝料と逸失利益の金額の目安がわかります。
とくに弁護士基準での金額は、保険会社が提示する金額より数十万円〜数百万円も高額になるケースが少なくありません。
この計算結果を把握しておくことで、示談時に「もっと高い金額を請求できたはずなのに…」と後悔するリスクを防ぐことができます。
加害者側の任意保険会社が提示してくる慰謝料が低額な理由は、「任意保険基準」で計算された金額だからです。
対して、記事冒頭の慰謝料計算機でも用いている「弁護士基準」で計算した慰謝料が、適正相場かつ最も高い金額になる計算基準です。
慰謝料の計算基準3つ
計算機の結果通り(相場通り)となる弁護士基準の慰謝料がもらえる可能性を高めるためには、弁護士依頼が最も有力です。理由を解説します。
まず弁護士基準は、裁判で認められる慰謝料の計算基準です。
しかし、交通事故の慰謝料請求で裁判までもつれこむケースは少ないため、加害者側の任意保険会社は「被害者本人が裁判を起こす可能性は低いから、わざわざ弁護士基準の慰謝料を払わなくてもいい」と考えます。
そのため弁護士基準の慰謝料は、被害者本人が増額交渉をしても認められないことがほとんどなのです。
弁護士基準の慰謝料を獲得するためには、弁護士に示談交渉を依頼して、加害者側の任意保険会社に「このままだと裁判に発展するかもしれない…」と思わせる必要があります。
裁判になれば加害者側の任意保険会社にも大きな負担がかかるため、弁護士基準の慰謝料を払った方がコストがかからないと考え、慰謝料の増額に応じてくれるようになるのです。
弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。
提示額の137万円から、最終的な受取金額が312万円まで増額された。
20~30代、会社員
むちうち
14級9号
弁護士費用特約が使える場合、被害者本人の金銭的負担はゼロになるケースが多いです。弁護士費用特約について詳しくは、本記事内「弁護士費用特約があれば安心して依頼できる」をお読みください。
また、弁護士費用特約がなく、弁護士費用を負担する場合でも、慰謝料の増額幅によっては弁護士に依頼した方がいいケースもあります。
アトム法律事務所は基本的に、交通事故でケガされた方を対象に法律相談料と着手金を無料としていますので、まずは無料相談を活用して慰謝料の増額幅を確認してみましょう。

加害者側の任意保険会社が提示してきた金額がすでにわかっている方は、記事冒頭で紹介した「慰謝料計算機」という自動計算ツールをご利用ください。
慰謝料計算機は、「被害者が通常、受け取ることのできる慰謝料の額」を自動計算する、慰謝料のシミュレーションツールです。
慰謝料計算機の結果と、加害者側から提示された慰謝料金額に差がある場合は、弁護士に依頼することで増額できる可能性があります。
まずは弁護士への無料相談で「弁護士が介入することでどのくらい慰謝料増額が見込めるか」をご確認ください。
慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するために支払われる損害賠償金をいいます。
物損事故の場合は修理などにより損害を回復させることが可能なので、通常、慰謝料は発生しません。
また、慰謝料は交通事故の損害賠償金として支払われる示談金の一部です。示談金のなかには、慰謝料のほか、治療費・休業損害・逸失利益などが含まれます。
なお、交通事故の慰謝料は「入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料」の3つの種類に分けられます。
それでは3つの慰謝料の中身について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
入通院慰謝料とは、交通事故により入院や通院をしたことによって支払われる慰謝料です。入通院慰謝料は、「傷害慰謝料」ともいわれます。
交通事故によるケガを負ってしまった場合、被害者は大変な苦痛をともないます。しかし、精神的苦痛の程度は人によってさまざまなので、苦痛そのものを金額に換算することはできません。
そこで、入通院慰謝料は、入通院日数や期間により金額を設定しています。
条件を満たしていれば、入院なし・通院のみの場合でも請求できます。
通院のみの慰謝料については『通院のみなら交通事故慰謝料はいくら?』が参考になります。
あわせてお読みください。
後遺障害慰謝料とは、交通事故の後遺症により、後遺障害が残ったことに対して支払われる慰謝料です。
後遺症とは「傷害が完治せずに残存した障害」をいい、その後遺症を後遺障害というためには、後遺障害等級に認定されなければいけません。
後遺障害等級に認定された場合、後遺障害慰謝料に加えて逸失利益も請求できるようになります。
後遺障害等級は、後遺症の程度により1級から14級まで区分されており、後遺障害慰謝料も1級から14級ごとに金額が区分されています。
なお、等級に該当しない「非該当」の場合、後遺障害慰謝料の金額は原則0円ですが、後遺障害に相当する症状が残っていると判断されれば、慰謝料を認められたというケースもあります。
後遺障害等級認定を受けるためには、後遺障害の有無を証明する医師の正確な後遺障害診断書が欠かせません。後遺障害の認定につながる充実した内容の後遺障害診断書にするには工夫が必要なので、『後遺障害診断書とは?もらい方と書き方、自覚症状の伝え方を解説』の記事もあわせてご確認ください。
また、後遺障害慰謝料は、被害者本人のみならず近親者に対しても認められることがあります。
判例によれば、重度の後遺症の場合であって、死亡に匹敵するような精神的苦痛を受けたときに認められてることがあるでしょう。
近親者固有の後遺障害慰謝料が認められた判例
(裁判要旨) 不法行為により身体を害された者の母は、そのために被害者が生命を害されたときにも比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合、自己の権利として慰藉料を請求しうるものと解するのが相当である。
最判昭和33年8月5日民集12巻12号1901頁
死亡慰謝料とは、被害者が交通事故で死亡してしまった場合、その精神的苦痛に対して支払われる慰謝料をいいます。
死亡慰謝料は、被害者の立場や地位により金額が変わってきます。
たとえば、被害者が「一家の支柱」であった場合と、「一家の支柱以外」であった場合で金額に差があります。被害者が一家の支柱であった場合、死亡したことによって経済的な支柱をも失うと考えられているためです。
また、死亡慰謝料には、被害者本人に対するものと遺族に対するものとがあります。被害者本人が被る精神的苦痛と、遺族が被る精神的苦痛は別物と考えられているのです。
原則として、死亡慰謝料を受け取ることのできる遺族は、被害者の配偶者(事実婚の配偶者を含む)、子、父母に限られています。
つづいては、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料が3つの計算基準ごとにどのように計算されるのかみていきましょう。
どのように計算されるのかを知っておくことで、任意保険会社から提示される金額が適正でないことをご自身の目で確認することができます。
まず、入通院慰謝料の計算方法をみていきましょう。
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準でそれぞれ計算し、金額にどのくらいの違いがあるのかを確認できます。
相手方から慰謝料を提示されている被害者の方は、その金額と見比べてみてください。
事故例
交通事故の被害に遭い、骨折などの傷害を負った。
治療期間180日間のうち、入院日数は30日、実通院日数は60日であった。
※慰謝料の算定では、1ヶ月=30日と考えます。
では、事故例に沿ってそれぞれの基準で計算していきます。
はじめに、最も低額な自賠責基準で計算してみましょう。
自賠責基準で入通院慰謝料を計算する場合、以下の2つの計算式のうち金額が少ない方を採用します。
※ 2020年3月31日までに起きた事故については1日あたり4,200円で計算します。
※ 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。
事故例を、自賠責基準の計算式にあてはめてみましょう。(4,300円の支払い基準で計算します。)
金額の少ない方を採用するため、自賠責基準で計算された入通院慰謝料は645,000円になります。
任意保険基準については、任意保険会社により異なります。
示談をおこなう保険担当者によって慰謝料の金額が変わる可能性もあるでしょう。
ここでは、過去に任意保険会社が用いていた「旧任意保険基準」を参考に慰謝料を出してみます。
旧任意保険基準|入通院慰謝料の算定表
事故例を、旧任意保険基準にあてはめてみましょう。
入院日数は30日間のため1ヶ月です。治療期間180日間から入院日数30日間を除くと、通院期間150日間が求められます。
したがって、通院期間150日間は5ヶ月です。
入院月数1月と通院月数5月が交差するマスは、769,000円となっています。
自賠責保険の645,000円を上回る金額となりました。
弁護士基準での入通院慰謝料は、「赤い本」を参考にします。
弁護士基準では、むちうちなどの軽傷ケースと、重傷ケースによって用いる算定表が変わるので注意しましょう。
軽傷ケース|入通院慰謝料の算定表
重傷ケース|入通院慰謝料の算定表
事故例は「骨折などの傷害」という設定のため、重傷ケースの算定表を用いてください。(軽傷ケースの代表例である「むちうち」に関しては、関連記事『交通事故によるむちうちの症状・治療期間・後遺症|慰謝料相場も解説』にて深掘り解説しています。)
事故例を、弁護士基準にあてはめてみましょう。
入院日数は30日間のため1ヶ月です。治療期間180日間から入院日数30日間を除くと、通院期間150日間が求められます。
したがって、通院期間150日間は5ヶ月です。
入院月数1月と通院月数5月が交差するマスは、1,410,000円となります。
任意保険基準の769,000円をはるかに上回る金額となりました。
端数がある場合の計算例
月数は暦に関係なく1月=30日とし、30日未満の端数がある場合は、日割り計算を行います。
重傷で20日間入院し、80日間通院したケースで、弁護士基準の入通院慰謝料を計算してみましょう。
(1)入院20日間分の入院慰謝料を計算する
まずは、入院20日に対する慰謝料を計算します。
入院30日(1月)は53万円なので、30日単位で割り算して日額を出し、20日分を求めましょう。
53万円÷30日=約17,666円
17,666円×20日=約353,320円
入院20日間への慰謝料は353,320円です。
(2)総治療期間(100日間)の通院慰謝料を計算する
次に、総治療期間あたりの通院に対する慰謝料を計算します。
入院20日と通院80日なので、合計100日分です。
100日は3月と10日に分けて、まず端数の10日分を求めていきましょう。
10日分は「4月目」の10日にあたりますので、通院4月から通院3月の通院慰謝料を引き算して「4月目」の日額を求めます。
(90万円-73万円)÷30日=約5,666円
5,666円×10日=56,660円
通院3月分の慰謝料73万円と合計して、総治療期間(100日間)の通院慰謝料は786,660円です。
(3)総治療期間の通院慰謝料から「入院」分を控除する
入院は通院に比べて精神的苦痛が大きいとされ、慰謝料も高く設定されています。先ほど求めた入院20日間の慰謝料(約353,320円)は、すでに通院慰謝料も考慮されているのです。
つまり、総治療期間786,660円の金額には入院20日分の通院慰謝料が既に含まれていますので、20日分の通院慰謝料を控除しなくてはなりません。
28万円÷30日=約9,333円
9,333円×20日=186,660円(入院20日間の通院慰謝料)
786,660円-186,660円=600,000円
20日分を控除した通院慰謝料は600,000円です。
(4)入院と通院に対する慰謝料を合算する
最初に求めた入院20日分の入院慰謝料(353,320円)と合算します。
600,000+353,320=953,320(円)
よって、重傷で入院20日、通院80日のとき、入通院慰謝料は953,320円となります。
上記のような日割り計算が必要なケースでは、慰謝料の計算方法は複雑になります。
より簡単にご自身のケースの慰謝料を求めたい方は、記事冒頭の慰謝料計算機をご利用ください。入通院開始日や治療終了日を入力するだけで、慰謝料の目安がわかります。
3つの計算基準で計算された金額をまとめると、以下の通りです。
| 基準 | 入通院慰謝料の額 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 645,000円 |
| 任意保険基準 | 769,000円 |
| 弁護士基準 | 1,410,000円 |
自賠責基準や任意保険基準と比較すると、弁護士基準で計算された入通院慰謝料の額は桁違いに高額です。
いかに弁護士基準で慰謝料を計算することの大切さがお分かりいただけたと思います。
ここまでで説明した入通院慰謝料の計算方法がすこし複雑だと感じた方は「慰謝料計算シート」をお使いください。計算シートを使えば、入通院慰謝料をもっと簡単にご自分で計算できるでしょう。
やはり自分で計算するのが苦手だという方は、記事冒頭にある慰謝料の自動計算が可能な「慰謝料計算機」で金額をシミュレーションしてみてください。
後遺障害慰謝料の金額についても、3つの計算基準を用いて算定をおこないます。
3つの基準を表にまとめてみました。
| 等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,150万円 (1,100万円) | 1,300万円 | 2,800万円 |
| 2 | 998万円 (958万円) | 1,120万円 | 2,370万円 |
| 3 | 861万円 (829万円) | 950万円 | 1,990万円 |
| 4 | 737万円 (712万円) | 800万円 | 1,670万円 |
| 5 | 618万円 (599万円) | 700万円 | 1,400万円 |
| 6 | 512万円 (498万円) | 600万円 | 1,180万円 |
| 7 | 419万円 (409万円) | 500万円 | 1,000万円 |
| 8 | 331万円 (324万円) | 400万円 | 830万円 |
| 9 | 249万円 (245万円) | 300万円 | 690万円 |
| 10 | 190万円 (187万円) | 200万円 | 550万円 |
| 11 | 136万円 (135万円) | 150万円 | 420万円 |
| 12 | 94万円 (93万円) | 100万円 | 290万円 |
| 13 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
| 14 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
表中()は2020年3月31日以前発生の事故に適用
任意保険基準は「旧任意保険基準」(現在は各保険会社が独自に設定)
たとえば、障害の程度が最も重い後遺障害等級1級の慰謝料額をみてください。最も低額な自賠責基準と最も高額な弁護士基準を比べると、1,600万円以上の差が生じています。
後遺障害慰謝料の金額や後遺障害等級認定については、『後遺障害慰謝料の相場はいくら?いつ支払い?後遺障害等級認定と賠償金額のすべて』もご覧ください。
交通事故の被害者に被扶養者がいる場合、被扶養者に対しても慰謝料が支払われます。
自賠責基準では、後遺障害慰謝料の金額が以下のように増額するという形で支払われるでしょう。
被扶養者がいた場合の弁護士基準での後遺障害慰謝料については、個別具体的に判断されます。
被扶養者がいた場合に支払われた後遺障害慰謝料の判例は以下の通りです。
【1級の事例】
民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
高次脳機能障害(1級3号)の大学院生(男・固定時27歳・博士課程在学)につき,障がい分600万円のほか,本人分3000万円,父母各400万円の後遺障害分合計3800万円を認めた。
(事故日平9.4.24 東京地判平16.6.29 交民37・3・838)
【2級の事例】
民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
高次脳機能障害(2級3号)の専門学校生・アルバイト(男・固定時20歳)につき,傷害分300万円のほか,本人分2,600万円,母200万円の後遺障害分合計2800万円を認めた。
(事故日平12.10.22 大阪地判平19.6.20 自保ジ1705・7)
交通事故の被害者に介護が必要となった場合についても、金額に差が出てきます。
後遺障害等級の要介護1級・要介護2級については、要介護者として慰謝料が増額されるのです。
自賠責基準での慰謝料額は以下のようになります。
弁護士基準での要介護者の慰謝料については、個別具体的に判断されます。
死亡慰謝料の金額についてもこれまでと同様、3つの計算基準を用いて算定をおこないます。
ぞれぞれの基準で計算すると、金額にどのくらいの違いがあるのかみていきましょう。
自賠責基準では、死亡した被害者本人に対する慰謝料と、遺族に対する慰謝料がそれぞれ設定されているので、それらを合計した金額が死亡慰謝料となります。
自賠責基準では、死亡した被害者本人に対して400万円(350万円)の死亡慰謝料が払われます。
また、自賠責基準では被害者の立場によって金額差はもうけられていません。
死亡した被害者が、一家の支柱であってもなくても、死亡した被害者本人に対する金額は一律なのです。
遺族分の慰謝料は、被扶養者がいる場合といない場合で受け取れる金額が異なります。
| 慰謝料 | |
|---|---|
| 被害者本人 | 400万円(※350万円) |
| + | |
| 遺族1人 | 550万円(※※750万円) |
| 遺族2人 | 650万円(※※850万円) |
| 遺族3人 | 750万円(※※950万円) |
※ 2020年3月31日以前発生の事故に適用
※※ 被扶養者がいる場合の金額
たとえば、死亡した被害者に扶養されていた遺族が1人いた場合、自賠責基準では400万円+750万円=1,150万円ということになります。
任意保険基準で支払われる死亡慰謝料は、あくまで推定金額となります。
一般には非公開とされている基準のため、おおよその金額であることを前提にご覧ください。
| 被害者の立場 | 慰謝料 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 1,700万円程度 |
| 配偶者・母親 | 1,500万円程度 |
| それ以外 | 1,500万円程度 |
保険会社により異なります
任意保険基準で設定された死亡慰謝料の金額は、遺族分をすでに含んだものと考えられています。
たとえば、死亡した被害者に扶養されていた遺族が1人いた場合、任意保険基準では1,700万円程度ということになるのです。
弁護士基準では、被害者の立場によって金額差がもうけられています。
| 被害者の立場 | 慰謝料 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2,800万円 |
| 配偶者・母親 | 2,500万円 |
| それ以外※ | 2,250万円 |
※「それ以外」は、独身の男女、子供、幼児等をいいます。
弁護士基準で設定された死亡慰謝料の金額は、遺族分をすでに含んだものと考えられています。
たとえば、死亡した被害者に扶養されていた遺族が1人いた場合、弁護士基準では2,800万円ということになるのです。
死亡した被害者に扶養されていた遺族が1人いた場合、3つの計算基準で計算された金額をまとめると以下の通りです。
| 基準 | 死亡慰謝料の額 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 1,150万円 |
| 任意保険基準 | 1,700万円程度 |
| 弁護士基準 | 2,800万円 |
死亡した被害者に扶養する遺族が1人いた場合を想定
自賠責基準は2020年4月1日以降発生の事故を想定
自賠責基準・任意保険基準と弁護士基準を比べると、弁護士基準の方が1.6~2.4倍ほど高い金額であることがわかります。
死亡慰謝料は金額も大きいので、慎重に示談を進める必要があるでしょう。
交通事故の慰謝料相場についてさらに具体的に知りたい方は、関連記事『交通事故で慰謝料はいくらもらった?事例や相場から増額のポイントまで解説』もおすすめです。死亡事故はもちろん症状別に慰謝料相場を紹介しています。
次に、モデルケース別に交通事故の慰謝料の計算例を確認してみましょう。
なお、任意保険基準は各社によって異なり、非公開であるため、ここでは計算例を割愛します。任意保険基準は自賠責基準とほぼ同額~やや高額になると考えてご覧ください。
まずは、交通事故でむちうちを負った場合の入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の計算例を見てみましょう。
むちうちで1か月~6か月通院した場合、入通院慰謝料の計算例は以下の通りになります。
| 治療期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 通院1か月 | 12.9万円 | 19万円 |
| 通院2か月 | 25.8万円 | 36万円 |
| 通院3か月 | 38.7万円 | 53万円 |
| 通院4か月 | 51.6万円 | 67万円 |
| 通院5か月 | 64.5万円 | 79万円 |
| 通院6か月 | 77.4万円 | 89万円 |
※2020年4月1日以降に発生した事故で、ひと月半分以上の通院をした場合
※弁護士基準の金額は軽傷用の算定表を用いたもの
なお、表中の自賠責基準の慰謝料は、最も高額になる条件で計算しています。通院日数によっては、自賠責基準の慰謝料は表中の金額よりも低くなる可能性があるでしょう。
通院期間ごとの慰謝料相場が知りたい方は、以下の記事もご参考ください。
むちうちで後遺症が残ったなら、後遺障害12級か14級に認定される可能性があります。その場合、以下の後遺障害慰謝料も請求可能です。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
※2020年4月1日以降に発生した事故の場合
算定基準によって、後遺障害14級の場合は80万円弱、12級の場合は200万円弱も金額が異なってくることがわかります。
むちうちの慰謝料額については、『交通事故のむちうちの慰謝料はいくら?慰謝料が倍増する方法を紹介』の記事でも詳しく解説しているので、ご確認ください。
次に、交通事故で骨折した場合の入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の計算例を見ていきます。ここでは仮に、大腿骨を骨折して入院し、退院後にリハビリのため通院した場合の慰謝料を算出してみましょう。
足の骨折で1か月入院し、3か月~9か月通院した場合、入通院慰謝料の計算例は以下の通りになります。
| 治療期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 入院1か月 通院3か月 | 51.6万円 | 115万円 |
| 入院1か月 通院6か月 | 90.3万円 | 149万円 |
| 入院1か月 通院9か月 | 129万円 | 170万円 |
※2020年4月1日以降に発生した事故で、ひと月半分以上の通院をした場合
※弁護士基準の金額は重傷用の算定表を用いたもの
上記の表中の金額も、むちうちの場合と同様に、自賠責基準の慰謝料が最も高額になる条件で計算されています。通院日数によっては自賠責基準の慰謝料はより低額になるので、注意してください。
足の骨折によって足の欠損や変形、可動域の制限、神経症状といった後遺症が残った場合、後遺障害等級に認定される可能性があるでしょう。大腿骨の骨折では、もらえる後遺障害慰謝料の例は以下の通りです。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |
| 4級 | 737万円 | 1,670万円 |
| 7級 | 419万円 | 1,000万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
※2020年4月1日以降に発生した事故の場合
算定基準によって、後遺障害14級の場合は80万円弱、1級の場合は1,650万円も慰謝料の金額が変わってきます。後遺障害が残った場合は、弁護士に依頼して弁護士基準の慰謝料を請求することをおすすめします。
関連記事『交通事故による骨折の慰謝料相場はいくら?骨折部位や後遺症別の賠償金』では、骨折の部位別の慰謝料相場を紹介しているので、あわせてご一読ください。
また、アトム法律事務所では交通事故でお怪我をされた方からの相談を無料で受け付けています。慰謝料の相場や過失割合の交渉など、お困りごとがあればお気軽にお問い合わせください。
最後に、交通事故で一家の大黒柱が亡くなった場合の死亡慰謝料の計算例を見てみましょう。
交通事故で死亡した場合、死亡慰謝料の計算例は以下の通りになります。
| 被害者 | 自賠責 | 弁護士 |
|---|---|---|
| 一家の支柱 | 400万円 (350万円) | 2,800万円 |
| 遺族1名※ | + 550万円 | – |
| 遺族2名※ | + 650万円 | – |
| 遺族3名以上※ | + 750万円 | – |
| 被扶養者有※ | + 200万円 | – |
遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)
( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
※該当する場合のみ
専業主婦の妻、子ども2人を一家の大黒柱として養う自営業者の夫が亡くなったとしましょう。
この場合、自賠責基準では合計1350万円(本人分400万円+遺族3名以上750万円+被扶養者有200万円)の死亡慰謝料になるところ、弁護士基準では2800万円となります。その差額が1450万円なので、弁護士に依頼して弁護士基準の慰謝料を請求することをおすすめします。
交通事故の慰謝料は計算方法によって大きく変わりますが、それだけでなく被害者自身の対応次第によって相場の金額が得られるかどうかが決まってきます。
示談交渉の際に適正な金額を獲得するためには、証拠を揃える、適切な通院を心がける、過失割合を見直すといった工夫が重要です。
慰謝料の計算を適切に行うために必要となる具体的なポイントを解説します。
慰謝料の交渉では、証拠の有無が慰謝料の増額に大きく影響します。
加害者側の保険会社はできるだけ支払いを抑えようとするため、証拠が不十分だと、適切な金額を計算したうえで請求を行っても、低額の慰謝料しか認められない可能性があります。
相場額の慰謝料を請求するためには、次のような証拠をしっかり揃えましょう。
特に、後遺症が残って後遺障害慰謝料を請求するには、適正な等級の後遺障害に認定される必要があります。
そのためには、医師の診断内容や後遺障害診断書がカギとなるため、早い段階で医師と相談することが大切です。
関連記事
慰謝料の金額は、通院方法や頻度、治療期間などによっても大きく変わります。
相場の慰謝料を計算し、主張するためには、通院の際に以下のような点に関して注意してください。
治療期間が長期に渡ると、保険会社が「そろそろ治療費の支払いを打ち切る」と言い出すことがありますが、適切な慰謝料の請求を行うためには、医師が終了すべきと判断するまでは治療を続けるべきです。
必要な治療が終わる前に打ち切られそうな場合は、弁護士に相談して適正な治療期間を確保しましょう。
関連記事
慰謝料の金額は、被害者の過失割合(発生した交通事故に対する各当事者の責任の度合い)により減額されることがあります。たとえば、過失割合が2割の場合、受け取れる慰謝料を含む損害賠償金額が全体から2割減ってしまいます。
しかし、過失割合は保険会社が一方的に決めるものではなく、実際の事故状況に基づいて適正な判断をすべきものです。次のような場合は、過失割合の見直しを検討しましょう。
過失割合が変われば、慰謝料も増額される可能性があるため、適正な割合を主張することが重要です。
関連記事
交通事故の過失割合が納得いかない!おかしいと感じたら弁護士を通じて交渉を
交通事故の慰謝料を請求するにあたって、さまざまな疑問が生じるでしょう。よくある疑問をまとめて紹介していきます。
主婦でも交通事故の慰謝料は請求できます。
慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償金と位置付けられているので、被害者の立場にかかわらず請求可能な賠償金だからです。
慰謝料の請求に関しては、専業主婦でも兼業主婦でも関係ありません。
また、性別による差異もなく、男性の主夫に対しても慰謝料は支払われます。(本記事では便宜上、専業主婦・兼業主婦、専業主夫・兼業主夫のすべてを「主婦」と表して説明を進めます。)
慰謝料の計算方法についても、主婦であることで変わりはありません。
もっとも、主婦の場合、休業損害や逸失利益といった補償の請求に関して、主婦という立場が影響してくるので注意しましょう。
主婦という立場が与える計算方法への影響
| 入通院慰謝料 | ない |
| 後遺障害慰謝料 | ない |
| 死亡慰謝料 | ある |
| 休業損害 | ある |
| 後遺障害逸失利益 | ある |
| 死亡逸失利益 | ある |
主婦が交通事故の被害者となった場合に特化した以下の関連記事では、計算方法はもちろん、主婦手当と呼ばれる休業損害の計算方法など、主婦特有の疑問をまとめて解説しています。
主婦(主夫)向けの解説記事
学生や無職であっても慰謝料を請求することが可能です。
もっとも、主婦の場合と同じように、休業損害や逸失利益といった補償の請求に関しては、事故当時の立場(年齢、学歴など)が影響してくるので注意しましょう。
学生・無職の方向けの解説記事
整骨院への通院も、医師の指示があるのであれば慰謝料は認められます。
ただし、事故後、いきなり整骨院に行くのではなく、まずは病院を受診するようにしましょう。
そして、病院の医師から整骨院への通院許可をもらってください。
整骨院への通院がはじまっても、病院への定期的な通院も継続して行うことが大切です。
関連記事『交通事故の治療を整骨院で受けても慰謝料はもらえる』では、整骨院へ通う場合の注意点についてわかりやすく解説しています。
慰謝料は「精神的苦痛に対する補償」である一方、休業損害と逸失利益はどちらも簡単に述べると「収入に関する補償」となります。休業損害や逸失利益は慰謝料と全く異なる補償です。
休業損害は交通事故のケガで仕事を休んだことで失った収入のことをいい、逸失利益は交通事故がなければ得られたはずの将来的な収入のことをいいます。
休業損害は「基礎収入×休業日数」で計算します。
ただし、基礎収入の求め方は、用いる計算基準と職業によって異なります。
休業損害の詳しい計算方法については下記の関連記事が参考になります。こちらの関連記事では、休業損害に特化した計算機も紹介していますのであわせてご確認ください。
関連記事
交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方・いつもらえるか弁護士解説
逸失利益は、後遺障害等級に認定された場合に請求できる後遺障害逸失利益と、死亡事故の場合に請求できる死亡逸失利益に分けられます。
後遺障害逸失利益と死亡逸失利益は用いる計算式が異なり、被害者が若年の未就労者の場合も計算式が変わってくるので注意が必要です。
逸失利益は記事冒頭の「慰謝料計算機」で自動計算できますので、ぜひご活用ください。
逸失利益の詳しい計算方法については下記の関連記事が参考になります。
関連記事
交通事故の逸失利益は?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】
交通事故の被害者は、慰謝料・休業損害・逸失利益の他に、治療関係費や介護費用など、損害に応じた項目を請求できます。
具体的には、主に以下のような損害について請求が可能です。
| 内容 | |
|---|---|
| 治療関係費 | 治療のために必要となった投薬代、手術費用、交通費など |
| 介護費用 | 被害者の介護に必要となる費用。将来分も請求可能 |
| 葬儀費用 | 死亡事故の場合における被害者の葬儀のための費用 |
| 物損 | 自動車の修理費用や代車費用など |
具体的な計算方法については下記の関連記事をご覧ください。
関連記事
交通事故の損害賠償とは?賠償金の範囲や計算方法、請求時の注意点を解説
被害者だけで保険会社と示談交渉を進めても、被害者が本来手にできるはずの慰謝料額を得られる可能性は非常に低いです。
適正で妥当な慰謝料を得るためには、弁護士の存在が欠かせません。
加害者側の任意保険が提示する慰謝料を含む示談金の金額は適正ではありません。
適正な慰謝料といえるのは、弁護士基準で計算した慰謝料です。
もっとも、弁護士基準で計算して適正な金額を算出するには、事故における個別事情を考慮することが必要な場合があるため、機械的に算出できるとは限りません。
弁護士であれば、事故における個別事情を考慮したうえで、適正な金額を算出することが可能です。
加害者側の任意保険会社が提示する慰謝料を含む示談金の金額は、基本的に適正な金額ではないため、示談交渉において増額交渉が必要です。
しかし、示談交渉にプロである任意保険会社相手に増額交渉を行っても、知識や経験の差から、任意保険会社はほとんど増額には応じてくれません。
弁護士基準で算出した適正な金額に増額したいのであれば、専門家である弁護士に依頼して示談交渉を行ってもらいましょう。
専門家である弁護士による根拠のある主張であることや、増額に応じない場合には裁判に発展する恐れがあることから、任意保険会社が増額に応じる可能性が高くなるのです。
交通事故の示談の基本的な内容や、弁護士に示談交渉を頼むメリットなどについて解説した関連記事『交通事故の示談とは?示談交渉の流れや示談をうまく進めるための注意点』もあわせてごらんください。
弁護士に依頼した方がいいとわかっても、気になるのは弁護士費用の存在です。
弁護士費用が高くつくと、依頼する必要もないと思われるかもしれません。
そんな時は、ご自身が加入する任意保険に「弁護士費用特約」が付帯されているか確認してみましょう。
弁護士費用特約が付いていれば、上限はあるものの弁護士費用を自己負担することなく弁護士に依頼することができます。
弁護士費用特約の特徴については、関連記事『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』が参考になりますので、あわせてご確認ください。
弁護士費用特約を利用できない場合でも、弁護士への依頼を検討することをおすすめします。
「弁護士に依頼すると弁護士費用がかかるだろうからやめておこう」と判断されがちですが、弁護士費用を差し引いても弁護士に依頼した方が多くの金額が手元に入るケースも非常に多いためです。
実際に弁護士費用がいくらかかるか知り、増額幅との比較をすれば、弁護士に依頼したことで損をすることはないでしょう。
簡単に弁護士費用と慰謝料の増額幅を比較する方法としては、各法律事務所が実施している無料相談を利用して見積もりをとることがあげられます。
治療が終わっている、保険会社から慰謝料が提示されているといった状況なら、弁護士費用と慰謝料の増額幅の両方の見積もりを作ってもらえることが多いです。
具体的に弁護士費用がいくらかかるかは、法律事務所によって異なります。目安として弁護士費用の相場を知りたい方は、『交通事故の弁護士費用相場はいくら?弁護士費用特約を使って負担軽減』の記事をご覧ください。
実際に見積もりをとってみて、弁護士に依頼した方がよいのか確認してみましょう。
弁護士費用特約がなかったり、弁護士費用を払ってまで依頼すべき案件かどうかわからないような場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。
交通事故の被害者の方を対象に、弁護士による法律相談を無料で受け付けています。
慰謝料に関することはもちろん、交通事故で被害を受けた方のあらゆる悩みに対して弁護士が真摯にお答えします。
まずは予約受付窓口にお問い合わせいただき、無料相談の予約をお取りいただくところからお願いしています。予約受付窓口は24時間いつでも受付中なので、空いた時間を使って気軽にお問い合わせください。

実際にアトム法律事務所で慰謝料増額を叶えられた方からは、以下のようなお声をいただいております。
常に迅速丁寧にご対応いただき感謝しています。想定以上の賠償金を受け取れました。自分一人で対応していたら絶対に不可能な金額だったと思います。この度は本当にありがとうございました。
ご依頼者からのお手紙
交通事故で担当して頂きました。仕事が忙しい為、個人で保険会社と話し合いを行うのは時間的にも精神的にも負担になるところを、すべて担当して頂き、短い時間で納得のいく解決をして頂けました。有難うございました。
ご依頼者からのお手紙
この度は誠にお世話になりありがとうございました。やはり示談交渉はプロの先生にお願いするのがベストだと感じました。
ご依頼者からのお手紙

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。








