山道で対向車がセンターラインオーバーし腰椎破裂骨折を負った事例
弁護士に依頼後...
回収
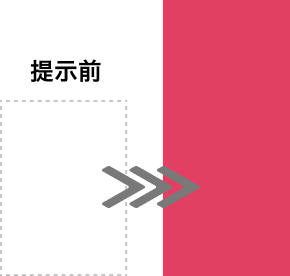
更新日:

交通事故の後遺障害11級とは、著しい目の調節機能障害や運動障害、歯の欠損、聴力障害、脊柱の変形障害、手足の指の障害、内臓の障害などで認定される等級です。
後遺障害11級における慰謝料相場は420万円です。加えて数百万〜数千万円の後遺障害逸失利益やその他の賠償金も請求できるため、示談金全体では1,000万円を超えるケースもあります。
後遺障害11級の認定基準や慰謝料・逸失利益の相場・計算方法、11級の認定を受けるポイントを見ていきましょう。
目次
後遺障害の認定基準は、「交通事故損害賠償法施行令」で定められています。後遺障害11級の認定基準は以下の10区分です。
後遺障害11級の認定基準
| 11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
| 11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
| 11級3号 | 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
| 11級4号 | 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 11級5号 | 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの |
| 11級6号 | 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの |
| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
| 11級8号 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの |
| 11級9号 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの |
| 11級10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
「著しい調節機能障害」「労務の遂行に相当な程度の支障がある」など、具体的にイメージしづらいものも多いのではないでしょうか。
それぞれの認定基準を、詳しく確認していきましょう。
後遺障害11級1号の症状は、「両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの」です。
「眼球の著しい調節機能障害」「眼球の著しい運動障害」とは、具体的には以下のような状態を指します。
両目の障害
※注視野とは:頭を固定した状態で直視できる範囲のこと
両眼が著しい調節機能障害を負った場合、年齢別の調節力と比較して程度を判定することになります。
眼球周辺の筋肉などに麻痺が残り、目のピントを合わせる能力が半分以下になるか、頭を固定した状態の視野が半分以下になった場合、後遺障害11級1号に認定されるのです。
もっとも、55歳以上の場合は通常年齢のため調節力が低下しているため、後遺障害認定を受けられません。
交通事故による目の後遺症については『交通事故による目の後遺障害と慰謝料相場|失明・視力低下などの認定基準』の記事で網羅的に解説しています。調節機能障害・運動障害の測定方法もわかるので、あわせてご一読ください。
後遺障害11級2号の症状は、「両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの」です。「まぶたに著しい運動障害を残す」とは、以下のような状態をいいます。
まぶたの著しい運動障害とは
両方のまぶたに麻痺などが残り、目を開いたときに瞳孔が隠れてしまうか、目を閉じたときに角膜が完全に覆われない状態になると、後遺障害11級2号に認定されるでしょう。
後遺障害11級3号の症状は、「一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの」です。
片目のまぶたが欠損し、目を閉じたときに角膜が完全に覆われない状態になると、後遺障害11級3号に認定されることになります。
後遺障害11級4号の症状は、「十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」です。
後遺障害認定における歯科補綴の定義とは、「喪失した歯や歯冠部の4分の3以上を欠損した歯を義歯やクラウンなどで補った」を指します。
なお、ブリッジでダミーを作ったような状況で失った歯と義歯の数が異なる場合、失った歯の数をカウントしてください。
また、親知らずは認定の対象となりません。乳歯についても、永久歯が生えないという医師の証明がなければ認定の対象とはならないでしょう。
10本以上の歯が失われるか歯冠部の4分の3以上が欠け、義歯などの治療で補った場合、後遺障害11級4号に認定されるのです。
歯に関する後遺障害は、欠損だけではありません。詳しく知りたい方は『交通事故で歯が折れたら慰謝料いくら?前歯欠損は後遺障害認定される?』の記事をご覧ください。
後遺障害11級5号の症状は、「両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの」です。
具体的には、「両耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上」の状態を指します。
上記の聴力では、1メートル以上の距離では小声を聞き取れないとみなされ、後遺障害11級5号に認定されるのです。
聴覚に関する後遺障害については『交通事故での聴覚障害や難聴(聴力低下)、耳鳴りの後遺障害|等級や認定ポイント』の記事で網羅的に説明を行っています。
聴力低下以外の聴覚に関する後遺障害に関しても知ることができるので、聴力低下以外にも聴覚に関する後遺症が気になる方は、一度ご覧ください。
後遺障害11級6号の症状は、「一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの」です。
具体的には、以下の状態をいいます。
後遺障害11級の聴力障害
聴力低下の結果このような検査結果が出た場合には、40センチメートル以上の距離では普通の話声を聞き取れないとみなされ、後遺障害11級6号に認定されるでしょう。
なお、片耳の平均純音聴力レベルが90デシベル以上という検査結果になったときには、ほとんど聞こえないような状態と判断される見通しです。
そうすると「一耳の聴力を全く失った」として後遺障害9級認定される可能性があります。
後遺障害11級7号の症状は、「脊柱に変形を残すもの」です。
「脊柱に変形を残す」とは、以下のいずれかの状態に該当していることを言います。
後遺障害11級の脊柱変形
脊椎に変形が残っていることが客観的にわかる場合や手術を受けている場合、後遺障害11級7号に認定されることになります。
脊柱の変形は圧迫骨折によって起こることが多いです。
関連記事『交通事故による圧迫骨折の後遺障害等級の基準と慰謝料・逸失利益を弁護士が解説』もお読みいただければ、より後遺障害認定や損害賠償請求について理解を深められます。
後遺障害11級8号の症状は、「一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの」です。
「指を失った」とは、具体的には以下の状態をいいます。
手指の骨や関節の位置は、以下の図をご覧ください。
つまり、片手の人差し指、中指、薬指のいずれかを根元から失った場合、後遺障害11級8号に認定されるのです。
交通事故で手指を切断した障害については、どの指か、欠損した指の本数は何本かなどでこまかく等級が変わります。たとえば、片方の親指を失ったら後遺障害10級認定となる見通しです。
以下の関連記事もあわせて参考にご覧ください。
関連記事
後遺障害11級9号の症状は、「一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの」です。
「足指の用を廃した」とは、以下の状態のことを指します。
つまり、片足の親指を含む2本の足指が途中で切り離されたか麻痺などで動かなくなった場合、後遺障害11級9号に認定されることになります。
足指が曲がらない症状が残った方は『交通事故で足指を切断した・曲がらなくなった|後遺障害等級の認定基準は?』の記事もご一読ください。後遺障害認定を受けるためのポイントがわかります。
後遺障害11級10号の症状は、「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」です。
内臓に障害が残り、働くことはできるものの業務にかなりの差し障りがある場合、後遺障害11級10号に認定されます。
11級10号に認定されうる症状は、内臓の種類ごとに異なります。器官系ごとに詳しく確認していきましょう。
呼吸器の状態として、以下のような検査結果となったときには後遺障害11級10号に認定される見込みです。
呼吸器の状態
循環器の状態として、以下のような検査結果となったときには後遺障害11級10号に認定される見込みです。
循環器の状態
消化器(胃・大腸・小腸など)の状態として、以下のような検査結果となったときには後遺障害11級10号に認定される見込みです。
消化器の状態
泌尿器の状態として、以下のような検査結果となったときには後遺障害11級10号に認定される見込みです。
泌尿器の状態
交通事故による内臓機能障害の後遺障害認定については『交通事故での内臓損傷・内臓破裂の後遺障害等級と認定ポイント、慰謝料相場を解説』の記事で網羅的に解説しています。こちらの記事もご確認ください。
後遺障害11級に認定されたら、治療終了後にも残る損害への補償として、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できるようになります。
後遺障害11級の場合、自賠責基準だと後遺障害慰謝料と逸失利益は合計で331万円です。弁護士基準だと後遺障害慰謝料だけでも420万円で、さらに事故前の年齢や年収に応じた逸失利益が加わります。
後遺障害11級の慰謝料・逸失利益について詳しく解説します。
後遺障害11級の慰謝料相場は420万円です。この金額は裁判でも認められ、法的に正当性の高い弁護士基準(裁判基準)による相場となります。
ただし、加害者側の任意保険会社は、示談交渉で「自賠責基準」や「任意保険基準」という別の基準に沿った金額を提示してきます。
自賠責基準とは、法令で定められた最低水準の金額です。後遺障害11級の後遺障害慰謝料は、自賠責基準だと136万円となります。
任意保険基準は任意保険会社独自の基準です。各社で異なり非公開ですが、自賠責基準と同水準であることが多いです。
後遺障害11級の後遺障害慰謝料
| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
|---|---|---|
| 11級 | 136万円 (135万円) | 420万円 |
たとえ加害者側が自賠責基準や任意保険基準の金額を提示してきても、弁護士が示談交渉すれば、弁護士基準まで増額できる可能性があります。
弁護士に依頼すると他の示談金の費目も高額になりやすいため、弁護士費用がかかったとしても、弁護士に依頼した方が多くの金額が手元に入ることが多いです。
また、弁護士費用の負担は任意保険の「弁護士費用特約」で軽減できます。
まずは無料相談で弁護士に増額幅の見積もりをとってみましょう。
後遺障害逸失利益は、後遺障害の影響で減ってしまう生涯収入を補償するものです。
事故時の年齢や年収、後遺障害によりどの程度労働能力が低下するかなどの要素から金額が決まります。具体的な計算方法は以下のとおりです。
逸失利益の計算式
例えば被害者が37歳で症状固定となり、事故前の収入が500万円だったとすると、逸失利益の計算は以下のとおりです。
逸失利益の計算例
500万円×労働能力喪失率20%(0.2)×ライプニッツ係数19.60=1,960万円
ここでは、労働能力喪失率や労働能力喪失期間、ライプニッツ係数とは何なのか解説します。
なお、手っ取り早く逸失利益の相場を知りたい場合は、以下の計算機をご利用ください。
関連記事『交通事故の逸失利益は?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】』も参考になります。
労働能力喪失率とは、後遺障害によって労働能力がどの程度低下したかを示す数値です。
後遺障害等級ごとに目安が決められており、11級の場合は20%となります。
ただし、労働能力喪失率はあくまでも目安です。実際にどの程度仕事に影響が出ているかによって、増減することもあります。
労働能力喪失期間は、後遺障害による労働能力低下の影響を受ける期間のことです。原則として「症状固定~67歳」の年数だと考えてください。
ライプニッツ係数とは、逸失利益として受け取った金額を預金・運用する中で生じる利益をあらかじめ差し引くための数値です。
労働能力喪失期間に応じて決まっています。
労働能力喪失期間ごとのライプニッツ係数
| 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
|---|---|
| 1年 | 0.97 |
| 5年 | 4.58 |
| 10年 | 8.53 |
| 20年 | 14.88 |
| 30年 | 19.60 |
大阪地判平27・4・16(平成26年(ワ)第3004号)
シルバー人材センターで清掃作業に従事する77歳の女性が、夕方5時30分頃に赤信号を無視して横断歩道を横断中、青信号を直進してきた普通乗用車と衝突。女性は左脛骨骨幹部骨折、頚椎骨折など重篤な多発骨折を負い、後遺障害等級併合11級の認定を受けた。
「…併合一一級と判断するのが相当である」
大阪地判平27・4・16(平成26年(ワ)第3004号)
84万1,671円
高齢者であっても就労実績があれば逸失利益は認めらます。
この判例では、女性には「赤信号無視」という重大な過失があったにもかかわらず、裁判所は彼女の労働能力と将来の収入の機会を評価し、約84万円の逸失利益を認定しました。
労働能力喪失期間は原則として症状固定時から67歳までですが、高齢者の場合は平均余命の約2分の1とする傾向があります。55歳以上の男性及び50歳以上の女性については、平均余命の2分の1の年数に対応する係数を使用することが一般的です。
後遺障害11級の認定を受けても、以下の場合は逸失利益がもらえない可能性があります。
それぞれについて解説します。
後遺障害が残っても、減収が生じていない場合は逸失利益を請求できないことがあります。
逸失利益は、後遺障害による減収を補償するものだからです。
ただし、本来なら減収が生じているはずのところ、周囲の理解や協力、本人の努力によって減収せずに済んでいるだけなら、逸失利益を請求できる可能性があります。
後遺障害が残っても、仕事への影響が小さいと逸失利益がもらえなかったり、低額になったりすることがあります。
例えば後遺障害11級7号の脊柱変形は、デスクワークなど身体的負担の少ない職業では、影響が小さくなることもあります。
この場合、労働能力喪失率は20%以下だとされ、逸失利益が低額になる可能性があるのです。
後遺障害に見合った逸失利益をきちんと請求するには、診断書や検査結果などを根拠に、後遺障害の程度や仕事への影響を主張することが重要です。
ただし、逸失利益は高額になりやすい分、示談交渉で揉める傾向にあります。お困りの場合はぜひ弁護士にご相談ください。
交通事故に遭った場合、後遺障害慰謝料や逸失利益以外にも請求できる費目があります。
よって、後遺障害11級の示談金の総額は1,000万円を超えることも十分あるでしょう。
後遺障害11級認定を受けたときの示談金の費目の代表例を以下に示します。
交通事故の示談金内訳(後遺障害認定を受けた場合)
| 概要 | |
|---|---|
| 治療関係費 | 治療費、入院費、手術費、付添看護費など |
| 入通院慰謝料 | ケガを負った精神的苦痛の補償 |
| 休業損害 | 休業や家事ができないことへの補償 |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害による精神的苦痛の補償 |
| 逸失利益 | 後遺障害による将来的な収入減の補償 |
| 修理関係費用 | 修理費用、評価損など |
関連記事『交通事故の示談金相場は?一覧表や増額のコツ・示談交渉の注意点を弁護士解説』では、よりくわしく交通事故の示談金の費目や内訳を解説しています。
次に、後遺障害11級に認定されるまでの流れと、適切な認定を受けるためのポイントを見ていきましょう。
後遺障害11級の認定を受ける流れは、次の通りです。
(1)医師から症状固定の診断を受ける
(2)後遺障害診断書の作成を依頼する
(3)後遺障害の申請をする
各フェーズに分けて解説します。
後遺障害認定の申請をするのは、医師から「症状固定」と診断されたあとです。
症状固定とは、「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと判断された状態」のことを言います。症状固定と診断されたことは、すなわち交通事故による後遺症が残ったこということです。
なお、後遺障害認定を受けるためには、治療開始から症状固定までおおよそ6か月経過していることが必要になります。
ただし、指の欠損といった後遺障害の残存が客観的に明らかな症状は6か月経過していなくても後遺障害認定を受けられる可能性があります。
症状固定の診断を受けたら、医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼しましょう。
後遺障害診断書とは、症状固定日、他覚症状、検査結果といった内容が記載されている書類です。後遺障害認定の際には提出しなければなりません。
様式は相手方の自賠責保険会社から取り寄せるか、インターネット上でダウンロードできます。
後遺障害診断書の準備ができたら、後遺障害の申請方法についても検討しましょう。
後遺障害認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2つがあり、被害者が手間をかけずに済む、後遺障害認定されやすい工夫ができるなど、それぞれに特徴があります。
事前認定と被害者請求の特徴について、手続きの手間、書類提出時の工夫、被害者の準備書類について比較してみましょう。
事前認定と被害者申請のメリット・デメリット
| 事前認定 | 被害者請求 | |
|---|---|---|
| 準備・手間 | かからない | かかる |
| 提出の工夫 | しづらい | しやすい |
| 準備書類 | 後遺障害診断書のみ | すべて |
事前認定と被害者請求のどちらで申請するのが最適かは、症状によって異なります。ご自身の場合はどちらを選べばよいか迷ったら、無料相談で弁護士からアドバイスを受けるようにしましょう。
後遺障害11級の認定を受けるためには、事故と後遺障害との因果関係を証明するようにしましょう。
後遺障害11級の症状の中には、交通事故以外の要因で発生しうるものもあります。
例えば腰椎圧迫骨折は後遺障害11級7号に認定されうるものですが、骨粗鬆症などにより、日常生活の中でも発生することがあるのです。
交通事故にあったら速やかに病院で受診し、定期的な治療や検査を受け、「この症状は交通事故で生じたものだ」と証明できるようにしておきましょう。
後遺障害診断書は、後遺障害認定の審査でとくに重要な書類です。後遺障害診断書に不適切な記載があったため、本来なら認定されるはずの等級に認定されないこともあります。
後遺障害診断書の記載に問題がないかは、後遺障害認定を取り扱っている弁護士に確認を受けることをおすすめします。
「医師に任せていたら大丈夫だろう」と思われる方もいらっしゃいますが、医師は医療の専門家であり、後遺障害認定の専門家ではありません。
後遺障害診断書の記載例は、『後遺障害診断書とは?もらい方と書き方、自覚症状の伝え方を解説』の記事で紹介しています。様式もダウンロードできるため、ぜひお役立てください。
後遺障害11級に該当する症状で障害者手帳を取得することは、基本的に難しいでしょう。後遺障害11級の症状では、障害者手帳の交付条件である「身体障害者障害程度等級6級以上」を満たさないからです。
もっとも、他に条件を満たす後遺障害が残っていれば、障害者手帳の交付とそれによる補償を受けられる可能性はあります。後遺障害等級と障害者手帳の関係や、手帳を受け取るための具体的な申請方法などについては、『後遺障害等級の認定で「障害者手帳」ももらえる?交付の基準と申請方法』の記事をご覧ください。
一方、労災保険からは条件を満たしていれば保険金を受け取れます。後遺障害に関する保険金を挙げると、以下のとおりです。
労災保険の支給ルールは一律であるため、増額という考え方はありませんし、同じ損害についての補償を労災と任意保険の両方から二重で受け取ることはできない決まりです。
ただし労災保険から慰謝料は一切支払われないため、交通事故の賠償にくわしい弁護士にも相談して、適正な慰謝料獲得を目指していきましょう。
関連記事『労災保険と自賠責保険の優先順位は?慰謝料請求は自賠責・任意保険へ』では、労災事故でもあり、交通事故でもある場合の対応をわかりやすく説明しています。
後遺障害11級に認定される可能性がある場合は、一度弁護士にご相談ください。
弁護士に相談・依頼するメリットや、無料相談のご案内を紹介します。
交通事故により後遺症が残り、後遺症の症状が後遺障害に該当する可能性があるなら、弁護士に相談するべきです。
弁護士に相談や依頼を行うことで、以下のようなメリット受けることができます。
弁護士相談・依頼のメリット
それぞれのメリットの具体的内容を、以下において紹介します。
後遺障害等級11級の認定を受けるためには、後遺症の症状が11級各号の症状に該当することを、後遺障害診断書の記載内容やそのほかの書類により証明する必要があります。
証明のために必要となる後遺障害診断書の記載内容や、書類の種類などについては、専門家である弁護士が熟知しているのです。
そのため、弁護士に依頼を行うと、後遺障害等級11級の認定を受けるために必要な書類の作成や収集のサポートを受けることができるため、11級の認定を受けられる可能性が上昇します。
弁護士に依頼すると、弁護士が加害者側からの連絡の窓口となってくれます。そのため、相手方からの連絡に対する対応を弁護士に任せることが可能となるのです。
後遺障害等級11級に該当するような後遺症が生じているのであれば、長期の治療やリハビリが必要となることも珍しくありません。
その中で相手方への対応まで行うと、身体的にも精神的にも疲労がたまってしまう恐れがあります。
弁護士に窓口となってもらうことでこのような疲労を回避し、穏やかな生活を取り戻すことに専念することができるのです。
後遺障害11級に認定されたら、相手方の任意保険会社と慰謝料・示談金の金額などを決める「示談交渉」を行うことになります。
相手方の任意保険会社は、本来被害者が受け取れる慰謝料・示談金より大幅に低い金額を提示してくることが多いでしょう。
相場の金額で示談するには増額交渉が必要となりますが、知識や示談交渉経験が豊富な相手方の任意保険会社に対して増額を認めさせることは簡単ではありません。
しかし、弁護士に依頼し、示談交渉に介入してもらうことで、交渉態度が軟化して示談でまとまる可能性も出てきます。
これまでの事例を熟知した弁護士からの根拠のある主張であり、示談交渉が決裂すると裁判となるおそれがあるためです。
どの弁護士に相談すべきか迷ったら、アトム法律事務所もご検討ください。
アトム法律事務所には、交通事故の解決実績豊富な弁護士が多く在籍しています。
また、電話・LINEでの無料相談も実施しているため、事務所にお越しいただかなくとも手軽に相談が可能です。
弁護士費用については、弁護士費用特約を利用することで金銭的な負担を和らげることができます。
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、弁護士に相談・依頼する際の費用について、保険会社が代わりに負担してくれる特約です。
負担の上限は契約内容ごとに異なりますが、相談料10万円、依頼による費用300万円としていることが多く、実際の相談料や費用がこの上限を上回ることは少ないでしょう。
そのため、弁護士費用特約を利用すると、依頼者が金銭的な負担なく依頼することができるのです。
仮に、弁護士費用特約が利用できない場合であっても、アトム法律事務所では、依頼の際に生じる着手金を原則無料としているので、加害者側から賠償金を得た後に費用の支払いとすることができます。
そのため、依頼の時点で金銭的に余裕がないない方でも、依頼可能です。
無料相談の予約は24時間365日受け付けています。まずは以下のバナーからお気軽にお問い合わせください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。









