バイク対バイクの事故で左足甲骨折し併合10級の事例
弁護士に依頼後...
回収
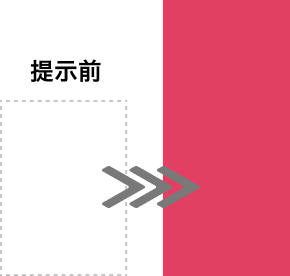
更新日:

交通事故後、後遺障害10級に認定されうる症状は11種類あり、目や耳、歯、手足の指・関節など様々です。
具体的には「片目の視力が矯正しても0.1以下」、「14本以上の歯が入れ歯」、「腕や足の関節の動く範囲が、半分以下」などの症状は、後遺障害10級に該当する可能性があります。
後遺障害10級の症状は、一般に、労働能力を27%低下させると考えられています。精神的苦痛を受けるだけでなく、生涯収入にも影響が大きいです。
本記事では、後遺障害10級の症状と認定基準、精神的苦痛の賠償金(後遺障害慰謝料)や、生涯収入の減少を補償する「逸失利益」の相場などを解説します。
目次
後遺障害等級の認定基準は「交通事故損害賠償法施行令」で規定されています。
後遺障害10級の認定基準は以下のとおりです。
後遺障害10級の認定基準
| 10級1号 | 一眼の視力が〇・一以下になつたもの |
| 10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
| 10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
| 10級4号 | 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 10級5号 | 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの |
| 10級6号 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの |
| 10級7号 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの |
| 10級8号 | 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
| 10級9号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの |
| 10級10号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 10級11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
どのような症状が後遺障害10級に認定されるのか、各号ごとの基準を具体的にみていきましょう。
後遺障害10級1号の症状は、「一眼の視力が〇・一以下になつたもの」です。
眼鏡やコンタクトを使った時の片目の視力(矯正視力)が0.1以下になった場合、後遺障害10級1号に認定されることになります。裸眼の視力は含みません。
なお、事故前から矯正視力が0.1以下だった場合は、後遺障害10級には該当しません。
後遺障害10級2号の症状は、「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」です。
複視を残す定義は、以下のいずれにも該当する場合になります。
複視とは、眼筋の麻痺などによって、ものが二重に見えることです。
なお、正面以外を見た時に複視の症状がある場合は、後遺障害13級に認定される可能性があります。
交通事故による目の後遺症の後遺障害認定については『交通事故による目の後遺障害と慰謝料相場|失明・視力低下などの認定基準』の記事で解説しているので、ご確認ください。
神戸地判平26・11・5(平成25年(ワ)第322号)
交差点を右折しようとした原告X(症状固定時61歳)運転の原動機付自転車に、後方から直進してきた被告Y運転の普通自動二輪車が右側から追い抜こうとして衝突した事例。原告Xは左滑⾞神経⿇痺により正面視での複視の後遺障害(後遺障害10級2号)が残存した。
「後遺障害等級10級2号の程度を超えるものとはいえず、被告主張の不安障害の影響を受けているものとはいえない」
神戸地判平26・11・5(平成25年(ワ)第322号)
599万1,353円
後遺障害10級3号の症状は、「咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの」とされます。
咀嚼機能に障害を残す定義は、以下のとおりです。
咀嚼機能の障害とは
固形の食べ物のうち、たくあん、らっきょう、ピーナッツなど一定の固さのものは咀嚼がまったくできないか、十分にできない
言語機能に障害を残す定義は、以下のとおりです。
言語機能の障害とは
以下の4種の子音のうち、1種以上の発音ができない
かみ合わせや顎関節などの障害で固めの食べ物を十分に噛めないか、一部の音が発音できない場合、後遺障害10級3号に認定されることになります。
両方の障害が残った場合は、後遺障害9級に認定されるでしょう。
後遺障害10級4号の症状は、「十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」です。
歯科補綴とは、歯を失ったり著しく欠損したりした場合、入歯やブリッジなどの人工物で補う処置のことをいいます。また、治療のために歯冠部を4分の3以上削ることになり欠損した場合も、歯科補綴に含まれます。
つまり、14本以上の歯に対して、入れ歯やブリッジといった処置が行われた場合、後遺障害10級4号が認定されることになるでしょう。
なお、交通事故によって歯を失ったり欠損した場合の後遺障害認定については、『交通事故で歯が折れたら慰謝料いくら?前歯欠損は後遺障害認定される?』の記事で網羅的に解説しています。
後遺障害10級5号の症状は、「両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの」です。
具体的には以下の症状が後遺障害10級5号に該当します。
後遺障害10級6号の症状は、「一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの」です。
具体的には以下の聴力だと、大声でも耳に接しなければ聞き取れないと判断されます。
なお、交通事故による聴覚障害の後遺障害認定については、『交通事故での聴覚障害や難聴(聴力低下)、耳鳴りの後遺障害|等級や認定ポイント』の記事をご確認ください。
後遺障害10級7号の症状は、「一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの」です。
手指の用を廃するの定義は、以下のとおりです。
片手の親指が麻痺などで動かなくなるか、片手の親指以外の2本の指が麻痺などで動かなくなった場合、後遺障害10級7号に認定されることになるでしょう。
手指の可動域制限の後遺障害については『指切断・欠損、指が曲がらない可動域制限、マレット指の後遺障害等級認定基準』の記事でも紹介しています。上記の認定基準に当てはまらない方はこちらの記事もご参考ください。
後遺障害10級8号の症状は、「一下肢を三センチメートル以上短縮したもの」です。
X線写真などで左右の足を比較し、一方の足が3㎝以上短くなっていることが認められた場合、後遺障害10級8号に認定されることになります。
なお、ここでは3cm以上5cm未満の短縮が該当するので、5cmを超えて短くなった場合は後遺障害8級5号に認定される可能性があります。
また、子どもの場合、過成長によって片方の足が3cm以上長くなってしまったケースでも、短縮障害に準じた相当等級として、後遺障害10級8号が認定されます。
短縮障害は逸失利益の請求で相手方ともめやすいです。『交通事故による足の短縮・変形の後遺障害認定|認定基準と慰謝料がわかる』の記事もあわせてご一読ください。
後遺障害10級9号の症状は、「一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの」です。
「足指を失ったもの」とは、中足指節関節(足指の根元)から先を失った状態をいいます。
片足の親指を付け根から先まで失うか、親指以外の4本の足指を付け根から先まで失った場合、後遺障害10級9号に認定されるのです。
交通事故で足指を切断したものの、上記の認定基準に当てはまらない方は、『交通事故で足指を切断した・曲がらなくなった|後遺障害等級の認定基準は?』の基準で認定されうる等級をご確認ください。
後遺障害10級10号の症状は、「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」です。
上肢の3大関節とは、「肩関節」「ひじ関節」「手関節」ををさします。
関節の機能に著しい障害を残すの定義は以下のとおりです。
片方の肩・ひじ・手の関節のうちひとつが半分ほどしか動かなくなったり、人工関節・人工骨頭に置き換えても半分を超える程度しか動かなかったりする場合、後遺障害10級10号に認定されることになります。
なお、上肢の3大関節がほとんど動かなくなったり、人工関節・人工骨頭に置き換えても半分しか動かなかったりする場合は、後遺障害8級6号に認定されることになるでしょう。
交通事故で肩・肘・手首に可動域制限が残った方は、『肩や手首の後遺障害・可動域制限とは?』の記事もご確認ください。後遺障害認定を受けるためのヒントもわかります。
岐阜地判令3・4・13(令和1年(ワ)第489号)
信号機のない交差点で、自転車で西進中の原告Xと、普通乗用自動車で南進中の被告Yが出合頭に衝突した事例。原告Xは右鎖骨遠位端骨折を負い、右肩関節の可動域制限(健側180度に対し85度)の後遺障害(後遺障害等級は10級10号)が残存した。
「原告の治療に対する慎重かつ消極的な姿勢が相当程度影響している」
岐阜地判令3・4・13(令和1年(ワ)第489号)
925万4,888円
後遺障害10級11号の症状は、「一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」です。
下肢の3大関節とは、「股関節」「膝関節」「足関節」をさします。
関節の機能に著しい障害を残すの定義は以下のとおりです。
片方の股関節・膝関節・足関節のうちひとつが半分ほどしか動かなくなったり、人工関節・人工骨頭に置き換えても半分を超える程度しか動かなかったりする場合、後遺障害10級11号に認定されることになります。
なお、下肢の3大関節がほとんど動かなくなったり、人工関節・人工骨頭に置き換えても半分しか動かなかったりする場合は、後遺障害8級7号に認定されることになるでしょう。
3大関節のうち、股関節の後遺障害については『股関節脱臼・股関節骨折の後遺障害等級は?人工関節や人工骨頭でも後遺障害になる?』の記事で認定のポイントもあわせてご確認ください。
後遺障害10級に認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能です。
ここからは上記2費目の相場を解説します。
また、交通事故では他にも請求できる賠償金があります。この点も合わせて確認していきましょう。
後遺障害10級における後遺障害慰謝料の相場は、550万円です。
ただし、これは過去の判例に基づく基準で、弁護士や裁判所が用いる「弁護士基準」にのっとった金額です。
国が定めた最低限の金額基準「自賠責基準」では、後遺障害10級の後遺障害慰謝料は190万円です。
後遺障害10級の後遺障害慰謝料
| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
|---|---|---|
| 10級 | 190万円 (187万円) | 550万円 |
※()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用
示談交渉では、加害者側の任意保険会社は自賠責基準か、自賠責基準に近い自社独自の基準(任意保険基準)に基づく金額を提示してくるでしょう。
3つの基準の中で、最も高額かつ法的正当性が高いのは、弁護士基準です。
加害者側の任意保険会社が弁護士基準である550万円より低い金額を提示してきた場合は、そのまま受け入れるのではなく増額交渉をしましょう。
ただし、加害者側の任意保険会社は交渉のプロなので、増額交渉は難航しがちです。弁護士を立てることで提示された金額を増額させられることがあるので、弁護士への相談もご検討ください。
ご自身の保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士費用の負担は大幅に軽減できます。
後遺障害による労働能力の低下で減少する生涯収入は、逸失利益として補償されます。
後遺障害10級の逸失利益は、「労働能力が27%低下した状態で、67歳まで働くと考えた場合の減収額」です。
具体的な金額は、事故前の収入や症状固定時の年齢により異なります。
具体的な逸失利益の計算方法と、モデルケースにおける逸失利益の相場一覧は以下のとおりです。
逸失利益の計算式
計算式の補足
※国土交通省HP「各種資料」参照
モデルケースにおける逸失利益の相場一覧
| 被害者の例 | 逸失利益 |
|---|---|
| 25歳男性会社員 (平均賃金330万円) | 2112万円 |
| 40歳男性会社員 (年収700万円) | 3464万円 |
| 25歳主婦 (平均賃金310万円) | 1984万円 |
| 40歳女性会社員 (年収500万円) | 2474万円 |
逸失利益の計算式の内容や、より具体的な計算方法について詳しくは、関連記事『交通事故の逸失利益は?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】』をご確認ください。
また、以下の計算機を使えば、後遺障害慰謝料と逸失利益の目安がすぐにわかります。
交通事故で障害が残り、後遺障害10級に認定されたときに請求できる示談金は、後遺障害慰謝料や逸失利益だけではありません。
交通事故で請求できる主な請求項目については、以下のようなものがあります。
| 概要 | |
|---|---|
| 治療関係費 | 治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用、将来介護費など |
| 入通院慰謝料 | 交通事故で怪我を負った精神的苦痛の補償 |
| 休業損害 | 交通事故で休業したことによる減収の補償 |
| 後遺障害慰謝料※ | 交通事故で後遺障害が残った精神的苦痛の補償 |
| 逸失利益※ | 交通事故で後遺障害が残ったため減る生涯収入の補償 |
| 修理関係費用 | 修理費用、評価損など |
※後遺障害認定により請求可能となる
ここからは、治療関係費・入通院慰謝料・休業損害・修理関係費についてそれぞれ簡単にみていきましょう。
交通事故の怪我の治療にかかった治療費や入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費などは治療関係費として請求が可能です。基本的に、受傷から症状固定までにかかった治療に必要で相当な範囲が認められます。
また、症状固定後でも必要に応じて将来介護費や将来手術費などが認められる可能性もあるでしょう。
交通事故による怪我によって受けた精神的苦痛に対しては、入通院慰謝料の請求が可能です。
受傷から症状固定までの精神的苦痛は入通院慰謝料、症状固定以降の精神的苦痛は後遺障害慰謝料で補償されるイメージです。
後遺障害10級の症状が残るような重傷の場合、弁護士基準における入通院慰謝料の相場は以下のとおりです。
たとえば、2ヶ月の入院を経て6ヶ月の通院で治療が終了した場合、入通院慰謝料は181万円が妥当な金額といえます。この金額より保険会社の提示額が低ければ、弁護士による示談交渉で増額の可能性が見込めるでしょう。
入通院慰謝料は通院1日からでも請求可能です。関連記事『交通事故の慰謝料は通院1日いくら?』では、自賠責基準や任意保険基準の入通院慰謝料も解説していますので、併せてご確認ください。
交通事故による怪我で働けずに減少した収入に対する補償として、休業損害の請求が可能です。
ただし、休業損害の対象となるのは受傷から症状固定までの間で、仕事を休む必要性・相当性が認められた日です。
以下の計算式で休業損害は算定できます。
休業損害の計算式
計算式のより詳しい解説は、関連記事『交通事故の休業損害』をご確認ください。
交通事故によって車やバイクが壊れた場合の修理費用、評価損などを修理関係費として請求できます。
修理するか新車に買い替えるか迷った場合や評価損について詳しく知りたい場合は、関連記事『過失割合10対0の事故で新車が損壊…買い替え費用や修理代はどうなる?』が参考になります。あわせてご確認ください。
後遺障害10級で請求できる賠償金について解説しましたが、特に逸失利益については注意点があります。
また、加害者側に請求できる賠償金以外にも、交通事故では労災保険金や障害者手帳交付による補償を受けられることがあります。
後遺障害10級でもこれらの保険金・補償を受けられるのかも併せて解説します。
後遺障害10級でも、「職業柄、労働能力に影響はなく、生涯収入は減らない」と判断されると、逸失利益が認められない可能性があります。
例えばパソコン仕事の人が交通事故に遭い、片足が3cm短くなり、後遺障害10級8号に認定されたとしても、日々の業務にはそれほど影響がないと考えられます。
この場合、逸失利益の請求が認められないことがあるのです。
もし加害者側の任意保険会社から「逸失利益は発生しない」と言われたら、実際に後遺障害が業務にどう影響しているのかを主張する必要があります。
「日常生活報告書」や「医師の意見書」などを根拠として提示することがおすすめです。
大阪地判平25・8・28(平成25年(ワ)第2477号・第4017号)
片側2車線の道路を横断歩行していた原告X(当時14歳)に、被告Y運転の普通乗用自動車が衝突した事例。原告Xは高次脳機能障害(7級4号)と聴力障害(10級5号)の後遺障害が残存した事案。原告Xには、事故前から難聴の既存障害(11級程度)があった。
「もっぱら高次脳機能障害による問題である」
大阪地判平25・8・28(平成25年(ワ)第2477号・第4017号)
4,330万8,034円
たとえ後遺障害10級で逸失利益が認められても、必ずしも「労働能力27%低下」として金額が計算されるとは限りません。
業務の内容・性質から考えて労働能力喪失率が27%以下だと判断された場合は、その分逸失利益の金額が低くなるのです。
一方で、「職業柄、労働能力喪失率は27%より大きい」と判断されれば、逸失利益が高額になることもあります。
加害者側と労働能力喪失率について争う場合も、実際に後遺障害がどの程度業務に影響しているのか資料なども合わせて主張していくことが重要です。
名古屋地判平成22・10・15(平成21年(ワ)第3909号)
被告Y運転車が、信号待ちで停止中の被害車両に追突し、被害車両に同乗していた原告X(造園業)が負傷した事故。原告Aは左膝前十字靱帯断裂等の傷害を負い、左膝関節の可動域制限(健側の2分の1以下)で後遺障害10級と認定された。
「仕事の性質からすれば、(略)労働能力は35パーセント喪失したと認めるのが相当」
名古屋地判平成22・10・15(平成21年(ワ)第3909号)
3,714万0,428円
後遺障害が残った場合には、労災保険金や障害者手帳交付による補償を受けられることがあります。
後遺障害10級の場合は、条件を満たせば労災保険金はもらえますが、障害者手帳の交付は難しいでしょう。
それぞれについて解説します。
交通事故が業務中や通勤中に発生したものであれば、労災保険金を請求できます。
後遺障害10級に関連して請求できる費目は、次のとおりです。
給付基礎日額とは、事故前3ヵ月間の賃金総額を暦日数で割ったものです。
算定基礎日額は、事故前1年間に支払われたボーナスなどの特別給与の総額を365日で割ったものです。
なお、労災保険で給付されるその他の費目については、関連記事『労災保険と自賠責保険の優先順位は?慰謝料請求は自賠責・任意保険へ』にて解説しています。
後遺障害10級では、障害者手帳の交付は難しいでしょう。
後遺障害10級の症状では、障害者手帳の交付条件である「身体障害者障害程度等級6級以上」を満たさないからです。
ただし、他に条件を満たす後遺障害が残っていれば、障害者手帳の交付とそれによる補償を受けられる可能性があります。
後遺障害等級と障害者手帳の関係や、手帳を受け取るための具体的な申請方法などについては、『後遺障害等級の認定で「障害者手帳」ももらえる?交付の基準と申請方法』の記事をご覧ください。
どのような手続きをとれば、後遺障害10級認定までたどり着けるのでしょうか。ここからは、後遺障害10級に認定されるまでの流れを簡単に解説していきたいと思います。
まず、後遺障害10級の等級認定を目指すには、「症状固定」に至るまで、医師のもと、しっかりと治療をおこなう必要があります。
医学上、一般的な「治療」を続けたとしても、これ以上症状の回復が期待できなくなるタイミングがあります。
このようなタイミングを迎えると、医師から「症状固定」の診断がなされます。
後遺障害が残るようなお怪我では、多くの場合、症状固定のタイミングは事故日から約6か月程度になることが多いです。
ただし、具体的な症状・部位・治療経過によっては、後遺障害10級の症状固定のタイミングは異なります。
適切な治療・検査を経たうえで、症状固定の診断をしてもらうようにしましょう。
症状固定の診断が出ることは、交通事故によって「後遺症」が残ったことを意味します。
ただし、症状固定の診断を受けて「後遺症」が残っただけでは、交通事故によって生じた障害分の補償を請求できるようになるわけではありません。
症状固定時に残った「後遺症」が、「後遺障害」に認定されることではじめて障害分の補償を請求できるようになるのです。
症状固定の診断が出たら、医師に後遺障害診断書の作成を依頼してください。
後遺障害診断書は、後遺障害認定の申請に欠かせない資料です。
通常の診断書と違って、後遺障害診断書は症状固定日・残った他覚症状・検査結果などが記載されます。後遺障害診断書は、後遺障害を認定するか判断される審査のなかで、特に重視される書類です。
後遺障害診断書の記載内容に不備があると、本来であれば認定されたはずの等級に認定されないリスクが生じます。
申請する前に一度、後遺障害認定を専門的に取り扱う弁護士に後遺障害診断書の中身を確認してもらうのがおすすめです。
後遺障害認定に精通した弁護士であれば、後遺障害診断書の記載内容に過不足がないか、適切な表現になっているかなどチェックできるでしょう。
後遺障害認定につながりやすい後遺障害診断書の書き方や入手方法などについては、『後遺障害診断書とは?もらい方と書き方、自覚症状の伝え方を解説』の記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
後遺障害診断書が準備できたら、いよいよ後遺障害認定の申請をおこないます。
後遺障害の申請方法は、以下の2種類です。
いずれの方法にもメリットとデメリットがあるので、自身のケースや状況に応じて適切な方を選びましょう。
症状によっては障害が明らかなため、事前認定でも十分に適切な後遺障害に認定されるケースがあります。
一方、症状によっては障害の判断がむずかしく、事前認定では障害の状態を伝えるには不十分となり、適切な後遺障害に認定されないケースもあるでしょう。
こういった障害の判断がむずかしいラインの場合は、適切な後遺障害に認定されるよう積極的な工夫が行える被害者請求を選択するのがおすすめです。
もっとも、どちらの方法を選択すべきかは、自身のケースや状況をみて総合的に判断する必要があるので、後遺障害認定に詳しい弁護士に相談してみましょう。
弁護士に依頼すれば、後遺障害認定に関する手続きを一任してしまえます。
後遺障害10級に認定された方や、これから後遺障害申請をすすめようとしている場合は、弁護士に一度ご相談ください。
実際の示談金の金額に関しては、怪我の程度や通院状況、収入額など被害者の状況に応じて様々です。
先述した通り、後遺障害10級に認定された場合、後遺障害慰謝料と逸失利益に加えて、治療関係費や入通院慰謝料、休業損害など多くの損害を示談金として請求できます。どの損害をどのくらいの金額になるか漏れなく計算しておくことが重要です。
ご自身のケースではどのくらいの示談金が妥当なのか、具体的に知りたい場合は弁護士相談をおすすめします。
もっとも、相談の前に大まかな金額の目安だけでも確認しておきたい方は、以下の計算機をご活用ください。
計算機の操作方法は、後遺障害等級や治療期間などを入力するだけなので簡単です。ぜひご活用ください。
弁護士に相談すれば、これから後遺障害申請をすすめるなら申請に関するアドバイスがもらえますし、認定後の場合は任意保険会社との示談交渉について相談できます。
示談は一度でも成立してしまうとやり直しがききません。被害者が受け取れるはずの金額を取りこぼさないためには、弁護士への相談がおすすめです。
被害者だけで任意保険会社に増額を主張しても聞き入れてくれないことも多いですが、弁護士が代わりに主張することで増額の可能性が高まります。
アトム法律事務所は、弁護士による無料相談を実施しています。無料相談の予約受付は年中無休いつでも対応中です。
予約受付では、専属スタッフから法律相談で必要な事故状況や治療状況などについてお伺いさせていただきます。弁護士費用特約の有無もお伝えいただければその後のご案内もスムーズです。
認定の可能性がある後遺障害等級や、後遺障害申請で注意すべきポイント、慰謝料の増額見込みなどについて、無料相談を通して弁護士に気軽に聞いてみましょう。
無料相談の特徴

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。







