交通事故による怪我の治療の流れは?治療費の支払いや整形外科に行くべき理由も解説

交通事故で怪我をした場合は、整骨院や接骨院ではなく整形外科で医師に診断してもらい、治療を受けましょう。
病院における適切な治療を受けることで、治療費や慰謝料の請求が可能となります。
整形外科でなく整骨院や接骨院で治療を受けたい場合には、適切な手順を踏むことが必要です。
正しい手順を守ることで、整骨院や接骨院の治療であっても治療費や慰謝料は支払われます。
このページでは、交通事故後の治療の流れ、治療期間などを一通り解説していきます。ぜひ最後まで目を通して、適切な治療と妥当な補償を受けられるようにするための知識を身に着けていきましょう。
目次
交通事故の怪我の治療はまず整形外科で!
整形外科で怪我の治療をすべき理由
交通事故発生後は、速やかに病院の整形外科で受診して医師の診断を受けてください。
事故から日がたって受診すると、事故と怪我との因果関係を証明しにくくなるので、遅くとも1週間以内には受診することが重要です。
また、整骨院や接骨院ではなくまずは整形外科に行くべき理由は、次の通りです。
- 整骨院や接骨院では、MRI検査やCT検査など厳密な検査ができない
- 整骨院や接骨院では、診断書を作成してもらえない
- 整骨院や接骨院への通院では、施術料や慰謝料が補償されない可能性がある
それぞれについて、詳しく解説します。
整形外科でないと、MRI検査やCT検査など厳密な検査ができない
整骨院や接骨院では、整形外科のような厳密な検査ができません。
その結果、事故直後の怪我の様子を正確に把握できなくなり、以下のような悪影響が生じる可能性があります。
- 適切な治療ができず、治療が長引いたり完治しなかったりする
- のちの示談交渉で怪我の状態について問題になった場合、提示できる証拠がない
整形外科でないと、診断書を作成してもらえない
整骨院や接骨院では、診断書を作成してもらえません。その結果、以下のような不利益が生じる可能性があります。
- 警察に事故を人身事故として届け出られず、治療費や慰謝料の請求に支障が生じる
- 事故によって怪我したことを証明できない
- 後遺症が残っても後遺障害認定の申請ができず、後遺障害関連の慰謝料・賠償金を請求できない
整形外科でないと、治療費や慰謝料が補償されない可能性がある
整骨院や接骨院での施術は整形外科での治療と違い、厳密には医療行為ではありません。
そのため、「絶対に必要な施術ではなかった」として、施術料や慰謝料が補償されない可能性があります。
痛みがなくても事故後は整形外科に行くべき
事故による怪我が確認できず、特に自覚症状が出ていない場合でも、交通事故後は速やかに病院で受診することが重要です。
交通事故では、むちうちのように受傷後しばらくしてから症状が強くなる怪我もあります。また、事故直後は興奮状態にあり、怪我をしていても痛みを感じないケースも見られます。
そのため、痛みがなくても念のため整形外科へ行き、身体の状態を調べてもらっておきましょう。
事故直後に痛みが出なかったためにすぐに治療を行わなかった場合の対処法については『交通事故で後から痛みが…対処法と因果関係の立証方法は?判例も紹介』の記事をご覧ください。
整骨院や接骨院に通いたい場合はどうする?
適切な流れを踏まえれば、交通事故による怪我の治療で整骨院や接骨院など(以下、「整骨院等」とします。)に通うことも可能です。
整骨院等に通いたい場合は、以下の流れを守りましょう。
- 整形外科などで医師の診断を受ける
- 整骨院等に通うことについて医師の許可をもらう
- 整骨院等に通う旨を相手方の保険会社に伝える
- 整骨院等に通い始める
- 1ヶ月に1回以上、病院でも診察してもらい、治療継続の必要性を判断してもらう
- 治療の必要性が無くなるまで、病院と整骨院を併用して通い続ける
最初に整形外科に通い、医師の許可を得たうえで整骨院等に通院すると、整骨院等での施術の必要性が認められやすくなります。
そのため、整骨院等への通院でも治療費・慰謝料が補償されやすくなるでしょう。
ただし、整体院やカイロプラクティックなどは、上記の流れを踏んでも施術料や慰謝料の補償対象とならない可能性が高いです。
整骨院等と違い、整体院やカイロプラクティックは国家資格がなくても施術が可能なため、「本当に必要性のある施術なのか」が問題になりやすいからです。
各施術に必要な国家資格の種類
| 施術名・施設名 | 必要な国家資格の種類 |
|---|---|
| 整骨院 | 柔道整復師 |
| 接骨院 | 柔道整復師 |
| あん摩マッサージ指圧 | あん摩マッサージ指圧師 |
| 鍼灸 | 鍼灸師 |
| 整体院* | 必要なし |
| カイロプラクティック* | 必要なし |
*国家資格保持者が施術を行っている場合もあります
交通事故で怪我をした場合の治療の流れ
治療の流れのフローチャートは以下の通りです。

ここからは、初診以降の流れを以下に分けて解説していきます。
- 整形外科で治療を受ける
- 適切な頻度・期間で通院
- 治癒または症状固定で治療終了
- 後遺障害認定を受ける(症状固定の場合)
- 加害者側と示談交渉
警察への連絡や事故現場の安全確保、警察への捜査協力など、初診以前の事故現場での対応については、関連記事『交通事故対応の流れ|交通事故にあった・起こしたときの初期対応〜後日対応までを解説』にてご確認ください。
(1)整形外科で治療を受ける
先述の通り、交通事故で怪我をしたら、まずは整形外科で診察を受けましょう。
初診の後に診断書を作成してもらったら、警察に提出して人身事故としての処理の手続きをしてもらいます。
物損事故として届け出てしまった後でも、早い段階で診断書を出せば人身事故に切り替えられることがあります。
物損事故から人身事故へ切り替える方法については、『物損から人身への切り替え方法と手続き期限!切り替えるべき理由もわかる』にてご確認ください。
(2)適切な頻度・期間で通院
初診後は、医師の指示に従って適切な頻度・期間で通院をしましょう。
通院の頻度や期間は、以下のような慰謝料・賠償金の金額にも影響することがあります。
- 入通院慰謝料
治療期間に応じて金額が決まる。また、通院頻度が著しく低い場合には、減額されることがある。 - 後遺障害慰謝料・逸失利益
適切な頻度・期間の治療を受けずに後遺症が残っても、後遺障害認定されず、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できない可能性がある。
基本的には、3日に1回以上の通院頻度が望ましいです。
しかし、通院頻度がそれ以下でも、医師の指示によるものであり、医学的根拠があるなら問題ありません。
通院頻度と慰謝料の関係については、『交通事故の被害者は毎日通院した方がいい?通院頻度や期間と慰謝料の関係』にて詳しく解説しています。
また、後遺障害慰謝料については『後遺障害慰謝料の相場はいくら?いつ支払い?後遺障害等級認定と賠償金額のすべて』をご覧ください。
(3)治癒または症状固定で治療終了
交通事故の治療は、怪我が治癒(完治)した、または症状固定(後遺症が残った)と診断されることで終了します。
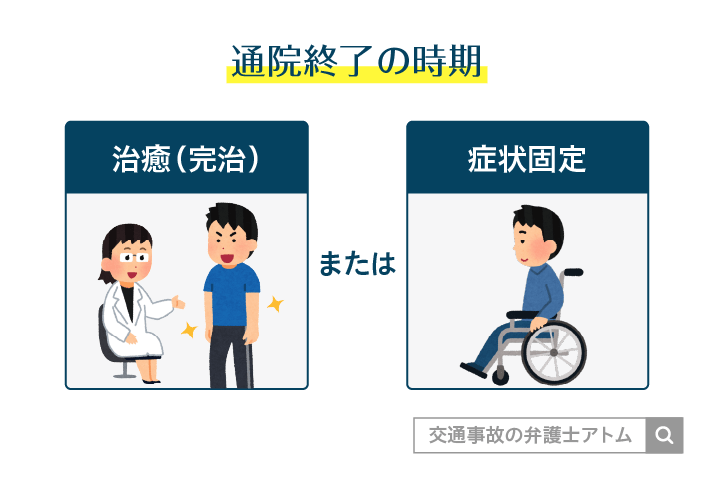
治癒や症状固定よりも前に自己判断で治療をやめてしまうと、以下の点で不利益が生じるでしょう。
- 治療期間が短くなることで、入通院慰謝料が低額になる
- 後遺症が残っても、最後まで治療を受ければ完治する可能性があるとして、後遺障害認定されない
なお、「医師から治癒と診断されてもまだ症状が残っていると感じる」、「症状固定と診断されたがまだ治療によって怪我が回復しつつある自覚がある」、といった場合は、医師に相談してみましょう。
相談の結果、治療を続けてもらえる可能性があります。
通院はいつまで続くのか、通院の継続が難しい場合はどう対処すべきかについては、『交通事故の治療はいつまで?平均治療期間や勝手にやめるリスク、やめるタイミング』にて詳しく解説しています。
(4)後遺障害認定を受ける(症状固定の場合)
症状固定の診断を受けた場合は、後遺障害認定を受けましょう。
審査の結果、後遺障害等級が認定されれば、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。
- 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を補償するもの
- 逸失利益:後遺障害により労働能力が低下することで、減少する生涯収入を補償するもの
後遺障害認定を受けるには、後遺障害診断書などの必要書類を審査機関に提出する必要があります。
基本的に書類審査となるため、書類で症状の残存や程度などを明確に示すことが重要です。
後遺障害診断書の作成は医師でなければできないため、並行して整骨院等に通院している場合でも、作成は医師に依頼しましょう。
関連記事
- 交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説
- 後遺障害診断書とは?もらい方と書き方、自覚症状の伝え方を解説
- 後遺障害認定の4つのデメリットとは?よくある誤解やメリット、申請方法も解説
(5)加害者側と示談交渉
怪我が治癒して治療が終了したり、症状固定となり後遺障害認定が終わったりしたタイミングで、加害者側との示談交渉を開始します。
基本的には、加害者側の保険担当者が慰謝料や賠償金などを算定し、示談案としてまとめて提示してくれるでしょう。
示談案に問題があれば交渉し、問題なければそのまま合意して問題ありません。ただし、示談案の慰謝料・賠償金は基本的に低く算定されています。
増額の余地があることが多いので、安易に合意するのは避けましょう。
なお、自力での交渉や、自身の保険の示談代行サービスを使っての交渉では、実現できる増額に限界があると言わざるを得ません。
十分な増額を実現するには、弁護士を立てての交渉がポイントです。
- 交通事故の示談の流れと手順!うまく進めるポイントも解説
- 示談代行サービスで保険会社に任せっきりでも大丈夫?任せるメリットとデメリット
- 交通事故の示談テクニック7つ!自分でできる交渉術と慰謝料増額の近道
交通事故の怪我の治療費はどう支払う?
パターン1. 加害者側の保険会社が病院に直接支払う
交通事故の治療費の支払いについて、事故の相手方である加害者が任意保険に加入している場合は、相手方の保険会社が治療費を直接病院に支払ってくれることがあります。
これを「任意一括対応」といいます。
この場合、被害者が病院の窓口で費用を負担する必要はありません。

なお、任意一括対応がなされるためには、任意保険会社が被害者の治療状況を知る必要があります。そのため、被害者の個人情報を取り扱うことへの同意が必要です。
任意保険会社から被害者へ同意書が送付され、同意書に必要事項を記載して返送すると、任意一括対応が開始される流れです。
任意一括対応や同意書の内容などに関して詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。
- 任意一括対応に関して具体的に知りたい
『交通事故の一括対応とは?注意点や一括対応を拒否・打ち切られた場合の対処法』 - 同意書の内容や作成によりどのようなことが生じるのかが知りたい
『保険会社の同意書はサインしても大丈夫?交通事故の医療照会は特に注意』
パターン2. 被害者が治療費をいったん立て替える
加害者側の任意保険会社に任意一括対応をしてもらえない場合は、治療費を被害者側で一旦負担する必要があります。
立て替えた治療費は、示談交渉の際に加害者側に請求しましょう。
なお、治療費立て替えの負担を軽減する方法としては、以下があります。
- 自分の健康保険を使う
- 自分の自動車保険に付いている保険で治療費を支払う
- 相手方の自賠責保険に被害者請求をする
- 労災保険を利用して治療を受ける
それぞれについて解説します。
自分の健康保険を使う
交通事故の怪我の治療でも、健康保険の利用は可能です。
以下の流れで健康保険を使えば、治療費の負担額が軽減されます。
- 加入している保険組合に、交通事故の怪我の治療で健康保険を使いたい旨を連絡する
- 病院窓口で保険証を提示し、健康保険を使いたいと伝える
- 保険組合に、「第三者行為による傷病届」などの必要書類を送付する
健康保険を使うと、自身に過失割合がつき治療費の一部が自己負担になった場合でも、負担額を減らせるなどのメリットがあります。
詳しくは『交通事故で健康保険は使える!切り替え手続きや医療保険の併用まで弁護士が解説』にてご確認ください。
自分の自動車保険を利用
被害者自身の自動車保険に人身傷害保険や無保険車傷害特約などある場合には、これらの特約を利用することで治療費の支払いを受けることが可能です。
また、特約の内容次第では、治療費以外にも慰謝料や休業損害などの支払いを受けられる可能性があります。
特約が利用できるかどうかについて、保険会社に確認を取りましょう。
人身傷害保険や類似の保険に関して詳しく知りたい方は『人身傷害補償特約は必要?いらない?補償内容や他の保険との違いとは』の記事をご覧ください。
相手方の自賠責保険に被害者請求
被害者請求とは、加害者側の自賠責保険に慰謝料・賠償金の一部を請求する手続きです。
交通事故の慰謝料・賠償金は、基本的に最低限の金額が加害者側の自賠責保険から、それを超える部分が加害者側の任意保険から支払われます。

多くの場合、すべてまとめて示談成立後に、加害者側の任意保険会社から支払われます。
しかし、被害者請求をすれば、示談成立前でも自賠責保険分の金額を受け取れるのです。
治療費の場合は、休業損害や入通院慰謝料と合わせて120万円まで、被害者請求で示談成立前に受け取れます。
被害者請求の方法について詳しく知りたい方は『交通事故の被害者請求|自賠責保険に請求するには?やり方とデメリット』の記事をご覧ください。
労災保険の利用
仕事中や通勤中の事故である場合は労災保険を利用して、治療費を負担することなく治療を受けることが可能です。
相手の自賠責保険・任意保険と労災保険ではどちらを優先すべきか、労災保険を利用するメリットについては、関連記事でくわしく解説しています。
【注意】治療費の補償は打ち切られることがある!対処法は?
まだ治療を受けているのに、相手方の保険会社から「これ以上治療を続けても意味があまり無いようなので」「そろそろ治療が終わるはずなので」といった理由で、治療費の支払いの打ち切りを打診されることがあります。
たとえば打撲・むちうち・骨折はDMK136と言われ、それぞれ1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月が治療期間の目安とされています。このタイミングで打ち切りを打診される可能性があるでしょう。
保険会社が設ける治療期間の目安|DMK136
| D1 | 打撲1ヶ月 |
| M3 | むちうち3ヶ月 |
| K6 | 骨折6ヶ月 |
しかし、治療期間は個々の怪我によって異なります。また、保険会社側に治療終了のタイミングを決める権限はありません。以下のように対応しましょう。
- 主治医にまだ治療が必要であることを確認し、その旨を相手方の保険会社に伝え、治療費打ち切りの延長を求める
- 治療費が打ち切られても治療は最後まで続け、示談交渉の際に打ち切り後の治療費を請求する
治療の必要性を医学的・客観的に証明できれば、治療費打ち切り後の費用は加害者側に請求できます。
もし保険会社から素直に支払ってもらえない場合は、訴訟や調停などで争っていくことになるでしょう。
しかし、交渉時に弁護士を立てれば、訴訟や調停まで進まずとも、治療費打ち切り後の費用を支払ってもらいやすくなります。
交通事故の治療費打ち切りに関しては、こちらの記事『交通事故で治療費打ち切りの連絡が保険会社から来た!阻止するための対応方法』でも詳しく解説しています。
関連記事
交通事故で怪我をした場合の慰謝料・賠償金
交通事故で怪我をした場合、請求できる慰謝料や賠償金としては以下があります。
- 通院や入院をした場合に請求できるもの
- 治療関連費:投薬代、手術費用、入通院の際における交通費等
- 休業損害:治療のために仕事ができなくなったことで生じる減収
- 入通院慰謝料:怪我や治療で生じる精神的苦痛への補償
- 後遺障害認定された場合に請求できるもの
- 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ることで生じる精神的苦痛への補償
- 逸失利益:後遺障害により以前のように仕事ができなくなったことで生じる将来の減収
たとえば入通院慰謝料相場額は、以下の計算表から知ることができます。(弁護士基準)
※軽い打撲や挫傷、むちうちであることが画像検査などの他覚的所見で証明できない場合の相場額

上記のケガ以外の場合における慰謝料相場は以下の表の通りです。

*縦軸は通院月数、横軸は入院月数を示す
また、後遺障害慰謝料の相場は以下の通りです。(弁護士基準)
| 等級 | 弁護士 |
|---|---|
| 1級・要介護 | 2,800万円 |
| 2級・要介護 | 2,370万円 |
| 1級 | 2,800万円 |
| 2級 | 2,370万円 |
| 3級 | 1,990万円 |
| 4級 | 1,670万円 |
| 5級 | 1,400万円 |
| 6級 | 1,180万円 |
| 7級 | 1,000万円 |
| 8級 | 830万円 |
| 9級 | 690万円 |
| 10級 | 550万円 |
| 11級 | 420万円 |
| 12級 | 290万円 |
| 13級 | 180万円 |
| 14級 | 110万円 |
*()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
慰謝料や逸失利益の大まかな相場は、以下の計算機からも確認可能です。
損害額の計算方法について詳しく知りたい方は『交通事故の損害賠償とは?賠償金の範囲や計算方法、請求時の注意点を解説』の記事をご覧ください。
交通事故の怪我・治療についてよくある質問
治療の途中で病院の変更はできる?
治療の途中でも病院を変更することは可能です。
治療方針や治療内容に納得がいかない、事故直後に搬送された病院と自宅が遠くて通院し辛い、別の病院の方がもっと専門的な治療や検査が受けられるといった理由があるなら病院を変更することもよいでしょう。
ただし、相手方の保険会社に治療費を支払ってもらっている場合、保険会社に病院を変更する旨を事前に連絡してください。
保険会社に連絡せず、無断で転院してしまうと、今後の治療費の支払に関してトラブルになってしまう可能性があります。
今の病院では十分な治療が受けられていないので病院を変更したいことや、転院先の病院で受けられる治療の特徴などもあわせて保険会社に説明できるとなおよいでしょう。
保険会社に転院を拒否されたら?
保険会社に転院を拒否されたのであれば、健康保険を利用して治療を継続し、自己負担した分の治療費については後で保険会社に交渉していくなどの対応が必要になります。
転院することでケガの回復につながる治療が受けられるなら、転院を拒否されてしまっても妥協してはいけません。
病院の変更を検討している場合は『交通事故で病院を変える注意点|転院・セカンドオピニオンの流れは?紹介状は必要?』の記事も参考になります。あわせてご確認ください。
交通事故でよくある怪我は?
交通事故で多い怪我として、むちうちがあります。
交通事故による衝撃で頭部が激しく揺さぶられて首に負担が掛かり、首の痛み、吐き気、手足のしびれなどの様々な症状が生じるのです。
正式には「頚椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」などといいます。
治療方法としては、牽引療法・電気療法・運動療法などが考えられ、通院期間は2、3ヶ月程度となることが多いでしょう。
適切な治療費や慰謝料を得るなら弁護士に相談・依頼を
治療段階から弁護士に相談・依頼するメリット
治療段階から弁護士に相談・依頼するメリットは、主に以下の通りです。
- 加害者側の保険会社から直接連絡が入ることがないので治療に専念できる
- 治療費打ち切りの対応を代わりにしてもらえる
- 治療費や慰謝料について適切な金額を請求してもらえる
- 完治しなかった場合の後遺障害認定申請もサポートを受けられる
弁護士に相談・依頼するタイミングとして、治療段階からであっても早すぎることはありません。
また、弁護士が示談交渉しないと適正相場での慰謝料獲得が難しいのが現状です。むしろいずれやってくる示談交渉に備えるためには重要といえます。
弁護士に依頼するメリットについて詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。
依頼の際には弁護士費用特約を利用しよう
弁護士に依頼する際の費用が気になる方は、自身の保険で弁護士費用特約を利用できるのかどうか確認をしましょう。
弁護士費用特約を利用すれば、弁護士に費用の負担なく弁護士に依頼できるケースが非常に多いためです。
弁護士費用特約については『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事で確認できます。
弁護士への無料相談予約を年中無休で受付中
弁護士に依頼を行うべきかどうかについては、弁護士に相談したうえで判断することが必要です。
アトム法律事務所では交通事故の被害者に向けて無料相談を受け付けています。
外出せずに相談をすることが可能な上に、ケースによっては事務所への訪問無しで請求の依頼から治療費や慰謝料等の振込みまで完了する場合もあります。
相談だけなら費用はかかりません。現在治療中の方から治療を終えた方まで、ぜひアトム法律事務所へお気軽にご相談ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了



