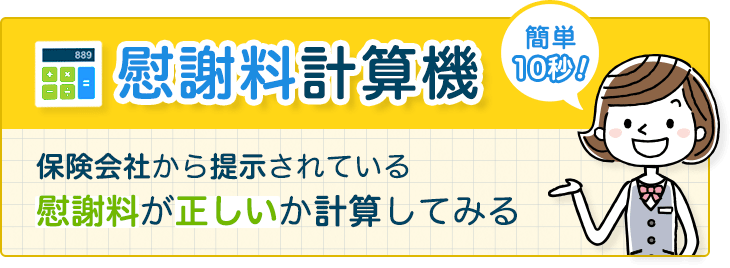交通事故の示談|弁護士による交渉で慰謝料増額と円滑な解決を目指そう!
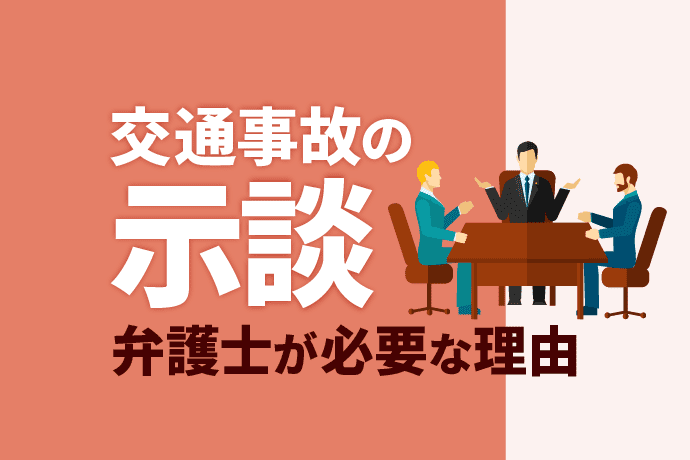
交通事故において、被害者と加害者同士が互いに紛争解決を合意することを示談といい、その時に支払われる金銭を示談金とよびます。
「示談交渉は弁護士に任せるといい」という話を見聞きする人は、こういった疑問を持っていませんか。
- 本当に弁護士に示談を任せた方が良いの?
- 弁護士に示談を任せて具体的に何が変わるの?
- 弁護士費用がかかってむしろ損をしそう
この記事は、交通事故の示談を弁護士に任せる方がいいのか、弁護士ならどんなことに対応できるのかを解説します。また、気になる弁護士費用についても説明します。「弁護士費用は高そう」と思っている人ほど、必見です。
目次
 毎日
毎日50件以上の
お問合せ
弁護士に示談を任せて示談金は増える?解決事例を紹介
交通事故の被害者の方が何よりも気になっているのは、弁護士に依頼することで十分な支払いを受けられるのか、早期に解決できるのかということでしょう。
ここでは、実際にアトム法律事務所で受任した案件の最終支払い額と、被害者へのお支払い額、契約から解決までにかかった期間をまとめてご紹介いたします。
逸失利益の主張が認められ900万円以上増額した事例
| 傷病名 | 顔の傷 |
| 事前提示額 | 780万円 |
| 最終支払い額 | 1700万円 |
| 解決までの期間 | 約3ヶ月 |
被害者は、小学生の男の子でした。遊んでいたところ車と衝突し、頭蓋骨を骨折し顔に傷が残った事案です。
当初、保険会社は後遺障害の内容が顔の傷であること、男子であることなどから逸失利益を0円として金額を提示してきました。
そこで、ご両親の協力を受けつつ、弁護士が保険会社と交渉を始めました。
主張内容は主に顔の傷が被害者の少年の今後の人生に及ぼしうる影響、また事故態様の詳細から過失割合が高すぎるという点です。
最終的に逸失利益の支払いだけでなく、過失割合の減少も認められ、大幅な増額となりました。
わずか1週間で60万円増額したむちうちの事例
| 傷病名 | むちうち |
| 事前提示額 | 40万円 |
| 最終支払い額 | 100万円 |
| 解決までの期間 | 8日 |
交通事故で最も多いむちうちの事例です。
自転車を走行させていたところ、自動車にぶつかられてしまいむちうち(頚椎捻挫)となった主婦の方でした。
依頼を受けてから弁護士が主に慰謝料の増額を交渉し、ほぼ主張が認められるかたちで示談締結となりました。
注目すべきはその解決のスピードです。契約してから保険会社との示談がまとまるまでの期間は、わずか8日でした。
弁護士に依頼したことでいかにスムーズに示談がまとまりやすくなるか、よくわかります。
将来介護費が認められ2300万円増額した事例
| 傷病名 | 脳挫傷・高次脳機能障害 |
| 事前提示額 | 1200万円 |
| 最終支払い額 | 3500万円 |
| 解決までの期間 | 約1年1カ月 |
この事案は、ご家族の自転車の後ろに乗っていた幼い女の子が車に衝突し、交通事故後にすっかり性格が変わってしまった、というものです。
このような頭への衝撃による症状を高次脳機能障害といい、認定や交渉の難しい事案の一つです。
交通事故によりご家族の負担が増大していたにもかかわらず、当初保険会社は将来介護費を認めませんでした。
示談がまとまらず、弁護士と訴訟を提起したことで相手方保険会社は介護費用を認容し、その結果、大幅な増額と共に無事和解することが出来ました。
弁護士に示談を任せるとこう変わる
- 正当な過失割合認定の主張が可能である
- 示談がスムーズにまとまる可能性が高まる
- 逸失利益や介護費用などの争いやすい示談項目にも判例を元に対応できる
- 示談が進まない場合には、裁判など次の手段へも移行できる
弁護士に示談を任せることで得られるメリットは多数あります。そこで、より具体的に弁護士への相談・依頼を検討していきたいという方は、関連記事『交通事故で弁護士相談を悩んでいる方へ|被害者の疑問を総まとめ』も併せてご覧ください。弁護士への相談・依頼にまつわる様々な疑問にもお応えしています。
交通事故の示談で弁護士が必要な理由
弁護士基準で示談金・慰謝料の増額を目指せる
交通事故の慰謝料とは、被害者が事故で負った精神的苦痛を補償する金銭とされています。しかし、精神的苦痛には個人の感じ方に違いがあるため、数値化は困難です。
そこで、慰謝料の支払いに関して一定の支払い基準を設け、基準に沿って一人ひとりの慰謝料額が決められています。
支払い基準は3つあり、誰が慰謝料を算定するかが決め手です。3つの慰謝料支払い基準は、以下の通りになっています。
- 自賠責基準…自賠責保険会社が用いる基準
- 任意保険基準…任意保険会社が用いる基準
- 弁護士基準…裁判例で支払いが認められた基準
特に、交通事故の被害者にとって重要なのは、弁護士基準です。
弁護士基準は、過去の裁判例から導き出された金額です。実際に裁判を行えば、ここまで受け取れる可能性があるという目安となります。慰謝料支払いの3基準の相場は、弁護士基準が最も高額で、自賠責基準は最も低額です。

自賠責保険は、国が法律によって加入を義務づけている、いわば最低限の補償のための保険です。したがって自賠責基準の慰謝料の金額も法律で定められています。
任意保険は、自賠責だけではまかないきれない損害を補償するもので、各保険会社が社内で独自の基準を設けています。
そのため値段は一概には言えませんが、自賠責基準とあまり変わらない金額である場合がほとんどです。
ここでは自賠責基準と弁護士基準で慰謝料を比較してみましょう。
| 自賠責基準* | 弁護士基準 | |
|---|---|---|
| むちうちで3ヶ月間・45日通院した場合 | 38.7万円 | 53万円 |
| 14級の後遺障害が残った場合 | 32万円 | 110万円 |
| 被害者(三人家族の支柱の父)が死亡した場合 | 1250万円 | 2800万円 |
なお自賠責では示談金全体の上限額が決まっており、慰謝料はこれよりも減る可能性がある
むちうちで3ヶ月間・45日通院した場合、自賠責基準では38.7万円程度の慰謝料となるでしょう。一方、弁護士基準で算定すると慰謝料相場は53万円程度になります。
14級の後遺障害が残ったとき、自賠責基準で支払われる相場は32万円ですが、弁護士基準では110万円が相場です。
死亡事故においては、三人家族の家計を支えるお父さんが死亡した場合、自賠責基準では1250万円の慰謝料が相場となりますが、弁護士基準で請求する場合の相場は2800万円です。
示談交渉の相手となる任意保険会社は、自賠責基準に近い金額を提示してくることがほとんどです。
弁護士基準は、相手方が提示してくる金額よりも3倍以上高い金額を受け取れる可能性があることがわかります。
慰謝料の決まり方がわかる記事
個人の示談交渉では弁護士基準への増額が難しい
示談金増額には、弁護士基準の算定が欠かせません。
同一の交通事故でも、誰が示談金を算定するかで、金額はずいぶん変わります。弁護士による「弁護士基準」で示談金を算定することが、極めて重要なのです。
しかし、「弁護士基準」で受け取りうる金額を知っており、保険会社に対して「弁護士基準で計算してほしい」と主張しても、その主張が受け入れられるとは限りません。

保険会社は交渉と保険のプロであり、なおかつ営利企業としてできるだけ支払う金額は少なくしたいという思惑があります。
仮に根拠を十分に用意して交渉したとしても、担当者は内部規律などを持ち出して「現在の提示額が限界」と主張することもあるでしょう。
場合によっては、被害者が根負けすることを狙っているとも考えられます。
主張の正しさの問題ではなく、いかに相手方保険会社に対し、こちらが本気で交渉しているのかを示さなければなりません。
そのための方法として裁判を起こすことが考えられますが、それよりも簡単なのが弁護士に交渉させることです。

実際に裁判を起こさずとも、専門家である弁護士を交渉の場に立たせるだけで相手方保険会社との交渉がスムーズになり、意見も呑んでもらいやすくなります。
一般的には、弁護士に交渉を任せることで、慰謝料に関しては弁護士基準の8~9割ほどで示談できることが多いです。
保険会社とのやり取りはストレスがかかる
示談交渉の相手は、多くのケースで、加害者側の任意保険会社となります。保険会社の担当者は、被害者の味方ではなく、あくまで加害者側の立場です。
保険会社の担当者が専門用語を使って話を進めてきたり、増額交渉を聞いてくれなかったり、ときには、連絡が全く来ずに、被害者は不安になってしまいます。
弁護士に示談を任せたら、弁護士が窓口となって交渉を進めるので、被害者は直接相手方と連絡を取る必要がありません。ストレスから解放されることで、治療に専念できたり、一刻も早い日常生活への復帰が実現できるでしょう。
相手方の保険会社との具体的なやり取りは、関連記事『交通事故の保険会社への対応の流れ』を参考にしてください。
被害者が悪くない事故も弁護士は重要
示談交渉は、加入している保険会社が「示談代行サービス」として行ってくれる場合もあります。
仮に、車で信号待ちしていたところを後ろから追突された場合など、被害者側がまったく悪くないようなもらい事故では、示談代行してもらえません。
被害者がまったく悪くない、すなわち被害者側の保険会社にとって、相手方となんら利害関係がない場合に、相手方と示談交渉を行うことは法律で禁じられています。
このような時は被害者ご自身で、あるいは弁護士に依頼して示談交渉をし、十分な額の示談金を獲得するのを目標にしていかなくてはなりません。
また、自身の保険会社に示談代行してもらえる場合であっても、弁護士に依頼することで、より高額の示談金を獲得できる可能性があります。
保険会社間の交渉では、示談金が安く抑えられてしまう傾向があるためです。
理解が深まる関連記事
示談内容は原則撤回できない
相手方が示談書を用意してきても安易にサインせず、まずは示談書の内容を自身で確認し、弁護士などの専門家の意見も求めるべきです。
示談を結ぶということは、「示談をしたら、その件についてはそれ以上争わない」という重大な効果を伴います。
示談内容を記した示談書には「この交通事故についてこれ以上争わない」「示談書以外の損害賠償はしない」という清算条項がついているのが一般的です。
つまり、示談後、新たに車の傷があるのを発見して修理費を払うよう請求したとしても、「その交通事故の件は解決した」と突っぱねられてしまうことになります。
このように、弁護士に依頼することで得られるメリットは多数あります。
納得のいく示談を迎えるためにも、弁護士依頼を検討してみませんか。
弁護士に依頼するメリットの解説記事
交通事故の示談で決めること
交通事故における示談とは何か
交通事故が発生すると、加害者と被害者との間でどちらが悪いのか、損害額はいくらになるのか、など様々な争いが起きます。
争いごとについて、両者の話し合いで解決することを示談といいます。そして、示談するためにお互いの意見をすり合わせていく過程が示談交渉です。
交通事故の示談金・損害賠償金・保険金の違い
交通事故の示談金とは、交通事故の示談で支払われる金銭のことです。
この記事では、一般的な「示談金」という言葉を使いますが、類似の意味を持つ言葉として「損害賠償金」「保険金」などの言葉もあります。
交通事故におけるこれらの単語の違いについて、今一度整理しておきましょう。
示談金・損害賠償金・保険金の違い
- 示談金:交通事故の示談の際に支払われる金銭
- 損害賠償金:交通事故で生じたあらゆる損害を必要・相当な範囲で賠償するための金銭
- 保険金:保険会社から支払われる金銭
次のように整理しておくとわかりやすいでしょう。
まとめ
- 保険金(保険会社から支払われるあらゆる金銭)>示談金(加害者側の保険会社から示談の際に支払われる金銭)
- 損害賠償金(損害を賠償するための金銭)≧示談金(その中から実際に示談のために支払われる金銭)
また、後の段落で詳しく説明しますが、慰謝料は示談金(損害賠償金・保険金)の内訳の一項目にすぎません。慰謝料の増額だけでなく、示談金全体として適正な金額を請求することが大切です。
示談金の内訳をみてみましょう。
交通事故示談金の内訳
加害者側の保険会社から示談の際に支払われる示談金には、様々な損害に対する費用が含まれています。慰謝料だけがすべてではない点を押さえておきましょう。
具体的には、主に以下のような費目です。
- 治療関係費(治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費)
- 将来介護費(介護費用、器具購入費、家屋改造費など)
- (死亡の場合)葬儀関係費
- 物損の修理費
- 慰謝料
- 休業損害
- (後遺障害・死亡の場合)逸失利益
交通事故の示談金|治療関係費
治療関係費とは、治療のため病院に支払うことになる治療費を指します。
また、治療費関係費として、付添人への手当、入院の際に必要となる雑費、通院するための交通費なども必要に応じて認められるでしょう。
治療費は原則として、病院が加害者側の保険会社に請求することになっています。これは、任意一括対応という、任意保険会社のサービスのひとつです。

任意一括対応を受けた場合、示談金としては「既払い」になります。示談金の費目には入っていても、金銭としては既に支払いを受けていることを理解しておいてください。
一方で、事故状況に争いがある場合や、加害者側の任意保険会社に交通事故のことが伝わっていない場合には、一括対応してもらえなかったり、治療費の支払いが遅れる場合もあります。
そのような時は一旦被害者側で治療費を立て替えて、後から損害賠償金として治療費の支払いを受けなくてはなりません。
治療には、被害者自身の健康保険を使った保険診療を受けることができます。被害者ご自身で治療費の立て替えが必要な場合には、特に、関連記事『交通事故の治療費を支払うのは誰?立て替え時は健康保険を使うべき!』を役立ててください。
交通事故の示談金|将来介護費
将来介護費とは、治療後の日常生活に必要な費用を指します。
具体的な介護費用は、家族による介護が可能か、介護は常に必要かなどを考慮して1日あたりの金額で計算します。
怪我の内容によっては車いすなど器具や装具の購入費、その買替費、家のバリアフリー化などが必要となることもあり、その費用も補償対象です。
交通事故の示談金|葬儀関係費
被害者が死亡した場合は、その葬儀にかかった費用が一定の上限まで支払われます。
また、仏壇や仏具の購入費のほか、遺体の搬送費用なども損害賠償請求できる可能性があるでしょう。
交通事故の示談金|物損の修理費
交通事故によって車を修理する必要が出てきた場合、その修理にかかる費用が支払われます。
また、事故車になったことによる市場価値の下落分(評価損)、修理が不可能なほどに壊れてしまった場合は、買い替え差額や代車使用料も認められる可能性があります。
そして、積荷が壊れてしまった場合も補償を受けることが可能です。
交通事故の示談金|慰謝料
示談金の増額を目指すとして、最も重要かつ高額になる可能性が高いものが慰謝料となります。
交通事故で支払われる主な慰謝料には、以下の3種類があります。
- 入通院をした精神的苦痛に対する入通院慰謝料
- 後遺障害が残った精神的苦痛に対する後遺障害慰謝料
- 被害者が死亡した精神的苦痛に対する死亡慰謝料(被害者の近親者の慰謝料も含む)
この通り、慰謝料は精神的苦痛に対して支払われるものですので、車など物にしか損害がない物損事故では支払われません。
なぜならば、物に対する損害は財産的損害について金銭を支払うことで十分に補償可能だと考えられているからです。
例外的に、交通事故でペットの犬が死んだなど特段の事情がある場合に、物損事故で慰謝料を認めた裁判例がありますが、まれなケースであると考えておいてください。
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3つについて、より詳しい計算方法を知りたい方は、次の「慰謝料計算機」を使ってみてください。
または、関連記事でも、慰謝料の解説をしています。相場や計算方法を知りたい方は、それぞれの慰謝料の解説記事を役立ててください。
交通事故の示談金|休業損害
休業損害とは、交通事故の怪我の治療などに伴い、仕事を休んだことによる収入の喪失を指します。
職場に休業損害証明書などを発行してもらい、事故前の収入や休業したことを証明できれば、自賠責基準よりも高い金額の休業損害を受け取ることが可能です。
ポイントとしては、通常の給与取得のほか、個人事業主の得られたはずの収入、現実収入のない主婦についても認められるので取り逃しのないようにしたい分野です。
休業損害については、被害者の立場・職業に応じて1日あたりの休業損害(日額)を算定する方法が異なります。関連記事を読んで、休業損害に関する知識を深めておきましょう。
交通事故の示談金|逸失利益
逸失利益とは、交通事故にあわなければ将来的に得られたであろう収入の喪失を補償するものです。
後遺障害が残った場合や、被害者が死亡した場合など、将来的に得られる収入が減少したり、収入が無くなった場合に支払われます。
将来の収入減少という不確定なことを推定して決めるので、金額について争いになりやすい項目です。
逸失利益の計算は、被害者の収入や年齢などの条件で複雑な計算式となります。どんな風に算定されるのかを知っておくことで、相手方からの提示案を見極めるヒントが見つかるでしょう。
逸失利益計算がわかる記事
交通事故の示談前に知っておきたいこと
交通事故発生から示談成立までの流れ
事故発生から示談成立までの流れを確認してみましょう。
事故発生から示談までの流れ
- 事故発生
- 入通院治療
- 示談交渉
- 示談金受け取り

交通事故の発生
交通事故が発生したら、ただちに警察と病院に連絡してください。
相手によっては、その場で示談しようと持ち掛けてくることがありますが、応じないのが賢明です。
交通事故現場ではまだ損害の全貌が明らかになっていないことが多く、その場で示談をしてしまうと後に発覚した損害の賠償を請求できなくなることがあるためです。
また、人身事故と物損事故の違いも知っておきましょう。
物損事故とは、なんら人身被害が出ていない事故態様をいいます。そのため、慰謝料や治療費、休業損害などを原則請求できません。
実務上、物損事故として扱っても補償を受けられることはありますが、警察での処理が全く異なります。
その場で相手方から「物損事故にしてほしい」と言われても、被害が確定しないうちは引き受けてはいけません。
入通院治療
交通事故で傷害を負った場合は、その後病院で治療を受けることになります。可能であれば事故当日、難しくても翌日中などには病院で診察を受けるべきです。
なぜなら、交通事故発生から症状の発覚まで日数が空いてしまうと「その期間に別の要因で怪我をしたのでは」という疑いが生じてしまいます。
それにより、後に支払われる示談金の金額に影響が出る場合もありますので、出来るだけ早く病院を受診しましょう。
また、その後の通院日数や頻度も入通院慰謝料の金額に大きくかかわってきます。可能であれば、週2~3回の通院を完治または症状固定となるまで続けましょう。
症状固定というのは、これ以上は治療を続けても良くなることはないだろうと判断されることをいいます。症状固定の判断は、医師の見解が重視されます。
症状固定となった場合には、後遺障害申請を検討しましょう。
症状固定の目安時期や症状固定を催促されたときの対処法はこちら:症状固定とは?時期や症状固定と言われた後にする後遺障害認定と示談
完治しなかった場合は後遺障害申請
治療を半年、一年と行ってもなおも症状が残っているような場合は、後遺障害等級への認定申請を考えなくてはいけません。
後遺障害等級に認定されることで、後遺障害慰謝料や逸失利益といった示談金の内訳が追加され、示談金の増額が見込めます。
後遺障害等級認定の申請には、「被害者請求」という方法がおすすめです。
後遺障害等級認定を受けることは簡単ではありません。
どのような症状が後遺障害に該当級に該当するのかを知りたい方は『【後遺障害等級表】症状別の等級や認定基準を解説!自賠責保険金もわかる』の記事において一覧表を確認してください。
被害者請求により後遺障害等級認定の申請方法を知りたい方は『後遺障害申請は被害者請求と弁護士依頼が正解|必要書類も紹介』の記事で確認可能です。あわせて、後遺障害の申請を弁護士に依頼するメリットもわかります。
示談交渉
一般的には治療が終了・後遺障害等級の認定を相手方の保険会社に伝えることで、相手方から示談金の提示がなされます。
書面に治療費や慰謝料などの内訳がありますので、それぞれの金額が適切か確認し、不適切だと感じるのであれば増額交渉をしていく流れです。
相手方からの示談金提示があったタイミングは、弁護士に相談するのにちょうどよい時機でもあります。
一見してそれなりの金額が受け取れるように感じられても、実際はその2倍、3倍の示談金が適正価格ということもあります。
お一人で判断せず、弁護士に示談内容の確認をお願いします。
この時点での弁護士への相談などは、原則無料としている弁護士事務所も多いです。まずはお気軽にご連絡ください。
 毎日
毎日50件以上の
お問合せ
なお、どうしても示談交渉が難航し示談が成立しないこともあります。
そのように当事者間で解決できなかった場合は、第三者による解決、すなわち民事裁判(民事訴訟)を視野に入れていくことになります。
裁判となると、相手方の保険会社は、おそらく顧問の弁護士を立ててくるでしょう。被害者側にだけ弁護士がいないという状況は、極めて不利になります。
交通事故に関する裁判の記事
示談金受け取り
交渉を重ねて示談が成立すると、およそ数週間ほどで示談金が一括で指定口座に振り込まれます。
なお、示談が成立するまでは示談書の送付、署名・捺印してからの返送、保険会社での決済手続きなどの手続きが必要となります。
また、依頼している弁護士事務所によっては一旦その事務所に示談金が振り込まれ、弁護士費用を差し引いてから被害者の口座に振り込まれる、という流れを踏むこともあります。
交通事故の示談交渉をいつ始めるのか
示談交渉を始めるには、交渉材料が十分に揃っている必要があります。よって、交通事故の状況や規模によって、示談交渉を始める時期は異なるのです。
示談開始の時期
- 物損事故:物の損害額が確定した後
- 人身事故(後遺障害なし):治療が終わった後
- 人身事故(後遺障害あり):納得のいく後遺障害等級が認定された日以降
- 死亡事故:法要などが終わった時
共通するのは、損害がまだ十分にわかっていない交通事故現場や事故直後に相手方から示談を持ち掛けられても応じてはならないということです。
決してその場で示談せず、怪我の可能性があれば病院を受診し、自身の健康状態を確かめてから示談のことを考えるようにしましょう。
交通事故の示談とは何か、どんなことに注意するべきかは関連記事を参考にしてください。
関連記事
交通事故の示談交渉にかかる期間はどれくらいか
交通事故の示談にかかる期間は、損害の内容や、争いの程度によります。損害額が高額な場合や、相手方との意見の食い違いが多いほど、難航する可能性があるでしょう。あくまで目安して、示談にかかる期間をまとめました。
示談開始から終了までの目安期間
- 物損事故:1ヶ月~2ヶ月程度
- 人身事故(後遺障害なし):半年以内
- 人身事故(後遺障害あり):半年から1年以上かかることもある
- 死亡事故:1年以上かかることもある
示談交渉は書類や電話、FAXで行われることがほとんどです。日常生活への復帰を目指す被害者にとっては、時間も労力もかかってしまいます。また、見慣れない書類を取り扱うため、書類の作成ミスなどで手間取ることもあるでしょう。
示談交渉をスムーズに進めるためには、弁護士による迅速で正確な対応が必要になります。
交通事故で示談交渉をする際の注意点4ポイント
もし今お一人で示談交渉をしているなら、次のようなポイントに気を付けてください。
- 相手方の提示金額を鵜呑みにしない
- 示談交渉で感情的になりすぎない
- 保険会社と交渉をする代表者を決めておく
- 相手方の保険加入状況に注意しよう
4つの注意点について、順番に解説します。
(1)相手方の提示金額を鵜呑みにしない
「交通事故で少し首を打った、でも治療費や車の修理費は支払ってもらえたし、示談金として10万円も貰えてラッキー」
このように考える人は非常に多くいらっしゃいます。
しかし、10万円という低額な示談金で示談してしまう人が多いからこそ、保険会社も低い基準での示談金を提示してくるのが一般的になっています。
例えば完治までに2ヶ月かかったのであれば、30万円以上を慰謝料として受け取れる可能性があります。
保険会社が提示してくるのは可能な限り低額な金額になりがちであるということを、まずは知らなければなりません。
(2)示談交渉で感情的になりすぎない
交通事故は心理的にも経済的にも非常に負担となりうる事態です。
保険会社や医師の対応に腹が立つこともあるでしょう。
自分の意思をきちんと伝えることは重要ですが、その際に感情的になりすぎてはいけません。
保険会社の担当も人間ですから、繰り返しクレームをいれてくるような事故当事者への対応がおろそかになってしまうこともあります。
また、医師ともある程度良い関係を築いていないと、後々必要な検査や記載の要請を受けてもらえなくなることがあります。
そのせいで病院から足が遠のくと、「真面目に通院していなかった」と評価され、後遺障害等級などに影響が及ぶこともあります。
さらに医師とあわないからといって無断で転院や整骨院での治療を行っていると、治療費の一部が損害として認められなくなることもあります。
そのような示談金の総額が下がる事由にも繋がりますので、治療中や交渉中は冷静に行動するようにしましょう。
(3)保険会社と交渉をする代表者を決めておく
遺族が複数人いる死亡事故、または同乗者も怪我を負ってしまった事故のような場合、複数人が示談金を受け取れる場合があります。
そのような時は、保険会社と交渉する代表を一人決めておくべきです。
複数人から問い合わせがあると保険会社の処理も混乱してしまい、示談までの手続きが遅れてしまうことになるためです。
(4)相手方の保険加入状況に注意しよう
相手方が任意保険未加入または無保険の場合は、示談金が受け取れないことも起こりえます。
残念ながら、相手方が任意保険に加入していなかったり、自賠責保険の加入期限が切れてしまっていたりと、様々な理由で相手方保険会社から十分な支払いが受けられないことがあります。
そのような場合、交通事故の相手方本人に直接不足する示談金などを請求することになりますが、個人の支払い能力には限界があります。示談金を受け取れないかもしれない、と覚悟しておかなければなりません。
無保険車相手の交渉についての注意点や対策は、関連記事にて確認してください。
無保険車への慰謝料請求を解説
交通事故の示談を任せられる弁護士とは?
現在、交通事故の被害者に向けては、無料相談を実施していると弁護士事務所は多数あります。いくつかの事務所に相談することでより親身になってくれる弁護士に出会えるでしょう。
実際に相談をしてみることで、態度が横柄な弁護士、こちらの主張を理解しようとしてくれない弁護士、無責任な弁護士などは、この時点で委任の選択肢から外すことが出来ます。
具体的には、次のような点に注意して弁護士をみてみましょう。
- 交通事故案件を数多く取り扱っている
- 医学的知識を持っている
- 被害者の話を聞いてくれる(連絡はこまめにしてほしいという要望や、弁護士の目線や態度、聞く姿勢など)
示談は、1年以上にわたって長期化する可能性があります。
長いお付き合いになりますので、信頼できそうかという観点をもつことも大事です。
弁護士選びで失敗したくない方は関連記事『交通事故で弁護士依頼は後悔する?失敗談と対策』をあわせてごらんください。弁護士に依頼して後悔したケースと対処法がわかります。
交通事故の示談を弁護士に依頼した時の費用はいくら?
また弁護士費用については高額なイメージがついて回りますが、実態は一切弁護士費用を支払わずに済むことも多いです。
多くの弁護士事務所では事前に見積もりを行うことが可能です。一般的にどのような費用構成になっているのか理解すると、より納得をもって依頼できるようになるかと存じます。
弁護士費用と一口に言っても、内訳は主に以下のようになっています。
- 相談料
- 着手金
- 報酬金
- 実費
- 日当
以下、それぞれの項目に関して相場と計算方法を解説します。
交通事故の弁護士費用の相場・計算方法は?
弁護士に依頼したときの相談料の相場
相談料は、依頼前に弁護士に相談をすることでかかる費用です。
相場としては30分5,000円が目安となりますが、初回無料としている弁護士事務所も多くあります。
時間制限があるため、相談前に交通事故状況の資料や質問したいことをまとめておくのがよいでしょう。
弁護士に依頼したときの着手金・報酬金の相場と計算方法
着手金とは弁護士に依頼する際に初期費用としてかかる金額、報酬金は成果に応じて支払う金額です。
弁護士費用の大部分を占めるのが、この着手金と報酬金です。
かつて弁護士の着手金・報酬金は、日弁連という弁護士組織で決定されていました。
現在は自由な料金設定が可能ですが、多くの弁護士事務所が従来の基準を維持しています。
その基準は以下のようになっています。
経済的利益というのは、保険会社によって計算の違いはありますがおおむね「最終的な支払い額−保険会社から提示された金額」すなわち弁護士が介入したことによる増額分のことを指します。
| 経済的利益* | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 経済的利益の8.8% | 経済的利益の17.6% |
| 300万円を超え3000万円以下 | 経済的利益の5.5%+9万9千円 | 経済的利益の11%+19万8千円 |
| 3000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の3.3%+75万9千円 | 経済的利益の6.6%+151万8千円 |
この表に従って、保険会社からの事前提示額100万、実際の回収額が400万であった場合を考えてみましょう。
経済的利益が300万円ちょうどとなりますから、着手金は26万4千円(3,000,000×0.088)、報酬金は52万8千円(3,000,000×0.176)となります。
なお現在は、着手金や報酬金に関して10万、20万などと定額を定めている事務所も多くあります。
また古いデータですが、日弁連が交通事故を含めた各弁護士費用の統計を発表しています。
弁護士に依頼したときの実費の相場
実費とは、紛争解決の過程で実際に支払うことになった費用です。
例えば保険会社に資料を送る際の郵便料金、病院に診断書を発行してもらう際の手数料、裁判所に支払う印紙代などです。
これについては相場を出すのは困難ですが、特にCTやMRIの画像発行代などが数万円程度になることもあり、実費のなかでは大きな出費になります。
弁護士に依頼したときの日当の相場
日当とは、弁護士が遠方に赴く際などに距離や日数に応じて支払う手当です。
交通事故ではあまり活用されることは無いですが、時に遠方の病院や裁判所に行く必要があった時に必要となります。
結局弁護士費用は総額いくらになる?
費用を知りたいと思ったとき、各弁護士事務所HPの料金体系を見るのが考えられますが、実際はそれだけでは把握しきれないことも多いです。
何故なら、実際は「提示額〇円以上なら」「〇〇保険なら」「この特約に入っているのなら」「その事案であれば~」と、各自が細かな内部基準を設けており、それに基づいて料金が決定されることが多くなっています。
ですから事務所HPだけではなく実際に相談し、見積もりをとってもらうのが重要です
例えばアトム法律事務所の料金体系では、交通事故に関する相談料や着手金は原則無料としています。
交通事故の弁護士費用を払わずに済む「弁護士費用特約」とは?
長く弁護士費用について説明しましたが、実は任意保険に入っている人のうちおよそ7割は弁護士費用を一切払わずに済む可能性があります。
それは、任意保険でオプションとして加入できる弁護士費用特約によるものです。
弁護士費用特約…自動車の任意保険などのオプションの一つ。紛争の際にかかった弁護士費用を保険会社が負担するもの
その内容は、以下の通りです。

図の通り、弁護士費用特約を活用すれば
- 相談料は10万円まで
- 着手金、報酬金、実費、日当などは300万円まで
保険会社が支払ってくれることになります。
最近は保険会社も加入を勧めており、データを公表しているセゾン自動車保険によるとは64.5%の人が弁護士費用特約に加入しています。
保険会社の担当者や、保険証書を見ることで加入の有無を確認できます。
なお、弁護士費用特約に加入していなくても不安に思うことはありません。
アトム法律事務所では、そのような場合被害者の方の支払いが少なくなるよう料金体系を組んでおり、また費用倒れにならないかといったご相談もいつでもお受けしています。
費用面に関するご不安についても、まずは気軽にご相談ください。
 毎日
毎日50件以上の
お問合せ
交通事故の示談はぜひ弁護士にお任せください
交通事故の示談において、最終的な支払い額・スムーズな解決・心理的負担の軽減と、どの要素を重視するにしても弁護士に依頼することは非常に有用な選択肢です。
示談交渉がご不安な方、相手方から提示された金額が妥当なのか迷っていらっしゃる方は、まずはお気軽にご相談ください。
 毎日
毎日50件以上の
お問合せ
アトム法律事務所では24時間365日、いつでも相談予約を受け付けております。
またLINEでの相談も承っておりますので、弁護士と直接話すのは気が引けるという方にもお気軽にご利用いただけます。
ご相談・お見積りだけでもまずは気軽にご相談ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了