妊娠中に信号停車中追突され腰部挫傷等を負った事例
弁護士に依頼後...
回収
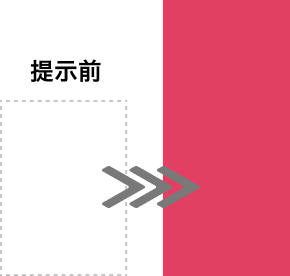
更新日:

交通事故にあった妊婦の方は、ご自身だけでなく、お腹の赤ちゃんの健康への計り知れないご不安、お察しいたします。
交通事故により流産・死産となった場合、妊婦の精神的苦痛に対する慰謝料は、通常の相場に150万円〜800万円程度加算(妊娠期間等により変動)されるケースがあります。すぐに産婦人科を受診し、医師の診断を受けることが重要です。
日本の民法上、胎児は「人」ではないため、胎児自身には損害賠償請求権が認められません。しかし、事故の衝撃や凄まじいストレスによる流産は、母親への甚大な損害として正当に評価されるべきです。
なお、無事に出産された後に、子どもに事故による障害が残った場合、別途、賠償請求ができる可能性はあります。
保険会社は、低額な自賠責基準を提示してくることが多いですが、弁護士基準による交渉で、正当な賠償へとつなげられます。この記事では、あなたとお腹の赤ちゃんの権利を守るための「適正な慰謝料相場」と「保険会社への対抗策」を、裁判例とともに解説します。
目次
慰謝料とは加害者側に請求できる損害賠償金の一部で、「精神的苦痛に対する補償」をするものです。
交通事故では、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
交通事故における慰謝料
どんな慰謝料なのかをそれぞれ説明していきます。
交通事故によるケガの治療で入院・通院したとき、精神的苦痛に対する補償として「入通院慰謝料」を請求できます。
基本的には、ケガの程度や治療期間に応じて金額が決まります。下表には、法的に正当とされる入通院慰謝料の相場(弁護士基準)をまとめていますので、参考にしてみてください。
入通院慰謝料の早見表|通院1~6か月
| 通院期間 | 弁護士基準 |
|---|---|
| 1か月 | 28万円(19万円) |
| 2か月 | 52万円(36万円) |
| 3か月 | 73万円(53万円) |
| 4か月 | 90万円(67万円) |
| 5か月 | 105万円(79万円) |
| 6か月 | 116万円(89万円) |
※ 弁護士基準の()内はむちうち等の軽症の場合
入通院慰謝料の細かい計算方法や仕組みについては関連記事『交通事故の慰謝料計算機|示談前に簡単シミュレーションできる無料ツール』でわかりやすく解説しています。記事冒頭にある「慰謝料計算機」を使えば簡単に慰謝料の目安が出せますので、あわせてお使いください。
相手の保険会社から提示される慰謝料の金額は、上で紹介した弁護士基準ものよりも低額なことがほとんどです。
そのため増額交渉が必要になりますが、弁護士なしでの交渉は相当厳しいと予想されます。
弁護士基準の相場は、本来であれば裁判を起こして獲得するようなものだからです。
弁護士基準での慰謝料請求を目指している方は、関連記事『交通事故慰謝料の弁護士基準(裁判基準)とは?相場や弁護士基準にするには?』もあわせてお読みいただき、弁護士への依頼も検討してください。
後遺障害慰謝料は交通事故で残った後遺障害によって生じた、精神的苦痛に対する補償をさします。
後遺障害とは、後遺症のうち「後遺障害等級」が認定されたもののことです。後遺障害慰謝料の金額は後遺障害等級に応じておおよそ決まります。
たとえば、むちうちによる神経症状がひどい場合は、後遺障害12級や後遺障害14級認定の可能性があります。後遺障害慰謝料は、12級であれば290万円、14級であれば110万円が相場です。
関連記事『後遺障害慰謝料の相場はいくら?いつ支払い?後遺障害等級認定と賠償金額のすべて』では後遺障害等級ごとの慰謝料相場がわかります。
後遺障害等級は認定を受けて決まるものですが、申請をしたからといって必ず認められるものではありません。等級認定の基準を満たしていなければ認定を受けられないのです。
適切な認定を受けるためには、審査機関に提出する資料の内容が大切です。
何らかの後遺症が残りそうだったり、医師から症状固定と言われたりした方は、後遺障害認定の対策に精通した弁護士にご相談ください。
関連記事『後遺障害等級が認定されるには?後遺症との違いや認定の仕組みを解説』を読めば、後遺障害や認定の概要をつかむことができます。
死亡慰謝料は、交通事故により死亡した妊婦本人の精神的苦痛と、その遺族の精神的苦痛に対する補償をさします。
死亡慰謝料は家庭内の立場で変わるため、事案ごとに算定が必要です。
たとえば、独身の女性であれば2,000万円~2,500万円、母親や配偶者という立場であれば2,500万円が死亡慰謝料の相場です。
慰謝料計算機を使えば、過去の判例をもとにした大まかな慰謝料相場がわかります。年齢や事故前の年収を入力するだけなので、簡単です。
主婦の方は、「年収」の欄で「301~400」(2022年発生の交通事故の場合)を選択してください。
交通事故の慰謝料に関する基本情報やどのくらいの金額をもらえるかについては『交通事故の慰謝料|相場や計算方法を知って損せず増額【2026年最新】』をご覧ください。
交通事故で妊婦が流産・中絶をした場合、多くの方が気にするのは「亡くなった胎児に対する慰謝料はどうなるのか」ということではないでしょうか。
ここでは、流産や中絶がどのように慰謝料に反映されるのかを解説します。
通常、交通事故の被害者は慰謝料を請求することができます。しかし、死亡事故の場合は死亡した本人が慰謝料を請求することはできませんから、家族などが被害者に発生した慰謝料請求権を相続して慰謝料を請求することになります。
しかし、胎児の場合には、たとえ交通事故が原因で流産や中絶をしても、胎児自身の慰謝料請求権は発生しません。
慰謝料請求をする権利は出生時から発生するとされているからです(民法3条1項)。
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
民法3条1項
もっとも、流産・中絶した妊婦や父親は、生まれてくるはずだった子どもを失った精神的苦痛を受けます。流産・中絶の際には身体的負担もかかるでしょう。
こうした点から、交通事故で流産・中絶した場合は、基本的に両親自身の慰謝料請求という形で認められます。
交通事故やその後の治療により流産してしまった場合の慰謝料額について、明確な相場はありません。
裁判例では、胎児死亡の慰謝料として、妊婦の慰謝料が150万円~800万円程度増額されています。
具体的に妊婦の慰謝料金額をどれくらい増額するかは、以下のような事情を総合的に考慮して判断されます。
これまでの裁判例から考えると、妊娠期間が長いほど慰謝料が高額になる傾向にあります。
妊娠初期よりも妊娠後期での流産の方が、より身体的負担が大きく、自然流産の可能性が低くなる分、精神的苦痛も大きいと判断されるからです。
ここで、交通事故による流産で妊婦に対する慰謝料が認められた事例をご紹介します。
【判例】流産の時期と妊婦への胎児死亡慰謝料
| 時期 | 慰謝料 |
|---|---|
| (1)妊娠2ヵ月 | 150万円 |
| (2)妊娠12週未満 | 200万円 |
| (3)妊娠27週 | 250万円 |
| (4)妊娠29週 | 400万円 |
| (5)妊娠36週 | 700万円 |
| (6)出産予定日の4日前 | 800万円 |
(1)大阪地判平8.5.31 交民29・3・830
(2)大阪地判平18.2.23 交民39・1・269
(3)横浜地判平10.9.3 自保ジ1274・2
(4)千葉地松戸支判令3.10.25 自保ジ2112・94
(5)東京地判平11.6.1 交民32・3・856
(6)高松高判平4.9.17 自保ジ994・2
東京地判平11・6・1(平成10年(ワ)21771号)
妊娠36週の女性が乗車していた停車中の車両に、後方からの追突事故が発生。事故の衝撃により、出産間近で異常のなかった胎児が子宮内で死亡した。胎児は正期産の時期に入っており、現在の医療水準では正常出産の可能性が高い状態だった。
「新生児と紙一重の状態にあり、これを失った両親の悲しみ、落胆は相当なものである」
東京地判平11・6・1(平成10年(ワ)21771号)
母親:700万円 父親:300万円
交通事故による中絶には次の3つのケースがありますが、いずれの場合も慰謝料請求が可能です。
ただし、交通事故が原因で中絶した場合の慰謝料についても、明確な相場はありません。
示談交渉での話し合いによって金額が決まることになります。
実際に交通事故や治療の影響による中絶で胎児死亡慰謝料が認められた事例を紹介します。
横浜地判平21・12・17(平成19年(ワ)92号)
17歳女性が原付3人乗り事故で脳挫傷等の重傷を負い2か月入院。事故時妊娠3~4週だったが本人は気づかず、退院後の妊娠15週目に判明。事故後の重度意識障害・呼吸障害による人工呼吸と多数薬剤使用の胎児への影響を考慮し、医師が「妊娠継続不可能」と診断。妊娠19週で人工妊娠中絶を実施した。
「本件事故の影響により人工妊娠中絶を受けることを余儀なくされ、出産という選択ができなくなったことは事実であるから、そのことによる精神的苦痛に対する慰謝料を損害として認める」
横浜地判平21・12・17(平成19年(ワ)92号)
100万円
※当時17歳未婚で出産可能性が不明確なことを考慮
慰謝料額には確立した基準がなく、妊娠週数、母親の年齢・婚姻状況、出産意思、経済状況等を総合考慮して決定されます。本件の胎児死亡慰謝料の額100万円については、被害者が当時17歳で婚姻しておらず事故がなかった場合の出産可能性が不明であることを考慮した結果低めの額になっています。
出産が確実であった場合には、もう少し慰謝料が高額になった可能性も考えられるでしょう。
因果関係の立証では、①事故による衝撃の程度、②事故以外の流産原因の有無、③事故から中絶までの期間、④医師による診断が重要となります。本件のように治療が直接原因となった場合は、通常の流産と比べて因果関係が認定されやすい傾向があります。
交通事故による衝撃や事故後の手術・治療の影響で、障害のある子どもが生まれてきた場合、その子どもに対する治療費・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益を加害者側に請求できます。
また、その障害が死にも比肩するものであった場合には、母親・父親に対する慰謝料も請求できる可能性があります。
ただし、子どもに障害が生じた原因が交通事故にあることを医学的に証明できなければ、賠償請求はできない可能性が高いです。
子どもの障害と交通事故の因果関係を医学的に証明することは難しい場合も多いので、お困りの場合は医師や弁護士にご相談ください。
東京地判平4・11・13(昭和61年(ワ)11553号)
妊娠中の女性が信号待ち停車中、免許停止中の運転手による2トントラックに時速約50kmで追突され玉突き事故に遭った。事故前は母子ともに健康だったが、事故後に性器出血・下腹部痛が出現し、事故から約2か月後に、仮死状態で早産。男児には高度難聴(80デシベル以上)と精神発達遅滞が残り、事故との因果関係が争点となった。
「受傷及び原告の右障害の発生との間には相当因果関係を十分に肯定することができる」
東京地判平成4・11・13(昭和61年(ワ)11553号)
2,377万1,372円
交通事故の影響で早産した場合には、その子どもの治療費や慰謝料など、子ども固有の損害賠償金を請求できます。
後遺症が残り、後遺障害等級に認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求も可能です。
また、早産にあたっては、妊婦にも身体的負担がかかることが考えられます。
例えば交通事故が原因で早産となり、そのために帝王切開をした場合は、その分の費用を加害者側に請求可能です。
早産による精神的苦痛が大きいと認められれば、慰謝料の増額も考えられるでしょう。
交通事故によって妊婦が流産した場合、母親だけではなく父親も精神的苦痛を受けると考えられます。しかし、父親に対する慰謝料は認められにくい傾向にあります。
父親に対しても慰謝料が認められた事例には、次のようなものがあります。
判例
妊婦(母)が受傷したことにより妊娠36週の胎児が死亡したとして、父親にも300万円を認めた
(事故日平9.12.1 東京地判平11.6.1 交民32・3・856)
流産により父親も強い精神的苦痛を受け、慰謝料を請求したいという場合には、一度請求可否の見通しを弁護士に聞いみることをおすすめします。
ここまで解説してきたように、妊婦の場合は、特有の事情を考慮した慰謝料を請求できます。
ただし、実際にどの程度事情が考慮され、慰謝料額に反映されるかは示談交渉次第です。
そこでここからは、事故の被害者が妊婦であるとき示談交渉をする際のポイントを紹介します。
妊婦が交通事故にあった場合、加害者に請求できるのは、慰謝料だけではありません。必要に応じて、その他の損害賠償金も忘れずに請求することが重要です。
通院交通費については、必要性が認められればタクシー代も請求できます。とくに妊婦の場合は無理をせず、必要であればタクシーの利用も検討しましょう。その際、領収書を保管しておくことを忘れないでください。
妊婦が交通事故に遭った場合、賠償金の示談交渉は出産後に開始すべきです。
交通事故の示談交渉は、事故による損害額が確定した後、一般的には以下のタイミングで始められます。
ただし、妊婦の場合は、出産後に示談交渉を始めることが望ましいです。たとえ検査の段階では胎児への影響はないとされていても、実際の影響は生まれてからでないとわかりません。
もし示談成立後に子どもに障害があっても、一度示談が成立している以上再交渉ができない可能性があるのです。
なお、出産後ただちに示談交渉を始める必要はありません。出産後は安静にして体を休めることを第一として、良いタイミングをみて交渉を始めてください。
示談交渉開始~示談金振り込みまでの流れや、その他の注意点については『交通事故慰謝料のもらい方|正しい相場・計算と請求方法【人身事故の被害者必見】』の記事も参考になります。
妊婦が交通事故について賠償請求を行う場合、損害賠償請求権の消滅時効にも要注意です。
すでに解説した通り、妊婦の場合は出産を待って示談交渉を始めることが望ましいです。
ただし、「損害賠償請求権の消滅時効」には注意する必要があります。
交通事故の被害者は加害者に対して損害賠償を請求する権利を持っていますが、この権利には時効があります。
時効が成立してしまうと損害賠償請求ができなくなるのです。
損害賠償請求権の消滅時効が成立するまでの期間は、以下のようになっています。
| 事故内容 | 消滅時効 |
|---|---|
| 人身事故 (後遺障害なし) | 事故日から5年 |
| 人身事故 (後遺障害あり) | 症状固定日から5年 |
| 死亡事故 | 死亡日から5年 |
※いずれも2017年4月1日以降に発生した事故に対するもの
生まれてきた子どもに障害があり損害賠償請求する場合にも、損害賠償請求権の消滅時効に注意しなければなりません。
この場合、時効が成立するのは「損害を知った時から5年」後です。
「損害を知った時」をいつとするのかについては、加害者側と議論になる可能性もあるでしょう。
ただ、基本的には出産日、または障害があると診断された日とされます。
損害賠償請求権の消滅時効は成立を阻止することも可能です。時効までに示談が成立しそうになくてお困りの場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故による流産・中絶で慰謝料請求するには、交通事故との因果関係を証明する必要があります。
交通事故と流産との因果関係は、以下のような事情を総合的に考慮して判断されます。
交通事故と流産との因果関係の主な考慮要素
1については衝撃が強いほど、2については事情がないほど、3については期間が短いほど因果関係が肯定されやすい傾向にあります。
医師にも協力を仰ぎ、上記項目について示す検査結果・資料はないか確認してもらったり、意見書を書いてもらったりしましょう。
交通事故にあうと誰もが動揺し不安になるものですが、妊娠中ならなおさら、お腹の赤ちゃん(胎児)への影響が一番に心配されるでしょう。
妊婦の方が事故後にとるべき対応は、単なるケガの治療だけではありません。「事故と症状(万一の流産など)の因果関係」を法的に証明するための、極めて重要なステップが含まれます。
そこでここからは、交通事故にあった直後に、妊婦がとるべき対応をご紹介していきます。
なお、一般的に被害者がすべき交通事故の対応については『交通事故被害者がすべき対応の流れは?示談のポイントや慰謝料も解説』の記事も参考になりますので、あわせてご確認ください。
お腹に痛みがあったり、出血していたりする場合は、すぐに救急車を呼びましょう。
それ以外の場合も、交通事故との因果関係を証明するため、できるだけ事故当日に病院で診察を受けてください。
基本的に母体については整形外科で、胎児の状況については産婦人科で診てもらいます。
診察では、妊婦であることや、交通事故で体のどの部位にどのような症状があらわれたのかなどを医師に伝えます。
特に、流産・死産、胎児の障害については、事故との因果関係について医師の医学的所見が重要となります。医師の理解を得られるよう、よくご相談ください。
この時の診察料は原則として、加害者側に請求ができます。領収書などは保管しておきましょう。
軽傷であってもケガをしているのであれば、警察には人身事故として届け出ましょう。
軽い事故の場合、物損事故として届け出るよう、加害者から頼まれることがあります。
しかし、物損事故として届け出ると、請求できる損害賠償金の種類で損をしたり、示談交渉で不利になったりする可能性があります。
また、事故直後は痛みを感じていなくても、その後に痛みが出てきたら人身事故に切り替えましょう。
人身事故として届け出る重要性や具体的な切り替えの方法は『物損から人身への切り替え方法と手続き期限!切り替えるべき理由もわかる』で解説しています。
続いて、交通事故にあった妊婦に見られる可能性のある症状と、注意すべき治療についてご紹介していきます。
交通事故後、妊娠中に注意が必要な症状は以下の通りです。
中には妊婦自身にはとくに症状があらわれず、胎児にのみ影響が出るものもあります。
妊婦に何らかの症状がある場合はもちろん、とくに症状はなくても少しでも不安がある場合は、速やかに受診することが大切です。
では、5つの症状についてもう少し詳しく解説します。
腹部に強い衝撃が加わることで、流産・早産しそうな状態になることです。
お腹の張りや出血、破水、子宮口の開大などの症状がみられます。
胎児への血液や酸素の供給が止まってしまうことです。
出血や激しい子宮の痛みなどが見られ、早急に帝王切開といった処置が必要になります。
妊娠後期に腹部に強い衝撃が加わることで発生する可能性がある症状です。
帝王切開の経験がある場合に発生しやすい症状といえます。
大量出血により母子ともに危険な状態に陥る可能性が高い症状です。
母体と胎児の血液が混ざらないようにしている膜が破れ、両者の血液が混ざってしまう状態のことをいいます。
胎児は貧血状態に陥るが、母体には大きな症状は見られません。
お腹の胎児に骨折などの外傷が生じる可能性があります。
妊婦の場合、妊娠していない方と同じような治療をしていると、胎児に悪影響が及ぶ可能性があります。
妊婦であることを医師に伝えればきちんと安全な治療をしてもらえますが、それでも不安な気持ちになるでしょう。
そこでここでは、妊娠している方が気を付けるべき治療方法をご紹介します。ただしあくまでも一般論ですので、詳細は主治医の指示に従ってください。
交通事故のけがにより日常的に痛みを感じる場合や治療をする場合、通常は痛み止めの薬や麻酔を投与します。
しかし、妊婦は胎児に対する悪影響を防ぐため、こうした薬を服用できない可能性が高いです。
痛みが強く我慢ができない場合は、かかりつけの産婦人科に相談してみましょう。この際の診察料も加害者側に請求できます。
交通事故により、むちうち・頸椎捻挫になった場合には、整骨院などでマッサージや電気治療を受けることが多いです。
しかし、こうした施術も胎児に悪影響を及ぼす可能性があるため、妊娠中は受けられなかったり、受けられたとしても弱めの施術となる可能性が高いでしょう。
とくに妊娠初期の場合、見た目だけでは妊娠していることがわかりにくいため、治療を受ける際は必ず妊婦であることを病院や整骨院に伝え、配慮してもらうべきです。
妊娠中はレントゲン検査を受けられないというイメージは世間的にも強いですが、実際にはそうではありません。
公益社団法人日本放射線技術学会は公式ホームページで、次の内容を発表しています。
妊婦のレントゲン検査を制限している病院もありますが、たとえ妊娠中でもレントゲン検査を絶対に受けてはいけないとは言い切れません。
とはいえ、やはり不安な気持ちもあるでしょう。もし医師からレントゲン検査を求められて不安を感じた場合には、医師にその旨を相談してみてください。
交通事故後、治療などが終わると示談交渉に入りますが、妊婦の方は特に弁護士に依頼するほうが安心です。
弁護士を立てるメリットや、弁護士費用の負担を軽減する方法を解説します。
交通事故の示談交渉は、弁護士に代理を依頼することをおすすめします。その理由は次の3点です。
それぞれについて解説していきます。
交通事故の示談交渉は、時間を作って加害者側と面会して行うのではなく、電話やFAXを通して行われることがほとんどです。
そのため、子どもを寝かしつけているときやおむつ替えをしているとき、授乳中や入浴中に電話がかかってくることもあります。
ただでさえ出産後は忙しいのに、タイミング悪く電話やFAXが来ると対応が難しく大変ですし、しっかり被害者側の主張をする気力も奪われてしまうと考えられます。
だからこそ、示談交渉は弁護士に代理してもらい、子育てに専念することがおすすめです。
交通事故の示談交渉では、加害者側の任意保険会社による言動にストレスを感じる方も多いです。
忙しい中示談交渉に対応しているにもかかわらず、このような態度をとられると、ストレスが溜まってしまいます。
示談交渉を弁護士に依頼すれば、加害者側の任意保険会社とのやりとりはすべて弁護士にしてもらえるため、ストレスを軽減できるのです。
加害者側の任意保険会社は、「任意保険基準」と呼ばれる、各社が独自に定めた基準にのっとって慰謝料を算出します。
この慰謝料額は相場の半分~3分の1程度でしかありません。しかし、被害者本人が慰謝料の増額を求めても、かたくなな態度をとり十分に増額してもらえないことがほとんどです。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、「弁護士基準」と呼ばれる、過去の判例をもとにした相場額を加害者側に主張してもらえます。
弁護士は法律の専門家・示談交渉のプロなので、加害者側の任意保険会社が態度を軟化しやすく、より良い条件で示談を成立させられる可能性が高いのです。
ここで、アトム法律事務所の弁護士による増額実績をご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
事例(1)
| 傷病名 | むちうち |
| 後遺障害等級 | 非該当 |
| 増額実績 | 89万円から142万円へ増額 |
※弁護士の見立てで増額の可能性が見込まれた比較的軽傷のケース
事例(2)
| 傷病名 | 左足関節骨折 |
| 後遺障害等級 | 12級13号 |
| 増額実績 | 347万円から750万円へ増額 |
※後遺障害等級は変わらずとも弁護士の交渉で増額を実現したケース
事例(3)
| 傷病名 | 肺挫傷、肋骨骨折など |
| 後遺障害等級 | 14級9号 |
| 増額実績 | 230万円から485万円へ増額 |
※後遺障害等級は変わらずとも弁護士の交渉で増額を実現したケース
アトム法律事務所の弁護士が実際に解決した事例をさらに知りたい場合は、「交通事故の解決事例」ページをご覧ください。
弁護士に相談・依頼した方が安心とは思いつつ、産後に多額の弁護士費用を用意するのは難しい、という方もいるでしょう。
そのような方は、弁護士費用特約が利用できないかご検討ください。
弁護士費用特約とは、ご自分が加入している任意保険についているオプションです。弁護士費用を任意保険会社に負担してもらえます。
その特徴は次の通りです。
弁護士費用特約の多くは、法律相談料10万円、弁護士費用300万円という補償上限があります。
ただし、交通事故の弁護士費用がこの補償額を上回るケースは少ないので、多くの場合は弁護士費用の全額を特約でカバーできるのです。
こうして保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、被害者自身の負担額は0円で弁護士を立てられます。
夫婦である場合には配偶者の加入する自動車保険に付帯している弁護士費用特約を利用できる可能性が高いので、ご自身の保険にこだわらず確認してみてください。
以下の関連記事を読むと、交通事故の弁護士費用特約についての理解がより深まります。
中には、ご自身の保険にもご家族の保険にも弁護士費用特約がついていないという方もいるでしょう。しかしご安心ください。
アトム法律事務所では、弁護士費用特約が使える方はもちろん、使えない方にも安心してご利用いただける料金体系をとっています。
アトム法律事務所の料金体系
つまり、示談金を獲得する前にお支払いいただく費用は基本的にありません。
アトム法律事務所の無料相談は、電話やLINEから可能です。
受付は24時間365日対応しております。
交通事故の被害でお腹の赤ちゃんへの不安を抱える中、体調や金銭面を気にせず、ご自宅からお好きなタイミングでご連絡いただけます。
まずは、今の状況をお聞かせください。経験豊富な弁護士が、あなたと赤ちゃんの権利を守るために全力でサポートいたします。
最後に、ご依頼者様から寄せられたお手紙の一部をご紹介いたします。
弁護士相談の際には、ぜひアトム法律事務所もご検討ください。お待ちしております。
契約前にも親切にアドバイス頂き、頼むことにしました。先生はとても話やすく、事故に強い先生だったので、思っていたより金額が出てびっくりしました。最初はLINE相談で簡易すぎて半信半疑でしたが、ここでお願いしてとても良かったです。
LINE無料相談の声|むちうちの増額事例
無料のLINE相談でも親切に対応していただき感謝しています。交通事故の保険のことなど無知な私には強い味方になってもらい、1ヶ月半ほどで慰謝料も2倍になり、本当にお願いしてよかったと思っています。
LINE無料相談の声|左手首骨折、左腸骨骨折の増額事例
毎日毎日頭の中の不安から開放され、やっと新しいスタートを切れます。弁護士というと、堅いイメージがあるのですが、LINEの無料想談は、相談しやすく、親しみやすかったです。
LINE無料相談の声|顔の神経症状、醜状障害の増額事例
『交通事故の体験談8選|示談交渉や後遺障害認定の様子、実際の慰謝料額は?』の記事でも、アトム法律事務所をご利用いただいた方の声を紹介しています。
お困りごとを一人で抱えることはありません。まずは相談してください。
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った解決事例の一部を、プライバシーに配慮したかたちでご紹介します。
妊婦が白線内に立っていたところ、加害者の車に轢かれて、右足首を骨折した事案。保険会社からの提示額について、慰謝料増額の可能性があったケース。ご依頼後、弁護士基準で慰謝料増額の交渉をおこなった。
保険会社の提示額の464,985円から、弁護士による交渉により、最終的な受取金額が120万円(約73万円増額)となった。
20~30代、介護職・妊婦
右足首骨折
なし
妊婦であるため、あまり通院できなかったところ、慰謝料・主婦休損について増額可能性があったケース。ご依頼後、弁護士基準で示談交渉をおこなった。
保険会社の提示額の176,760円から、弁護士による交渉により、最終的な受取金額が43万円(約25万円増額)となった。
20~30代、兼業主婦
腰痛
なし
このほかにも、アトム法律事務所には、多くの交通事故の解決事例がございます。
妊婦で交通事故に遭われて、今後に不安をお持ちの方は、ぜひ一度アトム法律事務所の弁護士相談をご利用ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。




