交通事故慰謝料って増額できる?弁護士への依頼で増額した実例5選

交通事故の被害にあった方の中には、弁護士への依頼についてハードルの高さを感じ、相談を躊躇する方もいらっしゃいます。
しかし、交通事故慰謝料は弁護士に依頼することで増額できる可能性が高いです。
本記事では、慰謝料の算定基準の仕組みや相手方保険会社の対応、弁護士依頼のメリットや増額事例などを紹介し、交通事故慰謝料の増額の可能性について徹底解説しています。
本記事を読めば交通事故慰謝料の増額方法について基礎の部分から知ることができるので、ぜひ参考にしてください。
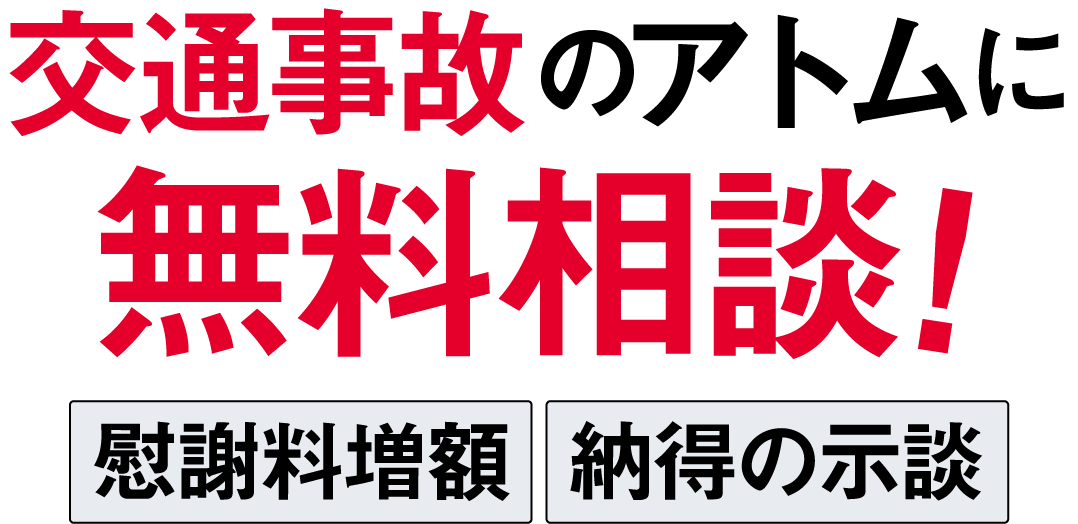
交通事故慰謝料を増額するために知っておくべきこと
慰謝料の算定基準は3つある
交通事故慰謝料には3つの算定基準があります。
自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(別名:裁判基準)です。
金額としては自賠責基準での算定が最も低額になり、次いで任意保険基準、一番金額が高くなるのが弁護士基準です。

相手方任意保険会社は、任意保険基準での金額を提示してきます。
交通事故に遭った際には、任意保険基準よりも高額な基準となる弁護士基準での賠償金の支払いを受けられるよう交渉をするべきです。
まず慰謝料の算定基準や慰謝料の種類などについて解説し、増額のためにすべきことについても触れていきます。
自賠責基準
自賠責保険における支払い基準が自賠責基準です。
自賠責保険というのは、各車それぞれに加入が義務付けられた保険です。
交通事故被害者の方が最低限の補償を受けられるよう整備されたものとなります。
自賠責保険はあくまで最低限の補償を目的に整備されたものであるため、補償の金額は被害者の方が本来もらうべき金額と比較して非常に低額です。
後遺障害などを除く、傷害部分の賠償金について上限120万円とされています。
自賠責保険の慰謝料についてさらに詳しく知りたい方は、関連記事『自賠責保険の慰謝料計算や限度額を解説|任意保険からも両方もらえる?』をご覧ください。
任意保険基準
任意保険基準は、相手方任意保険会社が慰謝料を計算する際に用いる支払い基準です。
示談交渉では、相手方からこの「任意保険基準」の金額を提示されるでしょう。
任意保険基準の金額は各保険会社が独自に設定しており非公開ですが、一般的には自賠責基準と同等または少し高額な程度であることが多いです。
任意保険会社は示談金で決まった金額のうち、自賠責保険では支払い切れない部分を補てんします。
示談金が多くなればなるほど、任意保険会社は多くの示談金を被害者に支払うことになるので、あえて示談金を少なめに計算して提示してくるのです。
なお、任意保険への介入は任意なので、加害者が任意保険に入っていないケースもあります。
この場合、自賠責保険では支払い切れない部分は加害者本人に請求します。
実際、損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」によれば、2022年3月末の段階で、日本の家庭用の普通乗用車のうちおよそ2割は任意保険未加入であるということです。
任意保険会社の算定基準について、さらに詳しく知りたい方は、『交通事故慰謝料の「任意保険基準」とは?』の記事をご覧ください。
弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準(裁判基準)は、交通事故裁判の判例から導き出された算定基準であるため、「日本の法律上、事故被害者の方が本来受けとるべき金額の基準」といえます。
弁護士基準の金額は3基準の中でもっとも高く、任意保険基準の2倍~3倍程度です。
この算定基準は、日本弁護士連合会(日弁連)の交通事故相談センターが発行する「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」や「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」といった書物にまとめられており、全国の交通事故実務に携わる弁護士のあいだで共有されています。
相手方任意保険会社が提示する金額を鵜呑みにしてはならない!
交通事故被害者の方の多くは、相手方任意保険と示談の交渉を行うことになります。
相手方任意保険会社が提示する慰謝料の金額は被害者の方が本来もらうべき金額と比較して低額になります。
任意保険会社の提示する金額を鵜呑みにすることなく、きちんと増額の交渉をする必要があるのです。
慰謝料は3種類ある|傷害・後遺障害・死亡慰謝料
慰謝料は「精神的な苦痛に対する賠償金」であり、交通事故の場合は傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
交通事故の増額交渉においては、これら慰謝料の種類や算定基準をしっかり把握することが重要です。
慰謝料についてさらに詳しく知りたい方、それぞれの種類の慰謝料は具体的にどのくらいの金額なのか知りたい方には、『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』の記事もおすすめします。
なお、交通事故で請求できる損害賠償金は慰謝料以外にも多くあるので、詳しくは『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』の記事をご覧ください。
傷害慰謝料
傷害慰謝料は「ケガを負ったという精神的な苦痛に対する賠償金」です。
ケガによる精神的なダメージを金銭に換算することで補償し、精神の均衡を回復するための賠償というわけです。
実務上は、慰謝料の算定基準が公表されており、傷害慰謝料については原則として入通院の期間に応じて金額を決定する仕組みになっています。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
後遺症が残り、「後遺障害等級」が認定されれば請求できます。
後遺障害等級は、ケガの治療を継続してもこれ以上良くならないという状態に至ったあと、損害保険料率算出機構という第三者機関の審査によって認定されます。
後遺障害には全14の等級があり、その認定された等級に応じて慰謝料の金額が算定されます。
後遺障害の認定の流れや申請方法の違いなど、さらに詳しく知りたい方は『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』の記事をご覧ください。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は「事故被害者が死亡したことによる精神的な苦痛に対する賠償金」です。
亡くなった本人のほか、父母、配偶者、子といった近親者にも固有の慰謝料が認められます。
死亡慰謝料の金額は、死亡した事故被害者の家庭内の立場により金額が決まります。
交通事故の死亡慰謝料についてくわしく知りたい方は『死亡事故の慰謝料相場と賠償金の計算は?示談の流れと注意点』の記事をご覧ください。
弁護士基準の慰謝料額を見てみよう
以下の計算機では、弁護士基準の慰謝料額がわかります。
すでに相手方から慰謝料の提示を受けている場合は、どれくらい増額の余地があるのかを知る目安となるでしょう。
ただし、あくまでも機械的な計算に過ぎないので、厳密な慰謝料額は弁護士に問い合わせることをおすすめします。
具体的な慰謝料の計算方法について知りたい方は、関連記事『交通事故の慰謝料の計算方法|正しい賠償金額がわかる』をあわせてご覧ください。増額事例とあわせて、計算式を使って解説しています。
慰謝料は交通事故における個別の事由により増額することがある
交通事故の慰謝料は、交通事故における個別の事情による増額が認められることがあります。
慰謝料増額の事由として認められる可能性のある個別の事情は以下のようなものです。
- 事故の原因が飲酒運転・無免許運転など加害者の悪質な行為による
- 事故後に加害者が謝罪しない・取り調べで嘘をつくなど不誠実な態度を示している
- 交通事故が原因で被害者の遺族の生活が厳しくなった
上記の事情以外でも、増額の可能性があるため、気になる方は専門家である弁護士に確認してみることをおすすめします。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、慰謝料増額が見込める
弁護士基準での賠償金を受けとりたい場合には、弁護士に示談交渉を依頼するのがおすすめです。
示談交渉で相手方の任意保険基準の金額を提示しますが、被害者本人が弁護士基準までの増額を求めても、受け入れてもらえないでしょう。
しかし、弁護士を立てれば以下の点から、弁護士基準の金額を聞き入れてもらえる可能性が高まります。
- 専門知識と資格を持つ弁護士の主張なら、保険会社側も無下にはできない。
- 弁護士の主張を拒否し続けると裁判を起こされる可能性がある。保険会社にとって裁判は以下の理由から避けたいので、態度を軟化させる。
- 裁判になれば時間や手間がかかる
- 裁判ではどの身に弁護士基準の金額が認められる可能性が高い
- 裁判になれば、裁判費用や遅延損害金なども請求されてしまう

上でも触れた通り、裁判を起こせば弁護士基準の金額が認められる可能性は高いです。
しかし、被害者にとっても裁判には以下のようなリスクがあるので、弁護士を立てて示談交渉を行う方が良いでしょう。
- 裁判を起こす手続きや、裁判での主張を裏付けるための準備などに非常に手間がかかる
- 裁判を起こすにあたって費用がかかる
- 裁判費用は勝訴すれば相手方に請求できるが、敗訴すれば被害者側の負担になる
- 裁判では解決までに時間がかかるケースが多い
- 裁判によって被害者に不利な判決が出る可能性もある
弁護士に示談交渉を行ってもらえば、交渉も手間もかからないうえ、裁判よりも早く弁護士基準の金額が得られる可能性が高まります。
弁護士費用は「弁護士費用特約」が使えれば多くのケースで負担せずに済むので、ご加入の保険を確認してみてください。
弁護士に依頼すべきタイミングとは?メリットとは?
弁護士に依頼するタイミングは早い方が良い!
慰謝料の増額という点において、弁護士に依頼するのはベストな選択です。
特に、依頼が早ければ早いほど慰謝料増額の可能性は上がります。
以下にその理由を挙げていきます。
弁護士に依頼するタイミングについては『交通事故で弁護士に相談・依頼するベストタイミングは?』の記事でも紹介しているので、あわせてご覧ください。
任意保険会社との交渉が有利になる!
先述のとおり、任意保険会社は原則として事故被害者の方からの増額交渉には応じません。
任意保険会社は営利組織です。
任意保険会社の視点に立つと、事故被害者の方に支払う金額が低ければ低いほど自社の利益になるのです。
増額交渉を行うときには弁護士に依頼すべきといえます。
依頼のタイミングが早いほど、示談交渉の対策が立てやすく増額の成功率も上がるので、早期の依頼をおすすめします。
適正な後遺障害認定を受けられる!
後遺症が残った場合は、示談交渉に入る前に後遺障害等級認定の申請を行います。
この時点で弁護士に依頼していれば、申請のサポートを受けられるので、適切な等級に認定され、適切な金額の後遺障害慰謝料が得られる可能性が高まります。
後遺障害等級の認定審査では、後遺障害診断書などが示す後遺症の症状や程度・治療過程などが確認されます。
同じような後遺症でも、書類の書き方や受けた検査の種類によっては、審査で不利になる可能性があるのです。
ここで注意すべきなのは、医学的に必要と判断される検査の種類や、医学的に問題のない診断書の書き方が、必ずしも後遺障害等級の認定審査で評価されるとは限らないということです。
もちろん、受けるべき検査は医師が決めるものですし、診断書も医師が作成するものです。
しかし、交通事故の場合は、ある程度「後遺障害等級の認定審査で有利に働くか」「審査に不利にならないか」といった視点も考慮する必要があるのです。
後遺障害等級認定については、弁護士が詳しく知っています。
早めに弁護士に依頼して、受けた検査の種類や診断書の内容が後遺障害等級認定の審査に耐えうるものかどうか、判断してもらうことをおすすめします。
後遺障害等級ごとに障害の内容を具体的に知りたい方は『【後遺障害等級表】認定される後遺症・症状の一覧と等級認定の仕組み』の一覧表をご覧ください。
適正な過失割合を主張できる!
過失割合とは
過失割合とは、交通事故の責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるか、割合で示したもの。
被害者にも過失割合が付くことは珍しくなく、つくとその割合分、慰謝料や損害賠償金が減額される。これを過失相殺という。
逆にいうと、示談交渉により被害者側の過失割合を減らせたら、その分受け取れる示談金が増額される。
示談交渉で相手方保険会社は、過失相殺による減額幅を大きくするため、あえて被害者の過失割合を多めに提示してくることがあります。
これを覆すには、事故状況を示す証拠や類似の判例、専門書の記載などを提示して、被害者の過失はもっと少ないということを主張しなければなりません。
しかし、ドライブレコーダーや監視カメラの映像、警察官が作成する実況見分調書といった証拠を集め、過去の判例や専門書まで提示するのは、被害者1人では困難でしょう。
また、たとえ弁護士に依頼をしても、示談交渉直前や示談交渉中の依頼だと、十分な準備ができない可能性があるので、弁護士にはできるだけ早く相談しておくことが大切なのです。
過失割合について詳しく知りたい方は『交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順』をご覧ください。
また、今まさに不当な過失割合を主張されて困っているという方は『交通事故の過失割合が納得いかない!おかしいと感じたらゴネ得を許さず対処』の記事がおすすめです。
弁護士に依頼するメリットは慰謝料増額にとどまらない!
弁護士に依頼するタイミングは早ければ早いほど、上記のようなメリットによって慰謝料増額の可能性があがります。
また、慰謝料増額という面以外にも弁護士に依頼するメリットがあるのです。
治療費打ち切りに対抗できる!
交通事故において、多くの場合、相手方保険会社は病院と連絡を取り合い、相手方保険会社が直接病院に治療費を支払います。
しかし、任意保険会社としては、なるべく早期に損害を確定させ、示談交渉を終わらせて紛争を解決したいと考えています。
また、治療が長引けばその分支払わなくてはならない治療費も増大していくことでしょう。
そのため、まだ治療が終了していないにも関わらず、治療費の打ち切りを打診してくることがあるのです。
保険会社から治療を打ち切るよう言われても、その段階で治療がまだ必要なら当然病院での治療を継続すべきです。
治療費打ち切りを打診されたときには、打ち切りの延長交渉を行うと良いでしょう。
具体的な対処法として担当医に治療継続の必要性を示した診断書を作成してもらい、保険会社に提出するというものが考えられます。
弁護士に依頼すれば、適切な交渉を行ってくれるため、治療費の打ち切りを延長してくれる可能性が上がるといえます。
治療費の支払いについては『交通事故被害者の治療費は誰が支払う?立て替えは健康保険を使う!過失割合との関係は?』をご覧ください。
また、治療費の打ち切りに関しては、関連記事『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』をお読みください。
裁判沙汰にも対応できる!
被害者の方と相手方保険会社の主張が決定的に決裂してしまった場合、裁判沙汰になる可能性もあります。
裁判にはメリットとデメリットがあります。
「相手方保険会社に要求したい費目・金額はいくらか」「その金額は判例と比べて認められ得るものなのか」「裁判にかかる労力と釣り合っているのか」など、慎重に検討するべきなのです。
弁護士は交通事故の裁判例や、慰謝料の相場などを熟知してします。
事故の状況、ケガの状況等に応じて、「示談交渉による増額を目指すべきか」「裁判も辞さない覚悟で臨むべきか」など、適切に判断することが可能です。
さらに裁判にかかる手間を軽減でき、法廷における被害者側の主張もより効率的に裁判官に提示できます。
つまり勝訴の可能性が上がるわけです。
交通事故の裁判についてくわしく知りたい方は『交通事故の裁判の起こし方や流れ|費用・期間や裁判になるケースを解説』をご覧ください。
弁護士相談により交通事故慰謝料が増額した実例
3000万円以上の増額となった事例
| 事故の概要 | 交差点において加害者車両が左折。 交差点を直進しようとしていた被害者自転車を巻き込んだという事故。 被害者は頭がい骨骨折、脳挫傷の傷害を負い、聴力の低下などの後遺症が残った。 後遺障害7級に認定された。 |
| 相手方保険会社提示額 | 3537万7384円 |
| 最終回収額 | 7350万円 |
| 増額金額 | 3812万2616円 |
こちらの事例では、相手方保険会社からまず3500万円を超える金額の提示がありました。
弁護士が交渉した結果、最終的には7350万円での示談となり、ほぼ倍に近い増額となったのです。
相手方保険会社提示の3537万7384円という金額は、一見すると大金のため妥当に見えます。
このような事例では、弁護士への依頼によって大幅な増額が見込めるのにもかかわらず、保険会社の言うことを鵜呑みにしてしまうという方が数多くいらっしゃるのです。
交通事故に遭ったらまずは一度、弁護士に相談するべきといえるでしょう。
適切な後遺障害認定で大幅な増額となった事例
| 事故の概要 | バイク対自動車の事故。 被害者バイクが交差点を直進中、対向の右折自動車と衝突した。 被害者は左手の親指を骨折し、可動域が半分以下になるという後遺症を負った。 |
| 保険会社提示額 | 36万440円 |
| 最終回収額 | 295万円 |
| 増額金額 | 258万9560円 |
こちらの事故は後遺障害の認定について争いとなった事例です。
相手方保険会社は事故被害者の方に対して「後遺障害には認定されないので申請しなくていい」等と主張しており、被害者の方もそれに従ってしまっていました。
当事務所の弁護士が受任後に後遺障害の申請を行ったところ、後遺障害14級相当だと認められ、大幅な増額となったのです。
任意保険会社は、時として事故被害者に対し後遺障害の申請をしないよう言ってくることがあります。
後遺障害認定されれば支払う賠償金の金額が増大し、保険会社にとっての不利益になるためです。
後遺障害になるかどうか疑問をお持ちの方は、一度弁護士に相談するべきと言えるでしょう。
相手方保険会社の提示額が低かった事例
| 事故の状況 | 被害者の乗る自転車と加害者の乗る自動車が衝突したという事故。 被害者は右肩腱板断裂の傷害を負った。 |
| 保険会社提示額 | 341万207円 |
| 最終回収額 | 1000万円 |
| 増額金額 | 658万9793円 |
こちらは、相手方任意保険会社提示の金額より600万円以上も増額したという事例です。
事故被害者の方は右肩の可動域に障害を残し、後遺障害12級が認定されていました。
任意保険会社によっては、自賠責基準とほとんど変わらないような金額を提示してくる場合もあります。
後遺障害12級に認定されていながら341万円の提示というのは、かなり足元を見ていると言わざるを得ません。
この事例では弁護士の介入により、元の金額の3倍弱もの金額を回収することができました。
軽傷の事例
| 事故の概要 | 被害者が路肩に停車中、加害者車両が横合いから追突した事故。 被害者は頚椎を捻挫した。 後遺障害なしの軽傷事例。 |
| 相手方保険会社提示額 | 42万7537円 |
| 最終回収額 | 74万1411円 |
| 増額金額 | 31万3874円 |
上記の事例は後遺障害の残らなかった軽傷事例ですが、弁護士費用を差し引いても依頼者に15万円以上の利益が発生しました。
実務上、ケガの重い事故の方が増額幅は大きくなります。
しかし、軽傷の場合であっても被害者の方の利益になるケースというのは数多くあるので、事故被害者の方は一度弁護士に相談するべきといえるでしょう。
また、事故被害者の方が任意保険の弁護士費用特約に加入している場合、費用倒れになる可能性はほとんどなくなります。
弁護士費用特約とは任意保険のオプションサービスで、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるというものです。
その金額は会社によって差異がありますが、おおむね、弁護士への相談料として上限10万円、弁護士費用としては上限300万円に設定されていることが多いです。
そのため、弁護士費用特約を利用すると、弁護士費用について事故被害者の方の負担を大きく減らすことができます。
弁護士費用特約に加入しているなら、ぜひ利用を検討してみてください。
軽傷の慰謝料相場については、『軽傷の交通事故慰謝料はどれくらい?十分にもらう方法と症状別の相場』の記事でもまとめていますので、あわせてご参考ください。
過失割合について争いとなっていた事例
| 事故の概要 | 細い路地の交差点において、加害者自転車がノーブレーキで交差点に進入。 被害者自転車に衝突したという事故。 |
| 相手方保険会社提示額 | 55万5030円 |
| 最終回収額 | 105万円 |
| 増額金額 | 49万4970円 |
こちらの事故は過失割合について争いが生じていた事例です。
当初、相手方保険会社は90対10の提示をしていたのに、交渉が進む中、突然80対20の主張をするようになりました。
弁護士が介入したところ当初の主張通り90対10の過失割合に戻すことができたのです。
事故によっては相手方保険会社が恣意的な過失割合を主張することがあります。
そのようなときには弁護士の立証活動により適正な過失割合に修正することで、慰謝料の増額が見込めます。
交通事故慰謝料を増額するためにまずは弁護士に相談を!
交通事故の慰謝料を増額させ、適切な金額を獲得するには、弁護士への依頼が欠かせません。
まずは、弁護士に相談を行い、慰謝料の増額が可能であるのか、弁護士費用を支払ってでも依頼すべきかどうかなどを確認してみましょう。
アトム法律事務所では、24時間365日対応のLINE無料相談サービスを提供しています。
お手持ちのスマホからアトム法律事務所のLINEアカウントを「友だち追加」すれば、無料で法律相談を受けることができます。
また電話窓口では24時間365日、いつでも相談の予約を受け付けています。
相談は初回30分無料です。
下記のフォームからお気軽にお問い合わせください。
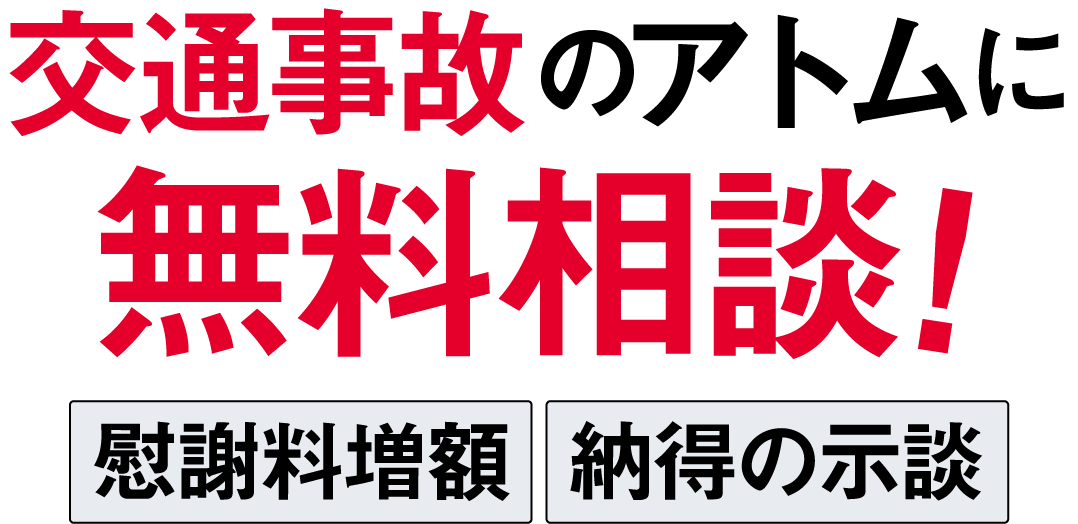

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了



