交通事故の示談金の計算方法・相場は?示談金増額のコツも徹底解説

交通事故に遭った場合、相手方の任意保険会社から示談金の提示を受けます。
しかし、提示された示談金をそのまま受け入れてしまうのは危険です。
示談金に含まれる慰謝料・休業損害・逸失利益は、わざと金額が低くなるように計算されている可能性があるからです。
この記事では、交通事故における示談金の内訳・計算方法・相場を解説しています。どうすれば十分な金額を得られるのかまで紹介しているので、ぜひ確認してみてください。
目次
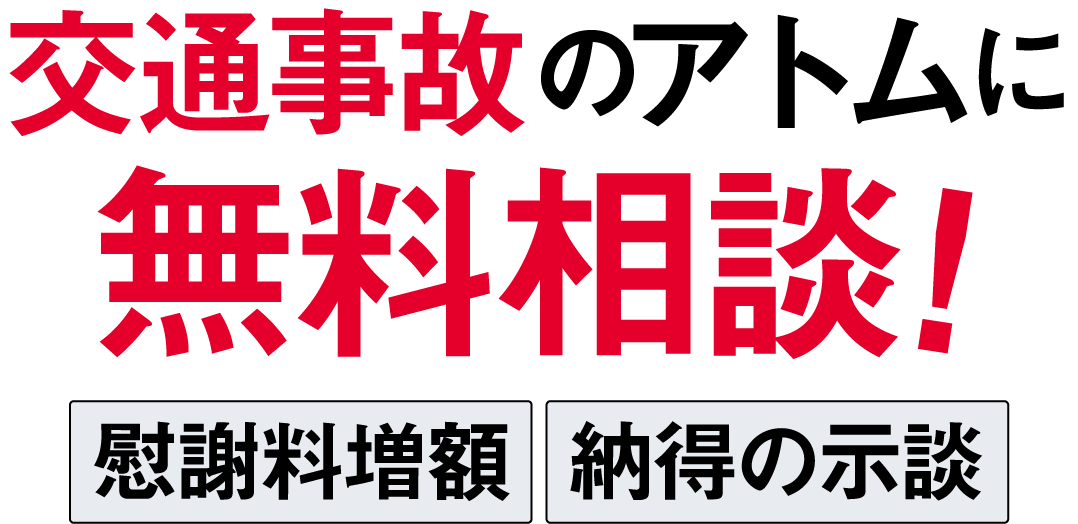
交通事故で請求できる示談金の種類は?
交通事故における示談金として支払われる損害とは、以下のようなものとなります。
- 治療関係費
- 慰謝料
- 休業損害
- 逸失利益
- 物的損害
それぞれの損害の内容について、説明を行います。
(1)治療関係費
治療関係費には、以下のものが含まれます。
- 投薬代、手術代、入院費用などのケガの治療費
- 通院のための交通費
- 診断書作成費
- 付き添い看護費など
交通事故の示談金は基本的に示談成立後に支払われますが、治療費については治療と並行して、加害者側の任意保険会社が病院に直接支払ってくれることが多いです。
しかし、中には一旦被害者側が治療費を立て替えたり、治療が終わっていないのに治療費を打ち切られたりすることもあります。
治療費の支払いについてお困りの場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
関連記事
交通事故の治療費は誰が支払う?過失割合がある場合や立て替えのポイントは?
(2)慰謝料|3種類あり
慰謝料とは、精神的苦痛に対する補償として支払われるものです。
交通事故の場合は入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があるので、紹介していきます。
各慰謝料の計算方法は、のちほどこの記事内で解説します。
入通院慰謝料|入通院で生じる精神的苦痛を補償
入通院慰謝料とは、交通事故によるケガの治療のための入院・通院で受けた精神的苦痛に対する補償のことを言います。
交通事故にあい、入院や通院が必要になると、次のような気持ちを感じませんか?
- どうしてこんな痛い思いをしないといけないの?
- 入院や通院のせいで元々の予定が狂ってしまった!
- 手術を受けなければいけないけれど怖くて不安…
このような入院や通院、治療で感じる精神的苦痛に対する補償が、入通院慰謝料なのです。
後遺障害慰謝料|後遺障害により今後も生じる精神的苦痛を補償
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺障害が残ったことで、今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償のことを言います。
交通事故によって後遺障害が残ると、その後将来にわたって痛みを感じたり、後遺障害を負ったことによるハンデを感じたりすることとなるでしょう。
そうした精神的苦痛に対する補償が、後遺障害慰謝料なのです。
ただし、後遺障害慰謝料はただ後遺症が残っただけでは受け取れません。
後遺障害等級認定の審査を受けて、後遺障害等級が認定された場合のみ請求できる慰謝料なのです。
- 後遺障害等級認定を受けるためにはどうしたらいいの?
- 後遺障害等級が認定される後遺症ってどんなもの?
- 症状別の慰謝料相場金額が知りたい!
そんな疑問をお持ちの方は、下記の関連記事をご覧ください。
死亡慰謝料|被害者と遺族の精神的苦痛を補償
死亡慰謝料は、交通事故によって死亡した被害者や、その遺族の精神的苦痛に対して支払われる補償です。
そのため、被害者に支払われる死亡慰謝料と、被害者の遺族に支払われる死亡慰謝料がそれぞれ存在します。
被害者の「遺族」とは基本的に、配偶者・親(養父母含む)・子(養子含む)を指します。
しかし、内縁の妻・夫や兄弟姉妹でも、上記の遺族と同じくらい被害者との関係が強く、悲しみも深いと判断されると、慰謝料を受け取れる可能性があるのです。
なお、慰謝料を含む示談金は本来、被害者本人が請求するものですが、死亡事故ではそれができません。
よって、慰謝料請求をする権利は遺族から選ばれる相続人に引き継がれます。
- 死亡慰謝料には相続税はかかるの?
- 受け取った慰謝料や賠償金はどう分配するの?
このような疑問をお持ちの方は、関連記事『死亡事故の慰謝料相場と賠償金の計算は?示談の流れと注意点』も合わせてご確認ください。
(3)休業損害
休業損害は、交通事故にあって仕事を休まざるを得なくなった場合に生じる減収を補償するためのものです。

交通事故によってやむを得ず仕事を休んだ場合でも、その分の収入はきちんと加害者側に請求できます。有給休暇を使って休んだ日も、基本的に休業損害の支払い対象となるので、安心してください。有給休暇と休業損害の関係については『交通事故で有給を使っても休業損害・休業補償はもらえる?』の記事が参考になります。
また、休業損害の詳しい計算方法については後ほど解説していきます。
(4)逸失利益|2種類あり
逸失利益とは「交通事故がなければ将来得られていたはずの利益」に対する補償で、後遺障害逸失利益・死亡逸失利益の2種類があります。

後遺障害逸失利益
交通事故にあい後遺障害が残ると、その後の仕事に影響が出て、生涯年収が減ってしまう可能性があります。後遺障害逸失利益とは、そうした損害を補償するものです。
ただし、後遺障害逸失利益は後遺障害慰謝料と同様、「後遺障害等級」が認定されていないと加害者側に請求できません。
後遺症が残っているのにまだ後遺障害等級認定を受けていない方は、必ず受けましょう。
後遺障害等級認定の方法や結果に疑問がある方は、弁護士がお力になりますのでお気軽にご相談ください。
死亡逸失利益
交通事故によって被害者が死亡したことで得られなくなった収入・利益に対する補償のことを死亡逸失利益と言います。
死亡事故で加害者側に請求できるのは慰謝料だけではありません。請求するべき項目をしっかり請求して、加害者側に補償してもらいましょう。
(5)物的損害
交通事故により物損が生じた場合には、壊れた物の修復費用等を請求することが可能です。
具体的には、以下のような損害をいいます。
- 自動車や自転車の修理費用
- 代車費用
- 事故により破損した持ち物の修理代、買換え費用
示談金の計算をするために知っておくべきこと
増額が望める示談金の項目がある
交通事故の示談金には、増額が見込める項目と、あまり増額が見込めない項目があります。
| 増額の見込みあり | 慰謝料、休業損害、逸失利益 |
| 増額の見込みなし | 治療関係費、物的損害 |
増額が見込める項目とは、裏を返せば「加害者側が相場よりも低い金額を提示してくる項目」といえます。
このことを知らずに示談交渉に臨むと、加害者側の任意保険会社が提示してきた低い金額をそのまま受け入れてしまう恐れがあるのです。
加害者側の任意保険会社から示談金額の提示があった場合には、特に慰謝料・休業損害・逸失利益の金額に注目してみてください。
- 何となく金額が低い気がする
- え?この程度の金額なの?
そう感じた場合、その感覚は正しい可能性が高いです。
具体的にどれくらい低額なのかわからない場合は、弁護士に相談してみるべきでしょう。
関連記事
増額が見込める費目は、わざと低額になるよう計算されている
慰謝料・休業損害・逸失利益は計算によって金額が導き出されますが、加害者側の任意保険会社はあえて低額になるように計算していることが多いです。
慰謝料・休業損害・逸失利益に増額の余地があると言えるのは、こうした背景があるからです。
ただし、慰謝料・休業損害と逸失利益とでは金額が低く計算されてしまう事情が少々異なるので、もう少し詳しく解説しておきます。
慰謝料・休業損害の計算方法は3つある
交通事故の慰謝料・休業損害には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの計算基準があり、どの基準を用いて計算するかで金額が変わります。
| 計算基準 | 金額の特徴 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 自賠責保険会社による支払分を計算するための計算基準 交通事故の被害者が受け取れる最低限の金額となっている |
| 任意保険基準 | 示談交渉で加害者側の任意保険会社が提示してくる金額基準 各保険会社独自の計算方法で算出される 弁護士基準よりも金額は低い |
| 弁護士基準 | 弁護士や裁判所が用いる金額基準 過去の判例をもとに設定されているため、裁判基準とも言われる 3つの計算基準の中で最も高額となる |

3つの計算基準の中で最も高額で妥当なのは弁護士基準の金額ですが、加害者側の任意保険会社は任意保険基準で計算した金額を提示してきます。
そのため、加害者側の任意保険会社の提示額は低くなっているのです。
一般的に、任意保険基準の金額は弁護士基準の半分~3分の1程度といわれています。
任意保険基準の金額をそのまま受け入れてしまうと、大幅な増額のチャンスを逃してしまうことになるので注意しましょう。
逸失利益は計算で用いる数値が少なく見積もられる
逸失利益の計算方法には、慰謝料や休業損害のような3つの計算基準はありません。
そのため、任意保険会社が計算する場合でも弁護士が計算する場合でも、計算式自体は同じです。
しかし、任意保険は計算で用いる数値を低く見積もっていることがあり、それによって逸失利益の金額が低くなっています。
逸失利益の金額を確認するときは、計算で用いられている数値が正しいかどうかを確認しましょう。
交通事故の示談金計算|慰謝料の場合
示談金の項目の一つである慰謝料の計算方法や具体的な金額を、計算基準ごとに紹介します。
なお、任意保険基準の計算方法は非公開であるため紹介していませんが、基本的には自賠責基準による金額と同程度、または、多少増額されている金額になることが多いでしょう。
入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料は、自賠責基準であれば計算式を用いて、弁護士基準であれば入通院慰謝料算定表という表を用いて金額が算定されます。
自賠責基準での計算方法
自賠責基準で用いる計算式は、以下のようになっています。
計算式:4300円 × 対象日数
次のうちどちらか短い方を「対象日数」として採用します。
- 治療期間
- 実際に治療した日数×2
※治療期間とは、一番最初に病院を受診した日~治療終了までの期間をさします。
実際に、むちうちで入院0日、実通院日数60日、通院期間90日であった場合の計算例を紹介します。(2020年4月1日以降の事故とします。)
計算例
- 入通院日数を確認
入院日数+通院期間=0日+90日=90日
入院日数+実通院日数×2=0日+60日×2=120日
前者の方が少ないため、前者(90日)を対象日数とする - 4300円×対象日数=4300円×90日=387000円
これが、自賠責基準での入通院慰謝料の計算方法です。
弁護士基準での計算方法
一方、弁護士基準で用いられる「入通院慰謝料算定表」には、軽傷用と重傷用があります。
以下のように使い分けてください。
- 打撲や挫傷、または、レントゲン写真やMRI画像のような他覚所見のないむちうち→軽傷用
- 軽傷用に該当しない症状→重傷用
では実際の表を見ていきましょう。
軽傷用の表

重傷用の表

表は1月を30日として、通院月数と入院月数の交わるところを見てください。
とはいえ、通院も入院もぴったり◯ヶ月という場合ばかりではなく、中には◯ヶ月△日というように端数があることもあるでしょう。
そのような場合の計算例をご紹介します。
たとえば、他覚所見のないむちうちで75日間(2ヶ月15日間)通院した場合の計算方法は、以下の通りです。
計算例
- 初めの2ヶ月間の通院は36万円
- 3ヶ月目の15日間は、日額を(53万円₋36万円)÷30日として約5666円
※53万円は、通院を3ヶ月した場合の金額 - したがって2ヶ月と15日間通院した場合は、36万円+5666円×15日=44万4990円
後遺障害慰謝料計算方法
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとに決まっています。
自賠責基準の金額と弁護士基準の金額を並べてみてみましょう。
| 等級 | 自賠責* | 弁護士 |
|---|---|---|
| 1級・要介護 | 1,650(1,600) | 2,800 |
| 2級・要介護 | 1,203(1,163) | 2,370 |
| 1級 | 1,150(1,100) | 2,800 |
| 2級 | 998(958) | 2,370 |
| 3級 | 861(829) | 1,990 |
| 4級 | 737(712) | 1,670 |
| 5級 | 618(599) | 1,400 |
| 6級 | 512(498) | 1,180 |
| 7級 | 419(409) | 1,000 |
| 8級 | 331(324) | 830 |
| 9級 | 249(245) | 690 |
| 10級 | 190(187) | 550 |
| 11級 | 136(135) | 420 |
| 12級 | 94(93) | 290 |
| 13級 | 57(57) | 180 |
| 14級 | 32(32) | 110 |
単位:万円
*()内は2020年3月31日以前に発生した事故に対するもの
- 同じ等級でも自賠責基準か弁護士基準かで金額が全く違う
- 同じ基準でも等級が1つ違うだけで金額が大きく違う
このような点が、後遺障害慰謝料の特徴です。
後遺障害慰謝料を最大限受け取りたい場合は、前提として適切な後遺障害等級の認定を受けることが重要になります。
弁護士のサポートを受けながら後遺障害の申請をすれば、より適切な等級に認定されやすくなるでしょう。
後遺障害等級認定の申請方法や流れについて詳しく知りたい方は、『後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由を解説』の記事をご覧ください。
死亡慰謝料の計算方法
死亡慰謝料には、交通事故で死亡した被害者に対する金額と遺族に対する金額があります。
死亡慰謝料の請求が可能なご遺族とは、基本的に父母(養父母含む)、配偶者、子(養子含む)のことを指します。
では、自賠責基準と弁護士基準の死亡慰謝料について見ていきましょう。
自賠責基準での計算方法
自賠責基準では、死亡慰謝料は被害者分400万円(2020年3月31日以前の事故については350万円)に、ご遺族の人数に応じた金額を加算します。
| 遺族 | 扶養なし | 扶養あり |
|---|---|---|
| 1名 | 550万円 | 750万円 |
| 2名 | 650万円 | 850万円 |
| 3名以上 | 750万円 | 950万円 |
死亡した被害者に扶養内の遺族が2人(妻・子)がいた場合の死亡慰謝料は、400万円+850万円で1250万円になるということです。
弁護士基準での計算方法
弁護士基準では被害者の家庭における立場により金額が異なり、具体的な金額は以下の通りです。
| 被害者の属性 | 死亡慰謝料 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2800万円 |
| 母親・配偶者 | 2500万円 |
| その他 | 2000万~2500万円 |
上述の金額は、遺族が請求できる金額も含めたものです。
弁護士基準では、一家の支柱の死亡慰謝料金額は扶養家族3人までを想定して設定されています。
そのため、扶養家族が4人以上の場合は、増額される可能性があります。
交通事故の示談金計算|休業損害の場合
休業損害の計算方法は、自賠責基準と弁護士基準でそれぞれ次のようになっています。
任意保険基準は各保険会社ごとに異なり非公開なので、割愛します。
| 自賠責基準 | 6100円×休業日数 (2020年3月31日以前の事故については5700円×休業日数) |
| 弁護士基準 | 収入の日額×休業日数 |
上の表のとおり、自賠責基準の場合は日額6100円です。
正直なところ、日額6100円では足りないという方もいらっしゃるでしょう。
一方、弁護士基準での日額は、被害者の職業・収入に合わせて決められます。具体的には次の通りです。
| 給与所得者 | 事故前3か月間の給与÷事故前3か月間の実労働日数 |
| 自営業者 | 事故前年の所得÷365日 |
| 専業主婦 | 賃金センサスの女性の全年齢平均賃金から算出 (約1万円) |
この他、学生や無職の方でも休業損害を受け取れる場合があります。
休業損害について詳しく知りたい方は、以下の関連記事を参考にして、適正な休業損害の獲得を目指しましょう。
関連記事
交通事故の示談金計算|逸失利益の場合
後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の基本的な計算方法をそれぞれ解説します。
もっとも、計算するうえで職業ごとに異なる点も出てくるので、職業別に逸失利益の計算が知りたい方は『交通事故の逸失利益とは?職業別の計算方法!早見表・計算機で相場も確認』の記事もあわせてご確認ください。
後遺障害逸失利益の計算方法
交通事故の後遺障害逸失利益は、次の計算式で計算されます。
収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
- 労働能力喪失率とは?
- 労働能力喪失期間とは?
- ライプニッツ係数とは?
聞きなれない言葉だけに、そんな疑問を持った方もいらっしゃるでしょう。
ここでは逸失利益の計算に必要な項目について、もう少し詳しく解説していきます。
逸失利益における収入とは?
逸失利益の計算を行う際の基準となる収入とは、交通事故の前年の収入になります。
給与所得者であれば事故前年の源泉徴収額、自営業者であれば事故前年の所得となるでしょう。
交通事故の時点で収入のない専業主婦や学生であっても、賃金センサスを基準として収入の判断が可能です。
労働能力喪失率とは?
労働能力喪失率とは、後遺障害によってどれくらい労働に支障が生じるのかを割合で示したものです。これは、目安が後遺障害等級ごとに決まっています。
| 等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 1 | 100% |
| 2 | 100% |
| 3 | 100% |
| 4 | 92% |
| 5 | 79% |
| 6 | 67% |
| 7 | 56% |
| 8 | 45% |
| 9 | 35% |
| 10 | 27% |
| 11 | 20% |
| 12 | 14% |
| 13 | 9% |
| 14 | 5% |
※2020年4月1日以降に発生した事故に適用される係数
ただし、後遺障害の症状の程度や内容を考慮して、表よりも大きい割合が適用されることもあれば、小さい割合が適用されることもあります。
任意保険会社が後遺障害逸失利益を計算する場合は、実際よりも小さい労働能力喪失率を適用し、金額を下げていることが多いです。
労働能力喪失期間とは?
労働能力喪失期間は、後遺障害によって労働能力が低下した状態で働く年数のことです。
基本的に、症状固定時~67歳までの年数となります。
ただし、むちうちで後遺障害14級に認定されている場合には、労働能力喪失期間は上限5年とされる場合があります。
労働能力喪失期間も、任意保険会社は少なく見積もることがあるので注意してください。
ライプニッツ係数とは?
後遺障害逸失利益の請求が認められると将来得られるはずの収入の一部が、早期に得られることとなります。
早期に得た利益を預金・運用すると利子や利益が生じることとなりますが、このような利益は本来得られないはずであったため、調整が必要となるのです。
ライプニッツ係数とは、そうした利子や利益をあらかじめ差し引くための数値になります。
具体的な数値は、労働能力喪失期間に応じて決まるのです。
2020年4月1日以降に発生した交通事故であれば、ライプニッツ係数は年利3%に基づいて算出されます(2020年3月31日以前は年利5%)。
以下の表でライプニッツ係数の一部を紹介します。
| 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
|---|---|
| 1年 | 0.97(0.95) |
| 5年 | 4.58(4.33) |
| 10年 | 8.53(7.72) |
| 20年 | 14.88(12.46) |
| 30年 | 19.60(15.37) |
死亡逸失利益の計算方法
死亡逸失利益の計算方法は、次のようになります。
死亡逸失利益=収入×(1‐生活費控除率)×死亡により就労できなくなった年数に対するライプニッツ係数
死亡により就労できなくなった年数は、基本的に死亡年齢~67歳までの年数を指します。収入、ライプニッツ係数は、後遺障害逸失利益でご紹介した通りです。
生活費控除率とは、死亡逸失利益のうち、交通事故にあわなければ被害者本人が生活費として消費したと考えられる金額を、あらかじめ差し引くための数値のことです。
生活率控除率は次のようになっています。
| 被害者の属性 | 生活費控除率 |
|---|---|
| 一家の支柱 (扶養家族1人) | 40% |
| 一家の支柱 (扶養家族2人以上) | 30% |
| 女性 | 30% |
| 男性 | 50% |
交通事故の示談金の相場は?計算機で確認
こちらの計算機では、示談金に含まれる慰謝料・逸失利益の金額を簡単に計算できます。
年齢や性別、交通事故前の年収などを入力するだけで簡単に計算でき、もちろん無料です。
- 自分が受け取れる慰謝料や損害賠償額の相場を知りたい
- 加害者側の任意保険会社から提示された金額が適正か知りたい
このような場合にはぜひご利用ください。
示談金増額のコツは弁護士に相談すること
理由(1)弁護士基準の金額を主張してもらえる
示談交渉で弁護士を立てると、弁護士基準の金額を主張してもらえます。
- 被害者自身でも知識を身につければ弁護士基準を主張できるのでは?
- 粘り強く交渉すれば被害者自身でも提示金額を増額させられるのでは?
そう思いがちですが、被害者自身で交渉をし、加害者側の任意保険会社に弁護士基準の金額を認めてもらうことは困難です。
弁護士基準は金額が大きいので、弁護士という専門家による主張でないと、加害者側の任意保険会社も受け入れない傾向にあるのです。
弁護士に交渉を依頼せず、被害者自身で交渉をした場合でも多少の増額はできる可能性があります。
しかし、任意保険基準の金額をベースとした金額にならざるを得ないため、示談交渉は弁護士に依頼する方が、納得のできる適切な金額を得られる可能性が高まります。
理由(2)事情に応じた慰謝料の増額も主張してもらえる
交通事故の慰謝料額は、ここで紹介したような方法で一律的に計算できるものばかりではありません。
たとえば、以下のような個別事情がある場合は、慰謝料が増額されて弁護士基準の金額以上になることもあるのです。
- 加害者に信号無視や飲酒運転など悪質な行為があった
- 事故前後における加害者の態度が悪い
- 重大な後遺障害が残り、被害者家族の負担が増した
- 被害者のケガにより被害者家族の経済状況が悪化した
- 事故を目撃した被害者側の家族が精神疾患となった
しかし、加害者側の任意保険会社はできるだけ慰謝料を増額させたくないと思っているため、被害者自身で増額を求めても聞き入れてもらえない可能性が高いです。
そのようなときでも、弁護士が主張すれば聞き入れてもらえる可能性が高くなります。
交通事故によって感じた苦しみや怒り、悔しさなどを加害者側に漏れなく理解してもらい、慰謝料という形で補償してもらいたいという場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士による示談金増額事例をご紹介
では、実際に弁護士による示談交渉で示談金が増額した事例をご紹介します。
いずれも、アトム法律事務所での事例です。
- 自分の場合でも本当にこんな風に増額できるの?
- もっと示談金が低い案件は受け付けてもらえないのでは?
そう思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは弁護士に相談してみないとわかりません。
弁護士に相談する=弁護士に示談交渉を依頼する、ということではありませんし、アトム法律事務所なら無料で相談ができます。
弁護士に相談してみて、やっぱり依頼はしないということも可能です。安心して、まずはお気軽にご連絡ください。
(1)600万円から900万円への増額
| 傷病名 | 左上腕骨外科頸骨折 |
| 後遺障害の内容 | 左肩の可動域制限 |
| 後遺障害等級 | 12級7号 |
バイク乗車中に車と衝突したケースです。ご依頼者様は加害者側の任意保険会社からの提示金額に疑問を持たれ、後遺障害等級の認定前に相談に来られました。
弁護活動のポイントは、次の通りです。
弁護士が保険会社との示談交渉に介入後に、示談金として約600万円が提示されましたが、これでもなお裁判基準の損害額には及ばないと担当弁護士は判断し、交渉を粘り強く継続しました。
保険会社は、800万円の示談金を提示しましたが、それでも低い水準であったため、弁護士が裁判提起を予告しつつ900万円への増額を主張しました。
(2)441万円から2153万円への増額
| 傷病名 | 足首骨折 |
| 後遺障害の内容 | 足首の可動域制限 |
| 後遺障害等級 | 10級11号 |
ご依頼者様は加害者側の任意保険会社から提示された疑問を持たれ、電話相談を利用されました。
その結果、大幅な増額が見込まれることがわかり、アトム法律事務所の弁護士に示談交渉を任せることに決めたのです。
弁護活動のポイントは、次のようになっています。
本件で特に問題となったものを挙げるとすると、逸失利益でしょう。
ご依頼者様の事故前の収入は、平均年収(賃金センサス)より低いものでした。この点裁判基準では、おおむね20代であれば、実際の収入より高い賃金センサスの基準で逸失利益を計算することになっています。
しかしご依頼者様は、症状固定時に30歳になっていたため、ギリギリ20代にはあたりませんでした。
そこで相手方の弁護士と交渉し、中間地をとって計算することで合意しました。
(3)123万円から250万円への増額
| 傷病名 | 左足関節捻挫、左腓骨神経麻痺 |
| 後遺障害の内容 | 左足の知覚鈍麻、しびれ |
| 後遺障害等級 | 14級9号 |
ご依頼者様は加害者側の任意保険会社の提示額に疑問を感じ、LINEにてご相談されました。その結果大幅な増額の可能性があるとわかったため、示談交渉の代理をご依頼されました。
弁護活動のポイントをご紹介します。
逸失利益の部分に関してしぶとく抵抗されましたが、裁判でも認められないような過大な請求をすることは他の主張まで弱くなってしまう可能性があるため、我々は裁判でも認められる可能性の高い正当な数字を主張しました。
その結果我々の主張通りに保険会社に認めてもらうことができました。
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益という損害項目の中でも比較的大きい部分がほぼ主張通りに認められたこと、正当な数字を主張したことで早期に増額し解決したといえます。
アトム法律事務所では、他にも示談金の増額実績が多数あります。まずはお気軽にご相談ください。
実際にアトムの弁護士が解決した事例をほかにも知りたい方は「交通事故の解決事例」のページもおすすめです。
弁護士への相談・依頼にかかる費用負担は軽くできる
弁護士費用特約で弁護士費用の自己負担なし
弁護士に相談・依頼をするためには、相談料・着手金・成功報酬といった弁護士費用がかかります。
しかし、弁護士費用特約を使えれば、多くのケースで自己負担なく弁護士への依頼が可能です。
弁護士費用特約とは、被害者加入の自動車保険のオプションとしてついているもので、利用すると保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。
具体的な負担金額の上限は保険によって異なることもありますが、相場は以下の通りです。
| 相談料 | 10万円 |
| 着手金・成功報酬 | 300万円 |
弁護士に支払う費用が負担金額の上限内に収まることは珍しくないので、金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼が可能となるでしょう。
弁護士費用特約の利用によって保険の等級が下がるということもありませんので、安心してご利用ください。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、関連記事『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』をお読みください。
アトム法律事務所は弁護士費用特約無しでも安心
アトム法律事務所は、弁護士費用特約が使える方にも使えない方にも安心してご利用いただける料金体系をとっております。
そのポイントは、次の2点です。
- 無料でメール・LINE・電話相談ができる
- 弁護士費用特約がなくても着手金は原則無料、弁護士費用は後払い
ご自身の保険にもご家族の保険にも弁護士費用特約がついていなかった…という場合でも、交通事故(人身事故)に関する無料相談が可能です。
また、アトム法律事務所では、人身事故の場合の着手金は基本的に無料です。
示談金獲得後に成功報酬などの弁護士費用をお支払いいただくことになりますので、すぐに費用を用意できないという方にも安心してご利用いただけます。
もちろん、ご相談いただいたときに契約を強いることはありません。
- 交通事故の適切な示談金額を計算してほしい
- 示談交渉のポイントを聞きたい
- 加害者側の提示額が適切か判断してほしい
上記のようなご相談をはじめ、様々なご相談を受けております。
法律相談の予約は24時間体制で受け付けているので、まずはお気軽にご連絡ください。
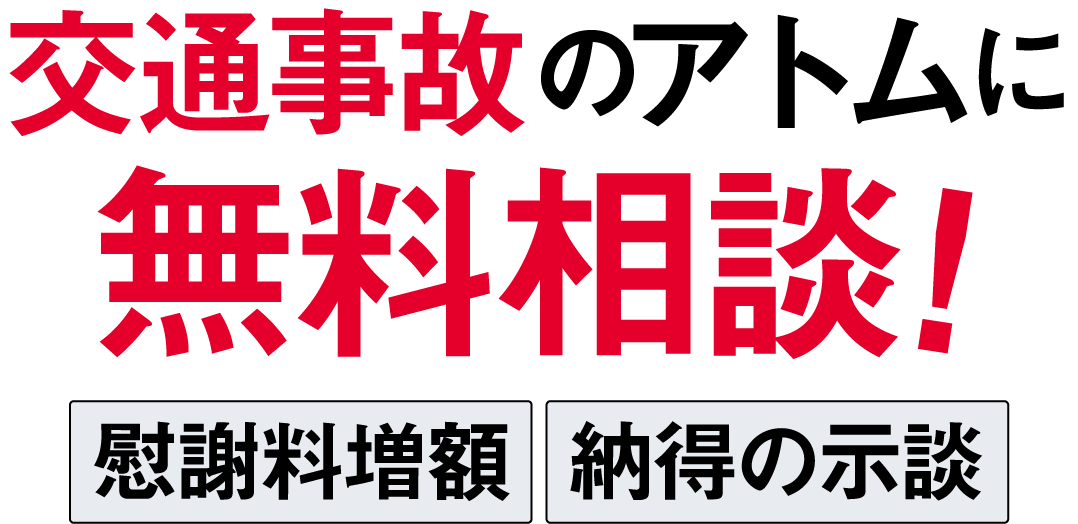
まとめ
交通事故にあい、適切な示談金を受け取るためには、適切な示談金の計算方法や増額交渉のポイントを知り、弁護士に示談を代理してもらうことが大切です。
よりご自身の状況に合った情報を得るためにも、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了



