十字路左折時に一時停止無視車と衝突し腰椎捻挫を負った事例
弁護士に依頼後...
回収
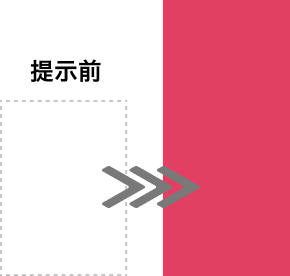

この記事でわかること
逸失利益とは、交通事故に遭わなければ将来的に得られたであろう、減ってしまった収入のことです。交通事故で後遺障害が残ったり、死亡したりした場合、逸失利益は損害賠償請求できるようになります。
もっとも、場合によっては逸失利益がもらえないこともあるので注意せねばなりません。
逸失利益を請求できない原因
本記事では、逸失利益がもらえない原因と対処法から、逸失利益の意味や損害賠償請求できる条件といった基本的な部分についても解説していきます。

逸失利益をもらえない原因としては、「後遺障害等級に認定されなかった」「労働能力に影響がなかった」「後遺障害や死亡によって減収が生じていない」「事故時に無職で事故後も働く予定がない」ことが考えられます。
ただし、上記に該当するケースでも例外的に逸失利益がもらえることはあります。
各ケースの詳細と、逸失利益がもらえない場合の対処法を見ていきましょう。
交通事故によって負ったケガが完治せず、痛みやしびれなどの症状が残っている場合でも、「労働能力に影響するほどの後遺症ではない」と判断され、後遺障害等級に認定されなければ、原則として逸失利益は認められません。
逸失利益とは、後遺障害や死亡によって将来得られたはずの収入が減ることによる損害だからです。そのため、まずは「後遺障害等級」が公式に認定される必要があります。
後遺障害の等級は、審査機関(損害保険料率算出機構)によって判断されますが、診断書や検査資料が不十分だと、適切な評価が得られないことがあります。
そのような場合は、必要な検査を受け直したり、専門医による意見書を提出したりして、「異議申立て」の手続きを通して再度、後遺障害等級の認定を目指すか、後遺障害非該当のまま示談交渉に入ることになるでしょう。
異議申立ては無料でできますが、新たな書類の準備が必要で、成功率も決して高くありません。対応に不安がある場合は、交通事故に強い弁護士への相談をおすすめします。
後遺障害等級が認定されていても、実際に労働能力に影響がないと判断されると、逸失利益が否定されることがあります。
たとえば、醜状障害(傷跡など)では、「見た目の変化が仕事に影響するとはいえない」として、労働能力の喪失が否定されやすい傾向にあります。特に家事従事者(主婦)では、「家の中での作業には支障がない」と主張されることもあるでしょう。
また、骨折による変形障害なども、等級上は労働能力の喪失が認められるものの、実際には症状が軽く、仕事に影響していないと評価されることがあります。
このような場合は、仕事や家事にどのような支障があるかを具体的に説明・立証することが重要です。たとえば「痛みで長時間座れない」「重い物が持てない」「動作に時間がかかる」といった影響を、日々の記録や医師の意見書で立証できれば、逸失利益が認められる可能性が高まります。
後遺障害が残ったり死亡したりしても、以下のような場合、後遺障害や死亡による減収は生じません。
もし上記以外に「後遺障害や死亡で働けなくなったことで生じる減収」があるなら、その部分についてのみ逸失利益を請求しましょう。
また、後遺障害認定を受けていても、減収につながらない症状であれば逸失利益がもらえない場合があります。
たとえば、後遺障害として顔の傷が残ったという事案では、職業によって逸失利益が認められるか争いになりやすいところです。
ただし、以下の場合、実際には減収が生じていなくても、後遺障害逸失利益の対象となることがあります。
本来であれば減収が生じていて然るべき状況であることを主張し、逸失利益の獲得を目指しましょう。
事故時に無職で、事故がなくてもその後も働いていなかったと思われる人も、逸失利益はもらえません。
事故があってもなくても、無収入であることに変わりはないからです。
事故がなければ将来的に就職していた可能性が高い場合は、平均収入などを参考に逸失利益が認められる可能性があります。
しかし、事故がなければ就職していたということを、被害者本人の体力や能力、事故当時の求職活動の状況などから立証しなければなりません。
加害者側と揉めることが予想されるので、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
そもそも、逸失利益とは交通事故による後遺障害や死亡によって得られなくなった、将来の収入を補償するものです。
具体的には、後遺障害や死亡により以前のように働けなくなった、昇進が望めなくなった、職業選択の幅が狭まったなどの事情で生じる収入減少という損害を金銭的に評価して換算したものを指します。
交通事故に遭わなければ得られていたはずの収入という点から、逸失利益は「得べかりし利益」「消極損害」とも呼ばれます。
逸失利益は、後遺障害によって減る生涯収入を補償する「後遺障害逸失利益」と、死亡によって得られなくなった収入を補償する「死亡逸失利益」にわけられます。
後遺障害逸失利益と死亡逸失利益はそれぞれ計算方法が異なります。
また、逸失利益の計算は非常に複雑で、一般的に慣れない用語も多く登場するため、具体的な計算方法については『交通事故の逸失利益は?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】』の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
なお、以下の計算機を使えば、慰謝料を含めた逸失利益の目安がすぐにわかります。
裁判で認められた逸失利益の請求に関して、判例をいくつか紹介します。
大阪地判平25・1・28(平成23年(ワ)5574号)
派遣社員の女性(事故時31歳)が横断歩道上を歩行中、自転車に衝突され頸椎捻挫等を受傷。事故前年収は約301万円だったが、事故当時に契約社員への昇格話があった。被害者は賃金センサス女性平均367万円を基礎とした逸失利益を主張したが、適正な基礎年収が争点となった。
「…派遣社員の場合の年収よりは増加するであろうことは容易に推認できる」
大阪地判平25・1・28(平成23年(ワ)5574号)
合計329万3,178円
大阪地判平11・12・8(平成9年(ワ)5854号)
医学部を卒業して2か月の研修医(24歳)が高速道路で死亡した事故。事故当時の医師男子全年齢平均年収1194万7200円を基礎収入として67歳までの43年間の逸失利益約1億円が算定された。もっとも、被害者の重大な過失(速度超過等)により8割の過失相殺が適用され大幅減額となった。
「…医師男子の全年齢平均給与額年一一九四万七二〇〇円の収入が得られた蓋然性が認められるというべき」
大阪地判平11・12・8(平成9年(ワ)5854号)
1億2601万2188円
逸失利益は、被害者の年齢や被害内容、将来性などさまざまな状況を考慮して決められます。
損害賠償請求とは、故意または過失による不法行為で被った損害について、不法行為を行った者に対して、金銭の支払いを求めることができます(民法709条)。
交通事故被害にあった場合には、逸失利益以外にも以下のような損害賠償金を請求できます。
支払いを求める損害賠償の具体的な金額は、これら項目ひとつひとつをそれぞれ金銭に換算し、最終的にすべてを合算して決まります。
逸失利益は損害賠償金のなかでも高額になりやすい項目なので、「逸失利益=損害賠償金」といったイメージを持たれることも多いですが、あくまで逸失利益は損害賠償金として請求できる項目の一つなのです。
損害賠償金の費目ごとのより詳しい内容や計算方法などについて具体的に知りたい方は『交通事故の損害賠償とは?賠償金の範囲や計算方法、請求時の注意点を解説』の記事をご覧ください。
逸失利益が将来の減収を補償するのに対し、慰謝料は交通事故による精神的苦痛を補償するものです。
たとえば、後遺障害逸失利益は「後遺障害による労働能力の低下で減ってしまう、生涯収入に対する補償」ですが、それに対して後遺障害慰謝料は「後遺障害が残ることで生じる精神的苦痛(悲しさや痛み、生活で感じる不便さなど)に対する補償」となります。
同じように、死亡逸失利益は「死亡により働けなくなったことで減ってしまう、収入に対する補償」ですが、死亡慰謝料は「死亡による本人及び遺族の精神的苦痛(無念さや悲しさなど)に対する補償」です。
逸失利益は事故前の収入や事故時の年齢などから算定されますが、慰謝料は別の要素から算定されるという違いもあります。
慰謝料の種類や計算方法については『交通事故の慰謝料|相場や計算方法を知って損せず増額【2026年最新】』の記事をご確認ください。
逸失利益と休業損害はともに交通事故による減収を補償するものですが、「いつ生じる減収を補償するか」「どのような人が請求できるか」が違います。
休業損害は基本的に「基礎収入×休業日数」で計算されますが、基礎収入の算出方法は職業によって異なります。
休業損害の計算方法について詳しくは、『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方・いつもらえるか弁護士解説』の記事をご覧ください。
逸失利益を請求できる人とは、「後遺障害等級が認定されたことで、生涯収入の減少が予想される人」もしくは「死亡したことで、生涯収入の減少が予想される人」です。
逸失利益を請求できる人
事故で亡くなった場合は明瞭ですが、後遺症が残った場合は注意が必要です。
後遺障害逸失利益については、単純に交通事故で後遺症が残っただけで請求できるものではありません。後遺症が後遺障害等級に認定されることではじめて、逸失利益を請求できるようになります。
後遺障害等級の認定を受けるには、専門機関に申請して審査を受けなければなりません。詳しい申請方法は『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ』の記事をご覧ください。
逸失利益を請求できる人には、給与所得者や自営業者など事故時に働いて収入を得ていた人のみならず、事故時に働いて収入を得ていなかった人も含まれます。
たとえば、子供・学生や専業主婦、一部の無職者、年金受給者(死亡逸失利益のみ)も、状況に応じて逸失利益の請求が可能です。
弁護士に依頼後...
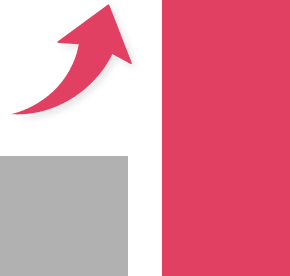
弁護士に依頼後...
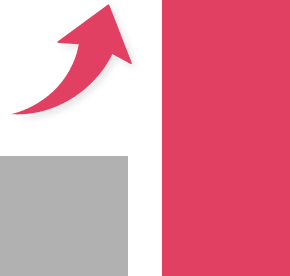
弁護士に依頼後...
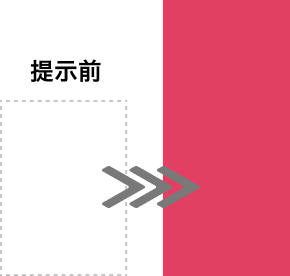
弁護士に依頼後...
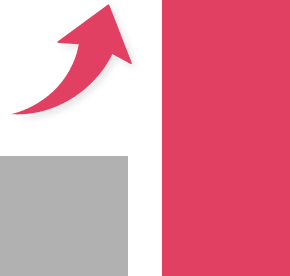
高齢者の逸失利益に関してさらに詳しく
一概に「無職だからという理由で逸失利益がもらえない」というわけではありません。
たとえば、学生・主婦・就職内定者・求職中だった人などは、将来的に収入を得る蓋然性(可能性)があれば、逸失利益が認められることがあります。家事従事者も「無償で労働している」と評価されるため、労働能力が失われれば逸失利益が認められる対象です。
ただし、高齢者や長いあいだ無職で就労の意思・能力が認められない場合などは、逸失利益が否定されることもあるため、個別事情の主張が重要です。
無職だったからといって諦めず、就労可能性を具体的に示すことで、請求できる可能性は十分にあります。
お気持ちはもっともですが、逸失利益は単純に「収入が減ったかどうか」ではなく、実際に「労働能力が失われたかどうか」で判断されます。
たとえば、事故後も仕事を休まず、周囲に助けてもらいながら働き続けた結果、収入が維持されている場合でも、医学的に労働能力が低下していると認められれば、逸失利益は請求可能です。
一方で、実収入が減っていても、後遺障害等級が認定されず、労働能力の喪失が証明できない場合、逸失利益は認められません。
したがって、逸失利益の請求において重要なのは、収入の有無だけでなく、後遺症による就労制限の程度を医証などで裏付けることです。努力して働き続けていること自体が不利に評価されるものではなく、証拠の整備や主張の工夫が重要といえます。
減収したと嘘をついてもバレるので、絶対にやめてください。
逸失利益の算定では、源泉徴収票・確定申告書・給与明細・課税証明書などの客観的な資料が必須とされ、虚偽申告はすぐに発覚します。
仮に虚偽が発覚すれば、逸失利益の請求自体が否定されるだけでなく、信用失墜により慰謝料や他の賠償額も下がる恐れがあります。最悪の場合は、詐欺罪に問われる可能性がある行為です。
逸失利益を正当に得るためには、実際の症状や生活の不便さ、医療記録をもとに誠実に立証することが最も有効な方法です。
交通事故における逸失利益について、その概念から請求できる条件、もらえない原因と対処法まで詳しく解説しました。
逸失利益を損害賠償請求するには、複雑で専門的な知識が必要であることがおわかりいただけたでしょう。特に、以下のような場合に陥っているのであれば、弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に相談すれば、交通事故の被害者が適切な損害賠償額を獲得できるようアドバイスをもらえます。
多くの弁護士は無料相談を行っています。まずは、気軽に無料相談の利用からはじめてみましょう。
アトム法律事務所は、弁護士による無料相談を実施しています。無料相談を希望される場合、まずは以下よりお問い合わせください。

問い合わせ窓口は24時間いつでもつながります。
交通事故の被害に遭われた方は、本記事の内容を参考に適切な対応を取り、正当な補償を受けられるよう行動しましょう。不安な点や疑問点がある場合は、早めに弁護士にご相談ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。

