専業主婦の離婚で知っておくべきこと|専業主婦の離婚準備を解説
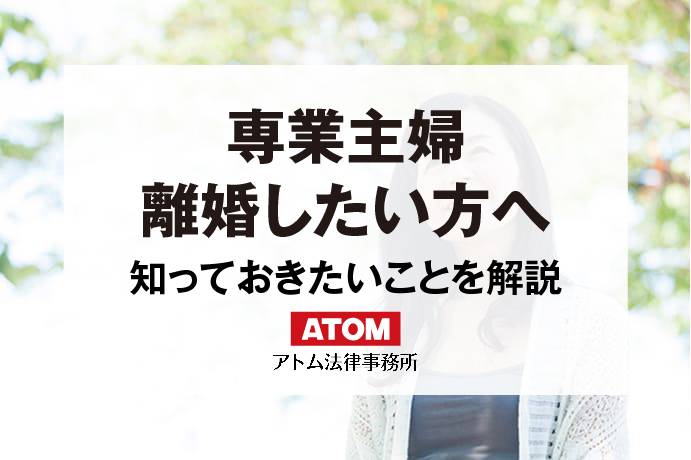
「これまで長く専業主婦をしていたが離婚したい。離婚後の生活はどうなるのか」
「専業主婦の離婚準備を知りたい」
これまで長く専業主婦をしていた方が離婚するという場合、離婚後に仕事や住まいを見つけることが難しくなってしまうリスクがあります。
離婚後のお金の問題についても不安に思うことがあるでしょうし、子どもがいるという場合はなおさらでしょう。
この記事では、離婚したい専業主婦の方に向け、やっておくべきことや知っておくべきことをわかりやすく解説します。
離婚したい専業主婦の方の準備
離婚理由を明確にする
専業主婦の離婚準備として、離婚の理由を明確にしておくということが挙げられます。
とくに、裁判で離婚が認められるためには、以下の5つの法定離婚事由のうち、どれかが必要になります。
法定離婚事由
- 不貞行為
- 悪意の遺棄.
- 3年以上の生死不明
- 回復見込みのない強度の精神病
- 婚姻を継続し難い重大な事由
当事者間の話し合いで離婚を決める協議離婚の場合は、双方が合意すればどのような理由でも離婚することができます。ただし、裁判では上記のような法定離婚事由が必要です。
5つの法定離婚事由についてより詳しく知りたいという方は、『離婚できる理由とは?|5つの法定離婚事由を解説』をご覧ください。
離婚原因を示す証拠を集める
専業主婦の離婚準備として、離婚原因を示すような証拠を集めておきましょう。
離婚原因をつくった側に対して、離婚慰謝料や慰謝料的財産分与を支払うよう請求できます。
ただし、裁判離婚が認められるには、民法が定める離婚原因が必要です。そのため、裁判の中で証拠を提出して、離婚原因の存在を主張立証しなければなりません。
また、不法行為を裏付ける強い証拠があるほど、慰謝料額は上がる可能性があります。離婚や慰謝料請求を認めさせるためにも、証拠を集めておくようにしましょう。
以下は、離婚原因を示すのに有効な証拠を簡単にまとめた表になります。
| 離婚原因 | 有効な証拠 |
|---|---|
| 不貞行為 | 配偶者と不倫相手が肉体関係を持ったことを示すメール など |
| DV・モラハラ | 録音や録画、詳細に記した日記 など |
より詳しく離婚の証拠について知りたいという方は、『離婚に必要な証拠|証拠集めの注意点と慰謝料請求のポイント』をご覧ください。
夫婦の財産を把握しておく
専業主婦の方の離婚準備として、離婚をする前に、夫婦で築いた財産を整理しておくということが重要になります。
夫婦が離婚をするときには、財産分与(婚姻期間中に2人が築いた財産を公平に分け合うこと)をすることになります。
「専業主婦なのに財産分与は受け取れるのか」と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、専業主婦の方も、夫婦の財産形成に貢献したといえ、財産分与を受けられます。
財産分与の対象は、土地や建物といった不動産、結婚生活でためた貯金など、婚姻中に夫婦で築いた共有財産です。
共有財産については、『夫婦の共有財産|離婚時に財産分与の対象になるもの・ならないもの』をご覧ください。
子どもがいる場合は親権・面会交流について考える
子どもがいるという場合は、どちらが親権者になるのかについて考えておきましょう。
夫婦の話し合いで決まらなかった場合は、裁判所の調停や離婚訴訟で親権者を決めることになります。
調停や訴訟では、これまで主に監護養育を担ってきた者が親権者とされる可能性が高いです。その他にも、現在の監護の態勢、育児を支援してくれる親族の有無、父母の就労状況等を総合的に判断し、親権者が決められます。
専業主婦の場合、「自分に収入がないために親権者になれないのではないか」と不安に感じる方が少なくありません。
しかし、離婚後は養育費の支払が見込まれるため、収入がないからと言ってそれだけで親権者の判断で不利になることはありませんのでご安心ください。
関連記事
また、離婚して自分が子どもを監護したいと考えている場合、相手と子どもとの面会交流をどうするかという点も想定しておく必要があります。
面会交流とは、離婚後に子どもと非監護親が面会することをいいます。
子どもへの虐待がある等例外的な場合を除き、継続的な面会交流は、子どもの成長にとって重要です。
感情的に受け入れるのが難しいケースも多いと思いますが、子どもの福祉につながるよう冷静に考えてみましょう。
なお、面会交流について当事者で合意できない場合は、家庭裁判所での調停・審判等で決めることになります。
関連記事
離婚後の住居を検討する
離婚後の住居についても検討しておきましょう。
「離婚しても子どもを転校させたくない」といった理由から、離婚後も同じ家に住み続けたいと考える方は多いです。
持ち家が誰の名義なのか、住宅ローンの残額はいくらかなどによって、解決策は様々ですので、ぜひ弁護士などの外部の相談窓口を利用することをおすすめします。
「家を出て新しく賃貸に住む」「実家に帰る」といった選択肢もあります。子どもがいるという場合は、子どもの学区や通学に配慮して家を探してみることも重要です。
関連記事
・離婚後も住宅ローンのある家に妻が住む5つの方法とは?注意点も解説!
・離婚したら賃貸契約はどうなる?そのまま住み続けられるか解説
離婚後の生活費を計算する|ひとり親家庭の相場は約23万円
専業主婦の離婚準備として、離婚後の生活費を計算しておくことが重要です。
以下は女性の一人暮らしとシングルマザーの家庭における、1か月の生活費の平均を示したものになります。
| 生活費(円) | |
|---|---|
| 子どもが18歳未満の世帯 | 232,079 |
| 34歳以下の一人暮らし女性 | 172,242 |
| 35歳〜59歳の一人暮らし女性 | 182,527 |
| 60歳~の一人暮らし女性 | 151,414 |
一人暮らしの場合はおよそ17万円、小さな子どもをもつシングルマザーの場合はおよそ23万円が生活費の平均となっています。
離婚前に相場を確認して、離婚後の生活をイメージしておくことが大切です。
離婚後の生活の収入源を準備する
専業主婦の離婚準備として、離婚後の生活のために、資金の準備や収入源の確認をしておきましょう。
とくに専業主婦の方は、外で働くことに長期ブランクがあるため、仕事探しが難しいかもしれません。50代、60代からの熟年離婚の場合は、深刻な問題といえるでしょう。
そのため、財産分与や慰謝料、子どもが幼い場合は養育費など、金銭面での離婚条件について、しっかりと取り決めておくようにしましょう。
離婚条件については、のちほど説明していますのであわせてご覧ください。
公的支援を調べる
専業主婦の方が離婚する場合は、公的支援を調べておくことも重要です。
経済的に困窮してしまうリスクがありますし、子どもがいる場合はなおさらです。離婚後に受けられる公的支援として、以下のようなものが挙げられます。
離婚したら受けられる公的支援
- 児童手当
- 児童扶養手当(母子手当)
- 児童育成手当
- 特別児童扶養手当
- 障害児福祉手当
- 就学援助
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金
- 生活福祉資金貸付制度
- 女性福祉資金貸付制度
- ひとり親家庭の医療費助成
- 生活保護
- 養育費に関する公正証書等作成支援 など
よりくわしく離婚後にもらえるお金や公的支援について知りたい方は、『離婚したらもらえるお金は?離婚補助金はある?手当や公的支援を解説』や『離婚後に生活保護は受給できる?金額シミュレーションと申請手続き』をご覧ください。
専業主婦の離婚で請求できるお金
専業主婦でも財産分与できる
専業主婦の方でも財産分与を受けられるということを忘れてはいけません。
財産分与とは、離婚に際し、夫婦が婚姻期間中に築いた夫婦共有財産を分配する制度です。
夫婦が話し合いで財産分与の割合を決めた場合は、その割合に従います。話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で調停や裁判等を通じて財産分与の割合を決めます。
実務では、財産分与の割合は原則として2分の1としています(2分の1ルール)。たとえ専業主婦であったとしても2分の1の割合で財産分与を受けることができます。
夫婦が共働きであるか、一方が専業主婦であるかに関係なく、夫婦が協力し合ったからこそ、夫婦共有財産が築けたことに変わりはないからです。
ただし、配偶者が特別な能力や資格によって多額の収入を得ている(夫が医師や経営者、スポーツ選手である)場合、2分の1ルールが適用されず、専業主婦の財産分与の割合が小さくなることがあります。
たとえば、夫が医師で、妻が専業主婦をしている事案では、夫婦の共有財産(総額約1億円)について、夫:妻=6:4で財産分割をした事例があります(大阪高判決H26.3.13)。
また、財産分与は、離婚の時から2年経過すると請求できなくなります。
「相手と話し合うのが嫌なので、とりあえず離婚して財産分与は後で考えよう」という方も少なくありませんが、時効について忘れないよう注意が必要です。
特に専業主婦にとって、財産分与は離婚後の生活をスムーズに始めるために非常に重要です。当事者での話し合いが難しければ、早めに弁護士に相談するよう強くおすすめします。
専業主婦の方の財産分与については、『専業主婦も離婚で財産分与は可能!熟年離婚は1000万が相場?』もあわせてご覧ください。
慰謝料を請求する
専業主婦の方が離婚する場合、配偶者側に離婚原因があるときは、離婚慰謝料をきちんと請求するようにしましょう。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償を意味します。
離婚の場合、離婚原因を作った側に慰謝料の支払義務があります。例えば、相手の不貞行為やDVが原因で離婚に至った場合に慰謝料を請求することができます。
以下の表は、離婚慰謝料の相場を簡単にまとめたものになります。
| 離婚理由 | 慰謝料の相場 |
|---|---|
| 不貞行為 | 100万~500万円 |
| 悪意の遺棄 | 50~300万円 |
| DV | 50~500万円 |
| モラハラ | 50~300万円 |
なお、離婚成立後3年経つと、慰謝料請求権は時効で消滅するので注意しましょう。
ちなみに、離婚の慰謝料には、離婚に至ったことについての「離婚自体慰謝料」と、離婚原因となった不法行為についての「離婚原因慰謝料」の2つの側面があります。実務では、両方を合わせて請求するケースが多いです。
とくに専業主婦の方は、離婚後に経済的に困窮してしまうリスクが大きいことは否めません。きちんと慰謝料を請求して、離婚後の新しい生活をより良いものにしていきましょう。
関連記事
・離婚慰謝料の相場は?慰謝料がもらえるケース・種類・条件を弁護士が解説
養育費を請求する
専業主婦の方が離婚し、子どもを引き取るという場合は、監護していない親(ここでは夫)に対し、養育費を請求できます。
養育費も夫婦の合意で定めます。合意できなければ、家庭裁判所の調停や審判で決めます。実務では、養育費の金額は自分と配偶者の収入や子供の数をもとに、「改定標準算定表」に従って決められます。
専業主婦で子どもが幼く働くことができない場合は、収入は0円として算定されます。
ただし、子どもが大きくなった場合は、たとえ専業主婦であっても、働いていれば得られるであろう収入をもとに養育費を算定します。
具体的には、パートタイム労働者の平均収入である年120万円程度の収入があるものとして改定標準算定表にあてはめます。
以下は、離婚後にひとり親家庭が受け取っている養育費の平均額をまとめたものになります。
養育費の1世帯平均月額
| 子どもの数 | 母子家庭 | 子家庭 |
|---|---|---|
| 1人 | 40,468円 | 22,857円 |
| 2人 | 57,954円 | 28,777円 |
| 3人 | 87,300円 | 37,161円 |
| 4人 | 70,503円 | – |
| 5人 | 54,191円 | – |
| 不詳 | 39,062円 | 10,000円 |
| 平均 | 50,485円 | 26,992円 |
厚生労働省が実施した「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、養育費の平均金額は母子家庭で50,485円、父子家庭で26,992円でした。
小さな子どもをもつシングルマザーの場合、生活費の平均がおよそ23万円であることを考えると、生活費の20数%ほどを養育費が占めることになります。
このことからも、専業主婦の方が離婚し、ひとり親になるという場合は、養育費をきちんと相手に請求することが重要であるとわかります。
関連記事
年金分割
とくに50代、60代で熟年離婚を考えている専業主婦の方は、年金分割も忘れずに請求しましょう。
年金分割とは、離婚した場合、婚姻期間中に納付した厚生年金の保険料の納付記録を分割する制度です。
専業主婦の場合、国民年金の第3号被保険者(専業主婦やパートなど扶養の範囲内で働く人)となり、年金額は少なくなってしまいます。
しかし、夫の厚生年金の記録を分けてもらうことで、専業主婦であっても将来受け取れる年金が増え、離婚後の生活の安定を確保することができます。
年金分割については、合意分割と3号分割の2種類があります。以下は年金分割の2つの種類を簡単に比較した表になります。
| 合意分割 | 分割 | |
|---|---|---|
| 専業主婦はできる? | できる | できる |
| いつまでの年金が対象? | 2008年4月1日以前 | 2008年4月1日以降 |
| 夫の合意は必要? | 必要 | 必要ない |
| 分ける割合 | 上限2分の1 | 2分の1 |
合意分割は、夫婦の合意によって年金分割をする方法です。
年金の按分割合(年金をどれだけの割合で分けるか)は自由に決めることができますが、上限は2分の1となります。
合意がまとまらない場合は裁判で決めますが、大半のケースで按分割合は2分の1と決められます。
3号分割は、夫の合意がなくても、請求手続きをおこなえば、分割できるという制度です。
2008年4月1日以降に、夫婦の一方が第3号被保険者であった婚姻期間について、請求をすれば、夫の合意を得なくても自動的に、2分の1の按分割合で年金分割がなされます。
なお、合意分割も3号分割も、離婚時から2年以内に年金事務所を通じた年金分割の請求手続きが必要です。また、年金分割の対象となるのは厚生年金のみです。配偶者が自営業しか営んでこなかった場合は年金分割の対象外となる点にも留意してください。
合意分割と3号分割については、併用することが可能です。たとえば、2000年4月から2024年3月まで婚姻していた場合は、2008年4月から2024年3月までの間は、3号分割の期間となります。2000年4月から2008年3月30日までの間は、合意分割の期間となりますので、上限2分の1で厚生年金を分割することになります。
別々に手続きをする必要はなく、合意分割の請求をすれば、同時に3号分割の請求もしたとみなされます。
とくに長年専業主婦をしており、熟年離婚ということになると年金分割は非常に重要なポイントになります。必ず忘れずに請求するようにしましょう。
関連記事
別居中は婚姻費用を請求する
離婚したいと考えている専業主婦の方は、別居するとき、夫に婚姻費用を請求するのを忘れないようにしましょう。
婚姻費用とは、別居期間中の、別居期間中の生活費のことをいいます。
婚姻費用の金額は、養育費の場合と同様に、「改定標準算定表」に従って決められます。
婚姻費用の支払義務は、支払い請求したときから生じるのが原則です。
婚姻費用の請求方法としては、メールや内容証明郵便等などの方法があり、これらは請求をした証拠となります。
別居をしたら、離婚後の生活費の目減りを防ぐためにも、できる限り早めに婚姻費用の請求をしましょう。
相手が婚姻費用の支払に応じない場合、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
関連記事
・婚姻費用の相場は月10~15万円?別居・離婚調停の生活費請求を解説
専業主婦の離婚を進める方法
弁護士に依頼する場合は離婚にかかる費用をためる
「弁護士に依頼して離婚したい」と考えている専業主婦の方は、離婚にかかる費用を貯めておきましょう。
協議離婚をする場合、当事者がすべきことは離婚届の記入のみになるので、離婚にかかる費用は基本0円です。
一方、離婚調停をおこしたり、裁判離婚をしたりする場合は、裁判所の利用手数料がかかります。管轄となる裁判所により手数料は異なるとされ、数千円から数万円が相場です。
また、離婚を進めるために、弁護士に依頼する場合は、弁護士費用がかかります。弁護士費用の相場は、以下のようになります。
| 離婚の種類 | 弁護士費用の相場 |
|---|---|
| 協議離婚 | 40~80万円 |
| 調停離婚 | 50~100万円 |
| 裁判離婚 | 70~120万円 |
弁護士に依頼するという場合、弁護士費用がかかってしまうというデメリットはあります。しかし、「慰謝料や養育費などがどれくらいとれるか」といったことを計算してくれるほか、調停や裁判でも心強い味方になってくれます。
有利に離婚したいという専業主婦の方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
関連記事
・離婚にかかる費用の相場は?平均いくらあれば足りるかシミュレーション
冷静に離婚を切り出す
離婚したいと思っても、相手への離婚の切り出し方は悩ましいところです。
離婚の第一歩は、まずは当事者の話し合いです。事前に伝えたいことを整理して、冷静に離婚を切り出しましょう。
離婚の話題は、夫婦がお互いに冷静さを欠きやすい話題です。離婚したい理由を簡潔に述べ、感情的にならないよう心がける必要があります。
相手方が怒りをぶつけてきたり、罵倒してきたりした場合も、冷静に受け答えをすべきでしょう。
当事者での話し合いが困難な場合は、弁護士へ相談したり、離婚調停の利用を検討したりしてみてください。
関連記事
別居を検討してみる
自分は離婚したいけれど、相手が離婚に応じない場合、別居を検討するのも一つです。
別居のタイミングは様々ですが、別居をしてから離婚調停を申し立てるケースが多いです。
また、離婚事由が弱く、すぐに離婚するのが難しいと見込まれる場合、ある程度の期間別居を続けるのも選択肢の一つです。
なぜなら、実務上、別居期間が長くなるほど婚姻関係が破綻していると認められやすくなるからです。
離婚実務では、3年~5年以上の別居期間を置くと、離婚原因として認められ、裁判離婚の可能性がでてくるといわれています。
もし別居するということになった場合は、婚姻費用を忘れずに請求するようにしましょう。
関連記事
・家庭内別居は離婚の理由になる?財産分与や婚姻費用はどうなる?
離婚が合意できたら離婚届・公正証書を作成する
当事者間で離婚が合意できた場合は、離婚届を記入・提出し、受理されれば、協議離婚が成立します。
協議離婚のおおまかな流れは、以下のようになります。
協議離婚のおおまかな流れ
- 離婚届を準備する
- 離婚届への記入
- 提出書類の準備
- 離婚届の提出
より詳しく協議離婚の流れについて知りたい方は、『協議離婚とは?弁護士に依頼する必要はある?弁護士費用や選び方は?』をご覧ください。
協議離婚をする場合は、離婚届だけでなく、離婚協議書などの書類を作成し、親権や養育費等の合意内容をまとめておきましょう。
協議して合意した離婚条件を、後日、相手方に踏み倒されるケースも少なくありません。そのため、万一の場合に備えて、合意内容を目に見えるかたちで証拠化しておく必要があるのです。
まとめておいた離婚協議書などについては、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成して、公正証書の形に残しておくことを強くおすすめします。
強制執行認諾文言付き公正証書があれば、相手方の不払いがあったときに、強制執行(給料や口座の差し押さえなど)が可能です。
専業主婦の方にとって、取り決めた離婚条件は新しく生活をスタートさせるうえで非常に重要なものになります。取り決めた条件を相手に踏み倒されないようにするためにも、必ず公正証書の形で残しておきましょう。
関連記事
・離婚の公正証書の作り方・費用・必要書類【2025年10月法改正】
離婚が合意できない場合は裁判所を利用する
当事者間で離婚が合意できない場合、離婚調停や離婚訴訟を利用することになります。
離婚調停は、裁判官と2名以上の調停委員からなる調停委員会が関与して、離婚に向けた当事者の合意を目指す手続きです。
離婚調停は、申立人と相手方の双方が裁判所に出席して、話し合いを行います。
離婚調停は、当事者のみでも対応可能ですが、親権や養育費を決めるに当たっては、法的な専門知識が不可欠です。
したがって、離婚調停は、弁護士が関与した方が、有利な離婚条件で離婚できる可能性が高まります。
関連記事
・離婚調停中にやってはいけないこと&不利な発言は?対処法も解説!
離婚訴訟は、離婚調停が不成立の場合に提起することになります。
訴訟では、準備書面や証拠の提出が必要になるため、ご自分で対応するのは困難です。
相手方が離婚に応じないと見込まれる場合は、ぜひ早期の段階から弁護士に相談し、離婚訴訟を見越した準備をしておくことをおすすめします。
関連記事
・離婚するときに弁護士は必要?弁護士なしでは難しいケースを解説
離婚後の生活費は元夫に払うよう強制できないため注意
「離婚後の生活費を元夫に請求できないのか」と考える専業主婦の方もいるかもしれません。
離婚後の生活費を相手に支払うよう、法的に強制することはできません。ただし、双方の同意があれば、扶養的財産分与といった形で生活費を受け取ることは可能です。
扶養的財産分与とは、離婚後に生活が困窮する配偶者を扶養する目的の財産分与です。
離婚後の生活費について詳しく知りたいという方は、『離婚後の生活費はもらえる?支払い義務の解説と請求のための交渉術』をご覧ください。
離婚したい専業主婦の方は弁護士に相談!
専業主婦の方が離婚をする場合は、離婚後の経済的なリスクを考え、財産分与や年金分割、養育費などについて、よく話し合ったうえで後悔のないような選択をすることが重要です。
もし離婚をしたいと考えている専業主婦の方は、弁護士に相談することを強くおすすめします。
弁護士に相談すれば、財産分与や養育費などといった離婚条件についてアドバイスがもらえます。慰謝料が発生するようであれば、自分の代理として相手と交渉してもらえるというメリットもあります。
離婚して新しくスタートを切るうえで、心強い味方になってくれるはずです。
無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
