離婚時に年金分割をしないとどうなる?知っておきたいリスクと対処法
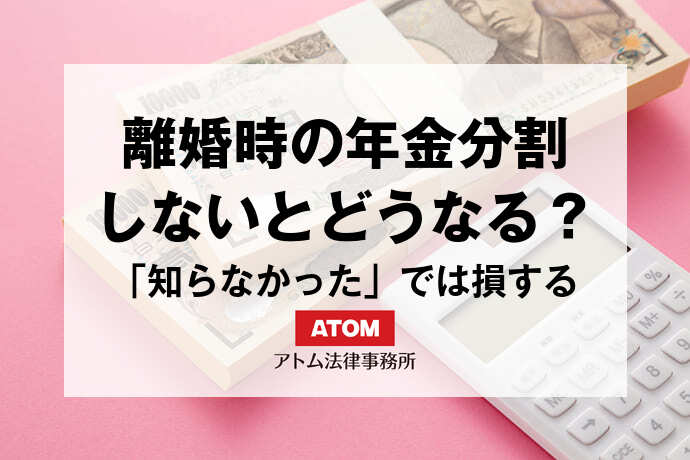
離婚時に年金分割をしないと、将来の年金受給額に大きな差が生まれることをご存知でしょうか。
特に婚姻中に収入格差があった場合、年金分割をしないことで月に数万円、生涯にわたって数百万円もの損失になる可能性があります。
また、年金分割の手続きには離婚後2年間という期限があり、知らないまま過ごしてしまうと二度と手続きできなくなってしまいます。
この記事では、離婚時に年金分割をしないとどうなるのか、具体的な受給額の違いや生活への影響を詳しく解説します。年金分割の基礎知識、手続き方法、離婚後の対応策についても分かりやすくご説明するので、将来の生活設計にお役立てください。
目次
離婚時の年金分割とは?
年金分割の基礎知識
年金分割とは、離婚の際に、結婚期間中に納めた厚生年金の保険料を分割する制度です。
離婚時に年金分割をおこなうことで、配偶者が納付した年金保険料の一部を自分の納付記録に移すことができ、将来受け取る年金額を増やすことが可能です。特に婚姻中に収入の差が大きかった夫婦は、離婚後の年金額が不公平になるため、年金分割の重要性が高いといえます。
関連記事
合意分割・3号分割の違い
合意分割とは、夫婦の合意に基づき、婚姻期間中の厚生年金を分割する制度です。分割割合は最大2分の1までで、双方の合意で割合を定めます。
3号分割とは、国民年金の第3号被保険者が、平成20年4月1日以降に第3号被保険者であった期間について、相手の合意がなくても厚生年金保険料を一律2分の1の割合で分割できる制度です。主に専業主婦・主夫などの被扶養配偶者が対象になります。3号分割の対象となるのは平成20年4月1日以降の年金であるため、それ以前の分について分割したい場合は合意分割の手続きが必要です。
合意分割の手続きをおこなった場合、同時に3号分割の手続きもおこなったとみなされます。
年金分割の手続き
年金分割の手続きの大まかな流れは以下の通りです。
年金分割の手続きの流れ
- 年金分割のための情報通知書を取得する
- (合意分割のみ)話し合って按分割合を決め、合意書を作成する
- 標準報酬改定請求書を年金事務所に提出する
必要な書類を揃えて年金事務所に提出するのが基本の流れですが、合意分割をおこなう際は夫婦が年金分割に合意したことを証明する文書を作成して提出する必要があります。合意ができない場合は調停や裁判で争うことになります。
なお、年金分割の手続きは離婚成立後でなければできないため、先に離婚届を提出する必要があります。
離婚時に年金分割をしないとどうなる?
年金分割しないと〇万円の損!増加額の相場は?
令和5年度の統計によれば、離婚時に合意分割をおこなった場合、分割を受けた側の年金月額は平均33,102円増加しています。また、3号分割のみをおこなった場合、年金月額は平均7,779円増加しています。
令和5年度 年金分割前後の平均年金月額
| 分割前 | 分割後 | |
|---|---|---|
| 合意分割 | 57,979円 | 91,081円(+33,102円) |
| 3号分割のみ | 45,420円 | 53,199円(+7,779円) |
※厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況(参考資料6)」より作成
合意分割をおこなって月額3万3千円ほど年金受給額が増加した場合、1年間で約40万円、5年間で約199万円、10年間で約400万円と、その差は一目瞭然です。
3号分割のみをおこなった場合でも、1年間で約9万円、5年間で約46万円、10年間で約93万円と、期間が長くなれば受け取れる額の差はかなり大きなものになります。
年金分割で分割の対象になるのは、婚姻中に厚生年金に加入していた期間に納めた年金保険料です。そのため、婚姻期間が長い夫婦ほど分割の対象となる年金保険料の額も大きくなります。
期限が切れると年金分割できない
年金分割の手続きができるのは、離婚をした日の翌日から2年間に限られています。また、2年以内に配偶者が死亡した場合は、死亡から1か月以内でなければ年金分割の請求ができません。
そのため、年金分割ができることを知らないまま離婚してしまい、気づいたときには請求期限が切れてしまっていたというケースも起こり得ます。
年金分割をすべきケースとは?
年金分割をするメリットがあるのは、「自身に公的年金の加入期間が10年以上あり、配偶者の方が多く厚生年金保険料を納めている」ケースです。
公的年金(国民年金または厚生年金)の加入期間が10年未満の方はそもそも老齢年金の受給資格がないため、年金分割をおこなっても年金を受け取ることができません。
自分の方が多く年金を納めている方は、年金分割の手続きをおこなうとかえって受け取れる年金が減ってしまうため注意が必要です。
なお、共働きでも相手の方が多くの保険料を納めていた場合は年金分割をおこなうメリットがあります。
年金分割をしなかった場合の生活シミュレーション
60代単身女性の生活費は〇万円!
2023年の家計調査によれば、65歳以上の単身女性の1か月の生活費は148,971円です。
これに対し、前記の統計表の通り、合意分割をしなかった場合の平均年金月額は57,979円です。
年金分割をしなかった場合、年金だけでは生活費が約9万円不足することになります。
不足する分は、貯蓄を切り崩したり、自分で働いたり、親族から援助を受けたりしてまかなう必要があるでしょう。また、離婚時に適正な財産分与を受け取っておくことも役立ちます。
関連記事
・熟年離婚を考える専業主婦へ|50代・60代から自由を手にするために今できる準備とは?
・熟年離婚の財産分与|相場は?持ち家・退職金・年金の分け方と対策を弁護士が解説
年金分割の見込み額を知る方法
年金分割をおこなったらどの程度年金が増えるのか知りたい場合は、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得する必要があります。
年金分割のための情報通知書は、夫婦の双方または一方が年金分割のための情報提供請求書を年金事務所に提出することで手に入ります。離婚前でも離婚後でも取得可能です。
参考
年金分割をしなかったけど、あとからしたくなった場合は?
離婚後に年金分割をする方法
離婚した後で年金分割をしたくなった場合、まずは離婚から2年(2年以内に配偶者が死亡した場合は死亡から1か月)の請求期限が過ぎていないか確認してください。2年が過ぎている場合は請求手続きができません。
3号分割には相手の同意が必要ないため、離婚後に自分だけで年金事務所へ行って手続きができます。
合意分割をしたい場合は、元配偶者と按分割合を話し合い、合意を証明する書面を作成・提出する必要があります。
離婚が成立した後に話し合いをおこなうのは難しいケースも多いでしょう。その場合は、家庭裁判所に年金分割の割合を定める審判・調停を申し立てて、裁判所の調停委員会の仲裁のもとで按分割合を決めることができます。
なお、離婚から2年以内に調停や審判が申し立てられていた場合は、調停成立または審判が確定した時点で離婚から2年間が経っていても、確定してから6か月の間は請求期限が延長されます。
そのため、年金分割の合意が成立しないうちに2年が経過してしまいそうな場合は、まず調停か審判を申し立てるとよいでしょう。
参考
年金分割をしないという合意は有効?
離婚時に「年金分割をしない」という合意をしていた場合は、あとから年金分割をしたいと思ってもできないのでしょうか。
この点、「年金分割をしない」という合意は、公序良俗に反するなどの特別の事情がない限り有効だとされています。離婚後に年金分割の審判を申し立てた際に、年金分割をしない合意は有効であるとして裁判所が申し立てを却下したケースがあります(静岡家浜松支審 平成20年6月16日)。
もっとも、3号分割については相手の同意がなくても手続きができるため、たとえおこなわない合意があったとしても手続きを防止する手段がありません。したがって、年金分割をしないという合意があっても3号分割は可能です。
まとめ|年金分割をしないとどうなる?
離婚時に年金分割をしないと、将来の年金受給額に大きな差が生まれ、老後の生活に深刻な影響を与える可能性があります。
年金分割の手続きには離婚後2年間という厳格な期限があり、これを過ぎると一切請求できなくなってしまいます。
離婚を検討している方や既に離婚している方は、この制度を知らずに損をしないよう、早めに年金事務所で情報通知書を取得し、適切な手続きをおこなうことが重要です。配偶者と年金分割の話し合いをすることが不安な方は、弁護士に交渉を依頼することも可能です。まずはお近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
