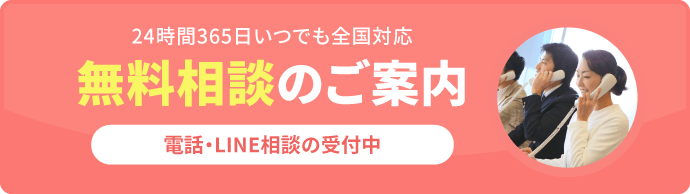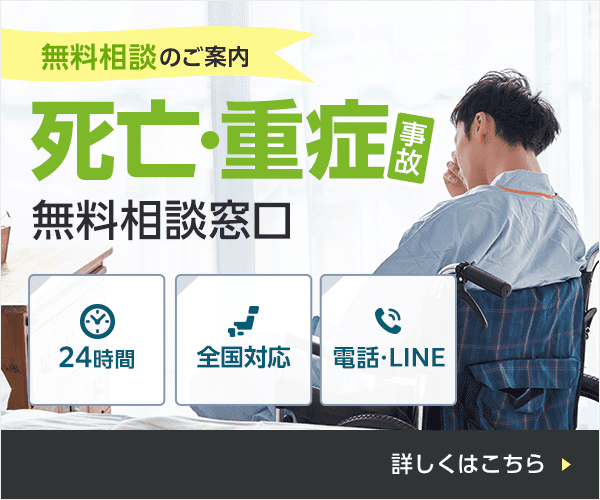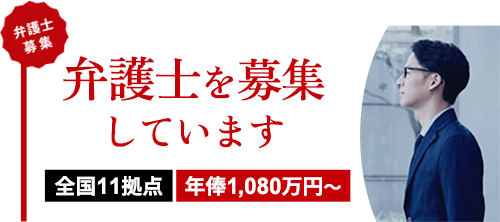介護施設とのトラブルの原因とは?事故事例ごとの賠償責任のポイント
更新日:
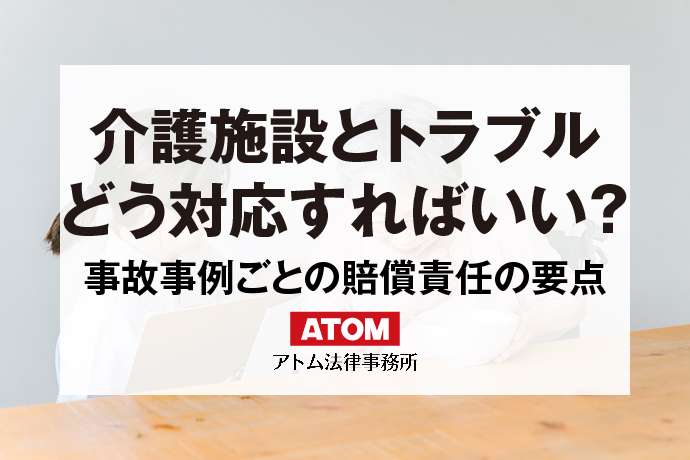
特別養護老人ホーム(特養)や民間の介護付き有料老人ホーム、グループホームなどの介護施設では、日々さまざまな介護トラブルが発生しています。
介護トラブルには、入居者同士の人間関係のトラブルなどもありますが、代表的なトラブルは利用者と介護施設とのトラブルになります。
利用者と介護施設との間には強制退去問題、金銭問題などさまざまなトラブルがつきものです。本記事においては、介護サービス中に利用者が怪我をしたり、症状が悪化したりする代表的な介護事故についてのトラブルを解説していきます。
介護事故が介護施設とのトラブルにまで発展するのには原因があり、介護施設側に責任があるとして、利用者側が介護施設へ損害賠償を求めるべきケースもあるのです。
この記事では、介護事故で介護施設とのトラブルになる原因のほか、事故事例ごとの介護施設側の責任検討における重要なポイント、介護施設とのトラブルで弁護士ニーズの高いケースを紹介します。
介護施設とのトラブルになる原因は?
介護サービスの内容が明確でない
介護事故は、発生が防げないようなケースもありますが、介護施設側は、事故防止に対する姿勢を示すため、介護契約書に「見守りを強化する」「気配りを徹底する」といった表現を使うことが多いです。
もっとも、上記のような表現は、具体的な介護サービスの内容が明確ではないため、利用者側と施設側との認識に食い違いが生じ、トラブルに発展する原因となる可能性があります。
利用者や家族は「見守りや気配りが不十分だから事故が起きたのだ」と責任を追及し、施設側は反論として「見守りや気配りはしっかり行っていた」として責任を否定するケースがあるのです。
介護の目的
介護の目的は、被介護者が能力に応じ自立した日常生活を営めるよう支援することにあります。
そのため、過剰な介護サービスの提供は、かえって被介護者の自立した日常生活の妨げとなる可能性があるのです。
たとえば、過剰な付き添い歩行介助をしていると、被介護者が自立歩行できなくなってしまう可能性がありますし、誤嚥を防ぐため、介護食をすべて柔らかいものにしていると、被介護者のそしゃくする力が弱まり、固形物が食べられなくなってしまう可能性があります。
上記の理由から、どこまで介護をすればいいのかが明確ではないことが、介護施設とのトラブルに発展する原因の一つと考えられます。
つまり、介護施設側が自立した日常生活を営めるように「利用者のできることは本人で行ってもらう」介護をしていたところ、介護事故が発生すると、利用者や家族から「介護スタッフが対応してくれないから事故が起きた」と思われ、介護トラブルに発展するケースがあるのです。
利用者にも事故発生の原因がある
介護事故は、利用者にも事故発生の原因があるケースが多いです。
たとえば、転倒の危険が高い利用者がスタッフも呼ばず、いきなり自分で立ち上がってそのまま転倒し骨折したようなケースです。
上記のケースの場合、施設側は「介護スタッフを呼んでくれていれば介助したのだから責任はない」と考え、家族は「利用者がいきなり自分で立ち上がることも想定してしっかり見守っておくべきだった」と考えて、介護トラブルに発展する可能性があります。
介護トラブルが発生したらどう対応すべき?
介護施設側に説明を求める
介護施設とのトラブルが発生した場合、まずそのトラブルが発生した経緯につき説明を求めるのが大切なポイントです。
先ほど解説したとおり、提供すべき介護サービスの内容やその介護サービスを提供していた理由の認識が利用者と介護施設側とで食い違っている可能性があるからです。
そして、その説明に納得いかないときには介護施設側に責任を問えるか検討すべきです。
介護施設の責任を慎重に検討する
介護施設は、利用者が危険な目にあわずに安全な環境で過ごせるよう注意を払う安全配慮義務を負っています。
安全配慮義務違反があるとして施設側に過失が認められた場合には、損害賠償請求が認められる可能性があるのです。
安全配慮義務違反とは、トラブルの発生を事前に予測できたのかや適切な回避措置をとったのかが検討されます。
安全配慮義務のポイント
- トラブルの発生を予測できたのか
- 適切な回避措置を取ったのか
いいかえれば、介護施設側がその責任を果たしてもなお事故が防げなかった場合には、介護施設側に責任追及することは難しいでしょう。
安全配慮義務が争点となった判例についても解説していますので、施設側への損害賠償請求を検討している方はあわせてお読みください。
関連記事
介護事故による介護施設や職員の法的責任|責任追及に役立つ法知識
誰を相手に損害賠償請求するかを決める
介護事故トラブルにおいては、多くの場合で介護施設への損害賠償請求になる見込みです。
介護トラブルが起こったとき、誰に責任があったのかを検討するときには、介護施設側や介護職員個人の責任を検討します。
しかし職員へ損害賠償請求するケースはめったにありません。個人の資力には限界がありますし、相当に悪質な行為をのぞいて介護施設側へに対する責任追及することが多いです。
介護施設とのトラブルでいったいどんな法的根拠にもとづいて請求するのかを整理しておくことは今後の話し合いにも役立ちますので、関連記事もあわせてお読みください。
関連記事
介護トラブルの事例
介護トラブルとして起こりやすい事故の事例を紹介します。
紹介する介護トラブル事例
- 見守りが不十分で怪我をする
- 転倒や転落などで骨折してしまう
- 寝たきりでひどい床ずれになった
- 入浴中に転倒、溺れる、ヒートショック
- 食事介助中に誤嚥してしまった
- 認知症による行動で事故にあう
- 薬の取り違えや飲み忘れなどの誤薬
- デイサービス利用での怪我
どういう着眼点があるのかを例示するので、介護施設から説明を受けている場合には、その説明内容と照らし合わせて検討してください。
見守りが不十分で怪我をする
介護施設には利用者の身体的・精神的状況に合わせた介護が求められており、見守りもその一つです。
もし介護中の事故で施設側と話し合う際には、次のような点に注目してみましょう。
- 介護計画書やカルテなどに「見守りが必要」との記載はなされていたか
- これまでに転倒はしていなかったのか(見守りの必要性は明らかであったか)
- 転倒防止に必要な設備を整えたか(手すり、滑り止め、照明など)
利用者には見守りが必要であるにもかかわらずその義務を怠って怪我をさせた場合には、施設側の責任を問える可能性があります。
関連記事では介護施設側が負う見守り義務のさらに詳細な解説や、見守り義務が争点となった損害賠償請求の判例を紹介しているので、あわせてお読みください。
関連記事
転倒や転落などで骨折してしまう
高齢者は骨がもろくなっていたり、身体をかばう動作を取るのが遅れたりして、転倒や転落により骨折してしまうことが多々あります。
ベッドから降りるときや車いすに移乗するときなど、高齢者にとっては日常の動作すら危険を伴う場合があるのです。
介護施設側は介護の知識やノウハウを生かして、そういったトラブルが起こらないように、適切なサポートが求められています。
次のような観点から介護施設側に求められる義務が適切に果たされていたのかを検討しましょう。
- なぜ転倒や転落事故が起こったのか
- 転倒や転落は防ぐことができなかったのか
- 転倒しないように適切に見守りをおこなったか
介護を必要とする高齢者には持病や既往症があることも多いです。そのため、介護施設で起こったトラブルと骨折の因果関係をはっきり示すことが重要です。
関連記事
介護事故で骨折した責任を施設側に問える?慰謝料相場と対応方法を解説
寝たきりでひどい床ずれになった
床ずれは、医療や介護の現場では褥瘡(じょくそう)といわれ、長時間同じ体勢を続けることで圧迫された箇所にできる創傷をさします。
褥瘡ができると感染症のリスクが高まり、身体全体が弱ってしまいます。寝たきりの場合には褥瘡のリスクが高く、安全な生活を送るための予防策が欠かせません。
- 褥瘡予防の体位交換はどのような頻度で行われていたか
- 万一に褥瘡の初期症状が見られた場合の対応は適切か
このように、介護施設において具体的にとられた対応から責任の所在がみえてくるでしょう。
関連記事
褥瘡で裁判は可能か裁判例から解説|損害賠償請求と義務違反の関係
入浴中に転倒、溺れる、ヒートショック
入浴も事故が起こる可能性が高く、トラブルのひとつになりやすい介護のひとつです。
浴室内やバスマットで足を滑らせて転倒してしまったり、浴槽内でバランスを崩して起き上がれずに溺れたり、温度差により血圧が急に下がるヒートショックが起こるリスクを十分に把握し、介護をする側が対策しなくてはなりません。
また複数名を入浴させているあいだに少し目を離したすきに溺れてしまう人もおられます。
- 入浴中には目を離さない
- 入浴介助は複数名で行う
- 浴室内や脱衣所の温度管理を行う
具体的にどのような対策が取られていたか説明をしてもらい、対策が適切で十分だったかを検討すべきです。
食事介助中に誤嚥してしまった
介護施設での食事介助は十分配慮して行われているものの、加齢に伴う嚥下能力の低下や判断力の低下により、誤嚥が起こる可能性はあります。
日ごろの観察から利用者の嚥下能力を正しく把握した対応が必要です。
- その人にとって飲み込みやすい食材や調理方法で対応していたか
- 口いっぱいに含むなどリスクの高い食べ方をさせないように見守っていたか
- 誤嚥が起こった時には食べ物を吐き出させたり、救急車を呼ぶなどの対応をしたか
食事介助時の誤嚥を防ぐための対策や、誤嚥事故発生時の対応について、施設側からの説明と共に介護記録などの資料提供も求めていきましょう。
関連記事
認知症による行動で事故にあう
認知機能の低下した利用者は、思わぬトラブルに巻き込まれたり、トラブルを引き起こしてしまったりする可能性も十分にあります。
介護施設側としては、利用者の認知症を把握して、トラブルが発生しないよう十分な対策をとらなくてはなりません。
たとえば、施設の出入り口が誰でも簡単に出入りできる状況になっていると、よく分からないまま施設外へ出ていってしまうこともあるでしょう。施設の出入り口のシステムを工夫する必要があります。
- 今回のトラブルについては施設に予測できたことなのか
- 施設側のトラブル予防策は適切であったか
「家族が認知症だったから仕方ない」とすぐに諦める必要はありません。介護施設としっかり話し合いをして、本当に避けられないものであったかを確かめてみましょう。
薬の取り違えや飲み忘れなどの誤薬
介護施設の利用者の中には持病のために服薬が欠かせない方も多くいます。ご自身で判断してきちんと服薬できる人もいれば、介護者のサポートが必要な人もいるでしょう。
他の人の薬を間違えて飲ませてしまったり、服薬量・服薬のタイミングを誤ってしまったり、服薬そのものを忘れてしまうなど誤薬事故もさまざまにありますが、ときに死亡事故につながる恐れもある重大なトラブルです。
- 薬を取り違えないように対策は取っていたのか
- 誤薬事故が発生したあとの対応は適切であったか
過去には似た名前の利用者の薬を取り違えてしまう重大な事例もあります。経緯をしっかりと説明してもらい、介護施設が安全配慮義務を全うしていたのかという観点から検討すべきです。
関連記事
デイサービス利用での怪我
デイサービスでは利用者向けのレクリエーションも盛んに行われているので、移動時の転倒事故が多いともいわれています。
また施設内での怪我のほかにも、デイサービス送迎時にトラブルに巻き込まれることもあり、送迎車への乗り降り・居宅内への移動中の転倒などもトラブルとしてあげられるでしょう。
- デイサービス利用中の事故を防ぐ対策は適切であったか
- 送迎時にはシートベルトや車いすの固定など安全面に配慮されていたか
- 送迎車から居宅内までの移動は送迎の一環であるのか
デイサービス利用におけるトラブルについても、そのトラブルの発生原因や対策次第では、デイサービス側に責任を求めることもできます。送迎の範囲については、まず契約書の確認をしてみてください。
介護トラブルのなかでも弁護士に相談したほうが良いケース
介護トラブルのなかには法的責任問題に発展しやすいケースや、弁護士を味方につけることで不当な扱いを避けるべきケースがあります。
ここからは弁護士に相談すべき介護トラブルのケースをみていきましょう。
死亡事故という重大ケース
死亡事故という重大な結果になった場合には、次のような事由から弁護士への相談・依頼をおすすめします。
弁護士へ相談・依頼すべき理由
- 介護施設側との交渉を一任できる
- これまでの事例・判例に沿った交渉ができる
- 損害賠償請求額の相場を教えてもらえる
大事な家族を突然のトラブルでうしなってしまい疲弊したところでの交渉はとても難しいことです。
相手との交渉、介護記録などの証拠の確認・収集を弁護士に任せて精神的・肉体的な負担から少しでも解放されるだけでなく、適切な損害賠償請求に近づくことができるでしょう。
後遺症が残ったケース
後遺症が残った場合は、完治した場合と比べて負った損害が高額です。そのため損害賠償請求額も高額になり、介護施設側との交渉も難航傾向にあります。
また「後遺症が残った」という事実だけでなく、「後遺障害等級の何級に相当する」という主張をすることがポイントです。
後遺障害等級とは?
後遺障害等級とは交通事故や労災などで後遺症が残った場合に認定を受けるものです。介護事故については特定の認定機関がないため、自らで認定基準に照らして何級相当であるかを主張しなくてはいけません。
弁護士であれば後遺障害等級で何級相当なのかという判断についてもアドバイス可能です。さらに弁護士に依頼することで、これまでの判例をふまえた適正な慰謝料額を目指した交渉を任せられます。
介護事故の慰謝料相場は、利用者の負った損害の程度によって様々です。たとえば後遺症が残った際には後遺障害等級に応じて110万円~2,800万円の慰謝料が相場になります。
関連記事では介護事故の慰謝料相場を判例とあわせて解説しているので、損害賠償請求を検討している方はあわせてお読みください。
関連記事
介護施設との話し合いが難航しているケース
介護トラブルの解決方法としては、いきなり裁判を起こすのではなく、施設との話し合いによる解決を目指すことが多いです。この話し合いによる解決を示談交渉といいます。
示談交渉とは?
当事者同士がお互いに一定の譲歩をしながら、裁判外の話し合いで解決を目指す方法のこと
しかし、なかには介護施設側と話し合いの場が持てなかったり、とうてい納得できない説明で終わられたりと利用者側にとって「話し合いがうまく進まない」と感じる場合があります。
弁護士に相談して対応を依頼すれば、弁護士は施設側との話し合いの代理人となって活動可能です。弁護士からの連絡であれば施設側も話し合いに応じる可能性が高まるでしょう。
施設側が弁護士を立ててくることも十分あります。法律の知識で不利にならない、対等な交渉をするために弁護士が役立つのです。
裁判を視野に入れているケース
介護トラブルの解決は、まず話し合いから始まることがほとんどです。しかし示談交渉が決裂した場合には、裁判所での調停を利用したり、民事裁判を起こすことも視野に入れなくてはなりません。
裁判となると手続きも複雑になりますし、証拠の収集や書類の確認・作成機会も増えたり、結論が出るまでに一定の期間を要します。
専門家である弁護士に任せればスムーズに進めることができますし、裁判対応にご家族が拘束される時間を減らし、日常生活への復帰も早まります。
介護事故裁判の争点は?訴訟準備から裁判進行の流れ!裁判事例も解説
介護施設とのトラブル相談窓口のご案内
介護施設とのトラブルが起こったときの相談窓口を見つけるポイントと、アトム法律事務所の相談窓口をご案内します。
介護施設とのトラブル相談先を見つけよう
介護施設とのトラブル相談先はトラブルの内容によって使い分けることをおすすめします。
たとえば高齢者に対する虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業などは地域包括支援センターへの相談も有用でしょう。
しかし、介護トラブルで負った損害を利用者やその家族の代わりに交渉してくれるのは、代理人となれる弁護士に限られます。よって、相談内容次第では弁護士への相談も検討すべきです。
相談先に連絡を取る際には、どんなことに困っていて、どんな対応を取りたいのかを明確に伝え、取り扱い可能な範囲なのかを確認してください。
介護事故の相談先は?窓口一覧と弁護士の法律相談がおすすめな理由
アトム法律事務所の無料相談のご案内
ご家族が介護施設や介護サービスにおいて事故に見舞われ、重い後遺症が残ってしまったり、亡くなられてしまった場合は、アトム法律事務所の無料法律相談をご活用ください。
- 介護施設から提示された賠償案に納得がいかない
- 介護施設側との交渉が進まないので示談交渉を任せたい
- 介護事故で家族が死亡してしまった
まずは専属スタッフがヒアリングをさせていただき、適切なご案内をいたします。
法律相談を利用するには、以下のフォームから予約をお取りください。予約は24時間・365日受け付け中です。
無料法律相談ご希望される方はこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了