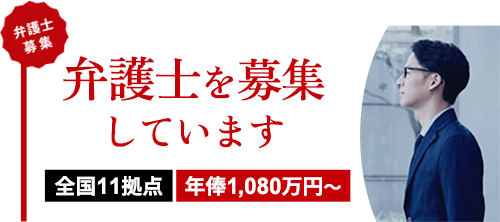訪問介護の裁判事例|在宅サービス利用中の事故とヘルパーの賠償責任
更新日:
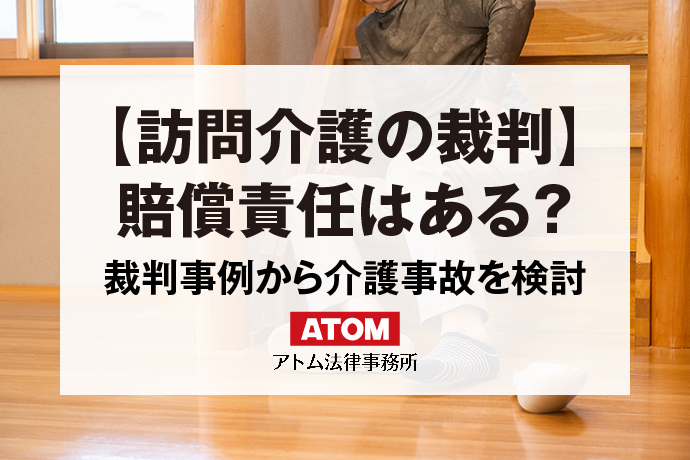
訪問介護中の事故がヘルパー側の安全配慮義務違反などによって引き起こされた場合、示談や裁判などの方法で損害賠償請求が可能です。
とくに裁判は、示談での解決が難しい場合に選択される手段になります。しかし、裁判であってもすべての事故についてヘルパーや介護事業者に責任を問えるものではありません。
訪問介護は自宅で自立した生活を送るために欠かせないサポートで、多くの介護スタッフに支えられて成り立っています。しかし、事故の発生原因を調査していくことで、ときにヘルパー側に安全配慮義務違反が認められるケースがあるのです。
訪問介護における事故の判例からみえる、訪問ヘルパー側に事故の責任が問えるケース・問えないケースの判断基準を解説します。
介護事故は裁判だけでなく、示談や調停などの解決方法があるので、各方法の違いを知りましょう。
目次
判例(1)常時介護が必要な少年の誤嚥による死亡事故
概要と争点|誤嚥が生じたのはヘルパーの過失だったのか
中枢神経障害による体幹機能障害で常時の身体・生活介助を必要としていた15歳の少年が、訪問介護サービスを提供する会社の訪問介護職員であるヘルパーから食事の介助を受けていました。
食事が終盤に差し掛かった頃、少年が上半身を前後に大きく揺らして顔色が悪くなったので、ヘルパーは少年の背中を叩いて声をかけたり、少年の祖母に報告したりしました。祖母は少年の様子を見て、てんかんの発作であると判断し、てんかんの発作に使用する座薬を投与しますが変化はありません。
帰宅した少年の母が119番通報し、同じころヘルパーも会社に事態を説明して誤嚥の可能性があることから救命措置を指示され、救急隊が到着するまで母とヘルパーが交代で救命措置を行いましたが、搬送された翌日に少年は死亡したのです。
死亡した少年の両親が原告となり、ヘルパーの食事介助によって誤嚥したことで窒息に陥り死亡したとして、ヘルパー・会社・代表取締役を相手取って訴訟を提起しました。(名古屋地方裁判所一宮支部 平成18年(ワ)第52号 損害賠償請求事件 平成20年9月24日)
遺族側とヘルパー側の主な争点は以下の通りです。
- ホームヘルパーに誤嚥を防ぐ注意義務を怠った過失は認められるか
- 会社に故意または重大な過失があったか(介護体制の整備に不備があったか)
- 少年が死亡したことで生じた損害項目と損害額
- 事故時における同居祖母による判断に過失があったか
判決|請求の一部が認められた
裁判所は、少年の異変にヘルパーが気づいた際に、会社に連絡をとるべきであったのに怠ったという過失がみとめられることから、ヘルパーと会社に約2000万円の損害賠償を命じました。
裁判所による判断
裁判所は、ヘルパーが少年の異変に気付いた時に会社や代表取締役に連絡をとるべきであったにもかかわらず、連絡を怠ったという過失が認められ、死亡との因果関係を認定しました。
もっとも、代表取締役に関しては、従業員に新人研修を受けさせたり、事故が発生した場合には会社に報告・連絡・相談を徹底するようマニュアルを用意するなどの整備を整えていたことから、代表取締役に故意や重大な過失はなかったと裁判所は判断しています。
また、少年の祖母がてんかんであると判断して対応を行った点については過失があるとし、損害賠償額から2割の過失相殺が行われることとなりました。
裁判所が認定した賠償金額
裁判所は、被害者固有の慰謝料と遺族固有の慰謝料、葬儀費用などを認めています。もっとも、遺族が主張した逸失利益は認められませんでした。裁判所が認定した賠償金額は、以下の通りです。
損害の内訳と賠償金額
| 損害の内訳 | 賠償金額 |
|---|---|
| 逸失利益 | 認められず |
| 被害者固有の慰謝料 | 1800万円 |
| 遺族固有の慰謝料 | 600万円※ |
| 葬儀費用等 | 140万円 |
| 過失相殺後の合計 | 2032万円※ |
※ 原告2名分の合計
判例(2)介護サービスの利用者がお茶をこぼして火傷した
概要と争点|お茶の提供方法に配慮する義務がヘルパーにあったのか
ヘルパーによる訪問介護を受けていた原告は、お茶の入ったマグカップを自身で引き寄せた際に倒し、左大腿にお茶をこぼして約2ヶ月の加療を要する火傷を負いました。
原告は、お茶をこぼして火傷しないように配慮する義務や火傷を負った後に氷で冷やすなどの手当を行うべき義務を怠ったとして、治療費や慰謝料などを損害賠償請求するために、ヘルパーが勤務する会社を相手取って訴訟を提起しました。(和歌山地方裁判所 平成25年(ワ)第366号 損害賠償請求事件 平成27年1月28日)
原告とヘルパー側の主な争点は以下の通りです。
- ヘルパーに安全配慮義務違反があったか
- ヘルパーに救護義務違反があったか
- 事故によって被った原告の損害内容と損害額
判決|損害賠償請求が認められなかった
ヘルパーの安全配慮義務違反や救護義務違反はなかったとし、原告側の損害賠償請求は認められませんでした。裁判所による判断は以下のとおりです。
裁判所による判断
ヘルパーが勤務する会社との間で交わされた契約において、提供するサービスは「身体介護」ではなく、あくまで「生活援助」であることから、お茶の提供方法に関してとられた配慮に不適切な点はなかったと裁判所は判断しました。
また、原告はヘルパーが患部を氷で冷やしたり救急車を呼ぶなどの救護措置を怠ったと主張していましたが、実際はヘルパーが状況を把握してから氷で患部を冷やしたり、家族へ連絡するか原告に確認をとったりするなどしていたと裁判所は判断しています。
以上のような理由からヘルパーに安全配慮義務違反や救護義務違反はなかったとして、原告が請求した損害賠償は認められませんでした。
判例(3)介護サービスの利用者が階段から転落した
概要と争点|介護ヘルパーは事故発生を予見できたか
視力障害のある原告は、自宅の階段を踏み外して2階から段ボールを持ったまま転落してケガをしました。
原告側は、2階で原告の依頼を受けて片付け作業をおこなっていた被告従業員の介護ヘルパーが、危険行為を制止するなどの安全配慮義務を怠ったためであるとして、損害賠償を請求した事案です。(東京地方裁判所 平成31年(ワ)第2352号 損害賠償請求事件 令和3年9月16日)
判決|損害賠償請求が認められなかった
裁判所は、介護ヘルパーは原告が転落の危険がある行動をとっていることを認識しておらず、部屋で片付け作業をしており、階段からの転落を予見することは困難だとして、安全配慮義務違反はないと判断しました。
原告の損害賠償請求を棄却したのです。
裁判所による判断
裁判所は、ヘルパーが片付けをはじめた際に、原告の運搬行為を認識していなかったことから、運搬行為を制止したり、目を離さないようにして注意・声掛けするという注意義務違反があったという主張は認められないとしました。
また、原告は一人暮らしをしており、2階で就寝するなど日常的に本件階段を利用していたことから、原告が2階にいて片付け作業をしていること自体が危険な行動とは評価できないと指摘したのです。
また、介護サービスの内容(買い物、調理、洗濯及び掃除等)からして、ヘルパーが途切れることなく常時見守りをすることを予定していないことからも、本件階段からの転落を予見することは困難であると結論づけました。
訪問介護の事故で裁判を検討する前に確認したいポイント
裁判をはじめるかどうか検討する前に、訪問介護の際に事故にあったと被害者側が主張して賠償金を請求しても、すべての主張が通るわけではないことを認識しておきましょう。
介護を行ったヘルパーやヘルパーの雇用主である会社に賠償責任があると認められる場合に限って、賠償金が支払われることになります。
ヘルパーや雇用主の賠償責任を検討するポイントは、予見可能性、因果関係、解決方法、賠償額です。
賠償責任を検討するポイント
- 予見可能性
- 因果関係
- 解決方法
- 賠償額
裁判を起こす前に検討しておきたい賠償責任のポイントを解説します。
ホームヘルパーは事故を予見できたのか
裁判所は一般的に、介護ヘルパー側が転倒などの事故を予見できる場合、事故を予見すべき義務があり、さらに結果を回避するための措置を講じる義務があると認定する傾向にあります。
よって、予見可能性の程度しだいで責任の有無が大きく左右されるのです。
事故の予見可能性があったときには、ホームヘルパー側は安全配慮義務を負っているにも関わらず、義務を怠ったとして賠償請求が認められる可能性があります。
安全配慮義務
介護サービスを提供する側は、利用者が危険にさらされることのないよう安全に配慮しなければならない義務を負う
予見可能性を判断する要素は?
予見可能性の程度を判断する要素は複数ありますが、たとえば次のような要素を検討する場合があります。
予見可能性の程度を判断する要素の例
| 判断要素 | |
|---|---|
| 利用者の個人的属性 | 年齢、要介護度 疾患の有無と症状(身体的・精神的両面) 経歴や普段の行動パターン |
| 事業者側の情報把握 | 利用者に関する情報の内容と程度 訪問介護計画表や病院の診療録などの記録内容 |
| 環境要因 | 事故発生場所の状況(転倒しやすい環境かどうか) 職員の配置状況 |
| 事故発生時の状況 | 実際の事故時の利用者の動作 職員の行動や対応 |
予見可能性の判断においては、これらの要素を総合的に検討して結論が導かれます。安全配慮義務違反についてさらに知りたい方は、以下の関連記事をお役立てください。
一緒に読みたい関連記事
損害賠償請求の相手は誰になるのか
ヘルパーの安全配慮義務違反があった事故では、ヘルパーが勤める会社に対しても損害賠償請求が可能となります。
ヘルパーが勤める会社に対しても損害賠償請求できることを「使用者責任」と呼びます。
使用者責任とは?
従業員が仕事中に第三者に損害を与えた場合、雇用主(会社など)がその損害を賠償する法的責任のことを指します(民法715条)。
ヘルパー個人に損害賠償の全額を請求することはできますが、ヘルパーが全額負担できる資力を持ち合わせているとは限りません。
ヘルパーと比べて資力が期待できる会社に対して請求することで、適正な賠償を受けられる可能性が高いです。
過失と結果の間に因果関係はあるのか
訪問介護中の事故で過失があったとしても、過失と結果の間に因果関係があったのかわからなければ損害賠償の請求はできません。
介護ヘルパーによる過失があったとしても、その過失が原因でない限り、因果関係はないので損害賠償請求はできないのです。
因果関係が認められない例
たとえば、介護ヘルパーが目を離したすきに転倒して足首を骨折したとします。その後、骨折の治療を受け、数か月後に脳内出血で亡くなった場合、ケガ(骨折)との因果関係が認められる可能性はあっても、死亡との因果関係までは認められないでしょう。
因果関係は、診断書や介護日誌、関係者の証言などさまざまな証拠にもとづいて判断される見込みです。
もっとも、訪問介護は在宅で行われることから、防犯カメラのような客観的な証拠が集めにくいとも考えられます。
弁護士に相談すれば、どのような資料が証拠となり得るのかアドバイスがもらえるでしょう。
集めた証拠を用いてどのような法的主張を行えば賠償請求できるのかについては、法律の専門家である弁護士に相談してみてください。
裁判以外にも示談や調停といった解決方法がある
訪問介護中の事故に関する補償を請求するにあたっては、多くの方が「裁判」をイメージされることでしょう。
しかし、裁判以外にも「示談」や「調停」といった請求方法があり、特に示談に関しては裁判をはじめる前に多くのケースで選ばれるのが一般的といえます。
示談・調停と裁判との違いは?
裁判は裁判所で紛争に関する審理が行われ、訴訟費用の負担が生じ、解決までに時間がかかります。
一方、示談は紛争の相手方と話し合いを行うものなので、基本的に費用はかかりません。
また、お互いの主張内容に大きな違いがなければ解決までに時間はそうかからないでしょう。
調停は示談と同じように話し合いを行うものではありますが、間に第三者を介入させる点に違いがあります。
裁判より調停は手軽にはじめられますが、示談より手間と費用がかかるので、示談で決裂した後にとられる場合が多い手段です。
示談・調停・裁判の違い
| 裁判 | 示談 | 調停 | |
|---|---|---|---|
| 費用 | かかる | 不要 | かかる |
| 期間※ | 長い | 短い | やや長い |
| 第三者の 介入 | あり | なし | あり |
※示談の期間は争点の数によって長くなることもある
介護事故が起こったときにはまず示談による解決を図ることが多いため、いきなり裁判と考えている場合は、一度関連記事にも目を通すことをおすすめします。
正しい損害賠償額はどのくらいなのか
訪問介護中の事故で受けた損害に対する補償を請求するには、どのくらいの損害を被り、損害を回復するためにはどのくらいの補償を要するのか算定しておかねばなりません。
訪問介護などの事故で生じる主な損害内容と損害額の算定方法は、以下の表のとおりです。
主な損害内容と基本の算定方法
| 損害 | 算定方法 |
|---|---|
| 入通院慰謝料 | 治療期間や怪我の程度 |
| 後遺障害慰謝料 | 障害の部位や程度 |
| 死亡慰謝料 | 家庭内の役割 |
| 治療費 | 実費 |
| 葬儀費用 | 上限150万円とした実費 |
| 逸失利益 | 得られなくなった収入補償 |
以上の損害内容は、多くの方が共通して請求するだろう主なものだけを紹介しています。実際に請求可能な項目は、事案ごとに異なるので、事案に応じた丁寧な算定が必須です。
なお、介護ミスによる死亡事故であれば、亡くなられた被害者本人に対する慰謝料はもちろん、近親者に対する慰謝料も認められる可能性が高くなるでしょう。
妥当な金額の賠償金を算定できているか、請求漏れがないかなどは弁護士に相談することをおすすめします。
訪問介護で受けた被害の相談は弁護士へ
訪問介護で家族がケガをしてしまったり、死亡してしまったりといった事故被害を受けたときには、弁護士に相談することが有効です。
裁判を起こそうと思っている方も、まずは示談交渉での解決を目指すことが多くなっています。
ただし示談交渉であっても裁判であっても、ヘルパーに全面的に責任を問える事故ばかりではありません。
また、慰謝料をはじめとした示談金についても、最初から十分な補償を提示される可能性は低いです。
介護事故の責任の有無を検討したい、損害賠償請求をおこないたいという方は弁護士への相談・依頼を検討していきましょう。
アトム法律事務所の無料相談のご案内
訪問介護の際に発生した事故で、ご家族がお亡くなりになったり、重い後遺障害を負われたりした場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。
- 損害賠償請求可能な事案か弁護士の意見が聞きたい
- 提示を受けた示談金の金額が妥当なものか確認してほしい
- ヘルパー側との示談交渉を頼みたい
相談予約に関するお問い合わせは、下記フォームの電話またはLINEから可能です。法律相談の予約受付は、24時間いつでも専属スタッフが対応中です。お問い合わせお待ちしております。
無料法律相談ご希望される方はこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了