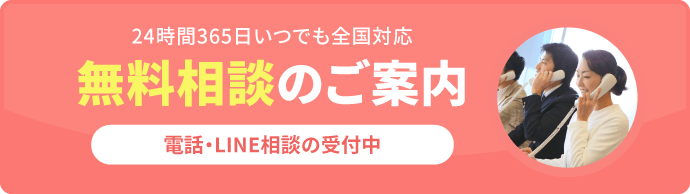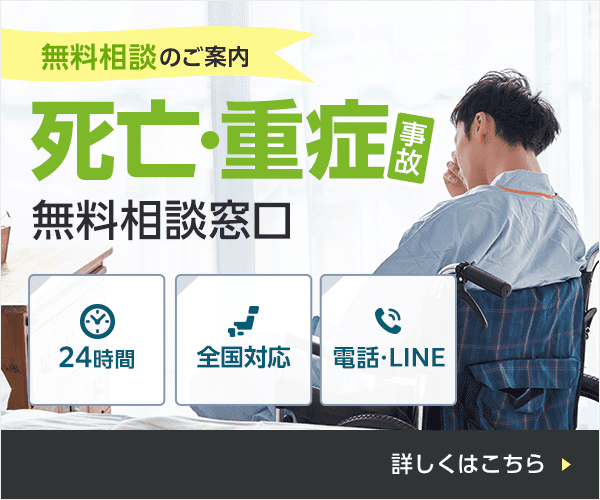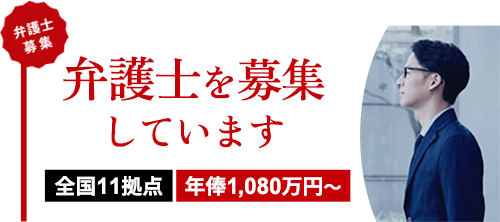介護事故のケガや死亡の慰謝料相場は?損害賠償の内訳や判例も紹介
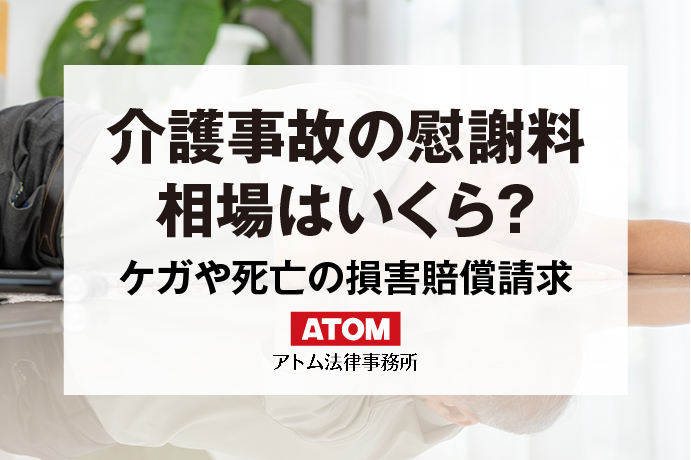
高齢化が進むなか、介護施設の社会的意義と需要はますます高まっています。
そして、なかには介護施設利用者がケガをしてしまったり、ケガによる後遺症が残ったり、最悪のケースでは死亡してしまったりと、さまざまな「介護事故」が起こっているのです。
介護施設側も懸命なサービスを提供しているものの、事故態様によっては義務を怠ったことが原因であるとして、介護施設側の責任が問われるケースもあります。
介護施設側に落ち度があったときには、その損害について慰謝料をはじめとした損害賠償請求が認められる可能性があります。
目次
そもそも慰謝料を請求できる介護事故とは?
介護施設側に「安全配慮義務違反」が認められるとき、介護事故で慰謝料請求が可能になります。
たとえば、誤嚥事故によって寝たきりになってしまった利用者がいたとします。その利用者が以前から誤嚥を繰り返しているのに、適正な見守りをつけていなかったことで事故が起こり、寝たきりになってしまった場合は施設側の責任を問える可能性があるでしょう。
しかし、その利用者がこれまで一度も誤嚥をしたことがなく、適切に配膳された食事中に突発的に詰まらせてしまった場合には、介護施設側の責任を問えるかどうかは慎重な判断が必要です。
介護施設側が事故の発生を予見することは可能だったのか、そして事故発生を回避する措置を適切にとっていたかなどを検討して、安全配慮義務違反の有無を判断するのです。
重要ポイント
介護施設内で起こった事故だからと必ずしも慰謝料請求できるわけではなく、個別のケースについて検証し、損害賠償請求の検討が必要になります。
介護事故の慰謝料相場|ケガ・後遺障害・死亡のケース
介護事故の慰謝料相場は一律に決まっているものではありません。事故類型や損害程度などを確認して、過去の判例を参考にすることになります。
もっぱら、交通事故の慰謝料算定基準「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(赤い本の基準)によって計算することも多いので、慰謝料相場の参考になるでしょう。
ここからは交通事故の慰謝料算定に用いられる基準を元に、慰謝料の相場をみていきます。
入通院慰謝料の相場
入通院慰謝料とは、介護事故で負ったケガの治療における精神的苦痛を緩和するために請求できる金銭をさします。
「つらさ」や「痛みに耐えた」といった精神的苦痛が大きいほど金額は高くなるので、入院している場合は通院のみよりも高額化しますし、治療期間が長いほど慰謝料の金額は増える傾向にあります。
具体的な入通院慰謝料の算定方法は、ケガの症状と治療期間をもとにした算定表によって相場を決めることが多いです。
入通院慰謝料の算定表の一部を抜粋します。
入通院慰謝料の算定表(交通事故の慰謝料算定基準に照らした場合)
| 0月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 0月 | 0 | 53 | 101 | 145 |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 |
※表の横軸は入院月数・縦軸は通院月数
※慰謝料の単位は万円
※むちうち・打撲などの軽傷時は表よりも低額になる可能性あり
たとえば、骨折で2ヶ月入院して、3ヶ月の通院治療を行った場合の慰謝料を、交通事故の基準に照らして計算してみましょう。
2ヶ月通院した場合は、横軸の「2月」に該当します。さらに通院が3ヶ月なので、縦軸は「3月」となり、双方の交わる部分が慰謝料の相場です。骨折で2ヶ月入院し、3ヶ月通院した場合の慰謝料相場は154万円となります。
なお、例で示した慰謝料はあくまで相場に過ぎません。むちうちや打撲など比較的軽傷であったり、既往症の関係で入通院期間が長期化していると判断されたりすると、相場より低額になる可能性は十分あるでしょう。
慰謝料を含む損害賠償の見積もりは、一度弁護士に依頼することをおすすめします。相場も教えてもらえますし、増減の可能性についても見解を聞いておくと安心です。
介護事故で骨折した場合の慰謝料については関連記事でよりくわしく解説しています。
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料の相場は110万円から2,800万円で、後遺障害等級1級から14級に応じておおよその相場があります。
また、高齢者の場合には事故発生前からの既往症を加味する必要もあるため、金額が表の通りに認められるとは限りません。弁護士に見解を尋ねておくことをおすすめします。
後遺障害慰謝料の相場(交通事故の慰謝料算定基準に照らした場合)
| 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料の相場 |
|---|---|
| 1級 | 2,800万円 |
| 2級 | 2,370万円 |
| 3級 | 1,990万円 |
| 4級 | 1,670万円 |
| 5級 | 1,400万円 |
| 6級 | 1,180万円 |
| 7級 | 1,000万円 |
| 8級 | 830万円 |
| 9級 | 690万円 |
| 10級 | 550万円 |
| 11級 | 420万円 |
| 12級 | 290万円 |
| 13級 | 180万円 |
| 14級 | 110万円 |
後遺障害慰謝料を請求するための前提
後遺障害慰謝料を算定するにあたっては、まず後遺障害等級を決めなければならないのですが、交通事故などと異なり、介護事故では後遺障害等級を認定する機関がありません。
そのため、被害者は介護事故によりどのような後遺障害が残っているのかを具体的に自ら立証しなければなりません。後遺障害の有無を立証後に、後遺障害等級を参考にしながら、その慰謝料の金額を決めていくことになるのです。
具体例
介護施設内でしりもちをついて大腿骨骨折を負ったとします。その後、きれいに癒合せずに変形や動かしづらさが残った場合には、後遺障害にあたるとして賠償請求を検討すべきです。
大腿骨骨折によって運動障害が残ったなら、その障害の程度によって8級7号、10級11号、12級7号に相当する可能性があります。あるいは変形障害が残ったなら12級5号相当の障害です。
このように、骨盤骨折の後遺症も内容や程度によって後遺障害等級は変わります。それぞれの後遺障害認定要件を満たしていることを医師の診断書などに記載してもらうことが重要です。
死亡慰謝料の相場
介護事故における死亡慰謝料の相場は1,000万円~2,000万円です。
また、遺族は固有の慰謝料として100万円程度の損害請求が認められる可能性があります。
【注意】慰謝料は過失の影響を受ける
介護事故で施設側に責任があると認められた場合、被害者やその家族は慰謝料請求が可能です。ただし、被害者側にも過失があった場合、過失の程度に応じて慰謝料が減額されることがあります。この考え方が過失相殺です。
事故の発生を介護施設側が予見できたとして施設側に責任がある事故においても、その責任のすべてが施設側にあるとはいえないケースも多くあります。
もっとも不当に高い過失を受け入れる必要はありません。介護施設側が被害者の過失を主張してきた場合、念のため弁護士の見解を聞いておくことが大切です。
「これまで施設にはたくさんお世話になった」という感謝の気持ちと、事故発生に対して疑問を持ったり、理由を知りたいと思うことは全く別だからです。
介護事故で損害賠償請求できるものは?
介護事故で損害賠償請求すべき費目は慰謝料だけでなく、被害者が負った損害によって異なります。
そこで、本記事では被害者が亡くなってしまった死亡事故と、死亡には至らなかった事故にわけて一般的な賠償金内訳をみていきましょう。
死亡事故の損害賠償請求費目
介護施設では誤飲事故など、命を奪う事故が発生する危険もあります。
介護施設における死亡事故ではおおむね1,500万円以上の賠償金が支払われています。
交通事故による死亡のケースではさらに賠償金が高額になる傾向があり、2,000万円を超えるケースも珍しくありません。しかし、介護事故の場合、元々体調が悪化しており、かつ高齢であることも考慮され賠償金が減額される傾向にあります。
死亡事故で請求できる賠償項目としては以下のようなものが考えられます。
- 本人に対する死亡慰謝料
本人の家庭名における立場を基礎に金額が決まる。 - 遺族に対する慰謝料
法律上、配偶者、両親、子どもが本人とは個別に請求可能。
ただし、家族関係によっては兄弟や孫なども請求できる可能性がある。 - 年金の逸失利益
死亡したことで、事故がなければ得られていたはずの年金による利益が得られなくなったという損害。年金の金額や死亡時点の年齢などから金額が決まる。 - 葬儀費用
葬儀代、四十九日といった法要代、墓石建立費用など。
おおよその相場としては、本人の慰謝料だけでも1,000万円を超える場合が多いです。本人の慰謝料といっても、当然のことながら判決時点で本人はこの世にはいないので遺族が受け取る形になります。
介護事故で家族が死亡してしまったときにどういったケースなら慰謝料請求できる可能性があるのか、年金を受給できなくなったことへの賠償は関連記事で解説していますので、あわせてお読みください。
関連記事
- 死亡事故の損害賠償請求について
介護事故で家族が死亡|損害賠償請求するときの法的根拠を解説 - 年金の逸失利益の計算について
死亡事故の逸失利益|計算方法と職業ごとの具体例、生活費控除とは?
非死亡事故の損害賠償請求費目
非死亡事故の場合、治療費などさまざまな項目の賠償を受けられます。
非死亡事故で請求できる賠償項目としては以下のようなものが考えられます。
- 治療費
治療のために必要となった費用全般(投薬費、手術代、入院代等)。 - 通院交通費
通院を行うための交通費。基本的に公共交通機関の利用費用となる。 - 入院雑費
入院中の日用品や生活雑貨等の費用。
入院日数に応じて金額が決められる。 - 休業損害
被害者が仕事をしていた場合に、治療のために仕事を休んだことで生じる給料を得らえないといった損害。
事故前の収入や休業期間にもとづいて金額が決まる。 - 後遺障害逸失利益
被害者に生じた後遺障害により労働能力が低下したため、将来仕事によって得られたはずの利益が得られなくなったという損害。
事故前の収入、事故当時の年齢、後遺障害の程度により金額が決まる。 - 入通院慰謝料
治療のために入院や通院を行わなうことになったという精神的苦痛に対する慰謝料。
入通院の期間に応じて金額が異なる。 - 後遺障害慰謝料
後遺障害が生じたことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料。
後遺障害の程度に応じて金額が異なる。 - 将来の介護費用
など
この中でも特徴的な項目が将来の介護費用です。介護事故の場合では元々、介護費用がかかっていたことになるので、事故前の容態・介護費用と事故後の容態・介護費用を比較し、その差額分が賠償対象となります。
ただし、当該事故が無かったとしても、介護費用の増額が見込まれるケースではすべての賠償金を得られないケースもあるので注意してください。
また、後遺障害が残った場合、損害賠償の金額を大きく左右する要因となります。後遺障害とは治療が完了したにもかかわらず、身体に残ってしまった障害のことです。
後遺障害の程度によって後遺障害等級の認定を受けますが、障害の程度が重い程、多額の賠償金を獲得できる傾向があります。
介護事故の慰謝料を請求する方法
介護事故で慰謝料等を請求する方法には、示談、調停、裁判の3つがあります。
介護事故の慰謝料請求方法
- 示談
- 調停
- 裁判
それぞれどのような方法なのかみていきましょう。
請求方法(1)示談
介護施設に対して慰謝料等を請求する場合、まずは裁判所外での交渉をすることになります。
この交渉を「示談」といいます。示談とは、当事者双方の話し合いによって解決を図る方法です。
介護事故では、まず多くの場合で示談を通して、事故態様や慰謝料を含む損害賠償の金額についての話し合いが行われるでしょう。
双方で示談内容に合意できたときには、その旨を示談書などにして終了します。
示談には、裁判手続きと比べて費用をおさえられることや早期解決が期待できるメリットがあります。介護事故の示談の進め方や弁護士ができることをまとめた関連記事も、あわせてお読みください。
請求方法(2)調停
当事者同士で示談で話し合いが進まなかったり、折り合いがつかなかったりする場合もあるでしょう。
そこで、次にとられる方法で考えられるのが「調停」です。調停とは、裁判所の調停委員などが話し合いの間に入ってくれるものです。
示談交渉と同様に話し合いで進められていく方法ですが、当事者と利害関係を持たない公平で中立的な第三者の調停人が介入するという点に違いがあります。
請求方法(3)裁判
任意での示談交渉や調停による解決がむずかしければ、「裁判」を行うことになるでしょう。
裁判とは、裁判所が当事者双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりした後に判決による紛争の解決を図る方法です。
いずれにしても証拠が大切になります。専門家と相談をしながら、証拠の保全に努めましょう。
裁判の関連記事
介護事故における裁判事例の紹介
介護事故における裁判例を紹介します。ここでは、どのような事案でいくらの慰謝料が生じているのかという点を詳しく見てみたいと思います。
転倒して頭部を負傷した事案(大阪地裁平成29年2月2日判決)
この事案では、介護施設利用者であるAがトイレに行こうとした際に転倒して、頭部を負傷して硬膜下血腫を発症したというものです。Aは、いわゆる植物状態に準じる状態になり、意思疎通は不可能で回復可能性もほとんど無い状態になりました。
裁判所は、「本件事故後の治療経過、Aの年齢、健康状態等の一切の事情を踏まえ、慰謝料総額を1300万円と認めるのが相当である」と判断をしました。
なお、この事案では、Aもナースコールを押して職員を呼ぶなどするべきであったとしてAの過失も4割あると判断されております。
死亡した事案(東京高裁平成28年3月23日判決)
この事案では、介護老人保健施設の認知症専門棟に短期入所していたAが、2階にある食堂の窓を解放して身を乗り出したところ落下し死亡しました。窓の開放制限措置が不適切であったことから、施設の義務違反があったと認定をし、損害賠償請求が認められております。
裁判所は、「本件事故の態様のほか、本件事故当時のAの家族状況、Aの年齢(84歳)、Aは認知症患者であったが、運動能力の面では年齢相当を超える衰えがあったことをうかがわせる証拠は無いこと、その他本件に表れた一切の事情を考慮すれば、Aの死亡慰謝料額は2,000万円と認めるのが相当である」と判断をして死亡慰謝料2,000万円が認められました。
ベッドから転落して負傷した事案(東京地裁令和2年6月24日)
この事案では、Aが特別養護老人ホームBに入所していたところ、ベッドから転落して打撲などの傷害を負ったものです。
この事案では入院期間が約3ヶ月であること等を考慮して、入通院慰謝料として165万円が認められました。
また、後遺障害について、Aは本件受傷後、声かけに対する反応の低下が認められているものの、受傷前から声かけに対して目を開くといった反応であったことを考慮され、30万円が相当であると判断をされております。
介護事故で慰謝料請求するなら弁護士に相談
弁護士に相談するメリット
介護事故における慰謝料相場はあくまで目安です。個別の事案を丁寧に紐解いていくことで、適正な金額の慰謝料というものを算定することができます。
そのため、法律の専門知識がないと、慰謝料の算定はむずかしいでしょう。
また、慰謝料を請求する際は、介護施設側との示談交渉や裁判が必要となりますが不安が多いと思います。
弁護士に相談することで、慰謝料を含め、損害賠償請求によりいくら請求が可能であるのかを知ることが可能です。
さらに、弁護士に依頼すれば代わりに介護施設側への損害賠償手続きを行ってくれるので、手続き面における不安もなくなります。
以上のようなメリットが存在するため、介護事故に関するお困りごとやお悩みをお持ちの方は、一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。
アトム法律事務所の無料相談
介護事故でご家族を亡くされたり、重大な後遺障害が残ったりした場合は、アトム法律事務所の無料法律相談をご活用ください。
弁護士に相談するとしてもどこに相談すべきなのか、相談費用がいくらになるのかと迷っているという方は、相談費用を気にせず弁護士に介護事故の悩みを相談することが可能です。
無料相談の予約をまずはお取りください。予約の受付自体は24時間いつでも対応中です。下記フォームより、電話かLINEのいずれかの方法にてお問い合わせください。
なお、法律相談は正式契約とは異なります。法律相談後に契約をご検討いただければ十分で、無理に契約を迫ることはありません。
無料法律相談ご希望される方はこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了