鍵垢で誹謗中傷されたら開示請求できる?名誉毀損は成立する?
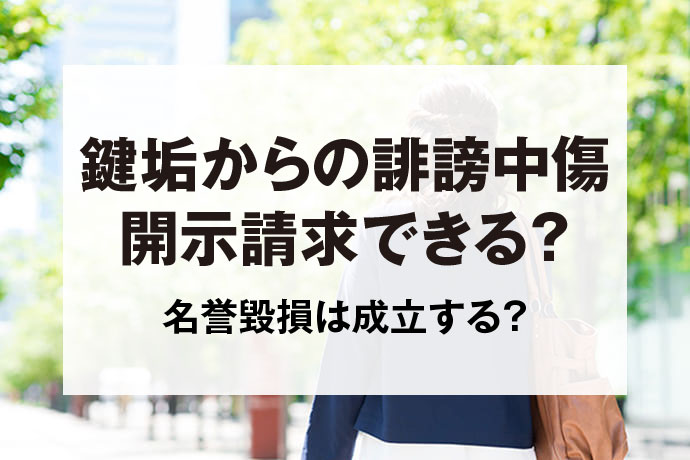
SNSには鍵垢(鍵付きアカウント)といって、特定の人物にしか閲覧ができないようなアカウントも存在します。
全く見ず知らずの鍵垢から誹謗中傷されることもあれば、知り合いの愚痴垢のような鍵垢から誹謗中傷されるケースもあるでしょう。
こうした鍵垢からの誹謗中傷も、名誉毀損が成立したり、開示請求が認められたりする可能性があります。本記事で鍵垢からの誹謗中傷における名誉毀損の成立や開示請求の可否などをみていきましょう。
もっとも、鍵垢が関わる誹謗中傷の開示請求や損害賠償請求については判例でも判断が分かれており、個別具体的な検討が必要です。
インターネットトラブルにくわしい弁護士に相談することで、より具体的な解決方法も見えてきますので、弁護士相談も検討しましょう。
目次
鍵垢からの誹謗中傷で開示請求が認められるポイント
鍵垢への開示請求が認められるポイントとして「鍵垢によって明らかに誹謗中傷されていること」「鍵垢に一定以上のフォロワーがいること」の2点について説明します。
ポイント
- 鍵垢によって明らかに誹謗中傷されていること
- 鍵垢に一定以上のフォロワーがいること
鍵垢によって明らかに誹謗中傷されていること
鍵垢であっても、投稿内容が名誉毀損や侮辱にあたる悪質なものや他者の権利を侵害する行為があれば、法的責任を問える可能性があります。
たとえば、被害者自身が鍵垢とフォロワーの関係にあり、その投稿内容を閲覧できる状態であれば重要な根拠となるでしょう。
もっとも鍵垢は特定の人しか投稿を閲覧できないので被害に気付く機会も限られています。
また、「誹謗中傷されていように感じる」「鍵垢に投稿が引用されて気味が悪い」といった憶測や気分の悪さでは権利侵害や犯罪が行われていると断言できず、法的対処が取れる可能性は低いです。
鍵垢に一定以上のフォロワーがいること
鍵垢であっても、フォロワーの数が多い場合は、より多くの人にその投稿内容が閲覧可能な状況といえます。
フォロワーが一定以上いる場合は「公然性が高い」として、権利侵害を受けている状況にあると判断される材料になるでしょう。
公然性は「名誉毀損罪」や「侮辱罪」の成立要件にかかわる重要な要素です。
鍵垢でどんなことを書かれたら名誉毀損罪に問える?
鍵垢による誹謗中傷でも名誉毀損は成立する可能性があります。
しかし一定の成立要件がありますので、名誉毀損にあたる投稿例、侮辱罪の検討、名誉毀損罪に問われないケースなどの詳細をみていきましょう。
名誉毀損罪の成立要件
名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為です。名誉毀損罪の成立要件を下表にまとめます。
名誉毀損の成立要件
| 成立要件 | 概要 |
|---|---|
| 公然性 | 不特定または多数の人が認識できる状態であること |
| 事実摘示性 | 具体的な事実をさすこと |
| 名誉の毀損性 | 人の社会的評価・信用を低下させるような内容 |
つづいて名誉毀損罪の成立要件である(1)公然性、(2)事実摘示性、(3)名誉の毀損性の3つに分けてくわしくみていきましょう。
公然性
インターネットを活用したSNSでは通常公然性を満たすことが多いですが、鍵垢は非公開アカウントなので、公然性については争いの余地があります。
鍵垢の内容を閲覧できる人数(フォロワー数)で検討することが多いですが、何人以上であれば公然性があるという明確な定義はなく個別の判断によります。
事実摘示性
具体的な事実により名誉を毀損しているいる必要があります。
たとえば、「逮捕歴がある」「不倫をしている」「人を騙して収入を得ている」などは、具体性があり、なおかつ一般的に周囲からの評価を下げる内容です。
これらは事実であっても、事実でなくても、名誉毀損罪の成立要件を満たします。
名誉の毀損性
具体的な事実であっても、「コーヒーが飲めない」「声が大きい」などは趣味嗜好の範囲と言えるでしょう。
一般的に社会的評価を下げるとまではいえない内容であれば、名誉毀損罪は成立しません。
名誉毀損が成立するかは弁護士に聞いてみる
誹謗中傷された人にとっては書いてほしくないという内容であっても、客観的にみれば名誉毀損とまではいえないこともあります。
また、鍵垢の状況次第では公然性の判断が分かれるでしょう。フォロワーが0のアカウントと、フォロワーを何人ももつアカウントでは公然性に違いがあります。
個別の判断については、弁護士に見解を聞いてみましょう。
関連記事では名誉毀損の成立要件についてくわしく解説しています。あわせてお読みください。
名誉毀損が成立しうる投稿の例
名誉毀損が成立する投稿の例をいくつか紹介します。
名誉毀損の例(1)前科や逮捕歴など
- ○○さん、実は窃盗犯だったらしいよ。証拠も見たんだけど。
- 盗撮常習犯の〇〇を許さない
- 〇〇さんは前科があるからあんな仕事しかできない。
前科や逮捕歴、あるいは現在も犯罪行為に加担しているような投稿は、その人の社会的評価を下げてしまうものです。
断定的な表現ではなくても、「証拠を見た」のように、真実であると受けとれるような投稿は名誉毀損にあたる可能性があります。
名誉毀損の例(2)職業やふるまいなど
- ○○さんは風俗店で働いている
- パパ活女子の〇〇さんは今日もブランド品自慢してる
- 〇〇はホス狂いの借金まみれ
風俗店での勤務
風俗店で働いていることを公言していない以上、一般的には風俗店での勤務は知られたくない情報といえます。
また周囲からの評価を下げうる情報になりますので、名誉毀損にあたる言葉といえるでしょう。
パパ活女子
パパ活女子という表現はなんらかの対価を得て男性との関係を持っていることを意味すると受けとられるため、社会的には不適切なものと判断されます。
そのため「パパ活女子」と名指しされることは、その人の社会的評価の低下につながり、名誉毀損にあたる可能性があるでしょう。
借金まみれ
借金があるということは、一般的には周囲に知られたくないことでもあり、まわりの人からの信用低下につながるため、名誉毀損にあたる可能性が高いです。
名誉毀損罪ではなくても侮辱になることはある
名誉毀損罪ではなくても、侮辱罪の成立を検討したり、名誉感情の侵害を理由に法的対処が取れる可能性は十分あります。
侮辱罪とは?
侮辱罪とは、公然と人の名誉を毀損する行為です。名誉毀損罪とは違い、事実の摘示は問われません。
「アホ」「ブス」「ノロマ」など具体性に欠けるものの、人の社会的評価を下げるような表現については侮辱罪を検討するべきです。
なお、ここまで説明してきた名誉毀損罪や侮辱罪は犯罪行為としての成立要件になります。
そのため、最終的な処分を決める警察・検察・裁判官は、あくまで刑罰に関与するのみです。
警察・検察・裁判官が加害者に損害賠償請求してくれるわけではないので、被害者の受けた損害を賠償請求するには民事面での訴えが必要になります。
名誉感情の侵害とは?
名誉感情の侵害とは、いわゆる権利侵害を受けて自分の人格権や自尊心が傷つけられたことです。民法上の不法行為として、名誉感情の侵害を根拠に損害賠償請求できます。
名誉毀損罪や侮辱罪といった「犯罪行為」で訴えることとは違うので、事実の摘示や公然性などがなくても民事上の訴えを起こして損害賠償請求することは可能です。
名誉毀損が成立しても罪にならないこともある
違法性阻却事由といって、投稿内容自体は名誉毀損にあたるものでも、その目的や内容しだいでは名誉毀損罪に問われないケースもあります。
具体的には、政治家の汚職の告発、企業の社内不正の告発などのように、公共性・公益性が高いと判断された場合があげられるでしょう。
みんなの知る利益になることや、誰かを貶めることが目的ではないことなどが着目されるのです。
もっとも一般人への名誉毀損においては、違法性阻却事由が適用される可能性は低いといえます。そのため、こうした名誉毀損になる言葉を投稿されたときには法的対処が取れる可能性は十分あるのです。
鍵垢も発信者情報開示請求の対象になる
鍵垢相手であっても発信者情報開示請求はできる可能性があります。
発信者情報開示請求の流れと注意点についてみていきましょう。
発信者情報開示請求の流れ
発信者情報開示請求は、原則として2段階の手続きが必要です。ひとつは鍵垢のIPアドレスを取得すること、そしてIPアドレスからわかったプロバイダに対して発信者情報の開示を求める流れになります。
ポイント
- 発信者情報開示請求には段階がある
- IPアドレスを取得し、つづいて住所や氏名といった発信者情報を開示請求する
サイトやプロバイダ側へ任意での開示請求もできますが、応じてくれる可能性は低いです。そのため発信者情報開示請求という法的手続きが必要になります。
法的手続きになるので、書類の作成や証拠の収集などすべきことは多く、独力でこなすことは大きな負担です。
鍵垢のアカウント情報をできる限り集め、インターネットにくわしい弁護士へ相談しておくことをおすすめします。弁護士と話をして、発信者情報開示請求が有効だと判断できたら、弁護士への依頼も検討していきましょう。
なお、関連記事『自分で開示請求する方法・注意点!開示請求のやり方と開示請求書の書き方』でも解説している通り、発信者情報開示請求の手続き自体は自分でもできます。
しかし、続いて説明する通り開示請求には期限があるので、手続きを熟知した弁護士に任せる人も多いです。
発信者情報開示請求の期限に注意
発信者情報開示請求には技術的な期限があります。なぜならサイト側のログ保存期間は一定で、それを過ぎるとログは消えるからです。
発信者情報開示請求でIPアドレスが分かっても、プロバイダに対して開示請求をしたタイミングが遅ければ、そのIPアドレスに関する情報はないと言われてしまいます。
そうするとそれ以上発信者情報を辿ることが難しくなってしまうのです。
発信者情報開示請求を成功させるためには、まずその情報が残っていることが大前提ですので、できるだけ早く手続きに着手せねばなりません。
鍵垢での誹謗中傷における判例もわかれている
鍵垢での誹謗中傷については、事案によって判断が分かれています。
ここでは裁判所が損害賠償請求を認めなかった判例と、損害賠償請求を認めた判例の2つをみていきましょう。
損害賠償請求を認めなかった判例
本事案は、高校時代からの友人同士である原告Aと被告Bにおける損害賠償請求事件です。
原告Aは、第三者からInstagramを介して次のような記載がされたスクリーンショット画像を受け取りました。
画像の記載内容
- 「ホルスタイン」
- 「マジ産む機械・・・むり・・・」
- 「子供4人も産んでまじ産む機械」
- 「36だよね笑笑 パート先のファミレスで高校生たちにババアって呼ばれてるらしいけどそらそうだわ。」
- 「ドブスドデブですよまじ」
スクリーンショット画像は、X(旧Twitter)のダイレクトメッセージ画面を撮影したものでした。
原告側は、Xにおける投稿はフォロワーに閲覧されつづけ、リツイートやコピーで&ペーストなどで簡単に拡散される状態であったと主張しました。
そして、鍵付きのアカウントあったかどうかではなく、本件投稿は不特定多数の第三者に対して投稿内容を閲覧させる行為であるとして名誉感情の侵害を訴えたのです。
裁判所は、被告の「△△」というアカウントはいわゆる鍵付きアカウントで、常時非公開であり、被告に許可された限られたフォロワーしかその内容を閲覧することができなかったことを指摘しました。
そして、たまたま原告に知らせた第三者のように、閲覧画面をスクリーンショットで保存して送信したものがいたとしても、不特定多数の第三者に拡散する可能性があったとまでは言えず、被告の予見可能性の立証にはならないから原告への不法行為には当たらないと判断したのです。
本判決は東京地方裁判所における損害賠償請求事件(令和元年5月29日)より抜粋しています。そのため表記は一部旧表現です。
損害賠償請求を認めた判例
本事案は、もともと同じアイドルグループで活動していた原告Aと被告Bのあいだでの損害賠償請求事件です。
原告Aは、被告BのSNS投稿により名誉が毀損されたと主張しました。原告Aが問題視した投稿は以下のとおりです。
投稿の内容
- 「あ、新宿のレズ風俗やめちゃったんだっけ?あれ」
- 「秋葉原の店舗型リフレでこの写真見せて上手く聞き出してくれませんかね~^-^」
原告Aは、原告が性風俗店で働いたことがある事実または今も働いている事実を摘示するもので、一般的な読み方をすれば社会的評価を下げる内容だと主張しました。
それに対して被告Bは、これらの投稿が原告Aに向けられたものかは不明であり、風俗店で働いているという事実の摘示には当たらないと主張したのです。
また、「原告Aから風俗店で働いていると聞かされていた」、500人程度のフォロワーがいたものの鍵付きアカウントであり、「仲のいい友達に愚痴をこぼしただけ」とも述べました。
裁判所は、「仕事もプライベートも人間関係全部崩れたのこの子もといメンバー緑の被害にあったから…」という投稿の後に、当該投稿(1)がなされたことを指摘しました。
原告のイメージカラーが緑であったことから、(1)の投稿は原告に対するものと言えると認めたのです。
そして、投稿内容が事実の摘示にあたり原告の社会的評価を著しく低下させること、投稿時にフォロワーが複数いたこと、鍵付きアカウントとはいえ今後も被告Bの承認次第で閲覧可能な人数が増えることなどから、原告の名誉感情侵害にあたると事案と認めました。
もっとも鍵付きアカウントで一時的な閲覧者が限定されたこと、投稿内容の表現、回数などを考慮して慰謝料20万円を相当したのです。
本判決は東京地方裁判所における損害賠償請求事件(令和2年6月19日)より抜粋しています。
鍵垢から誹謗中傷を受けた方へのQ&Aと補足情報
鍵垢から誹謗中傷を受けた方への補足情報をQ&A形式で説明します。
誹謗中傷の投稿を鍵垢でいいね・リポストされたときは?
あなたを誹謗中傷する投稿に対して、鍵垢でいいねしたり、リポストして拡散したりする行為は、法的対処が取れる可能性があります。
民事裁判での判決にはなりますが、名誉毀損にあたる投稿に「いいね」をしたり、「リポスト」したりする行為は民事上の損害賠償責任を負うという判例もあるのです。
たとえ鍵垢であっても発信者情報開示請求も認められる可能性はあります。
鍵垢からDMで誹謗中傷されたら開示請求できる?
DMは不特定多数に対するものではないので、民事上の手続きで開示請求することは難しいでしょう。
DMは1対1の個別やりとりになるので、不特定多数の人の目に触れる形ではありません。そのため名誉毀損や侮辱罪などは成立しないのです。
また、発信者情報開示請求について定める法律においても、「不特定多数の人に対する通信を媒介している特定電気通信役務提供者」を対象としています。
脅迫やネットストーカーは警察に相談
DMで「殺す」「会ってくれないと画像を晒す」「どこまでも追いかけてやる」などの脅迫やネットストーカーのようなことを言われたときには、警察へ相談してください。
犯罪が成立すると判断されれば警察が対応してくれます。
悪質なハッシュタグは裁判に影響する?
被害者を貶める内容のハッシュタグについては、裁判に影響します。
判例では、「#詐欺」「#犯罪者」「#毎日違法行為」といったハッシュタグをつけて投稿する行為が、閲覧者数の増加を狙う悪質なものとして開示請求を認めた判例があります。(東京地方裁判所における発信者情報開示請求事件 令和2年6月11日判決)
ハッシュタグは加害者側の行為の悪質性をはかるひとつの指標と言えるでしょう。
はっきり名指しされていなくても開示請求できる?
名指しをされていなくても、その前後の流れ・文脈・背景事情から、第三者がみても誰のことを言っているのか特定できるときには権利侵害を根拠に開示請求可能です。
そのため弁護士に相談する際には、前後の文脈についてもスクリーンショットで保存することも重要になります。
鍵垢からの誹謗中傷を弁護士に相談すべき理由
鍵垢から誹謗中傷を受けたときの対応は弁護士に相談するべきです。
弁護士相談が望ましい理由について説明します。
SNSごとに最適な対応のアドバイスがもらえる
X(旧Twitter)やインスタなどSNSごとの特徴やインターネットの仕組みにくわしい弁護士であれば、誹謗中傷に対する的確な助言が可能です。
たとえば、SNSサイトに対して発信者のIPアドレス開示を求める際には、書類の送付先(本社の所在地)や管轄の裁判所などの情報を理解しておくと最速で対応できます。
サイトによっては「このフォームから申請してほしい」と指定している場合もあるでしょう。
とくに発信者情報開示請求を検討している方は、早急に相談をして対処を考えねばなりません。開示請求のタイムリミットを意識した行動がポイントです。
以下の関連記事ではSNSごとの開示請求・特定の流れをまとめているので、参考にしてみてください。
法的根拠について専門家の意見が聞ける
ネット上で誹謗中傷されると、つらくかなしい気持ちになったり、怒りが込み上げてきたり、強い衝撃を受けてしまいます。そうすると、なかなか冷静な判断ができません。
該当の投稿を弁護士に見せることで、法律の専門家目線で、どういった権利侵害を受けていて、どんな対応が取れるのかを聞くことができます。
法的根拠は発信者情報開示請求はもちろん、特定後の損害賠償請求においても重要です。何を根拠に法的対処をとるのかを明確にしておきましょう。
なお、弁護士にもそれぞれ注力している領域がありますので、ネットトラブルにくわしい弁護士への相談がおすすめです。
弁護士選びの参考になる解説記事は以下のバナーより確認できますので、あわせてお読みください。
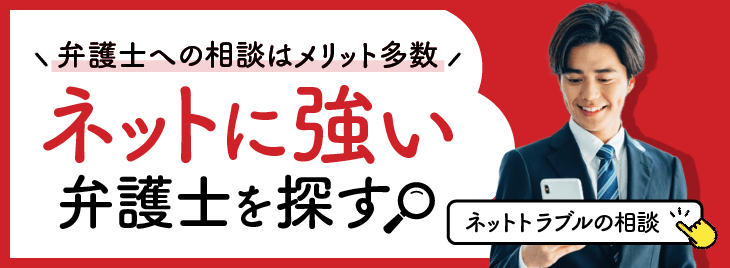
弁護士費用の相場がわかる
鍵垢への開示請求を弁護士に依頼すると弁護士費用がかかります。弁護士費用は各法律事務所の費用体系によって様々ですが、着手金、成功報酬、実費、日当などが主な内訳です。
これらの費用と、相手に対して請求できる見込みの金額とを比較検討してください。
なお弁護士費用を支払うことに抵抗がある場合、発信者情報開示請求の手続き自体は自分でもできます。
しかし、開示請求の手続きが大変そう、相手と直接やり取りしたくないなど、弁護士費用を支払ってでも依頼するメリットを感じる人もおられるのです。
関連記事では発信者情報開示請求の費用相場を解説しています。もっとも実際の費用は弁護士との相談時にお確かめください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了