誹謗中傷の弁護士費用はいくら?値段は削除や開示請求などの対策で変わる!
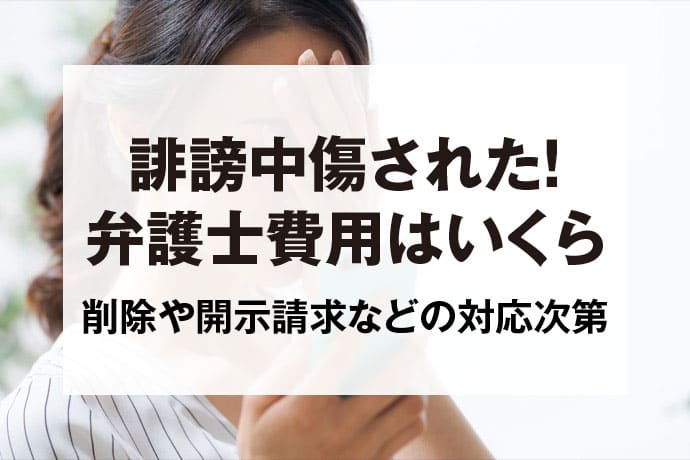
ネット上で誹謗中傷されたとき、相手に対して法的対処をとりたいと感じる方は多いものです。そして同時に、どれくらいの費用がかかるのかを知っておきたいと考えるのは当然でしょう。
誹謗中傷の削除請求であれば着手金として20万円程度、報酬金として10万円から20万円程度が弁護士費用の相場ともいわれています。
または誹謗中傷の投稿者を特定するなら、数十万円から100万円程度の弁護士費用がかかるケースもあるでしょう。
誹謗中傷の弁護士費用相場(裁判手続きを利用)
| 誹謗中傷への対策 | 弁護士費用の相場 |
|---|---|
| 投稿の削除 | 20万円程度から40万円程度 |
| 投稿者の特定 | 数十万円から100万円程度 |
ただし誹謗中傷への対策方法しだいで異なるので、事案に応じた弁護士費用については実際に法律相談で見積もりを取ってみてください。
この記事では誹謗中傷への対策として「削除」「投稿者の特定」の2つに分けて、弁護士費用の概要を解説します。
弁護士費用の相場について
弁護士費用は法律事務所ごとの費用体系があり、それぞれの設定した金額によります。本記事で紹介する弁護士費用は、あくまで相場のひとつとして参考になさってください。
目次
誹謗中傷対策への弁護士費用の基本
弁護士費用の相場を知るためには、まず弁護士費用の内訳について知っておくと、よりスムーズに理解できます。
弁護士費用の主な内訳
弁護士費用の主な内訳は、着手金、報酬金、実費の3つです。費用の概要を下表にしめします。
誹謗中傷の削除にかかる弁護士費用の内訳
| 費目 | 概要 |
|---|---|
| 着手金 | 契約時に発生する費用 |
| 報酬金 | 成功した際に発生する費用 |
| 実費 | 交通費や郵便代など実際にかかった費用 |
特に、着手金は契約時に発生するもので、結果にかかわらず原則返金はおこなわれない性質のものです。仮に削除に成功しても、削除できなくても発生する費用といえます。
報酬金は結果に左右される金額のことです。成功報酬ともいわれていますが、何をもって成功とするかは弁護士に必ず確かめておいてください。たとえば最終的な結果への割合で設定している場合もあれば、金額が固定されている場合もあります。
実費とは弁護活動のために弁護士が裁判所へ出廷した際の移動費、文書の郵送費などがあげられるでしょう。
弁護士費用は法律相談で見積もりを取る
通常、弁護士と契約をする前には法律相談を受けることになるので、弁護士費用の見積もりを依頼しましょう。
なお法律相談自体が無料だったり、対面・電話・メールなどのさまざまな相談方法だったりと、法律事務所ごとに特徴があります。
ご自身に合う法律事務所を見つけることもポイントです。
また法律相談料は無料のところもあれば、「回数」「時間」などで料金が変動する法律事務所もあります。各法律事務所の料金体系は事前にホームページなどで閲覧しておきましょう。
誹謗中傷の削除依頼にかかる弁護士費用はいくら?
誹謗中傷の削除依頼方法として、任意削除と仮処分申立てによる方法の2つを紹介します。
任意削除依頼の弁護士費用相場
任意削除の弁護士費用は1URLにつき約5万円~20万円が弁護士費用相場とされます。
任意削除依頼では費用をかけずに個人でおこなうことも可能です。しかし、サイトの特性や削除依頼の文面などは、ネットの誹謗中傷問題にくわしい弁護士の方が熟知しているので、弁護士に任せる方がスムーズに進む可能性があるといえます。
任意削除とは?
たとえば、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSで、投稿した本人に直接削除を依頼したり、運営会社に通報するという方法などです。
もう少しくわしく説明すると、サイトやSNSにおける誹謗中傷に対して、任意削除依頼の方法には次の3つが考えられます。
- 投稿者に直接削除依頼する
- 運営者(コンテンツプロバイダ)に削除依頼する
- ガイドラインに則った削除依頼(送信防止措置依頼)をする
ただし、あくまで任意の依頼ですので、必ず削除してもらえるとはかぎりません。
個人での任意交渉に応じてもらえない場合、また、自分で削除依頼をすることに不安がある場合は、弁護士に相談してアドバイスをもらったり、交渉そのものを任せることも検討しましょう。
削除の仮処分の申立てに必要な弁護士費用相場
裁判所への仮処分申立てを弁護士に任せる場合、弁護士費用として着手金や報酬金が別途必要です。着手金の相場は20万円程度、報酬金の相場は10万円から20万円程度など、法律事務所によって異なるので、かならず法律相談時に確認してください。
なお仮処分申立てを利用する場合は、印紙代2,000円や郵便切手代のほか、担保金として10万円から30万円程度を用意する必要があります。
仮処分とは何か?
仮処分とは、被害者の権利保護のため、通常の裁判手続きをとらずに発令される裁判所の緊急手続きです。
任意の削除依頼や、ガイドラインによる削除依頼をしても削除されなかった場合には、裁判所の仮処分手続きの利用を検討することになります。
なお、仮処分申立て後に訴訟に移行することもあるなど、展開により必要な費用は変動するものです。ご契約前には今後の展開と、展開に応じて必要になる弁護士費用も整理しておきましょう。
誹謗中傷の削除依頼の費用については、関連記事『削除請求の弁護士費用は?弁護士依頼で必要な着手金・報酬金の相場』でも解説しています。
投稿者の特定と損害賠償請求の弁護士費用はいくら?
誹謗中傷の発信者が誰なのかを特定するために、サイト運営側やインターネットプロバイダ側に対して情報開示を求める手続きを「発信者情報開示請求」といいます。
発信者情報は個人情報として厳格に保護されているので、任意のリクエストで応じてもらうことは難しく、法律に基づいて手続きを進めることがほとんどです。
発信者の情報開示請求にかかる弁護士費用相場
発信者情報開示請求の訴訟費用は、裁判所へ納める手続き費用として数万円、弁護士費用としては数十万円から100万円程度が相場とされています。
ただし訴訟を起こすためには、誹謗中傷の投稿に関するIPアドレス等の情報が必要です。そのため、まずはIPアドレスなどの情報を知るために裁判所へ仮処分申立てをおこなうケースが多く、この仮処分申立てにおいても別途弁護士費用が発生する法律事務所もあります。
また、仮処分手続きは担保金として10万円から30万円程度をいったん裁判所におさめなくてはいけません。正当な申立てであれば後に還付される金銭ではありますが、すぐにおさめられるように準備しておきましょう。
発信者情報開示請求の要点
まとめると、発信者の情報開示請求の流れは以下のようになります。
- サイトやSNSの管理者に、発信者の接続情報(IPアドレス等)を開示請求(仮処分申立て)
- インターネットプロバイダに、契約者情報(住所・名前等)を開示請求(発信者情報開示請求訴訟)
なお、改正プロバイダ責任制限法の施行により、開示請求の手間と費用負担が軽減される方法も選べるようになりました。
発信者情報開示請求の具体的な流れや費用については関連記事を参考にしてみてください。
損害賠償請求における弁護士費用相場
裁判外で直接相手方にアプローチする場合と、裁判手続きを使う場合では弁護士の活動内容や費用に違いが生じます。
そのため、どの方法で行うのか、またそれにはどのような費用が生じるか、担当弁護士に確認しておくことが大切です。
例えば、民事裁判をする場合には、訴額(相手方に支払いを求める金額)に応じて裁判所に収める印紙代が必要になりますので、その分の実費が計上されることになります。
ポイント
損害賠償請求とは別に、相手を「名誉毀損罪」などで刑事告訴することも考えられます。全ての誹謗中傷に対して刑事告訴ができるわけではありませんので、刑事告訴できる事案かどうかは、弁護士に相談して見通しをたてる必要があるでしょう。
誹謗中傷の弁護士費用に関するよくある質問
弁護士費用はいつ支払う?
弁護士費用の支払い方法は法律事務所の方針によって異なるため、必ず確認を取ってください。
たとえば、弁護士費用には「着手金」「報酬金」という項目がありますが、「着手金」については契約時に支払い、事後的に結果に応じた「報酬金」を支払うという方針の法律事務所もあるでしょう。
あるいは、事前に「預り金」を弁護士にわたし、事後に精算をするというシステムを採用している法律事務所もあります。
ケースによって費用は異なりますので、まずは相談を受けてみるのがおすすめです。また、複数の法律事務所から同じ条件で見積もりをとることも費用の目安・相場を知るには有効です。着手金はいくらか、完全成功報酬型なのかなど、確認しておくとよいでしょう。
誹謗中傷への削除は業者に頼むと安くできる?
法律上、報酬が生じる削除依頼は、本人かその代理人弁護士でなければすることができません。弁護士が対応してくれるのか、必ずチェックすることが必要です。
誹謗中傷の慰謝料はいくら請求できる?
誹謗中傷の慰謝料は、その誹謗中傷により名誉毀損を受けた場合、個人なら10万円から50万円、法人や企業であれば50万円から100万円程度といわれています。
名誉毀損ではなく侮辱罪と認定されると、慰謝料はやや下がる見込みです。
現在ネット上の誹謗中傷に対する慰謝料の金額は、決して多いとは言えません。そのため相手からの慰謝料で弁護士費用をまかないきれず、自己負担になる可能性もあるでしょう。
関連記事『誹謗中傷の慰謝料相場はいくら?損害賠償請求の流れと注意点をおさえよう』では、誹謗中傷における慰謝料相場を解説しています。
誹謗中傷の裁判費用は相手に請求できる?
発信者情報開示請求の弁護士費用は調査費用として請求でき、場合によっては全額加害者負担とできる可能性もあります。
ただし必ずしも全額とは言えず、一部認容にとどまる判例もある点には留意しておきましょう。
なお、誹謗中傷の投稿削除に関する仮処分申立てのとき、その弁護士費用は相手に請求できません。
誹謗中傷の弁護士費用は法律相談で聞いてみよう
弁護士費用は各法律事務所によって異なるため、まずは実際に法律相談で聞いてみることが大切です。
そして実際にかかる費用は弁護士費用だけとは限らず、裁判手続きを利用するなら別途用意しておきたい金銭もあるでしょう。
裁判手続きを利用するための手数料や、仮処分申立てにおける担保金など、弁護士費用の他にもどんな費用が必要になるのかを確かめておいてください。
誹謗中傷の弁護士費用について相手に請求したいという方は、まず誹謗中傷の投稿者を特定できるのかという見通しからたずねておくことをおすすめします。
ネットトラブルに詳しい弁護士を探したいという方は、以下のバナーより解説記事をお役立てください。
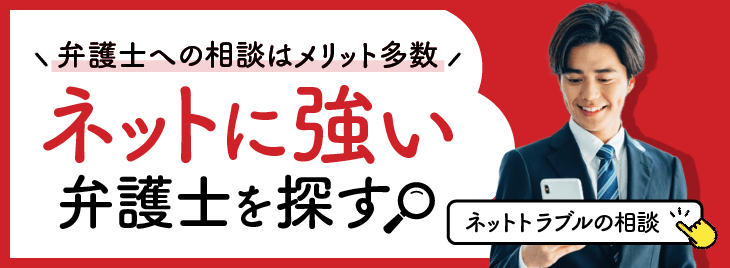
また、以下の関連記事も弁護士への相談メリットや具体的なサポート内容を解説中です。法律相談を検討している方はあわせてお読みください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了