子連れで別居したい!生活費や親権を守るための準備と手順
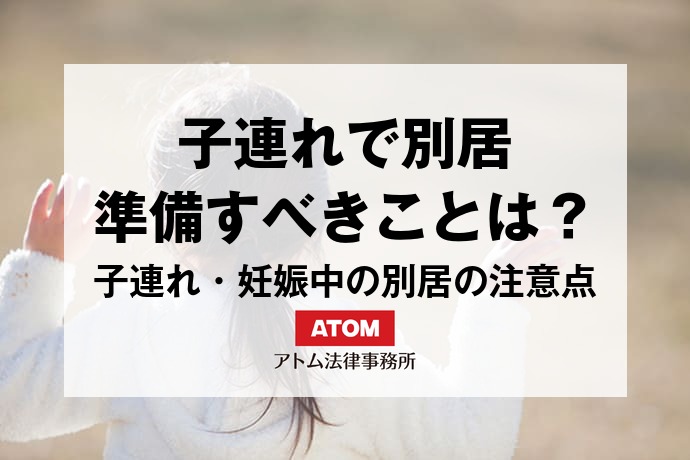
夫婦関係の悪化やDVにより子連れで別居、または妊娠中に別居を検討する際、最も重要なのは違法と判断されないための事前準備です。
感情的に家を出てしまうと親権や生活費で不利になるリスクがありますが、正しい手順を踏めば子連れ別居は法的に可能であり、当面の生活費(婚姻費用)も請求できます。
この記事では、親権と生活費を守りながら別居するための具体的な手順と注意点を弁護士が解説します。
目次
子持ち夫婦の別居が違法な連れ去りにならないための対策
子どもを連れて別居する際、最も注意すべきは違法な連れ去りと判断されないことです。
違法な連れ去りとみなされると、家庭裁判所で子の監護者指定や引渡しを求められ、親権争いで不利になる可能性があります。
違法な連れ去りと適法な別居の違い
子連れ別居が違法になるかは、以下の5つで判断されます。
| 違法になる可能性あり | 適法と判断されやすい |
|---|---|
| 普段世話をしていない親が連れ去る | 主に世話をしていた親が別居 |
| 何も告げず突然連れ去る | 話し合いか置き手紙で説明 |
| 連絡を完全に断つ | メール等の連絡手段を残す |
| 親権目的のみで連れ去る | DV・虐待から逃れるため |
| 暴力や脅迫を用いる | 平穏な方法で別居 |
違法な連れ去りは親権獲得で不利になるため注意
離婚を前提に別居したいと考えている方の中には、親権者の決定で不利にならないよう子どもを連れて家を出ようと思っている方も多いでしょう。
子どもを連れて別居する場合、違法な連れ去りをしないよう注意する必要があります。
子連れで別居した後、子の監護者指定及び子の引渡しを求める審判、それらの保全処分が申し立てられるケースは少なくありません。
違法な連れ去りをすると、裁判所は、相手方を子どもの監護者と指定し、子どもを相手方に引き渡すよう命じる判断をする可能性が高いのです。
子どもの違法な連れ去りの影響については、『子の連れ去りの対処法と親権への影響を解説』で詳しく解説しています。
違法な連れ去りにならないための対策
では、違法な連れ去りとならないために、具体的にはどうすればよいのでしょうか?
①まずは夫婦で話し合う
婚姻中は共同親権であるため、まずは夫婦で別居の子どもの監護をどちらが担うか冷静に話し合う必要があります。
合意できた場合は、後で相手方に否定されないように合意内容を書面化しておくのがおすすめです。
どのような内容の文書を作ればよいか不安な方は、アトム法律事務所が公開している別居合意書のサンプルを参考にしてください。
別居合意書の作成が難しければ、相手方が子連れでの別居に同意したことがわかるメールやLINEのやりとりをスクリーンショットに残しておきましょう。
②やむを得ない場合は置き手紙を残して別居する
合意が難しい場合、あなたが同居中に主として子どもの監護を担っていた立場であるなら、子どもを連れて別居するという結論もやむを得ないでしょう。
実務上、子の監護を主に担っていた者が、子どもを連れて別居したとしても、暴行等の社会的相当性を逸脱した手段を用いたのでない限り、違法ではないと考えられています。
その場合も、せめて置き手紙を残し、別居の理由や今後の考えについて説明しておくとよいでしょう。置き手紙のコピーをとっておくと、後で相手方から「妻は何も言わずに子どもを連れて家出した」と主張されたときに反論するための証拠として役立ちます。
関連記事
・別居したいときの切り出し方・伝え方|メールや置き手紙の例文を紹介
③相手方と連絡を断絶しない
別居後に相手方との連絡手段をすべて断絶してしまうと相手方を過度に刺激することになりかねず、離婚問題の解決も難しくなります。そのため、別居後もメールやLINEなどの連絡手段は残しておく方が穏当です。
相手方と直接連絡をとりたくないという方は、なるべく早めに弁護士に相談に行き、弁護士に連絡窓口となってもらうのが安心です。
ただし、DV事案の場合は、相手方に決して連絡先を教えてはいけません。別居前から弁護士や警察等に相談しておき、別居後の相手方との連絡はすべて弁護士を通して行うようにしてください。
子連れ別居で失敗しないための準備と持ち物
生活費は婚姻費用請求と児童手当で確保
子どもを連れて別居する場合、最も考えておかなければならない問題の一つが生活費です。
生活費を確保する重要な手段として、婚姻費用の請求と児童手当の受給手続きがあります。
相手に婚姻費用を請求する
婚姻費用とは、夫婦とその子どもの生活にかかる生活費を意味します。
収入の多い配偶者は、他方の配偶者に対し婚姻費用を支払う義務を負っています。離婚前提で別居中であっても、収入が低い方の配偶者は、相手方に対し、婚姻費用を請求できます。
婚姻費用は請求した時点から支払いを受けられるのが原則です。
そのため、婚姻費用を請求する一番のポイントは、婚姻費用を請求した事実と請求日付が残る方法で、できる限り早く支払請求することです。内容証明郵便や、弁護士による通知書、婚姻費用分担請求の申立てなどが請求の始期となります。
関連記事
・婚姻費用の相場は月10~15万円?別居・離婚調停の生活費請求を解説
児童手当の受給者を変更する
児童手当は、児童手当法に基づき、0歳から中学校卒業までの児童を養育している場合に、児童と生計を同じくする親に支給されるお金です。
通常、児童手当は生計中心者(収入の多い方の親)に支給されます。ただし、離婚協議中で両親が別居している場合は、その事実を証明できる書類を市区町村へ提出し、児童手当の認定請求を行えば、子どもと同居している親が児童手当を受給できるようになります。
離婚協議中で別居していることを証明する書類としては、以下のものが考えられます。
- 離婚協議を申し入れる内容の内容証明郵便の謄本
- 離婚調停の調停期日呼出状の写し
- 家庭裁判所における事件係属証明書
- 離婚調停の調停不成立証明書 など
DVのおそれがあるため住民票を異動できない場合は、次の資料を現在住んでいる市区町村に提出することで、子どもと同居している親が児童手当を受給できるようになります。
- 配偶者の暴力について確認できる資料
- 申請者と子どもが、社会保険上配偶者の扶養に入っていない(または申請者と子どものみ国民健康保険に加入しているなど)がわかる資料
参考
住居は実家・公営住宅など安全な転居先を確保
別居後の住居については、まずは実家を頼ることができないか相談してみましょう。
それが難しい場合は、民間の賃貸物件に入居できるよう仕事を見つけたり、ひとまず賃貸物件に入居してから公営住宅に優先入居できるよう手続きを進める方法が考えられます。
場合によっては、母子生活支援施設(児童福祉法により、18歳未満の子どもを養育している母子家庭や母子家庭に準ずる家庭の女性が子どもと一緒に利用できる施設)の利用について、現住所を管轄する福祉事務所に相談することも検討してみてください。
転校先には事情説明と連れ去り防止の要望
子どもを連れて別居した場合、相手方が転校先に突然やって来て子どもを強引に連れ去ってしまう可能性もゼロではありません。
このような事態を回避するため、転校先には、現在離婚協議中であり別居している配偶者がやってくるかもしれないこと、その際は決して子どもを引き渡さないでほしいことを伝えておく必要があります。
これに加え、DV事案の場合は、転校先または教育委員会に対し、転校前の学校に転校先が伝わらないようにしておくことも必要です。転校前の学校が転校先を知ってしまうと、別居の経緯を知らないまま、配偶者に転校先を伝えてしまうおそれがあるからです。
持ち物は現金と財産分与の証拠を準備
子どもを連れて別居する際は、持ち出す荷物を確認しておきましょう。必要な物の持ち出しを忘れてしまうと、相手方との間で荷物の持ち出しをめぐってやりとりをせざるを得なくなり、そのことで新たなトラブルが生じるケースはよくあります。
以下、子どもを連れて別居する際に持ち出しておきたい荷物をリストアップしていますので、参考にしてください。
子連れ別居の持ち物
- キャッシュカード、通帳
- 免許証、マイナンバー
- 子どもの学習や生活に必要なもの
- 医薬品
- 健康保険証
- 財産分与に必要な証拠
(不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書、通帳のコピー、生命保険証書、住宅ローンの残高証明書等) - 養育費や婚姻費用の請求に必要な証拠
(夫婦双方の源泉徴収票、課税証明書、確定申告書の控え等) - 慰謝料請求に必要な証拠
(不貞行為の場合:配偶者と不倫相手のLINE等でのやりとり、2人が写った写真や動画、DVやモラハラの場合:録音、録画、日記、メモ、診断書等) - 親権に関する証拠
(母子手帳、連絡帳、通知表、写真、育児日記、動画等)
関連記事
妊娠中に別居する場合の出産費用と親権のルール
ここでは、妊娠中に別居する場合の注意点について、出産費用、養育費、親権の3点について解説します。
別居中でも出産費用は婚姻費用として請求可能
別居中でも婚姻関係にあれば、婚姻費用として出産費用も請求できます。
ただし、離婚後に出産した場合は、元配偶者に出産費用の支払義務はないため出産費用の請求は難しくなります。
もっとも、元配偶者が任意に支払うことが自由であるため、出産費用の支払について一度話し合ってみると良いでしょう。
関連記事
・妊娠中の離婚|養育費や親権はどうなる?離婚したくなる理由は?
離婚後300日以内の出産は養育費の請求が可能
離婚後300日以内に生まれた子どもは、婚姻中に懐胎したものと推定され、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されます。したがって、母は父(元夫)に対し、養育費を請求できます。
これに対し、離婚後300日を超えてから生まれた子どもは、元夫の子どもとは推定されません。
つまり、このままでは法律上の親子関係はなく、養育費を請求することはできません。
養育費を請求するためには、任意認知または強制認知の方法をとる必要があります。認知を受ければ、母は父(元夫)に対し、養育費を請求できるようになります。
いずれの場合も、元夫が養育費の支払いに応じなければ、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てましょう。
離婚後に出産した子の親権者は原則として母親
離婚後300日以内に出生した場合は、母が親権者となります。親権者を父とするには、子どもが生まれてから、父母の協議で親権者を父と定める必要があります。
一方、離婚後300日を超えてから出生した場合は、母が親権者となります。父が子どもを認知した場合、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が親権者となります。
別居後の生活費を確保する方法は?
別居後に受け取れるお金には、離婚成立までの婚姻費用と、離婚後の養育費の2種類があります。
混同しやすいこれらの違いを整理しました。まずは、下表で「いつ・誰のために・いくら請求できるのか」という全体像を確認してください。
| 比較項目 | 婚姻費用 | 養育費 |
|---|---|---|
| 対象期間 | 別居開始から離婚成立まで | 離婚成立から子どもが自立するまで |
| 費用の内容 | 自分と子どもの生活費 | 子どもの養育にかかる費用のみ |
| 請求時期 | 別居直後 | 離婚協議時または離婚後 |
別居後の生活費(婚姻費用)を確保する方法
別居後の生活費である婚姻費用を確保するには、まずは当事者間で話し合うところから始めます。
婚姻費用の額は自由に決めることもできますが、調停や審判では裁判所が公開している算定表に従って決める方法が定着しています。アトム法律事務所の婚姻費用・養育費計算機を使えば、算定表に従って婚姻費用の相場が簡単に分かりますので、ぜひご活用ください。
合意できた場合は、別居合意書に金額や振込先などを明記しましょう。確実な支払を受けるには、強制執行認諾文言付き公正証書を作成すると良いでしょう。
合意できなかった場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てます。調停不成立の場合は、審判手続に自動的に移行し、裁判官が算定表に従って適切な養育費の金額を判断します。
関連記事
・養育費・婚姻費用算定表の計算方法|相場がおかしい時の対処法を弁護士解説
離婚後の養育費を確保する方法
養育費は、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用です。離婚後は、子どもを監護する親が、他方の親に請求することができます。
養育費の相場も、婚姻費用と同様、算定表に従って決められます。アトム法律事務所の婚姻費用・養育費計算機を使えば養育費の相場が簡単に分かります。
養育費の決め方も、まずは当事者間の話し合いが基本です。合意できた場合は、強制執行認諾文言付き公正証書等の法的拘束力のある文書を作成しましょう。
合意できなかった場合は、離婚調停の中で養育費についても話し合います。
調停不成立の場合は、離婚訴訟を提起してその中で養育費についても決めることになります。
養育費以外の点で合意できている場合は、養育費については別途調停や審判で決めることとし、離婚調停を成立させる方法も考えられます。
どちらの方法が良いかは個別の事情によって異なるため、弁護士に相談するのがおすすめです。
関連記事
子持ち夫婦の別居が子どもに与える影響と対策
離婚について子どもにきちんと説明する
別居による子どもへの影響を最小限に抑えるために大切なのは、子どもの発達度合いに応じた適切な方法で、離婚や別居について説明することです。
子どもに負担をかけまいと曖昧な言い方をしてしまうと、子どもはますます困惑し、場合によっては、自分のせいで両親が別居したのではと思い悩んでしまうおそれがあります。
父母は一緒に暮らせないと考えるようになったけれど、それは決して子どものせいではないことを伝えましょう。
その上で、今後も父と母であることは変わらないこと、父母とも子どものことを大切に思っていて、子どもの将来のために今後どうすればよいか話し合っているところだということを伝えてあげてください。
別居の子どもへの伝え方は『別居したいときの切り出し方・伝え方|メールや置き手紙の例文を紹介』でも解説しています。
子どもを紛争に巻き込まない
夫婦関係がどんなに悪化しても、子どもの面前で言い合いをするのは避けましょう。
また、「離婚についてどう思うか」「どちらの親と一緒に暮らしたいか」といった質問を子どもに直接するのはやめましょう。このような質問は、子どもにとってとても大きな負担となってしまいます。
子どものいる夫婦がどのように離婚の話し合いを進めれば良いかに関して、最高裁判所が公開している動画をぜひ参考にしてください。
参考
別居後に面会交流を行う
別居後、早い段階で子どもと別居親との面会交流が実現すると、子どもの心身の安定につながりやすくなるでしょう。
別居親としても、面会交流が実現すれば親子関係が続いていく安心感を得られ、親権者の決定や養育費の面で譲歩する気持ちになるケースが実務上よく見られます。
関連記事
専門家に相談してメンタルケアを行う
別居を始めとする離婚問題は、子どもにとって大きな心理的負担を与えます。子どものメンタルケアは、一人で悩まずに専門家に相談することが大切です。
特にDVによって子どもが心身ともに不安定になっている場合、医師や心理士、児童相談所等の専門機関を積極的に頼ってサポートを得るようにしてください。
子連れでの別居に関するよくある質問
Q. 相手が勝手に子どもを連れ戻しに来たらどうすればいい?
まず、学校や保育園に事情を説明し、相手方へ引き渡さないよう事前に依頼しておきましょう。
もし連れ去られてしまった場合は、速やかに家庭裁判所へ子の引渡しおよび監護者指定の審判と、これらの効力を確保するための保全処分を申し立てる必要があります。
違法な連れ去りがあった場合や、乳幼児が主たる監護者から引き離されることで心身に重大な影響が及ぶおそれがある場合などは、保全処分が認められやすい傾向があります。
Q. 専業主婦で収入がなくても子連れ別居はできる?
収入がない場合でも、婚姻中であれば相手に婚姻費用分担請求(生活費の請求)ができます。
あわせて、実家からの援助や行政の公的支援も活用し、別居後の生活基盤を整える準備を進めてください。
Q. 別居の置き手紙には何を書けばいい?
置き手紙は、無断家出ではないことを示す重要な証拠になります。
記載すべき主な内容は次のとおりです。
・離婚を前提に子どもと別居する意思
・現在の連絡先(または弁護士の連絡先)
・子どもが無事である旨
行き先を詳しく書く必要はありませんが、連絡手段を明示することで、自らの行動の正当性を示す資料になります。
子どもを連れて別居したい場合は弁護士に相談
離婚を前提に子どもを連れて別居したい場合、早い段階から弁護士に相談するのがおすすめです。
離婚する際は、財産分与や慰謝料請求など検討しなければならない問題が複数あります。しかも、未成年の子どもがいる場合は、親権者、養育費、面会交流など子どもの将来に大きな影響を与える問題も熟考する必要があるのです。
これらの問題について、弁護士に早期に相談しておけば、納得のいく形で離婚を実現することにつながります。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
