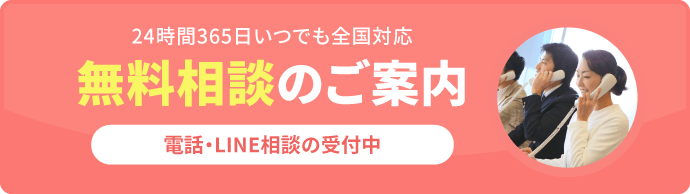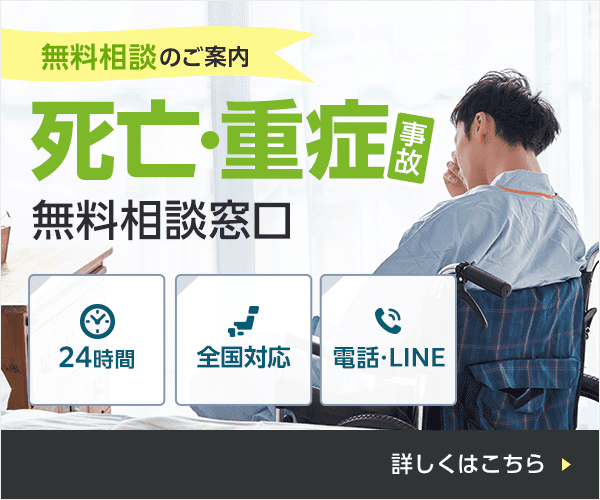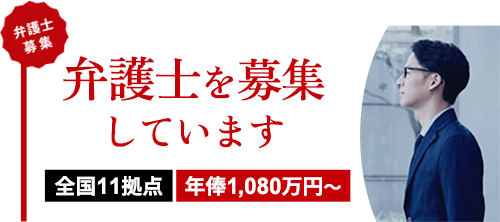医療過誤の問題点と取り組み|被害にあったときの解決策は?
更新日:

この記事でわかること
医療過誤によって重大な後遺症が残ったり、ご家族を亡くされたりした場合、どのような解決方法をとるのかが極めて重要です。
医療過誤の解決策のひとつには、医療機関側の民事責任を追及する方法があります。
民事責任の追及とは、簡潔に言えば損害賠償請求のことで、刑事責任や行政責任の追及は他に任せることになるのです。
刑事責任・行政責任・民事責任の主体
| 責任の種類 | 責任追及の主体 |
|---|---|
| 刑事責任 | 警察・検察や裁判所 |
| 行政責任 | 国 |
| 民事責任 | 患者本人や遺族 |
ただし医療過誤の民事責任の所在は曖昧な場合が多く患者側の立証が困難であること、医療訴訟は長期化する傾向があり患者の精神的な負担が大きくなることといった様々な問題があります。
本記事では、医療過誤による被害にあった時に生じる問題について弁護士が簡単に解説しています。
これからどうしたらいいのかと不安な方は、ぜひご確認ください。弁護士に無料で法律相談できる窓口も紹介しています。
医療過誤がかかえる問題と解決に向けた取り組み
医療過誤の被害にあったときには、どんな問題があるのかを知っておくことをおすすめします。
そして、医療過誤がかかえる問題は様々にありますが、なかにはその解決策が取れる場合がありますので、問題にぶつかったときには参考にしてみてください。
人為的なミスがゼロにならないという問題
病院では、患者の氏名・生年月日を点呼して患者を取り違えないこと、十分と思われる人員を配置して巡回にあたることなど、医療過誤防止の取り組みや努力が数多くおこなわれています。
それでも人為的なミスがゼロになることはなく、医療過誤という問題はなくなっていません。
人為的なミスの被害にあった場合の取り組み
ご自身のケースが医療過誤かもしれないと違和感をお持ちの場合は、「医療過誤のリスクは誰にでもある」ことを念頭に、医療機関側に問い合わせたり、法的対応を弁護士に相談したりすることが大切です。
技術は日々進化するなか、近年でも医師がCT結果を見落として肺がんが進行した医療過誤、カテーテル誤挿入によって新生児が負傷する医療過誤など、被害者の年齢や診療科を問わず発生しています。
医療過誤と医療事故の違い
医療事故と医療過誤は似たような意味合いをもちますが、とくに人為的なミスによって生じたケースを医療過誤ということが多いです。
一方の医療事故とは、医療行為とは直接的に関係しないケースや医療従事者本人に被害が生じたケースを含めて表現することが多いです。
例
- 医師が手術ミスをしたときには医療過誤、手術室で躓いて医師がケガをしたら医療事故
- 看護師が病棟の巡回を怠り患者が死亡したら医療過誤、看護師が巡回中に階段から落ちたら医療事故
もっとも、医療過誤も医療事故も法的に定義づけられたような言葉ではないので、明確な違いがあるとは言い切れません。
損害賠償責任の有無を判断することが難しいという問題
医師や病院に損害賠償責任が認められれば可能です。
医師や病院に損害賠償責任が認められる場合とは、医療過誤が不法行為または債務不履行があったために発生した医療過誤である場合をさします。
| 概要 | |
|---|---|
| 不法行為 | 故意または過失によって損害を被ること |
| 債務不履行 | 病院側と患者の間にある診療契約にもとづく義務が果たされなかったこと |
いいかえれば、不法行為や債務不履行が認められなければ、医師や病院に損害賠償責任を負わせることはできません。
よって、医療過誤の責任を問いたいときには、事故の発生原因や経緯を慎重に調べる必要があります。
しかし、カルテやCTの画像検査結果といった根拠資料は病院側に取り寄せるしかないという手間や、いざ記録を見ても一般の人には問題点を洗い出すことが難しいのが実情です。
病院側に責任を問えるのかどうかの判断は、法的な知識と医学的な知識の両方が必要になることが多いことも、医療過誤の問題点と言えるでしょう。
以下の関連記事では、医療過誤における損害賠償請求要件をより詳しく解説しています。医療過誤に置ける責任問題を追及したい方は、関連記事もあわせてお読みください。
損害賠償責任の検討が難しいことへの取り組み
患者の負った被害が医療過誤に当たるのかどうかは、カルテや検査結果などを調査して検討せねばなりません。
そうした調査は「医療調査」といわれ、医療過誤にまつわる損害賠償請求を進める上では重要な前準備の段階です。
患者ご本人や遺族でもカルテや検査結果を集めることはできますが、実際に損害賠償請求の検討をする上では法的知識が必要になります。
弁護士に医療調査を任せることで、損害賠償請求の検討を前へ進めることが可能です。
訴訟は長期化しやすく負担が大きいという問題
医療訴訟が長期化することで、訴えを起こす被害者側の精神的・金銭的負担は大きくなりがちです。
医療訴訟は、次のような理由から一般的に長期化する傾向があります。
| 時間がかかる理由 | |
|---|---|
| 専門性の高い内容 | 裁判所が医学的な専門知識まで把握が必要 |
| 証拠集めの困難さ | 収集手続きの難しさに加えて医学知識が必要 |
| 当事者間の主張の対立 | 事故原因や責任の所在に関する対立が多い |
| 手続きの複雑さ | 訴訟手続の複雑性や多くの手続きが必要 |
医療過誤の訴訟がかかえる問題への取り組み
裁判所によっては「医療集中部」へ医事関係訴訟の審理を集中させることや、判決までいかず和解を促すことなど審理期間を短くする取り組みがなされています。
それでも解決までに長期間がかかることは、いまだ医療訴訟の問題点なのです。
医療過誤の主な3つの解決策と和解の有効性
医療過誤の問題を解決する具体的な方法は、示談交渉、調停、裁判(民事訴訟)があげられます。
まずは示談交渉による解決を目指すことが多く、示談交渉が不成立となったときには調停、裁判(民事訴訟)といった解決方法を選択する流れです。
それぞれの方法には違いがあるので、どういった解決方法を望むのかを考えておくことが大切です。
示談・調停・裁判の違い
| 示談 | 調停 | 裁判 | |
|---|---|---|---|
| 費用 | 不要 | かかる | かかる |
| 期間※ | 短い | やや長い | 長い |
| 第三者 の介入 | なし | あり | あり |
| 納得感 | あり | あり | 判決次第 |
※示談の期間は争点の数によって長くなることもある
医療過誤の解決方法の特徴やメリット・デメリットを整理しましょう。
(1)示談交渉
医療過誤の解決方法には、病院側と示談交渉を行って示談金を受け取ることで解決する方法があります。
示談交渉とは、お互いに納得できる内容を話し合いで決めて争いを終結させることです。
医療過誤問題では、病院側にどのような責任があったのか、被害者が納得できる示談金はいくらなのかなどの内容が話し合われます。
示談は一度でも成立してしまうと、示談後の変更や破棄は原則として認められません。不本意な結果となってしまわないよう、示談は安易に合意しないようにしましょう。
示談のメリット
病院側との意見の対立が少ないほど早く示談が成立する可能性もあり、お互いが納得したうえでの示談締結のため、患者側も一定の成果を感じやすいです。
また調停や裁判のような手続き費用はかからないため、費用をおさえた解決方法といえます。
示談のデメリット
お互いの譲歩がないと成立しないため、片方だけの意見を押し通すことは難しいでしょう。また、当事者同士が納得すれば示談は原則成立するため、不当に低い示談金額で終わってしまうリスクもあります。
(2)調停
調停は、裁判のように勝敗を決めるのではなく、当事者同士が話し合い、お互いが納得できる解決策を見つけるための手続きです。
第三者の立場で、専門家である調停委員が間に入って、話し合いを円滑に進めるサポートをしてくれる方法になります。
調停のメリット
調停のメリットとしては、まず、訴訟に比べて比較的短期間で解決できる可能性が高い点があげられます。また、裁判のように費用がかさむこともなく、経済的な負担を抑えられるケースが多いです。
さらに、調停はお互いが納得できる解決策を見つけることが根底にあるため、裁判のように対立が激化してしまうのを防ぎ、当事者間の関係を修復する可能性も秘めています。
調停のデメリット
調停のデメリットは、調停委員の提案はあくまで提案であり、最終的に合意するのは当事者自身であるという点があげられます。
つまり、自分の希望する通りの解決にならない可能性もゼロではありません。また、調停は法的な手続きであるため、専門的な知識が必要になるケースもあります。
また裁判と比べると費用は少ないですが、示談交渉とはちがい手続きの費用が発生します。
(3)裁判(民事訴訟)
示談や調停など当事者間での合意による解決が難しい場合には、医療過誤の裁判による解決も検討が必要です。
原告が裁判所に訴状などを提出すると、裁判所によって審理期日が決められます。医療機関側からの答弁書が裁判所から送られてくると、口頭弁論が開始される流れです。
裁判のメリット
法的な観点から判断が受けられるので、法的に正当性の高い金額で解決できる可能性があります。
裁判のデメリット
専門性が高く、かかるコスト(時間・費用)も大きいことから、被害者にとって負担の大きい解決方法となります。
また、裁判をしたからといって患者側の主張が必ず認められるわけではないので、敗訴となれば一円も手にすることができません。
医療過誤はまず弁護士に相談
医療過誤での裁判を検討している方は、まず弁護士に相談をしてみましょう。いきなり裁判という方法ではなく、弁護士を交えて示談交渉をすることも有効です。
医療訴訟に向けて情報収集をしたいという方は、関連記事をお役立てください。
【コラム】医療過誤の解決方法には和解も多い
医療過誤の特徴として、裁判官から和解を促されることも多いことがあげられます。これは裁判上の和解といわれ、和解内容は確定判決と同じ意味を持つものです。
確定判決とは、裁判所が下した判決について、これ以上不服を申し立てることができなくなった状態をさします。つまり、その判決は最終的なものであり、当事者はその内容に従う義務が生じます。
医療過誤は勝訴率(認容率)が他の訴訟よりも低いことから、患者側にとって難易度が高いと思われがちです。
難易度が高いことは事実ではありますが、決して勝てないという意味合いではありません。
和解という解決方法によって、患者側にも一定の賠償が支払われている可能性は大いにあるのです。
医療過誤の問題を解決したい人に向けたQ&A
看護師に対しても医療過誤の責任は問える?
医療過誤が発生した原因に看護師の過失が認められるのであれば、看護師にも損害賠償請求することは可能です。
ただし、看護師個人の資力には限界があると考えられるので、損害賠償請求したところで回収が見込めない可能性が高くなります。そのため、看護師を雇用する病院に対しても使用者責任に基づく損害賠償請求が可能であることをおさえておきましょう。
医療過誤で損害賠償請求できるものは?
医療過誤の被害にあった場合、慰謝料、治療費、休業損害、逸失利益といった損害賠償費目について請求可能です。
医療過誤によってどんな損害が生じたのかで個別に算定する必要があります。
なお、示談交渉によって決まった金額を示談金といいますが、示談金と損害賠償金には大きな意味の違いはありません。
関連記事では示談金相場や慰謝料の請求額についての解説をしていますので、あわせてお読みください。
医療過誤問題の具体的なケースは?
医療過誤は事案ごとに複雑で、一言で言い表すのがむずかしいです。そこで、事案ごとに判例の内容を解説した「医療訴訟の判例集」を紹介します。
どのような場合なら病院側の過失が認められ、損害賠償金を受け取ることができたのかなど、判例の内容を簡単に解説しています。参考にご覧ください。
手術の同意書があっても損害賠償請求できる?
手術前に同意書にサインしていても、損害賠償請求できる可能性はあります。
医療過誤かもしれないと疑念を持っても、同意書にサインをしたことを思い出して対応に悩む方もおられます。しかし、医療過誤においては同意書の存在よりも、医師や看護師が適切に義務を果たしていたのかという点に注目して検討すべきです。
関連記事『「責任を負わない」免責同意書は無効?手術ミスやスポーツ事故での効力』では同意書の効力についてわかりやすく解説しています。
医療過誤の問題は弁護士に相談すべき
弁護士に相談すると具体的な解決策がわかる
医療過誤問題に直面すると、法律の知識がないと適切な解決に導くのはむずかしいでしょう。弁護士に相談すれば、解決につながる方法について具体的なアドバイスがもらえます。
医療過誤問題を解決するにあたっては、医療機関側の過失調査・医療過誤に関する証拠の収集・医療機関との交渉を行う必要があります。このような対応を弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人となって対応を進めてくれるのです。
医療ミスの示談・訴訟に強い弁護士に相談|医療事故は弁護士選びが重要
医療過誤問題を依頼する弁護士費用の相場
弁護士費用は弁護士が個々に設定できるものなので、依頼する弁護士ごとに費用が変わってきます。
依頼する前には、どのくらいの費用が必要なのか見積もりをとるようにしてください。
多くの弁護士は活動ごとに費用を設定しており、法律相談料・着手金・報酬金・日当・諸経費などの合計が弁護士費用となる場合が多いでしょう。
医療過誤の弁護士費用|医療訴訟までいくと高額になる?着手金無料の真実
医療過誤問題を無料で受け付ける相談窓口
医療過誤について示談や訴訟といった具体的な解決方法を実行にうつしたいときには、被害者本人や遺族の代理人となれる弁護士への相談・依頼が最適です。
医療過誤によって重大な後遺障害が残ったりご家族を亡くされたりした場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。
無料相談の予約受付は24時間いつでも対応中です。以下の相談窓口よりお問い合わせください。
無料法律相談ご希望される方はこちら
医療過誤・医療ミスの相談窓口を探している方は、弁護士や公的機関など幅広い相談先から検討しましょう。関連記事『医療事故の相談窓口|弁護士に無料で法律相談したい!公的機関には何がある?』もお役立てください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了