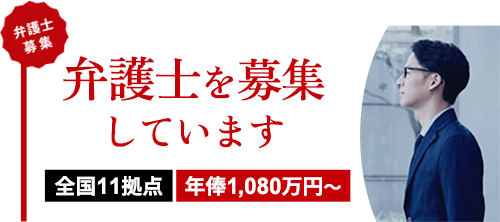医療過誤の損害賠償請求要件と方法|医師・病院に問うミスの責任とは?
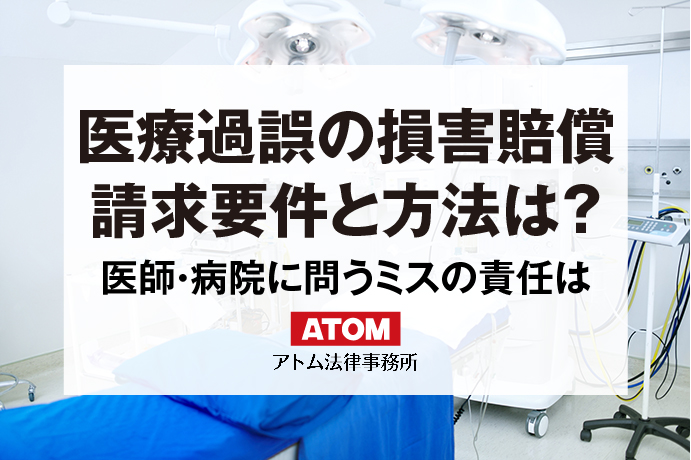
この記事でわかること
医療過誤・医療ミスの被害にあったときには、医師や病院などに対して損害賠償請求を行うことがほとんどです。
しかし、医療過誤の場合、「誰に・どのような根拠にもとづいて・どのくらいの金額の損害賠償請求が可能なのか」について、理解するのは容易ではありません。
また、そもそも医療過誤による損害賠償請求は、医師や病院側の過失によって実際に損害が生じていることが必要です。
本記事では、どのような医療過誤で損害賠償請求が可能なのかといった基本的なことから、損害賠償請求する相手や方法などについて解説していきます。
目次
医療過誤・医療ミスとは?
医療過誤とは、医療従事者の過失によって患者に被害が生じた事故のことであり、医療ミスともいわれます。
医療過誤により、患者の状態の悪化や後遺症の発生、死亡に至ることもあります。
医療過誤の具体例は、以下の通りです。
- 手術について医師が説明義務を怠り、後遺症が残った
- 手術中に切開する部分を間違えたために後遺症が残った
- 誤って投与すべきでない薬を投与してしまい、症状が悪化した
- 医師の緊急対応が遅れたために死亡した
医療過誤で損害賠償請求できる要件
医療過誤で損害賠償請求する場合、「医師や病院に債務不履行や不法行為があった」「医師や病院の債務不履行・不法行為によって損害が生じている」要件を満たすことが原則です。
医療過誤の要件
- 医師や病院の債務不履行や不法行為(過失がある)
- 医師や病院の債務不履行・不法行為によって損害が生じている
(1)医師や病院の債務不履行や不法行為(過失がある)
医療過誤における損害賠償請求は「医師や病院の債務不履行や不法行為があった場合」に限られます。
債務不履行
医師と患者の診療契約上の注意義務に違反したことで、患者に症状悪化あるいは死亡といった損害を負わせたときには、医療過誤の損害賠償請求の根拠になります。
不法行為
不法行為とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害されることです。
| 不法行為 | 内容 |
|---|---|
| 故意 | どのような結果が起こるのか理解していながら、わざとする行為のこと |
| 過失 | どのような結果が起こるのか予想しておらず、不注意で起きたミスのこと |
医療過誤における不法行為としては、医師や病院の過失について争われることが多いので、本記事では過失を基本にして解説を進めます。
注意義務に違反していたかが争点となりやすい
医療過誤において医師や病院に過失があったかどうかは、医療に携わるものとしての注意義務を果たしていたかという点が重要です。
医療に携わるものとしての注意義務に違反があったかどうかは、「当時の臨床医学の実践において医療水準にもとづいた医療行為がなされていたのか」という点で判断されます。もっとも、医療水準といっても以下のようなさまざまな事情を考慮して決める必要があります。
- 医療機関の特徴
医療機関が最先端医療を行う大学病院と町の診療所では医療水準が異なる - 所在地域の医療環境
都市部と地方では治療法の普及程度が異なる
債務不履行も不法行為責任もどちらも立証責任は患者側にあります。弁護士に事情を相談して、法律の専門家の観点から法的根拠を検討してもらいましょう。
こうした損害賠償請求の法的根拠については、本記事内「医療過誤で損害賠償請求する相手と法的根拠」もあわせてお読みください。
(2)医師や病院の不法行為によって損害が生じている
医師や病院の不法行為と患者の死亡・後遺症などという結果の間に、因果関係がなければ損害賠償請求することはできません。
因果関係を簡単にいうと、「医療過誤がなければ、生存していたり健康なままであったことがほぼ間違いない」ことです。
たとえば、救急車で緊急搬送された患者が病院に到着した後に行われた手術でミスがあった場合を考えてみます。
患者に行った手術において医師の手術ミスがあったとしても、病院に到着した時点ですでに患者が死亡していた場合であれば、医師の過失という不法行為と患者の死亡という結果の間には因果関係がないことが分かるでしょう。
このような因果関係は、損害賠償を請求するうえで必要な法律上の要件となるのです。
医療過誤における損害賠償請求の相手や内容
医療過誤で損害賠償請求する相手と法的根拠と責任
医療過誤で損害賠償請求する場合、請求相手は医師個人または病院です。
医師個人または病院に対して、以下のような法的根拠により損害賠償請求を行うこととなります。
損害賠償請求の法的根拠
- 不法行為
医師の過失により損害が生じたことを原因とする損害賠償請求 - 債務不履行
医師または病院が医療契約に基づいた義務を果たせず、損害が生じたことを原因とする損害賠償請求 - 使用者責任
病院が使用する医師が患者に対して不法行為により損害を生じさせた場合に、病院に対して行える損害賠償請求
勤務医である医師個人に損害賠償請求を行っても賠償金を支払えない可能性が高いです。
そのため、基本的には医師を雇用する病院に対して債務不履行や使用者責任を根拠とした損害賠償請求を行うこととなるでしょう。
医師個人と病院の両方に請求が可能であっても、二重取りは認められません。具体例でいえば、病院からも医師からも治療費を受け取るということはできないのです。
医療過誤で請求可能な損害賠償項目は?
医療過誤で請求可能な損害賠償項目は、以下のようなものとなります。
- 治療費用
治療のために必要となった投薬代、手術代、入院費用など - 休業損害
治療のために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償 - 後遺障害逸失利益
医療過誤により後遺障害が残ったことで生じる将来の減収に対する補償 - 死亡逸失利益
医療過誤により死亡したことで将来得られるはずの収入が得られなくなったことに対する補償 - 葬儀費用
葬儀代、仏壇購入費、墓石建立費など - 入通院慰謝料
医療過誤によるケガを治療するために入通院を行ったことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料 - 後遺障害慰謝料
医療過誤により後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料 - 死亡慰謝料
医療過誤により死亡した事故とで生じる精神的苦痛に対する慰謝料 - その他
入通院交通費、入通院付添費、入院雑費、装具購入費用など
以上のような項目をすべて合計したものは損害賠償金と呼びますが、示談交渉で決まった損害賠償金は示談金とも呼ばれます。
『医療事故の示談金相場はいくら?内訳と示談交渉の流れや賠償金との関係を解説』の記事では示談金の内訳や相場、計算方法などについて解説していますので、あわせてご確認ください。
医療過誤による損賠賠償請求をおこなうためにすべきこと
医療過誤の賠償賠償請求のために、まずは医療調査による証拠の収集が必要です。
具体的には、診療記録や検査結果などを調査し、事実関係を把握します。
これらの記録は病院が保管しているため開示請求が必要となりますが、改ざんの恐れがあることに注意が必要です。
改ざんの恐れがある場合には、弁護士に依頼したうえで証拠保全を行うことをおすすめします。
証拠保全は裁判所を通じて、病院から証拠を確保する手続きです。
この他に、協力してくれる医師の医療過誤の有無に関する意見書を用意するということも効果的でしょう。
医療調査についてより詳しく知りたい方は『医療調査の目的や内容とは?弁護士に任せる費用やメリットがわかる』の記事をご覧ください。
医療過誤で損害賠償請求する3つの方法
医療過誤で損害賠償請求する場合、「示談交渉」「調停」「医療訴訟」という3つの方法が用いられます。それぞれどのような請求方法なのかみていきましょう。
医療過誤の損害賠償請求方法
- 示談交渉
- 調停
- 医療訴訟
(1)医師や病院との示談交渉
医療過誤をはじめ、多くの民事上の紛争は示談交渉から損害賠償請求をはじめることになるでしょう。
示談交渉とは、民事上の紛争ごとに関して紛争相手との話し合いによって解決を図る方法をいいます。
つまり、医療過誤における示談交渉とは、医師や病院を相手にして話し合いを行うことです。生じた医療事故では誰にどのような責任があり、損害賠償金をどのくらい受けとれば被害回復につながるのかといった内容を話し合います。
調停や訴訟といったほかの請求方法とちがって、示談交渉は当事者同士の話し合いなので特に費用はかかりません。また、当事者双方が合意すれば示談は成立するものなので、比較的、短い時間で解決するといえます。
示談交渉のメリット
- 費用をおさえられる
- 短い時間で解決できる
(2)第三者を話し合いに入れた調停
医療過誤をはじめ、民事上の紛争ごとについて示談交渉が決裂すると、調停によって損害賠償請求を行うケースが多くなっています。
調停とは、民事上の紛争ごとに関する話し合いに第三者が介入して解決を図る方法をいいます。第三者が介入するだけで、調停は話し合いである以上、当事者間の合意が必要です。
話し合いに介入する第三者としては、裁判所とADR機関が代表的な存在です。
(3)裁判所を利用した医療訴訟
医療過誤をはじめ、民事上の争いごとについて示談交渉でも調停でも解決しない場合、訴訟によって損害賠償請求を行うことになるケースが多いでしょう。
訴訟とは、民事上の紛争ごとに関して裁判所が判決を出すことで解決を図る方法をいいます。
判決は裁判所が医療過誤に関する損害賠償の金額を確定させることです。示談や調停の当事者同士による話し合いとは違い、訴訟は裁判所が当事者双方の主張を聞いたり、証拠を確認したりして、判決が言い渡されます。
そのため、被害者の主張がすべて認められるとは限りませんし、損害賠償金をまったく受けとれない可能性もあることを理解しておく必要があるでしょう。
和解による解決という選択肢
また、判決が言い渡される前に裁判官から和解を促され、そこで訴訟が終了することもあります。
訴訟は審理期間が長引くことが予想されるので、損害賠償金を受けとるまでに時間がかかる可能性が高いことに注意せねばなりません。
その点、和解で終了すれば、訴訟よりも比較的早く損害賠償金を受けとることができるでしょう。
関連記事では、医療訴訟の流れや訴訟時に裁判所に支払う費用について解説しています。
医療訴訟の関連記事
【コラム】損害賠償責任(民事責任)は刑事責任とは別もの
病院や医師が負う損害賠償責任は民事上の責任、つまり損害をカバーするための金銭を支払うというもので、犯罪行為の責任を負わせるものではありません。
犯罪行為の責任は刑事責任といい、警察や検察の捜査・判断を経て、最終的に裁判所が量刑を決める流れです。
医療過誤の刑事責任を問いたいときは、警察・検察に対する被害届の提出や刑事告訴を検討してください。民事責任と刑事責任の違いについては、下記関連記事でくわしく解説しています。
医療過誤で損害賠償が認められた判例集
医療過誤で損害賠償が認められた誤診に関する判例と手術ミスに関する判例を紹介します。
良性腫瘍を乳がんだと誤診して乳房を不必要に切除した
乳がんの誤診を受けたため、全摘出によって右乳房を失い、外傷後ストレス障害(PTSD)を患うなどの損害を受けたとして、病院を経営する医療法人に対する損害賠償を求めた事例を紹介します。(那覇地方裁判所沖縄支部 平成16年(ワ)第396号 損害賠償請求事件 平成20年2月28日)
右乳腺のしこりが癌であると医師に診断されたため右乳房のすべてを摘出したが、術後に病理組織検査したところ、良性腫瘍であることがわかりました。
腫瘍が癌の疑いがあるにとどまり、良性の可能性もあるにもかかわらず、必要な検査を十分に行わなかったとして、裁判所は病院側の過失と被害者側の請求の一部を認めています。
もっとも、誤診で乳房を失ったことによりPTSDにり患していると被害者が主張した点について、裁判所は因果関係がないとして否定しています。
誤診に関する訴訟で認められた損害賠償金額
| 金額 | |
|---|---|
| 入院雑費 | 2万5500円 |
| 休業損害 | 52万円 |
| 入通院慰謝料 | 30万円 |
| 乳房喪失等による慰謝料 | 350万円 |
| 弁護士費用 | 43万円 |
| 損害合計額 | 477万5500円 |
乳房再建費・逸失利益・後遺障害慰謝料については認められませんでした。
こちらの関連記事『誤診で病院を訴えるなら医療訴訟?見落としの損害賠償と診断ミスの相談先』でも、誤診や病気の見落としに関する判例を紹介していますので、関心のある方はあわせてご確認ください。
手術ミスにより排便障害の後遺障害が残った
腹腔鏡補助下直腸切除術で手術ミスがあり、S字結腸と直腸の吻合部付近に穿孔が生じ、汎発性腹膜炎になったとして、医師や病院に対する損害賠償を求めた事例を紹介します。(水戸地方裁判所土浦支部 平成12年(ワ)第206号 損害賠償請求事件 平成20年10月20日)
医療事故後、被害者は外出に不安を覚えるほどの排便障害に悩まされていました。
後遺障害の程度について、原告側は後遺障害等級7級相当を主張していましたが、最終的に後遺障害等級11級相当であると裁判所に判断されています。
手術ミスに関する訴訟で認められた損害賠償金額
| 金額 | |
|---|---|
| 付添看護費 | 74万1000円 |
| 入院雑費 | 14万8200円 |
| 通院交通費 | 6000円 |
| 休業損害 | 163万3315円 |
| 逸失利益 | 409万4092円 |
| 入通院慰謝料 | 250万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 331万円 |
| 弁護士費用 | 124万円 |
| 損害額合計 | 1367万2607円 |
こちらの関連記事『手術失敗?裁判例から手術ミスの損害賠償を知る』でも手術ミスに関する判例を紹介中です。関心がある場合はあわせてご確認ください。
医療過誤における損害賠償に関する疑問
医療過誤と損害賠償金の請求に関する疑問を集めました。
Q1.損害賠償の金額は算定基準がある?
損害賠償の金額は一定の算定基準を用いて計算されるのが通常です。
算定基準は交通事故の損害賠償案件で積み重ねられてきたものを利用することとなるでしょう。
たとえば慰謝料であれば、裁判でも認められうる弁護士基準に基づいて算定・請求を行います。
関連記事『医療過誤の慰謝料相場は?病院に慰謝料を請求する前に知っておきたい基礎知識』では医療事故における慰謝料の相場やこれまでの判例を解説しています。
Q2.医療過誤の損害賠償金は低額?
医療過誤の被害者は、もとから何らかの病気をもった患者である可能性が高いので、損害賠償額から有していた病気による影響分について差し引かれる場合があります。
医療過誤があってもなくても、病気があったのだから医療過誤による損害ではないと判断されてしまうことがあるのです。
このような点を交通事故の損害賠償事案などと比べると、損害賠償金が低額であるといえるかもしれません。
Q3.多くの医師や病院が加入する賠償責任保険とは?
医師や病院は業務上の過誤によって生じた損害賠償責任のリスクに備えて、損害賠償責任保険に加入していることが多いです。
- 日本医師会医師賠償責任保険
日本医師会・都道府県医師会・保険会社の3者で提供する日本医師会会員向けの保険で、開業医の場合は自動加入となる - 病院賠償責任保険
各保険会社が提供する病院向けの保険商品 - 医師賠償責任保険(勤務医賠償責任保険)
各保険会社が提供する医師向けの保険商品
医師や病院が以上のような保険に加入していても、示談交渉に関しては医師や病院が行うのが原則です。保険会社が示談交渉の相手となることはありません。
もっとも、医師や病院が代理人として弁護士を立ててきた場合、示談交渉の相手は弁護士となります。
弁護士をつけていないと、ご自身だけで弁護士相手に交渉の対応にあたらなければなりません。弁護士相手の示談交渉が不安な場合は、ご自身も弁護士を選任することをおすすめします。
Q4.医療過誤で賠償請求できる時効はいつまで?
医療過誤で損害賠償請求できる時効は、医療過誤が起こった時期と損害賠償請求の根拠によって異なります。
不法行為にもとづく損害賠償請求の場合、事故発生が2020年3月31日以前であれば「損害および加害者を知った時から3年間」「医療過誤の時から20年間」、2020年4月1日以降であれば「損害および加害者を知った時から5年間」「医療過誤の時から20年間」となります。
不法行為にもとづく損害賠償請求の時効
| 事故発生時期 | 不法行為 |
|---|---|
| 2020/3/31以前 | ・損害および加害者を知った時から3年間 ・医療過誤の時から20年間 |
| 2020/4/1以降 | ・損害および加害者を知った時から5年間 ・医療過誤の時から20年間 |
債務不履行にもとづく損害賠償請求の場合、事故発生が2020年3月31日以前であれば「権利を行使することができる時から10年」、2020年4月1日以降であれば「権利を行使することができることを知った時から5年」「権利を行使することができる時から20年」となります。
債務不履行にもとづく損害賠償請求の時効
| 事故発生時期 | 債務不履行 |
|---|---|
| 2020/3/31以前 | 権利を行使することができる時から10年 |
| 2020/4/1以降 | ・権利を行使することができることを知った時から5年 ・権利を行使することができる時から20年 |
医療過誤に関する時効についてさらに詳しくは、こちらの関連記事『医療訴訟の時効は医療ミスから20年?それより前に時効が成立する場合とは?』で解説しています。時効がいつからはじまるのか、時効を延長させる方法などがわかるのであわせてご覧ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了