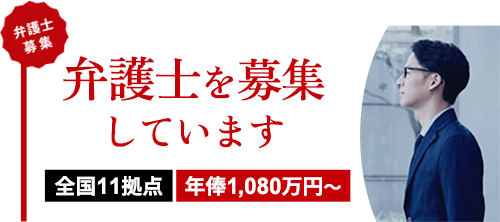医療訴訟は勝てない?勝訴率にあらわれない示談や和解にも注目
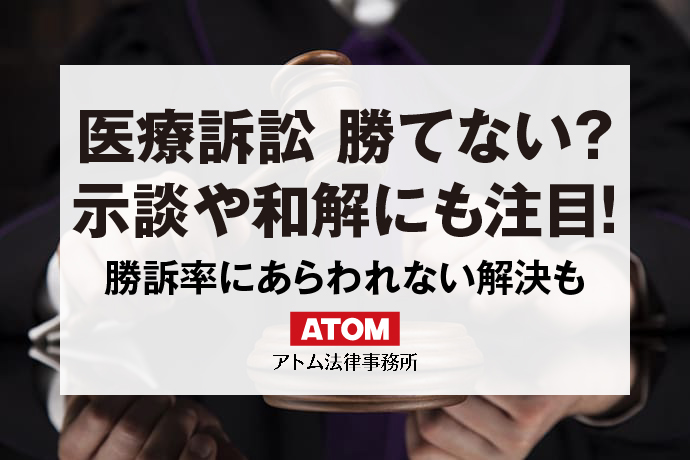
この記事でわかること
「医療訴訟をしても勝てないのなら提訴しない方がいいのかな…」
「医療訴訟をして負けるのが怖いから提訴に踏み切れない…」
医療ミスの損害賠償請求の訴訟を提起しても患者側はなかなか勝てないと言われることが多く、実際の統計でも医療訴訟の「勝訴率」は通常訴訟に比べて低くなっていることは事実です。
しかし、医療訴訟の勝訴率が低いことは、必ずしも患者側の損害賠償請求が認められないことや患者側の敗訴を意味するわけではありません。
この記事では、患者側の損害賠償請求は「医療訴訟の勝訴率」だけに注目すべきではないこと、示談や和解が選ばれる理由を紹介します。医療機関への損害賠償請求、医療訴訟を検討している方のお役に立てば幸いです。
なお、本記事における「勝訴」は、患者側の主張が全てまたは一部認められたもの(認容)をさします。患者側の全面勝訴だけでなく一部勝訴も含む点をご了承ください。
目次
医療訴訟の勝訴率と現況|勝つためのポイント
医療訴訟の勝訴率
令和5年、医療訴訟の勝訴率(認容率)は20%でした。
認容とは医療事故の患者側の主張が全てまたは一部認められたものをいいます。患者側の主張が一部でも通ることを「勝訴」とすると、医療事故の勝訴率は20%といえます。
下表に示す通り、医療事故の勝訴率はおおむね20%前後で推移しており、通常訴訟と比較すると勝訴率は決して高くありません。
地裁民事・医事関係訴訟の認容率
| 年 | 医療訴訟 | 通常訴訟 |
|---|---|---|
| 令和元年 | 17.0% | 85.9% |
| 令和2年 | 22.2% | 86.7% |
| 令和3年 | 20.1% | 84.3% |
| 令和4年 | 18.4% | 84.3% |
| 令和5年 | 20.0% | 86.3% |
最高裁判所 医事関係訴訟委員会について「医事関係訴訟に関する統計」より作成/令和5年は速報値
医療訴訟で勝てない理由
医療訴訟において患者側が勝てない理由としては、主に以下の3点といえます。
- 医療訴訟では医学知識も必要
- 協力してくれる医師(協力医)が必要
- 証拠の多くを病院側が有している
医学知識が必要
医療訴訟を行うのであれば基本的に弁護士に依頼することとなりますが、医療訴訟では法律だけでなく医学の専門知識が不可欠です。
しかし、医学の部分について適切に対応できる弁護士は限られているため、弁護士に依頼しても勝てるとは限りません。
協力医が必要
医療訴訟において勝訴するためには、専門的な意見の提示について協力してくれる医師(協力医)が必要になります。
協力医が作成した、病院側の過失を証明する意見書が有力な証拠となるでしょう。
しかし、同業者を批判することになるため、協力医となってくれる医師を探すことは非常に困難です。
証拠が病院側にある
医療訴訟において必要となる証拠の多くは、被告である病院側にあります。
そのため、証拠を収集することは容易ではなく、隠蔽や改ざんの恐れもあるのです。
カルテ等の証拠を収集するために専門的な手続きも必要となります。
医療訴訟は勝訴率だけが全てではない
令和5年の医療訴訟の勝訴率(認容率)は20%となっています。
数値を見ると、患者側は医療訴訟で勝てないといった印象を受ける方も多いかもしれません。
しかし、損害賠償請求の方法には、示談や調停、和解などの訴訟による判決以外にも複数あり、それらの結果は勝訴率には含まれていないのです。
つまり、患者の損害賠償請求が認められる可能性が20%というわけではないことを留意しておきましょう。
医療事故における損害賠償請求の方法
医療事故の損害賠償請求の方法は訴訟だけではありません。たとえば示談交渉であれば、訴訟費用もかからず、訴訟するよりも早期に解決できるといったメリットがあります。
ただし示談交渉においても病院や医師に損害賠償請求しうる事案かどうかは慎重に判断すべきです。
関連記事『医療過誤の損害賠償請求要件と方法|医師・病院に問うミスの責任とは?』では医療過誤における損害賠償請求の要件や方法をまとめていますので、あわせてお読みください。
裁判で勝つためのポイント
患者側の主張が認められることで、損害賠償を受けることができます。
ここからは裁判で勝つ、つまり患者が賠償金を得るための要素をみていきましょう。
医療訴訟で勝つには事前の十分な医療調査が大切
医療訴訟では、提訴に先立って、事実関係を主張・立証するための証拠や医学的な知識などを調査する医療調査という手続きが非常に大切となります。
医療機関への損害賠償請求が認められるには、医療機関側に過失があったこと、その過失によって患者に損害が発生したことを主張・立証しなくてはなりません。
しかし、医療訴訟では、通常訴訟とは異なり、患者側がどのような医療行為を受けたかなどの事実関係を主張・立証するための証拠が手元になく、過失や因果関係の有無の判断に医学知識が必要となるという特殊性があります。
そのため、医療調査によって証拠の収集や、必要となる医学知識の調査を行うこととなるのです。
具体的には、カルテなどの診療記録、CT・MRI・レントゲンなどの画像検査記録といった客観的な資料をカルテ開示や証拠保全という手続きなどにより証拠収集します。
その上で、医学文献や過去の類似裁判例を調査して、訴訟をした場合の勝訴の可能性や争点となる部分についての見通しを立てます。
さらに、協力医を探し出して、訴訟で証拠として提出するための意見書の作成を依頼したり、医療機関側に説明会実施の申し入れをしたりします。
医療調査のや医療訴訟の手続きをより詳しく知りたい方や、これまでの医療訴訟の判例を詳しく知りたい方は、関連記事も参考にしてください。
弁護士に依頼してサポートを受ける
医療訴訟を行う際には、弁護士に依頼を行いましょう。
医療裁判は長期化する傾向があり、ご家族や本人だけで対応すると大きな負担になります。
弁護士は患者の代理人として交渉可能です。裁判に必要な書類の作成や証拠の収集などのサポートを受けられるので、患者やご家族の負担は大きく軽減されます。
さらに、医療機関側は弁護士を立ててくる可能性が高いでしょう。患者側も弁護士を付けることで、より対等な立場で対応することをおすすめします。
このように医療訴訟において弁護士の役割は大きいものです。
関連記事では弁護士に依頼するメリットをより詳しく紹介しています。今は弁護士への相談・依頼を迷っている方も、弁護士に依頼することで何が変わるのかを知っておくと安心です。
あわせてよみたい関連記事
医療訴訟の注意点
裁判を起こす前に示談交渉を
医療ミスに対する損害賠償では、まず示談交渉による解決を目指すことが多いです。
示談とは、裁判所を介さずに当事者同士で話し合って損害賠償内容を決める方法です。
示談成立にはお互いに納得して合意することが要件になるので、自分の主張だけが通るわけではありません。そのため、最初に請求した金額から多少の減額はやむをえないでしょう。
それでも示談が選択肢として上がる理由は、訴訟費用などの経費・手数料が不要であること、合意さえできれば解決なので訴訟と比べて早期に解決できる可能性があるからです。
関連記事
- 医療事故における示談交渉の流れや示談金の相場が知りたい
『医療事故の示談金相場はいくら?示談金の内訳や示談交渉の流れを解説』 - 医療事故で請求できる慰謝料の相場について知りたい
『医療過誤の慰謝料相場は?病院に慰謝料を請求する前に知っておきたい基礎知識』
医療訴訟は長期化しやすい
令和5年、医療訴訟の平均審理期間は26.4ヶ月(約2年と2ヶ月)でした。
あくまで医療訴訟にかかる期間となるため、医療ミスの発生あるいは医療ミス発覚からの期間は、さらに長いものと予想されます。
また、判決内容に納得がいかない場合には、さらに上級の裁判所で審理が必要となるでしょう。
判決による解決までが長期間となりやすいので、他の方法による解決を検討する必要性が高いといえます。
医事関係訴訟事件の平均審理期間
| 年 | 審理期間 |
|---|---|
| 令和元年 | 25.2ヶ月 |
| 令和2年 | 26.1ヶ月 |
| 令和3年 | 26.7ヶ月 |
| 令和4年 | 26.4ヶ月 |
| 令和5年 | 26.4ヶ月 |
最高裁判所 医事関係訴訟委員会について「医事関係訴訟に関する統計」より作成/令和5年は速報値
医療訴訟中に和解よる解決がありうる
医療訴訟においては、訴訟中に和解による解決を検討することが多いでしょう。
和解とは、裁判所から提示されるひとつの解決方法で、判決とは別物です。
裁判が進むと、裁判所から和解案を提示されることがあります。その和解案を受けて、お互いが納得して合意した場合には、和解が成立する流れです。
和解が成立しなかった場合には、裁判所から判決が言い渡されます。
和解内容は判決と同じ効力をもつものです。そのため原則として、後から内容の変更や破棄はできません。和解内容をどちらかが守らない場合には、強制執行の手続きを取ることが可能です。
医療訴訟において和解を行うべきか
患者側が起こした医療訴訟の終結方法をみてみると、判決ではなく、和解により終結することが多いことが分かります。
医療訴訟は和解で終わることが多い
令和5年は医療訴訟の終局件数が764件あり、そのうち54.5%を占める416件が和解によって紛争を解決しています。
判決は276件(約36.1%)となっており、医療訴訟においては判決で決着するより和解で決着するケースが多いのです。
医療訴訟の終結方法
| 年 | 判決 | 和解 | その他 |
|---|---|---|---|
| 令和元年 | 29.7% | 55.7% | 14.6% |
| 令和2年 | 30.5% | 53.3% | 16.2% |
| 令和3年 | 32.6% | 52.5% | 14.9% |
| 令和4年 | 31.8% | 52.9% | 15.3% |
| 令和5年 | 36.1% | 54.5% | 9.4% |
最高裁判所 医事関係訴訟委員会について「医事関係訴訟に関する統計」より作成/令和5年は速報値
医療訴訟が和解で終わりやすい理由
医療訴訟が和解で終わりやすい理由としては、以下のようなものが考えられます。
- 早期の解決が期待できる
- 病院側に医療ミスがあったことが明らかにならない
- 再発防止条項などを盛り込める
判決がなされる前に和解で終了となれば、裁判を行うよりも早期の解決が期待できます。
病院側としても、裁判により敗訴すると病院側が医療ミスをしたことが公になってしまうリスクを回避できるので、和解に応じる可能性があるのです。
また、和解においては、病院側が謝罪する、再発防止のための対策を行うことを約束させるといった条項を盛り込むこともできるので、患者側が納得できる決着としやすいというメリットもあります。
和解案を受け入れるべきなのか、判決を待つべきなのかは慎重に検討すべきです。判決となった場合、患者側の損害賠償請求が認められずに賠償金を一切受けとれないリスクもあります。
弁護士がついていれば、こういった判断についてもアドバイスが受けられるでしょう。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了