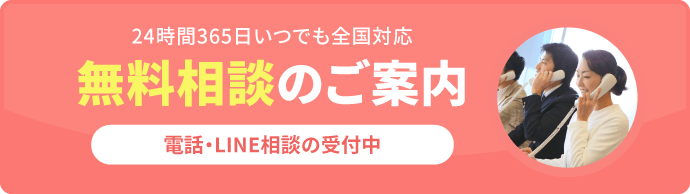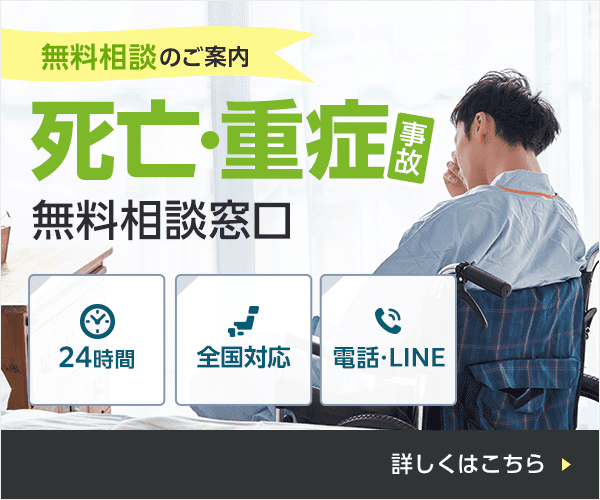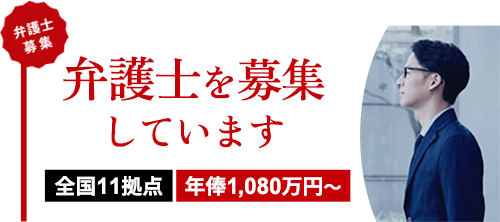労災事故の示談交渉を進める流れとコツ|示談交渉すべき労災とは?
更新日:
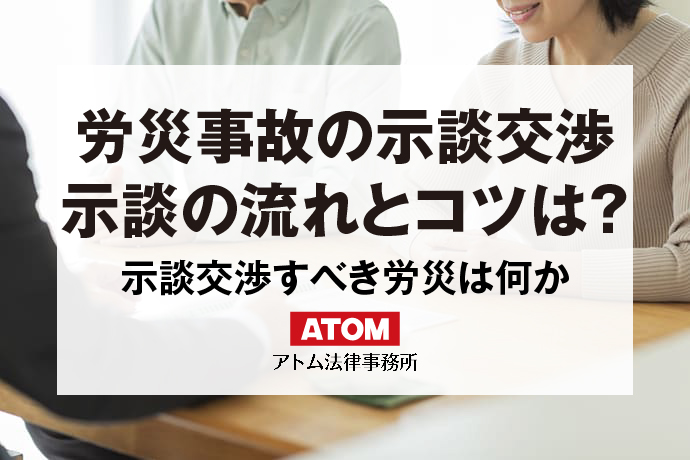
労災事故における示談は、労災保険の給付を超える損害を適切に受け取るために必要な手段です。
会社に安全配慮義務違反などが認められる場合や、業務中や通勤中に第三者と交通事故にあった場合などは示談交渉による「損害賠償請求」が必要になります。
示談の大まかな流れとしては、まず示談前に損害の算定が必要です。そこから会社側の責任を明らかにしつつ、話し合いを繰り返して示談内容をまとめていきます。
本記事では、労災事故における示談とは何かといった基本的なことから、示談の流れの詳細、示談金額の内訳、示談と裁判の違いなどをまとめて紹介していきます。
目次
労災事故における示談の基本|示談すべき労災とは?
労災事故での示談交渉を進める前に、示談が必要な理由や目的、裁判との違いといった基本情報について説明します。
示談が必要な労災事故がある
労災事故で示談が必要な理由は、「労災保険からもらえない補償」は、会社に示談交渉などで請求するしか受け取れないためです。
労災事故が起こったとき、労災保険に申請すると労災保険給付がもらえます。よって、まず大前提として、すべての労災事故において示談が必要なわけではありません。
一方で、労災保険からの給付は手厚いものではあるものの、損害全てを補償するものではないのです。
そこで、会社側の落ち度で起こった労災事故は、損害賠償として「労災保険からもらえない補償」の請求が必要になり、その手段として示談があります。
こうして示談交渉を通して支払われる損害賠償金のことを「示談金」と呼んでいるのです。
そもそも示談とは何か
「示談」とは話し合いによって民事上の争いごとを解決する方法をいいます。
示談とは?
示談とは民事上の争いごとを、裁判によらず当事者間の話し合いによって解決する方法のことです。一定額の損害賠償の支払いを受けたら、それ以上の損害賠償請求をしないという当事者間の合意が通常含まれます。
労災保険と示談による損害賠償請求の違い
労災保険は法律に基づく公的補償であるのに対し、示談は当事者間の合意に基づく解決方法であるという点で根本的に異なります。
そのほか法的根拠や会社の責任の有無、給付内容も異なる点です。
下表に主な違いをまとめています。
労災保険と示談による損害賠償請求の違い
| 項目 | 労災保険 | 民事損害賠償 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 労働基準法 | 民法 |
| 会社の責任 | 会社の責任は関係ない | 会社側に過失がある |
| 給付内容 | 一定の基準に基づく | 労災保険の給付を超えて可能 |
| 慰謝料 | 対象外 | 請求できる |
| 手続き | 公的な申請と手続きフロー | 示談や裁判など |
注意点として、労災保険から給付を受けた分について、会社側へも二重取りをする損害賠償請求はできません。
「二重取りできない」とは?
労災事故の治療に20万円かかったとします。労災保険から療養補償給付として20万円全額の補償を受けている場合、会社側への治療費請求は認められません。
この場合は労災保険から受け取った分を差し引いて(控除して)、損害賠償に関する示談金を決めていきます。
一方で実際には30万円かかったけれど、労災保険からは20万円しか認められていないということであれば、不足する10万円について会社に請求する権利があるのです。
関連記事『労災の損害賠償請求の方法とポイント|労災保険と民事賠償は調整される』ではこうした労災保険の給付と損害賠償費目の違いや、金銭の調整方法について解説しているので、参考にしてください。
示談交渉の相手
示談交渉の相手には、会社や第三者があげられます。もっとも、どんなケースの労災事故でも会社や第三者に請求できるわけではありません。
会社については会社の安全配慮義務違反を原因として事故が起きた場合など、第三者には故意や過失による不法行為があった場合など一定の場合に限られます。
請求できる相手
- 会社:安全配慮義務違反を原因として事故が起きた場合など
- 第三者:故意や過失による不法行為があった場合
ただし、労災事故における損害賠償請求を第三者(個人)にすることはめったにありません。なぜなら個人は資力が乏しく、損害賠償請求をしても認められづらいからです。
よって、業務中の労働者の不法行為に対する使用者責任を負うものとして、会社に損害賠償請求するケースが多くなっています。
会社への損害賠償請求に関する全体像を知りたい方は関連記事『会社のミスによる労働災害は損害賠償請求できる!会社の責任とは?』もあわせてお読みください。
示談は裁判より手間・費用・時間の負担が軽い傾向
裁判を行うには、まず裁判所に訴状や資料を提出する必要があります。
訴状には誰に何を請求したいのかなど具体的に明記せねばなりません。体裁が整っていないと裁判所が受け付けてくれない場合があり、法的手続きに不慣れな方が全ての資料を揃えるのは大きな負担です。
一方、示談交渉は当事者間の話し合いで進められるので、主張を裏付ける証拠などの資料は必要にはなりますが、裁判所に提出する訴状ほど体裁にこだわる必要はありません。
また、裁判所を利用する場合、裁判費用を収める必要がありますが、示談交渉なら当事者間の話し合いなので費用発生もないでしょう。
なにより、裁判になると解決までに長い時間を要する点について覚悟せねばなりません。
その点、示談は双方が納得すれば成立するものなので、お互いの言い分に大きな差がなければ比較的、短時間で解決する可能性があるといえます。
労災事故の示談の流れ
労災事故の示談の流れは、基本的に以下のとおりです。
示談の流れ
- 請求額の算定をする
- 示談交渉を開始する
- 示談書を作成・締結する
それぞれの詳細を説明します。
請求額の算定をする
労災事故で生じた損害は慰謝料・治療関係費・休業損害・逸失利益など多岐にわたります。ご自身にどのような損害が発生したのかきちんと計算しておかないと、適切な補償を受けとることができません。
労災認定されることで治療にかかった費用や休業したことで減った収入などに対する補償が給付されます。ただし、労災保険による給付は労災事故で生じた損害の100%を補償するものではありません。
とくに、労災事故で被った精神的苦痛に対する補償として請求できる「慰謝料」は損害賠償請求しなければ手にすることはできません。
本記事内「請求できる示談金の内訳を知っておく」でも解説も参考にして、請求漏れのないようにしましょう。
後遺症が残ったなら注意
労災で負ったケガが全て完治するとは限らず、何らかの後遺症が残ってしまうことがあります。そうした場合には、主治医が症状固定(治ゆ)と判断するまでは治療を続けましょう。
症状固定とは、現在可能な治療をこれ以上続けても症状の改善がみられない状態になることです。
示談交渉は損害算定から始めますが、後遺症については症状固定を経て後遺障害認定の結果を受けないと損害算定ができません。
後遺症が残った方は関連記事も参考にして、示談交渉をする前に、後遺障害認定の準備を始めましょう。
示談交渉を開始する
示談交渉を始める際には、会社に書面で示談交渉をもちかけて始まることが多いです。
示談では事故によって生じた損害賠償の金額と責任の所在などを主に話し合います。そうして話し合いを繰り返して、示談金額が決まっていくのです。
なお交渉の方法は直接顔を合わせるほか、電話やメールなど手段は様々に考えられます。
会社の人と直接やり取りをしたくない場合や、示談金額の判断がつかないといった場合には、損害賠償請求にくわしい弁護士に相談して助言を受けることをおすすめします。
示談交渉の際のポイントをまとめていますので、本記事内「労災の示談交渉をうまく進めるコツ」もあわせてお読みください。
示談書を作成・締結する
示談交渉を通して事故の相手方と話がまとまったら、必ず「示談書」に示談の内容をまとめるようにしましょう。
示談は、口約束でも成立してしまう性質をもっています。口約束で済ませてしまうと、双方の認識違いなどで後々のトラブルにつながることも多いです。
示談で合意した内容は必ず示談書という書面に書き起こし、認識違いがない示談内容になっているか確認しておく必要があるでしょう。
示談内容に相違なければ、示談書にサインして示談が成立します。
示談成立には慎重な判断をしよう
もっとも、示談書にまとめたとしても、弁護士の目からみるとふさわしくない内容になっている可能性もあります。
たとえば、法的に正当性の高い慰謝料額よりもずいぶん低い金額で示談してしまっているようなケースも考えられるでしょう。
一度でも示談に合意してしまうと、後から内容を変えられないのが通常です。
示談書にサインする前に、法律的に問題のない示談書となっているか、法律の専門家である弁護士に確認してみましょう。
労災の示談交渉をうまく進めるコツ
労災で示談交渉をする相手は会社側の方たちです。できるだけ穏便にしたいと思う一方で、労災で負った損害の補償はしっかりと受けたいと思うのも自然なことでしょう。
ここでは労災の示談交渉を進める際のコツを3つに絞って解説します。
示談交渉を進める際のコツ
- 示談交渉では会社の責任を明確にする
- 請求できる示談金の内訳を知っておく
- 弁護士に労災事故の示談を相談・依頼する
示談交渉では会社の責任を明確にする
労災事故において会社に責任があるとされる場合、通常は安全配慮義務違反や不法行為責任を根拠とすることが多いです。
安全配慮義務とは、会社は労働者が安全に働ける環境を提供する義務のことで、義務を怠った会社には賠償責任が生じます。
特に因果関係は非常に重要です。具体例を挙げて説明します。
例
労働者が工場内で手を巻き込まれ、そのまま死亡してしまったとしましょう。死因は機械に挟まれたことですが、なぜ事故が起こったのかを検討する必要があります。
工場側は巻き込まれるリスクを知っていたのに安全教育を怠った、巻き込まれないような予防策を講じていたなかった、作業員の配置が不適切であったなどの事情が「安全配慮義務違反」と認められれば、会社の責任を問える可能性が高いです。
こうした法的根拠に基づく請求には、弁護士に助言を受けることが有効といえます。ご本人や遺族だけで検討していくことよりも、法律の専門家である弁護士に見解を聞いてみましょう。
会社に安全配慮義務違反を問えるのかを判断するポイントは、関連記事『安全配慮義務違反は損害賠償の前提|慰謝料相場と会社を訴える方法』にて詳しく解説中です。
請求できる示談金の内訳を知っておく
労災事故の示談金は事案によってさまざまですが、慰謝料、治療関係費、休業損害、逸失利益、葬儀費用、物損に関する費用は示談金額に含まれること可能性が十分あります。
こうした費目は労災の補償外ものから、労災の給付内容では不十分なものまで幅広いです。
慰謝料・物損の費用
慰謝料や物損に関する費用は労災保険から給付されないため、示談交渉を通して損害賠償請求しなければ受け取れません。
慰謝料は、入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料と3種類あり、労災で受けた精神的苦痛に応じて請求が必要です。
精神的苦痛は目に見えないため、ある一定の算定基準にもとづいて相場が決まってきます。よって、会社と交渉する際には相場額を意識して請求しましょう。
関連記事では労災事故による慰謝料の相場を解説しているので、損害賠償請求を考えている方はあわせてお読みください。
関連記事
治療費・逸失利益
治療費は、基本的に労災保険から給付をうけられますが、労災保険の範囲を超えて必要な治療費は損害賠償請求する必要があります。
また、後遺障害が残った場合や死亡した場合の逸失利益も、労災保険の給付としては十分な補償とはいえない可能性があるのです。
逸失利益の計算には労働者が労災事故にあったときの年齢や、労災事故にあう前の収入、労災事故による後遺障害等級を用います。
計算式はやや複雑なので、関連記事の解説を参考にしたり、損害賠償請求にくわしい弁護士に相談したりして理解しておきましょう。
関連記事
休業時の給与補償
労災保険からは休業補償が給付されますが、給与に関する損害に対して60%しか補償されません。残りの40%の損害は、休業損害として会社に請求しないともらえないのです。
関連記事
弁護士に労災事故の示談を相談・依頼する
労災事故の示談交渉をうまく進めるためには、交渉ノウハウを多く持つ弁護士への相談・依頼が非常に有効です。
弁護士に依頼するメリットを以下に示します。
弁護士へ依頼するメリット
- 会社側の出方を予想して先手を打って対応できる
- 判例や過去の事例に基づく説得的な交渉ができる
- 法的に正当な金額の示談金を目指した交渉ができる
- 交渉の矢面に立ってくれて労働者側は負担が減る
なお、弁護士にはそれぞれ強みとする得意分野があります。
ホームページや弁護士の経歴などから確認できるので、労災事故・損害賠償請求に力を入れている弁護士への相談や依頼することがおすすめです。
関連記事は労災事故の相談窓口や弁護士費用の相場についてまとめていますので、参考にしてください。
示談交渉で合意できない場合の裁判対応も任せられる
事故の当事者同士で示談を進めても、お互いの主張や言い分が大きく食い違って、合意に至らないケースも当然あります。
このように示談によって解決に至らない場合は、裁判所が第三者の立場として介入する民事裁判の方法を用いて決着を図ります。
民事裁判とは
裁判官が当事者双方の主張を聞いたり、証拠を調べたりして、最終的な判決を言い渡して紛争の解決を図る手続きです。裁判所による判決は、事故の当事者双方の合意は必要ありません。判決がでていれば、事故の相手方に対して強制執行することも可能です。
もっとも、判決前に裁判所から和解案が提示されることもあります。この和解案に事故の当事者双方が同意すれば、裁判は終了します。
裁判の他にも、第三者が介入する方法としては民事調停などがあげられます。
労災事故における裁判の流れや裁判を起こす前に知っておきたいことは、関連記事『労災で裁判は起こせる?』で詳しく解説しています。
労災事故の示談交渉は弁護士に任せよう
一人で示談交渉をするのが不安な方はもちろん、一人でも問題なく示談交渉できるはずと思っている方も、弁護士に一度ご相談いただくことをおすすめします。
無料で示談交渉の悩みを法律相談
労災事故でご家族を亡くされたり、重い後遺障害を負われて示談交渉を検討されている場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。
相談の予約は24時間体制で行っているので、いつでも気軽にご連絡ください。
受付窓口は電話かLINEをお選びいただけます。ご都合のよい方法を選んでお問い合わせください。
無料法律相談ご希望される方はこちら
詳しくは受付にご確認ください。
アトム法律事務所 岡野武志弁護士
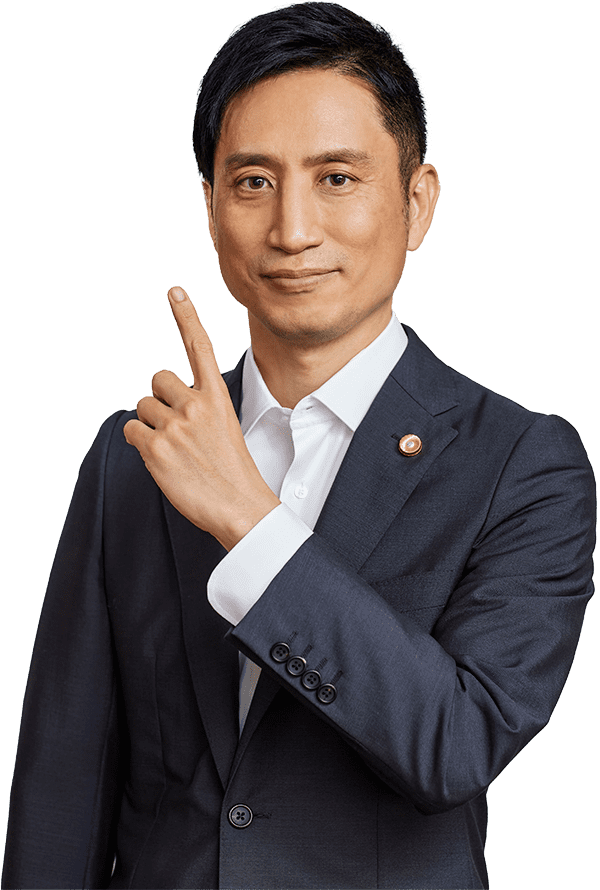

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了