別居が長いと離婚できる?5年・10年・20年のケースは?財産分与も解説
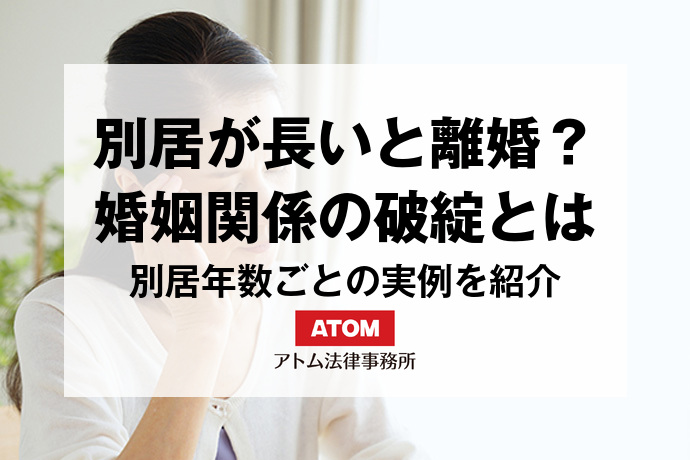
裁判で離婚が認められる別居期間の目安は通常3年~5年、不倫などをした有責配偶者からの請求であれば10年以上です。
ただし、これはあくまで目安であり、同居期間との対比や、婚姻関係が破綻している実態が重視されます。
この記事では、別居期間ごとの裁判所の判断傾向や、5年・10年・20年と別居が続いた場合の財産分与の注意点を、過去の判例をもとに解説します。
長期間の別居で離婚が認められる?
別居期間ごとの離婚成立の可能性を、まず目安表で確認しましょう。
| 別居期間 | 離婚成立の可能性 |
|---|---|
| 5年未満 | ケースによる |
| 5年~10年 | 可能性が高い |
| 10年以上 | 極めて高い |
| 20年以上 | ほぼ確実 |
上表はあくまで一般的な目安です。
実際には「単に期間が経過したから」という理由だけで機械的に離婚が決まるわけではありません。
なぜ長期間の別居が離婚理由になるのか、その法的な仕組みと注意点を説明します。
長期間の別居で裁判離婚できる理由
日本の民法では、夫婦の一方が離婚を望んでも相手が応じない場合は、裁判を起こして離婚を認めさせる必要があります。
このような裁判離婚が認められるのには厳しい条件があります。その条件が、民法770条1項に定める5つの離婚理由(法定離婚事由)です。これらの離婚理由のうち少なくとも1つが存在しなければ、裁判離婚は認められません。
法定離婚事由(民法770条1項)
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
この「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、簡単に言えば、夫婦関係がすでに回復不可能なほど破綻している状態を意味します。そして、その代表的な状況の一つが「相当長期間の別居」です。
不倫や悪意の遺棄といった明確な離婚理由がなくても、夫婦が相当の長期間にわたり別居しており、夫婦関係の修復の見込みがないと判断されれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、裁判離婚が認められます。
関連記事
・離婚できる理由とは?民法770条の5つの条件(法定離婚事由)も詳解
「長期間の別居=離婚」ではない|婚姻関係の破綻とは?
「何年別居すれば絶対に離婚できる」という明確な年数の基準はありません。
裁判所は以下の要素を総合的に判断します。
| 判断要素 | 破綻を示す具体例 |
|---|---|
| 別居期間の長さ | 5年以上の継続的な別居 |
| 同居期間との対比 | 別居期間が同居期間を上回る |
| 別居に至る経緯 | DV、不貞などの有責行為 |
| 別居中の夫婦間の交流 | 音信不通、一切の連絡なし |
| 未成熟子の有無 | 成人済み、または監護が安定 |
| 婚姻費用の支払状況 | 長期にわたる未払い |
| 離婚協議の状況 | 一方が一貫して離婚を拒否 |
これらの要素のうち、複数が該当すると婚姻関係の破綻が認められやすくなります。
別居が長いと有責配偶者からでも離婚できる?
有責配偶者(一方的に婚姻関係の破綻の原因を作った方)からの離婚請求は、基本的には認められません。離婚原因を作った側からの身勝手な離婚請求は信義則に反して認められないというのが裁判所の基本的な立場です。
ただし、最高裁昭和62年9月2日判決では、次の3つの要件を満たせば「有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」としており、別居期間が長いなどの事情があれば有責配偶者からの離婚請求も認められる余地があります。
- 夫婦の別居期間が相当の長期間に及んでいること
- 夫婦の間に未成熟子がいないこと
- 離婚によって他方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれないこと
もっとも、有責配偶者からの離婚請求が認められるには、そうでない場合よりも長い別居期間が必要です。
別居期間ごとの裁判実務の傾向と実例
別居期間ごとに、離婚が認められやすい事情と実際の裁判例を紹介します。
別居5年:離婚が認められやすくなる期間の目安
近年では、別居期間が3~5年でも裁判離婚が認められるケースが見られるようになりました。
特に、婚姻期間と比べて相対的に別居期間が長い場合は、夫婦関係の修復の見込みがないと判断される可能性が高くなります。
ただし、未成年の子どもがいるケースや、どちらかに夫婦関係を修復する意思があるケース、有責配偶者から離婚を請求しているケースなどは、慎重に判断されるでしょう。
7年以上の別居でも有責配偶者からの離婚請求が認められなかった事例
- 婚姻期間:15年
- 別居期間:7年
単身赴任中の夫が、専業主婦である妻に対して、離婚原因となるような事由がないのに突然離婚を切り出し、その後7年以上妻との連絡・接触を一切避けていた事案。
夫が家に帰らず専業主婦である妻や子ども、介護の必要な実父を放置したという事情を鑑み、夫からの離婚請求を認めて婚姻費用の分担義務から解放することは、信義に反し許されないとした。
(東京高裁平成30年12月5日判決)
未成熟子がいても約5年の別居で離婚が認められた事例
- 婚姻期間:14年
- 別居期間:4年10か月
妻が夫との関係に悩み、未成年の子どもを連れて別居した事案。
「控訴人(妻)の離婚意思は強固であり、被控訴人(夫)の修復意思が強いものであるとはいい難いことからすると、控訴人と被控訴人との婚姻関係は、既に破綻しており回復の見込みがない」として、妻の離婚請求を認めた。
(東京高裁平成28年5月25日判決)
別居10年:離婚が認められる可能性が高まる
10年の別居があれば、婚姻関係の破綻が強く推認され、離婚が認められる可能性が高いといえます。
- 10年間一切の夫婦関係がなく、音信不通
- 相手の復縁の意思が明らかにない
- 生活費の支払いが止まっている
こういった事情がそろっていれば、離婚が認められる可能性はかなり高くなります。
一方、10年間の別居実績があってもなお離婚が認められなかった事例もあります。
約10年間の別居で離婚が認められなかった事例
- 婚姻期間:37年
- 別居期間:10年
夫が愛人と同棲するために家を出て、妻に対して離婚を請求した事案。
「別居期間が10年に及ぶことを考慮してもなお、今後の事態の推移により、原・被告間の婚姻生活が回復する可能性が全くないとはいえ」ないとして、夫の離婚請求を認めなかった。
(東京地裁昭和60年5月21日判決)
本事案で裁判所は、以下の理由により婚姻生活の破綻を認めませんでした。
- 25年にわたる円満な夫婦生活の実績がある
- 妻が夫の実母と同居しており、夫の親族も夫が帰ることを望んでいる
- 夫の同棲相手が既に死亡している
- 夫婦が高齢である
別居10年のケースでは、財産分与の準備も重要です。
別居時に存在した財産が分与対象となるため、別居から長期間が経過すると財産の把握や証拠保全が困難になるリスクがあります。
財産分与の具体的な考え方については、この記事の後半で詳しく解説します。
別居20年:離婚が認められやすい
別居20年というケースでは、実質的に長期間の夫婦関係が存在しなかったといえるため、ほぼ婚姻関係は破綻していると認定されやすいです。
約22年間の別居で有責配偶者からの離婚請求が認められた事例
- 婚姻期間:30年
- 別居期間:22年
別居中の妻に対し、不貞行為を行った夫が離婚を請求した事案。
「控訴人と被控訴人との婚姻関係は、もはや夫婦としての実体を欠き、その回復の見込みが全くない破綻状態に至っている」として、有責配偶者である夫の離婚請求を認めた。
(東京高裁平成元年2月27日判決)
長期間別居したあとの財産分与はどうなる?
別居した時にあった財産が対象になる
離婚時の財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力によって形成された財産です。別居をしている場合、夫婦の協力関係は失われたとみなされるため、別居時に存在していた財産を財産分与の対象とするのが一般的です。
したがって、別居開始後に共有財産の増減があっても、財産分与では考慮しません。
ただし、別居期間が長期にわたる場合、財産の大部分がすでに処分されてしまい回収できないリスクがあります。
関連記事
・財産分与の基準時|いつの時点の財産が対象?よくあるトラブルと解決法
財産の評価は離婚時の基準で行う
財産分与の対象となる財産は別居時に存在したものですが、財産の評価は離婚時点を基準に行います。
例えば、別居時点で時価1,500万円だった土地が離婚時には1,000万円になっていた場合、1,000万円分を分け合うことになります。
ただし、価値の変動しない財産は、別居時の価値が基準となります。例えば、預貯金や保険の解約返戻金などは、別居時点の残高が財産分与の基準額となります。
別居と離婚に関するよくある質問
Q. 家庭内別居でも別居期間にカウントされる?
原則としてカウントされにくい傾向にあります。
居住空間が明確に区分されている、家計が完全に別である、顔を合わせない生活実態があるといった事情があれば認められる可能性もありますが、物理的な別居に比べてハードルは高いのが実情です。
Q. 相手が離婚を拒否し続けても別居を続ければ離婚できる?
最終的には離婚が認められる可能性が高いといえます。
実務上、別居期間が10年以上に及ぶ場合は「相当長期間」に該当し、同居期間や当事者の年齢などとの対比を要することなく、婚姻関係の破綻が推定されます。
婚姻関係の実体が完全に消滅していると裁判所が判断した場合には、離婚を命じる判決が下されます。
Q. 別居中に生活費をもらい続けることはできる?
離婚が成立するか、再度同居するまでの間は、収入の多い側から少ない側へ婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。
別居が長引けば、その分だけ婚姻費用の総額も大きくなるため、支払う側にとっては早期離婚への動機となり得ます。
まとめ|別居期間だけでなく「破綻の実態」が裁判離婚のカギ
長期間の別居があっても、裁判所は別居期間の長さだけでなく、婚姻関係の実質的な破綻状況を総合的に判断して離婚の可否を決定します。5年程度の別居でも離婚が認められるケースがある一方で、10年以上の別居があっても離婚が認められない場合もあります。
重要なのは、別居に至った経緯、別居中の夫婦間の交流、未成年の子どもの存在、有責配偶者からの請求かどうかなど、様々な事情を総合した「破綻の実態」です。
また、長期別居後の財産分与では、別居時点の財産が基準となるため、時間が経つほど財産の把握や回収が困難になるリスクにも注意が必要です。
長期間の別居により離婚を検討されている方は、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談し、ご自身のケースでの離婚の可能性や最適な進め方について専門的なアドバイスを受けることをお勧めします。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
