株式は離婚でどう分ける?財産分与の評価額から投資信託やNISAの扱いまで弁護士が解説
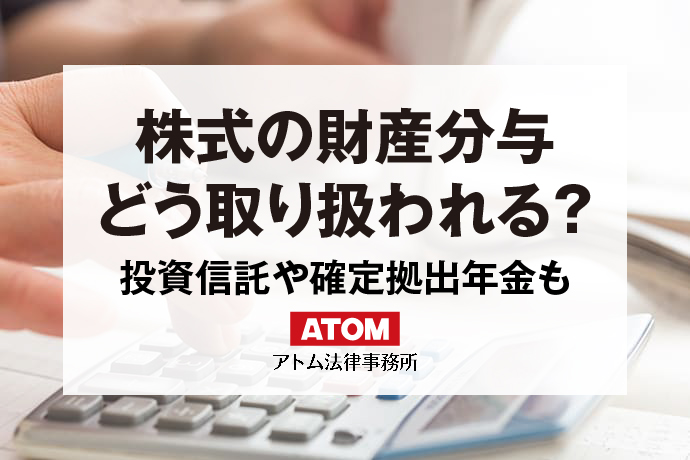
離婚の際に夫婦の財産を分ける「財産分与」では、株式や投資信託などの有価証券も対象になります。婚姻期間中に夫婦の協力によって取得した株式は、名義がどちらであっても、原則として2分の1ずつ分けることになります。
一方、婚姻前から保有していた株式や、相続によって取得した株式は「特有財産」とされ、分与の対象には含まれません。株式をいつの時点の価格で評価するのか、どの方法で分けるのか、税金をどのように負担するのかといった実務上の検討が欠かせません。
また、NISA口座で保有する投資信託やiDeCo(個人型確定拠出年金)も財産分与の対象になりますが、制度上の制約があるため慎重な対応が求められます。
この記事では、株式や投資信託に関する財産分与の基本ルールをはじめ、評価方法や分け方の実務、NISA・iDeCoの扱い、税務上のポイントまで、離婚時に押さえておきたい知識を、弁護士がわかりやすく解説します。
株式や投資信託は離婚するとどうなる?
財産分与の基本ルール|共有財産と特有財産
株式や投資信託が財産分与の対象となるかは、「婚姻中に取得したかどうか」「特有財産にあたるかどうか」で判断されます。
婚姻中に取得した株式や投資信託は財産分与の対象
婚姻期間中に取得した財産であれば、夫婦どちらの名義であるかを問わず、原則として共有財産として扱われ、財産分与の対象となります。
共有財産とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産のことです。
たとえば、夫名義の証券口座であっても、妻が家事・育児を通じて生活を支えていた場合、その資産は財産分与の対象となる共有財産とみなされます。
財産分与の対象となる共有財産について詳しくは、関連記事『夫婦の共有財産はどこまでが対象になるか離婚時の財産分与を解説』で具体例を交えて解説しています。
婚姻前や相続・贈与で得た財産は分与の対象外
夫婦の一方が婚姻前から有していた財産や、婚姻後に夫婦がそれぞれの親族からの相続・贈与によって取得した財産は、特有財産として財産分与の対象にはなりません。
特有財産とは、夫婦の一方が他方と無関係に取得・形成した財産をいいます。
どのような財産が特有財産なのか、特有財産をどのように証明するかは関連記事『財産分与の対象にならないものは?特有財産の具体例と証明方法を解説』で紹介しています。
株式や投資信託は基準時が重要
財産分与の対象となる財産は、基準時に存在するものでなければなりません。
株式や投資信託のように価格が変動する資産は、いつの時点を基準にするかが非常に重要です。
財産分与でいわれる基準時には、以下の2つがあります。
- 財産分与の対象財産を確定するための基準時
- 対象財産の評価額を決めるための基準時
財産分与の対象財産を確定するための基準時は、原則として別居時です。
もっとも、当事者間で合意できれば合意された時点を基準時とすることも可能です。
株式や投資信託など有価証券の評価額を決める基準時について詳しくは次章で解説します。
確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の扱い
確定拠出年金についても、財産分与の対象となる可能性があります。
確定拠出年金は、企業型(企業型DC)と個人型(iDeCo)の2種類に分けられます。
①企業型確定拠出年金(企業型DC)
企業型は企業が掛金を拠出します。
企業型確定拠出年金は、退職金の前払い的性質をもつものなので、婚姻期間中に積み立てられた部分については共有財産と判断されるケースもあります。
財産分与の対象となる金額は、基準時(別居時)における積立残高(評価額)の婚姻期間に対応する額です。
積立残高は、確定拠出年金運営管理機関(証券会社、銀行等)に問い合わせれば分かります。
②個人型確定拠出年金(iDeCo)
個人型は個人が掛金を拠出します。
婚姻中に掛金を拠出していた場合は、他方配偶者の協力があるといえるので、個人型確定拠出年金も財産分与の対象になります。
財産分与の対象となる額は、基準時(別居時)における積立残高(評価額)の婚姻期間に対応する額です。
積立残高は、確定拠出年金運営管理機関(証券会社、銀行等)に問い合わせれば分かります。
NISA(積立NISA)などの有価証券も対象
NISA口座の資産も、婚姻期間中に夫婦の協力によって形成されたものであれば、財産分与の対象になります。
NISAは、投資信託などの金融商品から得た利益が非課税になる制度です。2024年からの新NISA制度では、「つみたて投資枠(積立NISA)」と「成長投資枠」の2つの投資枠が設けられています。
財産分与では、原則として分与時の時価で評価します。離婚訴訟の場合は、口頭弁論終結時の価格が基準です。評価額は、証券会社や信託銀行が発行する残高証明書で確認できるほか、オンライン口座で最新の時価を確認することもできます。
もっとも、NISA口座は本人名義に限って開設でき、他人へ名義を変更することはできません。そのため実務では、口座内の商品をいったん売却して現金化し、その金銭を分ける方法が一般的です。
売却すると非課税のメリットはなくなります。また、売却時の市場価格によっては利益や損失が生じることもあるため、これらをどのように負担するかについて、あらかじめ話し合っておくことが大切です。
投資用不動産やゴルフ・リゾートの会員権は?
マンションやアパートなど、投資に用いるための不動産についても、財産分与の対象となる可能性があります。
投資用不動産の財産分与で注意しておきたいのが、離婚後の家賃収入を考慮する必要があるという点です。
不動産を売却してお互いに代金を分割するのか、どちらかが所有したまま代償金を一方に支払うのかを取り決めておくことが重要です。
なお、ローンの残債が不動産の時価を上回っているという場合には、原則としてプラスの財産を清算するという財産分与の特性上、該当する不動産について財産分与の対象外とすることも可能です。
ゴルフやリゾートを利用できる会員権も、財産分与の対象となる可能性があります。
評価額は、原則として離婚が成立した日の時価となります。
財産分与で株式を評価する方法
評価額を決める基準時は別居時ではない
財産分与には対象財産を確定する基準時と、評価額を決めるための基準時の2つがあります。
株式の評価額を決めるための基準時は、原則として、財産分与請求権を行使した時点です。
離婚訴訟であれば、口頭弁論終結時となります。
別居時点で保有していた株式や投資信託などの有価証券は、離婚訴訟であれば口頭弁論終結時の評価額で算定するのが原則です。
別居時から口頭弁論終結時までに株価が大きく変動したような場合は、公平の観点から、裁判所が裁量で基準時を判断するケースもあります。

弁護士
調停の場合は、当事者で合意した時点や、直近の時価で株式等の有価証券の評価額を算定します。
上場株式は原則として時価で評価する
上場株式の場合、別居時に保有していた株式数に、現在の時価をかけて評価します。
離婚訴訟であれば、口頭弁論終結時又は裁判時の時価によります。
株価は一定であることがなく、日々刻々と変化するものであり、価値が変わってしまうという点に留意してください。
非上場株式は評価方法が複雑
非上場株式の場合は、上場株式のように市場価格をもとに評価することができません。
そのため、以下のような評価方法を用いて会社の決算報告書や貸借対照表などの資料から評価することになります。
非上場株式の評価方法
- 純資産価額方式
- 類似業種比準価額方式
- 併用方式
- 配当還元方式 など
①純資産価額方式
純資産価額方式とは、今現在、「会社の借入金などの負債をすべて返済して、会社を解散させた」場合に、株主一人ひとりに返ってくる金額を評価額にするという評価方法です。
②類似業種比準価額方式
類似業種比準価額方式とは、非上場企業の株式について利益額、配当金額、純資産額の3つの要素から、類似する業種の上場企業と比較する評価方法です。
たとえば上場企業の1/3の利益額、1/3の配当金額、1/3の純資産額である非上場企業の株式については、上場企業の1/3の評価額とします。
そこに、会社規模を勘案して一定の率を乗じたものが、非上場株式の評価額となります。
③併用方式
併用方式では、会社規模に応じてそれぞれ類似業種比準価額方式、純資産価額方式の2つを併用して評価します。
④配当還元方式
配当還元方式とは、今後10年間でもらえるであろう配当金の合計額を評価額とする評価方式です。
4つの評価方式のほかに、より簡易的な評価方法として、「(総資産-負債)÷発行済み株式総数=一株あたりの価額」という計算式で株式の価値を算出する場合もあります。
非上場株式を評価する方法は複雑で、どれを選ぶかによって評価額が大きく変わることもあります。どの方法を選ぶべきか、個々の家庭の状況からも異なってくるでしょう。
「どの方法で評価すればよいかわからない」ということも考えられますので、お悩みの方は弁護士に相談することをおすすめします。
株式を財産分与する3つの方法
株式を財産分与する方法には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つがあります。
以下は、それぞれ3つの方法のメリット・デメリットを簡単に比較した表になります。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 現物分割 | 売却の手間を省ける | ・場合によっては公平に分与できない ・自社株の場合は注意が必要 |
| 代償分割 | ・公平に分与できる ・自社株の場合も安心 | 代償金が負担になることも |
| 換価分割 | 公平に分与できる | ・非上場株式は売却が困難 ・株価が低い時期に売却せざるをえないことも |

弁護士
それぞれの方法にはメリットとデメリットの両方があります。
最適な分割方法を選択するには、弁護士などの専門家に相談し十分に検討することが重要です。
現物分割
現物分割は、株式をそのまま分け合う方法です。
メリットとしては、売却の手間がかからないということが挙げられます。
ただし、株式の銘柄や数量が少ない場合は、公平な分与が困難になってしまうというデメリットがあります。
また、財産分与の対象が自社株の場合は、離婚後の元夫婦が自社株を持ち合うことになるので、経営上好ましくないという点がネックです。
代償分割
代償分割は、一方が株式を保有し続け、他方にその株式の評価額に相当する現金などを支払う方法です。
メリットとしては、公平な分与が可能になるということが挙げられます。また、配偶者が会社経営者である場合は、離婚後も自社株を保有し続けることになりますので、経営上の混乱を避けることができます。
ただし、代償金が多額に上る場合、資金の準備が負担になるというリスクがあるので注意が必要です。
換価分割
換価分割は、株式を売却して現金化し、その現金を分割する方法です。
メリットとしては、代償分割と同様に、公平に分与することが可能であるということが挙げられます。
ただし、非上場株式の場合は、そもそも売却することが難しいという点に注意してください。
また、売却時の市場状況によっては、株価が低い時期に売却せざるを得ないというリスクがあります。
株式を財産分与するときの注意点
婚姻前から所有していた株で儲けたお金は財産分与の対象にはならない
婚姻前から保有していた株式の配当金は、原則として特有財産にあたり、財産分与の対象にはなりません。
株価が婚姻後に上昇していても、その株式が婚姻前からのものである限り、値上がり益を含めて特有財産と考えられます。婚姻中に売却して預貯金の形にしていた場合でも、性質は変わりません。
ただし、婚姻中の収入(共有財産)で株式を買い増すなどの運用をしていた場合、その部分の利益は分与の対象となる可能性があります。また、婚姻前の株式から得た配当金を婚姻後に再投資していると、その再投資分が共有財産と評価されることもあります。
婚姻前からの保有であることを示すには、証券会社の取引報告書や残高証明書を取得し、婚姻前の日付で株式を持っていた記録を提示する必要があります。
長期間保有している場合は、過去の記録の取り寄せに時間を要することもあるため、早めに証券会社へ確認しておくと安心です。オンライン証券の場合でも、一定期間を超えた古い記録は別途申請が必要なことがあります。
婚姻前の株式投資と財産分与の裁判例
東京地判平30・10・18(平成29年(ワ)37984号)
離婚調停に伴う財産分与をめぐり、夫が婚姻前から保有していた株式を婚姻中に売却し、その売却益で再投資を繰り返して形成した1億円超の株式資産(および非上場株式)を妻が仮差押え。夫は「特有財産であり違法」として損害賠償請求。婚姻前の株式の運用益が財産分与対象となり得るかが判断の鍵に。
裁判所の判断
「特有性が失われたとされる場合もある」
東京地判平30・10・18(平成29年(ワ)37984号)
- 仮差押えが違法であったとは認められないとして、夫の請求を棄却
- 婚姻前の株式でも、婚姻後の家計と区別せず管理されていれば特有財産性が失われる可能性
- 婚姻期間10年、妻の家事・育児の貢献などから被保全権利(財産分与請求権)の存在を認定
- 財産の大半が価格変動しやすい株式であり、換価が容易なため保全の必要性あり
この判例では、もともと婚姻前に取得した株式であっても、婚姻後に売却や再投資を繰り返し、さらに家計と明確に分けて管理していなかった場合には、特有財産とはいえなくなる可能性があると裁判所は判断しました。
また、妻が専業主婦として家事や育児を担っていた点についても、その支えがあったからこそ夫は仕事や株式投資に専念できたとして、間接的な寄与として評価されました。
株式の譲渡益にかかる税金はどうすべきかを考えておく
株式等を売却する場合、売却益に対し一定の税金がかかります。

弁護士
現在の税率は所得税15%、住民税5%に復興特別所得税を加えた20.315%となっています。
たとえば、100万円で購入した株式が、基準時に200万円の評価額になっていた場合、売却すると約20万円の税金がかかります。
この200万円分の株式を、代償分割する場合、分与額はいくらにすべきでしょうか。
この税金分について当事者間でどのように負担するかは、合意によって自由に決めることができます。
税金分も公平に分け合い90万円を分与する、評価額をそのまま2分の1ずつ分け合い100万円を分与するなどの方法が考えられます。
株式の財産隠しに注意する
株式を財産分与するとき、相手が財産分与の対象となる株式を隠すことがあることに留意してください。
財産隠しが疑われる場合は、本人に開示を求めても断られる可能性が高いです。証券会社の名前がわかっているときは、弁護士会照会制度や調査嘱託を利用することをおすすめします。
株式以外にも、相手が財産隠しをしている場合があります。より詳しく財産隠しについて知りたい方は、『離婚の財産隠しの手口と調査方法|隠し口座やタンス預金を見抜くには?』をご覧ください。
夫が経営者の場合、自社株の扱いに注意
夫が会社経営者であるという場合は、自社株の扱いに注意が必要です。
経営者が保有している自社株は、婚姻中に得たものであれば財産分与の対象になる可能性が高いでしょう。
ただし、婚姻中に得た株式であっても、妻の貢献によるものではないとして、夫の特有財産であることを主張してくるおそれがあります。
また、株式の価値に相当する代償金や他の財産を渡すか、現物のまま分与するかの問題もあります。
現物で株式を渡した場合、妻が経営に口出しできる状態になってしまいます。これを避けるためにも代償金によって財産を分け与えるケースは多いですが、代償金を支払う場合に争いになりやすいのが株式の評価方法です。
会社が上場していない場合は、明確な時価が存在しないため、様々な評価方法の中から一つを選んで時価を決定することになりますが、どの評価方法を採用するかで争いが生じるおそれがあります。
自社株の扱いだけでなく、経営者の夫と離婚する場合は、さまざまな注意点があります。くわしくは『会社経営者の夫との離婚|3つの注意点を解説』をご覧ください。
財産分与案について考えておく
株式を財産分与するときは、どのように財産分与するかについて、ある程度見通しを立てておくようにしましょう。
財産分与の対象、分与額、分与方法について、具体的に書き出して整理するのがおすすめです。
また、離婚する場合、財産分与の他にも考えなければならない離婚条件がたくさんあります。
離婚条件の話し合いは交渉事である以上、自分の主張が100%通ることは難しいと考えておく必要があります。
ここで重要なのは、相手方がこちらの主張を拒否した場合に備え、代替案をあらかじめ用意しておくことです。
代替案を提示するには、離婚条件の優先順位を整理しておくことが大切です。
例えば、財産分与の対象に株式が含まれる場合、「株式の正確な折半にこだわるのか」「一定額の金銭の支払や不動産の分与があれば、その他の財産分与は求めないという譲歩が可能なのか」など、具体的な内容まで考えておくと交渉が進みやすいでしょう。
株式の財産分与に関するよくある質問
Q.婚姻前の株式の儲けも特有財産?
原則として、婚姻前に取得した株式の値上がり益も特有財産に含まれます。価格上昇が市場環境による自然な増加にとどまる場合は、特有財産として認められやすいといえます。
一方で、婚姻中に積極的な運用を行ったり、共有財産と混ぜて管理したりしていると、共有財産と評価されたり、分与の割合を調整する際に考慮されたりすることがあります。実際に、婚姻前の株式を売却・再投資して形成した資産について、共有財産と明確に区別せず管理していたケースで、特有財産とは認められなかった裁判例もあります。
特有財産であると主張するには、証券会社の取引報告書などの資料を用いて、婚姻前から保有していた事実や資金を分けて管理していた状況を客観的に示すことが重要です。
Q.つみたてNISAは離婚時の財産分与の対象になる?
NISA口座(つみたてNISA等)で保有している株式や投資信託も、離婚時の財産分与の対象になります。ただし、制度上、口座や商品を相手名義に変更することはできません。そのため実務では、いったん売却して現金に換えたうえで分ける方法が一般的です。
なお、売却すると、その資産に対する非課税メリットは失われます。新NISA制度では売却した分の非課税投資枠は翌年以降に再利用が可能になるため、売却によって一生枠が消えてしまうわけではありません。 分与後の生活設計に合わせて、改めて運用を検討するとよいでしょう。
Q.相手が株式を隠している疑いがある場合は?
弁護士に依頼すれば、弁護士会照会や裁判所の調査嘱託といった手続きを通じて、証券会社に取引内容を確認できます。別居直前に突然売却している、親族名義の口座へ資金を移している、取引履歴の開示を拒むなどは財産隠しを疑うサインです。
疑いがある段階でも、早めに弁護士へ相談し、証拠の確保を進めることが大切です。弁護士であれば、相手に気づかれずに調査を進める方法についてもアドバイスできます。
株式の財産分与のお悩みは弁護士へ
婚姻期間中に夫婦が協力して取得した株式や投資信託等の有価証券は、財産分与の対象です。
ただし、会社名義の株式や、結婚する前から保有していた株式については、財産分与の対象とはならない可能性があります。
財産分与の問題は、離婚問題の中でも特に激しい対立が起こりやすい分野です。
特に対象財産に株式が含まれる場合、その評価額や分与方法をめぐって、紛争が長期化する可能性があります。
株式の財産分与には、弁護士を始めとする専門家の関与が欠かせません。大きなトラブルに発展する前に、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

弁護士
確定拠出年金は原則60歳までは引き出すことができません。
財産分与するにはまとまった現金が必要になるケースも多いので、支払い能力によってはもめる原因になりやすいです。