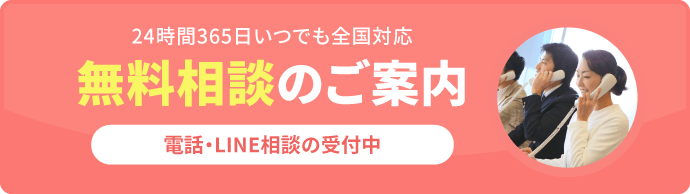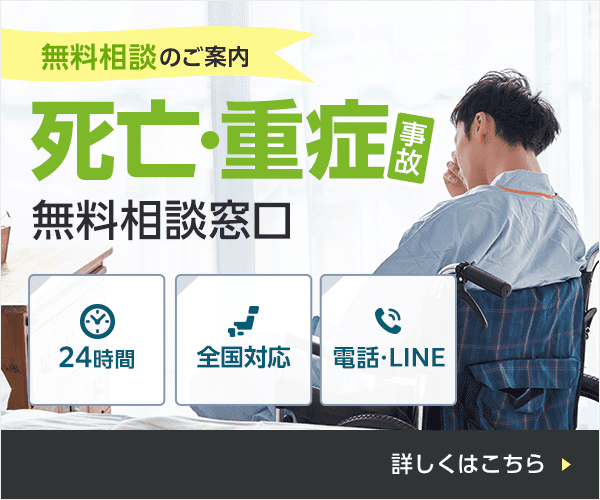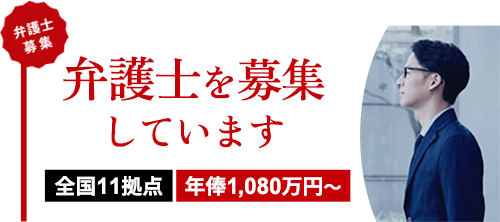日雇いでも労災保険の対象|給付を受けるために知っておくべきこと
更新日:
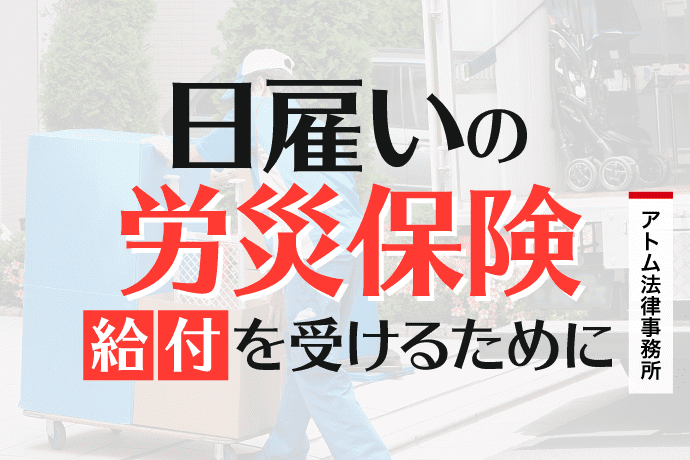
業務中や通勤中に生じる災害、いわゆる労災は、仕事をしているものであれば誰でも遭遇する可能性があるため、日雇い労働者も被害者となりえます。
日雇い労働者が労災に遭った場合「日雇いでは労災保険による補償が受けられないのではないのか」、「補償が受けられるとしても正社員に比べると減額になるのではないのか」といった疑問が生じ、不安になる方も多いでしょう。
結論から申し上げますと、1日だけ働く日雇い労働者も労災保険の補償を正社員と同じ内容で受けることが可能です。
本記事では、日雇い労働者が労災の被害にあった場合に知っておくべきことや、適切な補償を受けるために行うべきことについて解説を行います。
目次
労災の対象や要件を紹介
1日だけの日雇いでも労災保険が適用される
労災保険は、一人でも従業員を雇っているのであれば原則として保険者である事業主に加入義務があります。雇用形態や労働時間は関係ありません。
そのため、日雇い労働者であっても雇用契約が締結されている以上は労災保険の対象となるのです。
労災保険の保険料は事業主が全額負担するため、労働者に金銭的な負担は生じません。
また、1日だけの日雇いであるということから特別な加入手続きが必要ということもないのです。アルバイトやパートタイマーであるといったことも関係ありません。
そのため、「日雇いなので労災は使えない」、「労災保険に入っていないので健康保険を利用してほしい」などと事業主がいって労災を利用させないのは労災隠しにあたり、違法な行為となります。
このような場合には、自力で労災保険の申請手続きを行うべきでしょう。
労災といえる事故とは|業務災害と通勤災害
労災というと、仕事中の事故により損害を被ったという内容を想像しますが、仕事中の事故であれば常に労災に該当するとはいえません。
労災と認定されるためには、以下のような事故であることが必要です。
- 業務災害
労働者が業務上の災害によって負傷や疾病を負ったり死亡した - 通勤災害
労働者が通勤中に負傷や疾病を負ったり死亡した
業務災害や通勤災害の具体的な要件については、以下の通りです。
業務災害の要件
業務災害といえるには、「業務遂行性」と「業務起因性」が存在することが必要です。
- 業務遂行性
事業主の支配下や管理下にある状態で労災が発生した
事務所内や仕事現場、または、出張中の場合などが該当します。 - 業務起因性
業務が原因で労災が発生した
業務中に発生した事故であれば、基本的に認められます。
業務災害の具体例について知りたい方は『業務災害にあってしまったら|複雑な労災保険制度を弁護士が解説』の記事で確認可能です。
通勤災害の要件
通勤災害といえるには、「通勤中」の事故により損害が発生することが必要です。「通勤中」といえる移動は以下のようになります。
- 住居と就業場所の往復
- 就業場所から他の就業の場所への移動
- 単身赴任先と家族の住む住居間の移動
上記に該当する移動であるだけでなく、就業に関する移動であり、合理的な経路及び方法の移動であることも必要です。
通勤中に合理的な経路をそれたり、通勤とは関係のない行為を行うと通勤中とはいえなくなります。
ただし、日常生活に必要な最小限度の行為を行うためであるなら、行為が終わってから合理的な経路に戻った後は、通勤中に該当します。
通勤災害の具体例について知りたい方は『通勤災害とは何か|寄り道で怪我しても労災?誰にどんな請求ができる?』の記事を参考にしてください。
日雇いの労災事例(1)
足場工事の事業を行う会社に日雇いで雇用されていた労働者が、派遣先の現場における作業中に足場から転落して負傷したという事例です。
業務中に生じた負傷であるため、業務災害に該当するという認定を受け、労災保険の給付がなされました。
また、労働者を雇用していた会社や派遣先の会社に対して、労働者が転落しないようにするための安全対策を怠っていたことを原因とした損害賠償請求が認められています。
日雇いの労災事例(2)
日雇いの労働者として働いていた労働者が、派遣先の工事現場において足を滑らせて転倒した際に、鉄筋に顔面を打ち付け、死亡したという事例です。
業務中に生じた死亡事故であるため、業務災害に該当するという認定を受け、労災保険の給付がなされました。
また、労働者の遺族が、工事現場の請負会社や下請会社に対して損害賠償請求を行っています。
この請求については、労働者が転倒しないように適切な指示をすることを怠ったという安全配慮義務違反があったことから、損害賠償請求が認められました。
日雇いに対する労災保険給付
労災保険給付の具体的内容
労災保険により、以下のような給付が行われます。
給付内容や金額は、日雇い労働者であることで制限されません。
- 療養補償給付・療養給付
労災により生じた傷病を療養するために必要な費用の給付 - 休業補償給付・休業給付
労災による傷病の療養をするために仕事ができず、賃金を得られないという損害に対する給付 - 障害補償給付・障害給付
労災による傷病が完治せずに後遺障害が残った場合に給付される一時金や年金 - 遺族補償給付・遺族給付
労災により労働者が死亡した場合に、遺族が受け取ることができる一時金や年金 - 葬祭料・葬祭給付
労災により死亡した労働者の葬祭を行うために支給される - 傷病補償年金・傷病年金
労災による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても完治しない場合に給付される - 介護補償給付・介護給付
障害(補償)年金や傷病(補償)年金の受給者であり、症状が重く現に介護を受けている人に対する給付
業務災害の場合は「補償給付」や「補償年金」が、通勤災害の場合は「給付」や「年金」の支給がなされます。
この他にも、社会復帰促進事業の一環として、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、傷病(補償)年金には、上乗せの特別給付がなされます。
休業補償給付・休業給付の金額について
1日だけ働く日雇い労働者であっても、労災により休業する必要があるなら、労災保険により休業補償給付・休業給付を受けることが可能です。
では、実際の給付金額はどのような計算方法により算出されるのでしょうか。
通常、休業に関する給付を行う場合には、休業する直前3ヶ月間の給料の合計額を暦日数で割った給与基礎日額を基準とします。
しかし、日雇い労働者は以下のような計算方法となるのです。
- 休業する以前1ヶ月間に日雇い労働者が労災発生時に雇われていた事業場において使用された期間がある場合
使用中に支払われた賃金の総額÷労働日数×0.73 - 上記の方法による計算ができない場合
労災発生前1ヶ月間に事業場において同一業務に従事した日雇い労働者に対してい支払われた賃金の総額÷労働日数×0.73 - 上記した2つの方法による計算ができない、または、日雇い労働者や使用者が上記した2つの方法による計算を不適当と判断した場合
都道府県労働局長が定める金額 - 一定の事業又は職業について都道府県労働局長が日雇い労働者の平均賃金を定めている場合
上記3つの方法によらず、定められた金額
給付基礎日額は、休業だけでなく、障害や傷病に関する給付などでも金額計算の基礎となります。
正確な金額が気になる方は、労働基準監督署に相談するべきでしょう。
具体的な申請手続き
労災保険給付を受けるためには、労災認定がなされなくてはなりません。
労災が発生してから、実際の給付を受けるまでの流れは以下の通りです。
- 労働者が労働基準監督署へ請求書を提出する
- 労働基準監督署が労災に該当するのかについて調査する
- 労働基準監督署から支給・不支給の決定通知が届く
- 支給の決定があれば厚生労働省より指定口座へ振り込みがなされる
必要な書式が給付内容によって異なるため、注意してください。
書式への記載を行ったうえで、労働基準監督署へ書類を提出しましょう。
ただし、労災指定病院で治療を受け、療養補償給付・療養給付を請求する場合には、受診した病院への提出が必要です。
給付内容別の請求書書式は以下の通りになります。
勤務先に労災保険を利用したい旨を伝えると用意してくれるでしょう。
また、厚生労働省のホームページでダウンロードすることも可能です。
業務災害による場合の書式
| 請求書書式 | |
|---|---|
| 療養補償給付 | 労災指定病院で治療 様式第5号 労災指定病院以外で治療 様式第7号 柔整用 様式第7号(3) はり・きゅう用 様式第7号(4) |
| 休業補償給付 | 様式第8号 |
| 障害補償給付 | 様式第10号 |
| 傷病補償年金 | 様式第16号の2 |
| 介護補償給付 | 様式第16号2の2 |
| 遺族補償給付 | 様式第12号 |
| 葬祭料 | 様式第16号 |
通勤災害による場合の書式
| 請求書書式 | |
|---|---|
| 療養給付 | 労災指定病院で治療 様式第16号の3 労災指定病院以外で治療 様式第16号の5 柔整用 様式第16号の5(3) はり・きゅう用 様式第16号の5(4) |
| 休業給付 | 様式第16号の6 |
| 障害給付 | 様式第16号の7 |
| 傷病年金 | 様式第16号の2 |
| 介護給付 | 様式第16号2の2 |
| 遺族給付 | 様式第16号の8 |
| 葬祭給付 | 様式第16号の10 |
請求書には原則として事業主の証明が必要となるので、事業主に労災保険を利用したい旨を伝えて協力してもらいましょう。
事業主に協力してもらえなくても、請求自体は可能です。その場合には、労働基準監督署に相談しながら自分自身で書類の作成を行いましょう。
労災申請手続きについて詳しく知りたい方は『労災事故の申請方法と手続きは?すべき対応と労災保険受け取りの流れ』の記事をご覧ください。
あるいは記事『労災事故の相談窓口はどこ?お悩み別に無料相談や電話相談先を探そう』では、労働基準監督署をはじめとして労災保険の申請や制度についての相談を受けている公的機関を紹介しているので、あわせてお読みください。
労災保険以外でも請求できる方法がある
労災保険では不十分な部分を請求しよう
労災保険による給付は、法律にもとづいて一定の金額を支給するものであるため、発生した損害全てに対して補償を行ってくれるとは限りません。
特に重要な情報として、労災によって労働者に生じた精神的苦痛に対する慰謝料は、労災保険では給付なされないということを知っておきましょう。
労災保険による補償を受けられない部分については、基本的に損害賠償請求により支払いを受けることになります。
事業主へ請求する方法
労災が発生した場合には、事業主に対して損害賠償請求を行うことが可能なケースがあります。事業主への請求が可能となるためには、安全配慮義務違反の有無が問題となります。
事業主の安全配慮義務違反とは
事業主は、雇用契約にもとづいて、労働者の生命や身体等の安全を確保しつつ労働を行うことができるように職場の環境を整えるという安全配慮義務を負っています。
この義務は、継続的な雇用ではない日雇いの場合でも同様に発生します。
そのため、事業主は労働者に危険が生じないように、事前の安全指導や、適切な安全対策を行うことが求められるのです。
事業主が危険性を予見できるにもかかわらず、適切な対策を行っていなかったために労災が発生したのであれば、事業主に安全配慮義務違反が認められます。
安全配慮義務違反が認められるのであれば、事業主に対する損害賠償請求が可能となるのです。
事業主への損害賠償請求が認められるかどうかは、安全配慮義務違反の有無しだいです。安全配慮義務の具体例について知りたい方は『安全配慮義務違反は損害賠償の前提|慰謝料相場と会社を訴える方法』の記事を参考にしてください。
第三者へ請求する方法
労災の発生が、第三者の故意や過失を原因とする場合には、第三者に対する損害賠償請求が可能となります。
具体的には、通勤中に自動車に追突された場合や、接客業務中にお客から暴行を受けた場合などです。
また、加害者が業務行為を行っている最中であった場合には、加害者を雇用している使用者に対しても損害賠償請求が可能となるケースがあります。
具体的には、タクシーの運転手が仕事中に交通事故を起こしたというような場合です。
損害賠償請求を行っても、請求相手が資力を有していないのであれば、実際に支払いを得ることができません。会社であれば個人よりも資力を有している可能性が高いので、使用者に請求が可能である場合は、使用者への請求を行うべきでしょう。
具体的な請求内容
事業主や第三者への損害賠償請求により、以下のような損害を請求することが可能です。
- 治療費
治療のために必要となった費用 - 入通院交通費
入院や通院するために発生した交通費 - 入通院付添費用
入院中の生活や通院する際に付添が必要な場合に発生する費用 - 入院雑費
入院中の生活用品や通信費用などをいう - 休業損害
ケガの治療のために働けないことで生じる損害 - 逸失利益
後遺障害が生じた、または、死亡したことで将来得られるはずの収入がられなくなったという損害 - 葬儀費用
被害者の葬儀を行うために必要な費用 - 慰謝料
被害者に生じた精神的苦痛を金銭化したもの - 物損に関する費用
具体的な請求金額について知りたい方は、下記の関連記事をご覧ください。
労災保険以外の請求を行う際の注意点
労災保険給付との二重取りはできない
労災保険給付と損害賠償請求については、請求できる内容が重複している部分があります。
具体的には、以下の通りです。
| 労災保険の給付内容 | 損害賠償請求内容 |
|---|---|
| 療養(補償)給付 | 治療費 |
| 葬祭料・葬祭給付 | 葬儀費用 |
| 休業(補償)給付 傷病(補償)年金 | 休業損害 |
| 障害(補償)給付 遺族(補償)年金 | 逸失利益 |
そのため、二重取りにならないように、既に支払いを受けている部分については労災給付申請や損害賠償請求を行う際に減額されます。
例えば、労災保険給付により既に休業補償給付または休業給付を受けている場合は、給付を受けた金額分は休業損害の請求金額から減額する必要があるのです。
ただし、労災保険における特別給付については、二重取りの対象とはなりません。特別給付は、被害者の社会復帰という異なる目的のために支給されるためです。
そのため、特別給付の部分については減額せずに請求することができます。
被害者に過失があると減額
労災事故の発生に関して、労働者にも過失が認められることがあります。
損害賠償請求を行う際には、労働者に過失があると、過失の程度に応じて請求金額を減額する必要があるのです。
このような減額を過失相殺といい、具体的な減額の程度は、基本的に当事者間の話し合いにより決まります。
しかし、過失相殺ではどのような過失をどの程度評価するのかが不明確であるため、法的知識がないと正確な減額が困難です。
そのため、減額の程度に納得がいかない場合には、専門家である弁護士に相談しましょう。
労災事故の損害賠償請求は弁護士に相談
労災に遭った労働者が適切な補償を受けるためには、弁護士への相談を行いましょう。
弁護士に相談する必要性や、おすすめの相談方法について紹介します。
なぜ弁護士に相談するべきなのか
適切な金額の請求が可能
労災保険や損害賠償請求によりどのような請求ができ、いくらが妥当な金額なのかは、法的知識がないと正確に把握することが難しくなっています。
請求できる範囲が不明確なまま請求を行ってしまい、本来得られたはずの給付や賠償金を取り損ねる恐れもあるでしょう。
弁護士に相談すれば、どのような請求が可能であるのか、詳細な請求金額がわかります。
依頼すれば弁護士が手続きを行ってくれる
請求内容や請求金額がわかっても、日常生活を送ることと損害賠償請求の交渉を同時に行うのは簡単ではありません。
弁護士に相談すれば、手続きや方法についてアドバイスがもらえます。また、正式な契約を結ぶことで、代理人として労働者の代わりに手続きをしてもらえるため、適切な対応が期待できるでしょう。
裁判になっても安心
労災給付の内容に納得がいかない場合や、損害賠償請求の交渉がうまくいかない場合には裁判手続きによる解決が必要となってきます。
しかし、裁判の仕組みは非常に複雑で、労働者が独力でやるのは困難を伴うでしょう。
弁護士に依頼すれば、正確な裁判手続きを代わりに行ってくれるので安心でしょう。
相談するなら無料の法律相談を
労災で大きな後遺障害が残ったり、ご家族を亡くされたりして、会社などに対する損害賠償請求を検討している場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。
弁護士に相談することで様々なメリットが生じることが分かったかと思いますが、実際に相談するとなると相談料が気になってしまう方も多いのではないでしょうか。
弁護士への相談は、無料の法律相談を行っている事務所で行いましょう。金銭的な負担を気にすることなく、疑問点について質問することが可能です。
下記フォームにて法律相談の予約受付を24時間体制で行っているので、一度気軽にご連絡ください。
無料法律相談ご希望される方はこちら
詳しくは受付にご確認ください。
アトム法律事務所 岡野武志弁護士
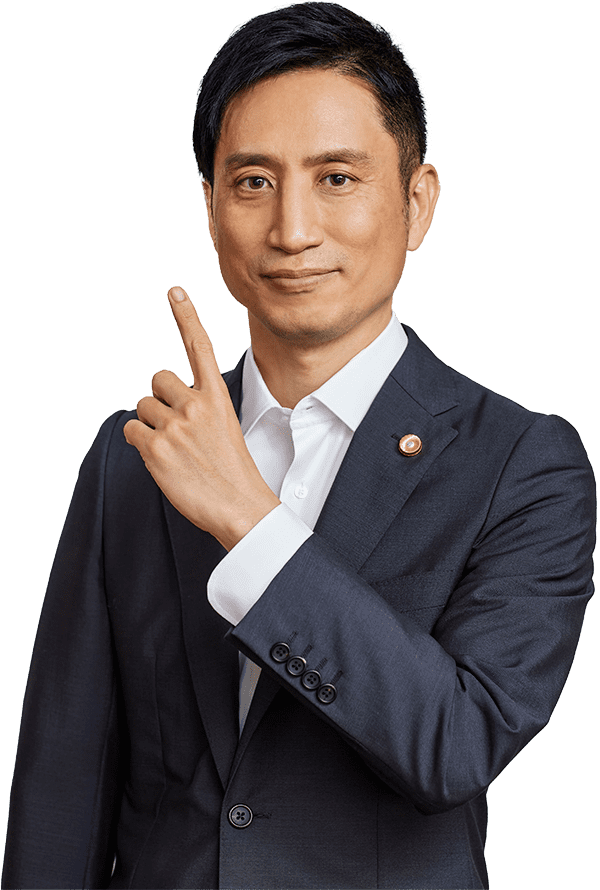

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了