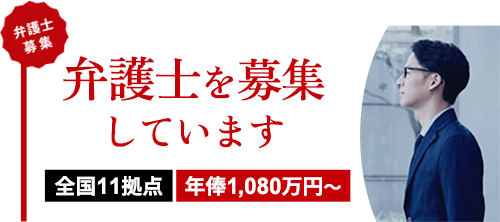労災における休業補償の計算方法は?給付条件・期間・申請手続きを解説

労災保険の休業補償とは、労災事故によって仕事を休むことになり、会社から給料が支払われない場合に給付される労災保険金のことです。
休業補償の給付額は給付基礎日額の80%分で、休業4日目から受け取ることができます。なお、業務災害の場合、待機期間の3日分の補償は事業主に義務付けられていますので、会社側に請求しましょう。
ケガの治療中である方にとって休業補償がもらえる期間がいつまでなのかということも、生活がかかってくるため気になるところでしょう。
この記事では休業補償の計算方法から給付期間に加えて、基本的な休業補償の申請手続き、気になる疑問についてわかりやすく説明していきます。
目次
労災で休業補償がもらえる条件
労災保険から休業補償を給付してもらうには次の条件をすべて満たす必要があります。
休業補償の給付条件
- 負傷や疾病が業務に起因するものであること
- 休業が4日以上続いていること
- 労働ができず賃金を受け取っていないこと
1つでも条件が欠けていると、労災保険から休業補償を給付してもらうことはできません。
負傷や疾病が業務に起因するものであること
労災事故といえるためには、業務上において生じた事故である業務災害、または、通勤途中に生じた事故である通勤災害のどちらかに該当することが必要です。
ワンポイント
労災事故は業務中の労災を業務災害、会社への通勤途中にあった労災を通勤災害と区別しています。
細かく言えば、業務災害では休業補償給付、通勤災害では休業給付というように名称にも違いがあり、申請書様式も異なるので、ご自身の労災事故がどちらに当たるのかは理解しておきましょう。
休業が4日以上続いていること
労災保険から休業補償が受け取れるのは、ケガや病気で休業した4日目からです。初日から3日目は待機期間であり、休業補償はありません。
もっとも初日から3日目の扱いについては、業務災害か通勤災害かで異なります。
業務災害の場合は待機期間中は会社が支払う
業務災害で休業した場合は、労働基準法上の規定にもとづいて、会社が初日から3日目の休業に対して補償を支払う義務があります。(労働基準法76条)
そのため、業務災害の場合は初日から休業に関する補償を受けることが可能となるのです。
休業補償の受給開始時期のちがい
| 業務災害 | 通勤災害 | |
|---|---|---|
| 労災保険 | 休業4日~ | 休業4日~ |
| 会社の義務 | 休業初日~3日 | 補償無し |
労働ができず賃金を受け取っていないこと
労災によるケガで働けず、賃金を受け取っていないことは休業補償を受け取る条件のひとつです。
労災でケガをしていても就労可能で賃金を受け取っている場合には、休業補償によって補てんされる損害は生じていません。
休業補償の計算方法を3ステップで説明
休業補償の計算方法は、給付基礎日額×60%×休業日数です。ただし実際に受け取る休業補償は、休業特別支給金もあわせて給付基礎日額の80%にあたる金額の休業日数分となります。
休業補償としてもらえるお金は以下の3つの計算方法で算定可能です。
休業補償としてもらえるお金
- 給付基礎日額を算定
- 休業日数を数える
- 休業補償と休業特別支給金の合計を算定
それぞれのステップについてくわしくみていきましょう。
(1)給付基礎日額を算定
給付基礎日額とは、労災事故で怪我を負った日や病気の診断を受けた日から直前3ヶ月間の平均賃金です。
直前3ヶ月の給与を合計したものを暦日数で割って、給付基礎日額を割り出します。
給付基礎日額の求め方
- まずは直前3ヶ月間の給与を合計する
- 給与の合計を直前3ヶ月間の暦日数で割る
直前3ヶ月間の給与にボーナスや臨時手当は含まないので注意してください。
また、暦の日数は勤務日数ではありません。カレンダーの日数で割る点にも注意しましょう。
(2)休業日数を数える|土日も休業期間に含んでよい
休業日数は休業開始から4日目を起算日とします。
また、もともと土日休みの仕事であり、休業期間に土日が含まれていても、休業補償の支給対象日数に数えることができます。会社が休みであることは関係ありません。
(3)休業補償と休業特別支給金の合計を算定
休業補償として受け取るお金は、給付基礎日額の80%にあたる金額を休業日数に掛け算して算定可能です。
休業補償で受け取る金額
休業補償としてもらえるお金=給付基礎日額の80%×休業日数
ただし、休業補償としてもらえるお金の算定を細かくみると、休業補償と休業特別支給金に分かれていることには留意しておきましょう。
休業補償と休業特別支給金とは?
休業補償として労働者が受け取る補償は、休業補償と休業特別支給金から成り立っています。
休業補償は給付基礎日額の60%を、休業特別支給金は給付基礎日額の20%を給付される仕組みで、両方を合算すると給付基礎日額の80%を受け取れるのです。
休業補償の計算方法
- 休業補償=給付基礎日額の60%×休業日数
- 休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数
休業補償としてもらえるトータル=給付基礎日額の80%×休業日数
とくに通勤災害の休業補償については関連記事でも掘り下げて説明していますので、あわせてお読みください。
関連記事
休業補償の期間|いつからいつまで休業補償をもらえる?
休業補償はいつからもらえる?
休業開始から4日目からもらえます。休業開始の1日目から3日目については待機期間ですので、労災保険の休業補償は対象外です。
なお、会社(事業主)は業務災害による休業補償に関して、待機期間中の補償を支払う義務があります。よって業務災害の場合、待機期間分は会社に請求しましょう。
休業補償はいつまでもらえる?
休業補償は、治って職場復帰できるとき、症状固定と判断されるとき、あるいは労災が原因となって死亡したときまでを受給期間とします。
休業補償の給付期間
- 治って職場復帰できるとき
- 症状固定と判断されるとき
- 労災が原因となって死亡したとき
症状固定とは、主治医の判断により「通常の医療行為をこれ以上続けても、よくなることも、悪くなることもない」と判断されることです。
いわゆる後遺症が残ったと判断される時期でもあるので、休業補償の給付は終了となります。
労災で症状固定を迎えることには、休業補償の給付がなくなることのほか、障害補償給付の申請の検討も必要です。関連記事では労災事故と症状固定について解説していますので、あわせてお読みください。
休業補償は労災発生後いつごろもらえる?
休業補償給付が支給されるまでには、通常、労災発生から1~2ヶ月程度の期間がかかることになります。
実際に休業補償給付を受けるには、支給決定がなされなければなりません。労災といえるかどうかや、休業補償の要件に該当するかどうかの判断が難しい事案の場合は、さらに期間がかかるでしょう。
そうすると、休業補償がすぐにもらえないことから、家計が厳しい状況となってしまうことがあります。このような問題に対応するため、受任払いという制度があるのです。
受任者払いとは
受任者払い制度とは、労災保険から給付される前に、労災保険による補償相当額を会社が立て替えて労働者に振り込まれる制度です。立て替えて支払ってもらったら、休業補償は会社に振り込まれることになります。
会社が受任者払い制度を利用していれば、先にお金を手にすることができるので安心です。
受任者払い制度を会社が利用する場合は、会社が申請を行います。その際、以下の書類にサインを求められるでしょう。
- 被災した労働者本人の委任状
- 受任者払いに関する届出書
これらの書類は、立て替え払いを受けた後にサインするようにしましょう。
【コラム】1年6ヶ月以上の休業なら傷病補償に切り替わる
療養をはじめて1年6ヶ月経過しても治ゆせず、ケガや病気の内容が傷病等級1級~3級に該当する場合、休業補償に代わって傷病補償の給付を受ける流れです。
療養をはじめて1年6ヶ月経過した日から1ヶ月以内に、労働基準監督署に必要書類を提出しましょう。
労働基準監督署が給付条件を満たしていると判断すれば、傷病補償が振り込まれるようになります。
休業補償を受けるための労災申請手続き
休業補償の申請手続きの流れ
労災保険の休業補償は、必要書類を所轄の労働基準監督署に提出し、労災認定されることで受け取ることができるようになります。
休業補償の申請手続き
- 労働基準監督署に必要書類を提出
- 労働基準監督署での調査
- 調査結果を踏まえて支給/不支給が決定、結果の通知
- 支給が決定したら厚生労働省から休業補償が支払われる
原則として、労災保険の申請手続きは被災した労働者本人かその家族が行います。
もっとも、多くの場合で会社(事業主)の担当者がサポートしてくれるので、まずは社内の担当者を確認しておきましょう。
休業補償の申請に必要な書類
休業補償の申請手続きで準備しなければならない必要書類は以下の通りです。
支給請求書には会社と医師の証明が原則として必要です。もっとも、会社が労災の発生を認めず証明してくれない場合は、その旨を支給請求書に記載するようにしましょう。
また、1ヶ月ごとに支給請求書を提出すれば、月ごとに休業補償を支払ってもらうこともできるので、休業が長期に及ぶ場合でも安心です。
休業補償についてのQ&A
午前に出勤して午後は通院したらどうなる?
午後に通院した場合、「平均賃金」と比べて「実働に対して支払われる賃金」が60%未満の賃金しか支払われていない場合は、休業日数として支給の対象になります。(「実働に対して支払われる賃金」とは、給付基礎日額からその賃金分を差し引いた額を意味します。)
60%を少しでも超える賃金が支払われていれば、休業日数としてカウントされません。
たとえば、平均賃金1万2,000円で所定労働時間8時間の場合で考えてみます。午前中の4時間働いた場合、その実働に対して支払われる賃金は6,000円です。平均賃金から実働賃金を差し引いた差額6,000円の60%である3,600円が休業補償となります。
実働に対して支払われる賃金の6,000円と差額60%の3,600円を足した9,600円以上の賃金が支払われていたのなら、労災保険からの給付は受けられないのです。
休業が1日だと休業補償がもらえないって本当?
休業が1日の場合では、休業補償の対象にはなりません。休業補償は3日間の待期期間を経て、休業4日目から支給されます。
もっとも、これは労災保険上の補償に限った話です。業務災害における最初の休業3日間の賃金については会社が補償する義務がありますので、会社に請求するようにしましょう。
退職後は休業補償がもらえない?
労災保険の休業補償は、退職後でも継続して受け取ることができます。
退職後も労災による負傷や疾病の療養のために就労できない状態が続く限り、休業補償を受け取ることができます。退職によって自動的に休業補償が打ち切られることはありません。
複数の雇用先から収入を得ているときの基礎日額は?
複数の会社に雇用されている場合、給付基礎日額は、すべての勤務先の賃金を合算した額を元に決定します。
この考え方は、労災保険の給付を規定する「労働者災害補償保険法」の令和2年改正によるものです。
従来の法律では、複数の勤務先があっても、労災が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額などが決定されていました。しかし、改正によって複数の勤務先がある場合は、すべての会社から支払われた賃金を合算して算定できるようになったのです。
副業が解禁されるなど働き方の多様性に応じて、労災保険の補償範囲もアップデートされる形となりました。
厚生労働省ホームページ「労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~」では、改正の内容についてさらに詳しく確認することができます。
休業中に有給が使える?
休業中であっても、有給休暇を利用することが可能です。
ただし、有給休暇を利用した日については給料として給付基礎日額の100%分が支給されるため、休業補償は給付されません。
有給休暇を使うメリットはいくつかあります。
たとえば、有給休暇を利用することで休業補償よりも多くの支給を得ることが可能です。また、通勤災害の場合は休業開始から3日間は休業補償の対象外であるため、有給休暇により収入を確保することができます。
ご事情にあわせて有給休暇を使うのか、労災の休業補償の給付を受けるのかを検討しましょう。
休業中における賞与や有給休暇の扱について詳しく知りたい方は『労災で休んでいる間は欠勤扱い?休業中の賃金・賞与に関する不安を解決』の記事をご覧ください。
会社や第三者に労災の原因があるなら休業損害も請求
会社や第三者などから何らかの被害を受けたことで労災が起こったとき、会社側や第三者に対して休業損害の請求が可能です。
休業損害は休業補償とは異なり、労災保険からの給付ではありません。また、法定で金額上限があるわけではないので、損害に応じた請求が可能です。
その一方で、労働者側にも落ち度があったときには過失相殺されて減額がされることがあります。
| 休業補償 | 休業損害 | |
|---|---|---|
| 休業原因 | 労災 | 第三者の不法行為 |
| 請求金額 | 給付基礎日額の80% | 交渉次第 |
| 過失の影響 | なし | あり |
休業損害も請求すべき労災事故とはどんなものか
休業損害を請求できる労災事故について、イメージしやすいように事例を示します。
事例
Aさんは会議室に向かう途中、会社の階段を上っていたところ、階段がとつぜん壊れて転落しました。頭を強く打ち付けてしまい、寝たきりになってしまったのです。
後日、会社側はこの階段が壊れかけていることを事前に知りながら、修理対応や通行不可にすることなく、放置していたことが発覚しました。
このケガは業務中に会社の施設内で起こっていますので、労災認定を受ける可能性は高いです。
さらにはこの階段が壊れていることを会社側が知っていて放置していたという事実から、労災事故の責任を会社に問い、会社に対して休業損害を請求できる可能性があります。
しかし、労災保険からの休業補償は給付基礎日額の80%にとどまり十分とはいえません。
労災保険の補償だけでは不十分な部分に関しては、会社や第三者に損害賠償請求しなければ手にすることができないのです。
会社に責任が問える場合とは?
会社や第三者に労災の原因がある場合について具体的には、「会社の安全配慮義務違反により労災が生じた場合」や「第三者行為災害により労災が生じた場合」が主にあげられます。
会社には、労働者の心身の安全を守るために職場環境を整えなければならないという安全配慮義務が課されています。
そのため、以下のような職場環境では安全配慮義務を怠ったために労災が発生したとみなされます。
- 高所での作業にもかかわらず安全ベルトなどの設備が不十分で転落した
- 有毒物質を吸って病気になった
- 長時間労働を強いたことでうつ病などを患った
このようなケースで労災が起こった場合、安全配慮義務違反にもとづいて会社に損害賠償請求が可能になります。
安全配慮義務違反については、こちらの関連記事『安全配慮義務違反は損害賠償の前提|慰謝料相場と会社を訴える方法』でも詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
第三者行為災害とは?
労災保険当事者以外の行為によって発生した労災事故を第三者行為災害といいます。
具体的には、以下のようなケースが第三者行為災害にあたります。
- 交通事故(自損事故をのぞく)
- 第三者から殴られた
- 第三者が飼っているペットに噛まれた
第三者行為災害は、第三者の故意や過失によって労災が生じたことなので、その第三者に対して損害賠償請求が可能になります。
労災保険給付と損害賠償請求で二重取りはできない
安全配慮義務違反や第三者行為災害の場合の労災は、労災保険に対する給付請求権と会社や第三者に対する損害賠償請求権の両方を取得したことになります。
つまり、労災保険に対して休業補償をはじめとした各給付を請求できるうえに、会社や第三者に対して損害賠償請求もできるということです。
ただし、両方から損害に対する補償を受け取ることは、実際に受けた損害よりも多くの補償を受け取ることになるため不合理です。
このため、労災保険法第12条の4において、労災保険給付と損害賠償請求との間で支給調整が行われて、どちらも受け取ることで労働者側が利益を得ないようになっています。
関連記事
被害者の過失割合によって減額される場合がある
会社や第三者だけでなく労働者にも労災の原因がある場合には、損害賠償でもらえる金額が減額となるので注意が必要です。
労災の原因の度合いを過失割合といい、休業損害は過失割合に応じて減額されることになります。
過失割合や休業損害額を決めるための会社との話し合いは「示談交渉」ともいい、交渉ノウハウを多く持つ弁護士に任せることで、不当な過失割合を押し付けられることを回避できるのです。
過失割合は最終的に手にできる損害賠償の金額に大きく影響するため、安易に決めてはいけません。
関連記事
休業補償だけでは不十分な場合は弁護士に相談しよう
労災事故の発生原因が会社にあるとき、労働者は会社に休業損害の損害賠償請求が可能です。
しかし、労災保険による休業補償のように法令で計算方法が定められているわけではありません。そのため、しばしば相手方と休業損害の金額が折り合わずに交渉が難航することもあります。
弁護士であれば休業損害の適正な金額を算定したり、会社側が提示してくる金額案の妥当性について判断可能です。
以上より、労災による休業補償とは別に会社へ休業損害を請求する場合は、法律の専門知識を豊富にもった弁護士に相談することをおすすめします。
労災で重い後遺障害が残ったり、ご家族を亡くされたりして、損害賠償請求を検討している場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。まずは下記フォームより、無料相談のご予約をお取りください。
ご予約の受付自体は24時間・365日いつでも受け付けております。気軽にご利用ください。
無料法律相談ご希望される方はこちら
詳しくは受付にご確認ください。
アトム法律事務所 岡野武志弁護士
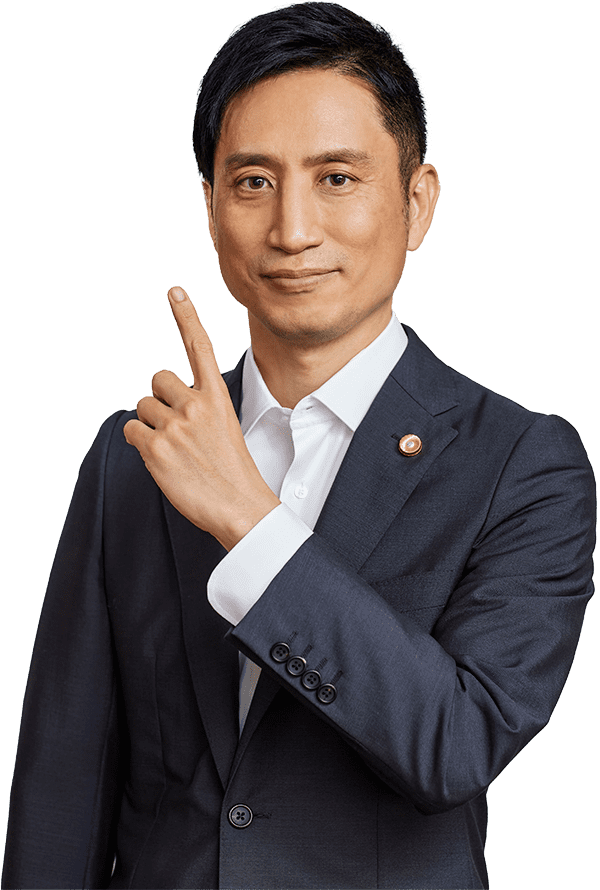

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了