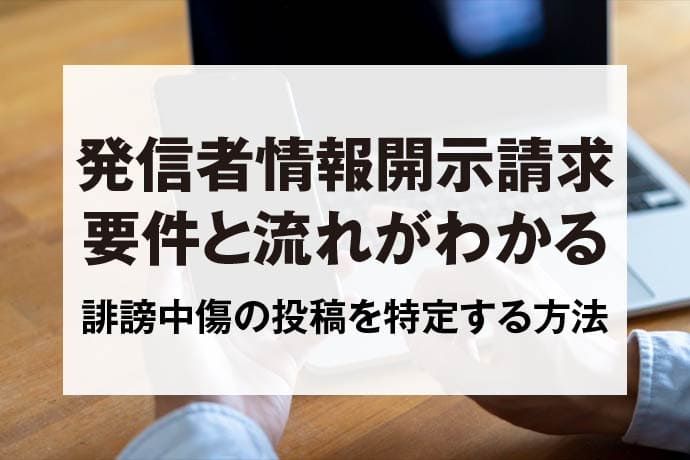【Q&A】削除依頼の対策はどうすればいい?|よくある質問
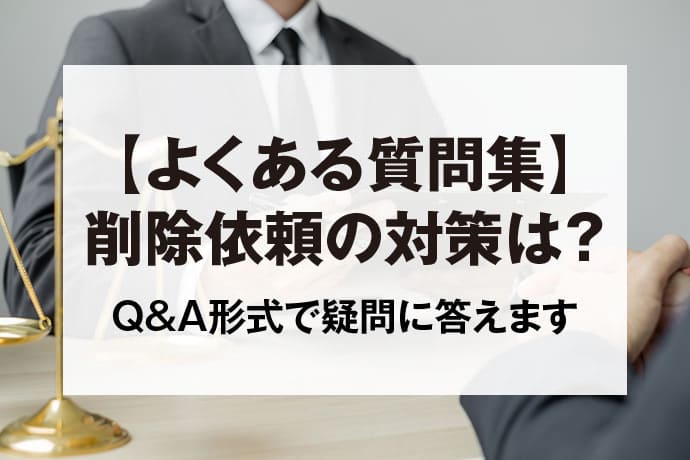
ここでは、次のようなお悩みを持つ方に向けて解説しています。
- ネット掲示板に書き込みされた個人情報を消したい
- ブログに無許可で掲載された顔写真を消したい
- ネットでの悪質な誹謗中傷による悩みを解決したい
ネット記事の削除依頼についてのQ&A
Q1 ネットで削除依頼ができるのはどんなケースですか?
基本的には、ネットで誹謗中傷された方が削除依頼をすることができます。特に問題になるのは、何らかの個人の権利が侵害されている場合です。
「名誉権」「プライバシー権」「著作権」などの権利侵害があれば、それを根拠に管理者に対して削除依頼をすることが可能です。
権利侵害の例
- 名誉権侵害:「Aさんには前科がある。」等の書き込み
- プライバシー侵害:住所、電話番号、口座番号などの書き込み
- 著作権侵害:他人が作成した動画を無断でYouTubeにアップする行為
インターネット上の誹謗中傷の対策方法については、以下の記事でも解説していますので参考にしていただければと思います。
Q2 自分で削除依頼をするとき、何かリスクはありますか?
削除依頼は、自分で管理者に対し行うことができます。その場合、正当な主張をしたからといって、必ずしも適切な対応をしてもらえるとは限りません。
削除依頼したこと自体をネットにさらされ、被害が拡大することもあります。管理者の運営方針や行動傾向から、さらなる炎上リスクを回避するためには、事前に専門家までご相談されることが望ましいでしょう。
弁護士が削除依頼をすることで、100%削除に成功するというわけでもありません。しかし、弁護士は法律の専門家ですので、様々な選択肢を用意することができます。少しでも炎上の可能性を下げるために、弁護士を通じて削除依頼をすることも検討してみてください。
Q3 誹謗中傷をした人の名前をTwitterで晒してもいいですか?
反撃としてTwitterなどのSNSで投稿者の情報をさらす行為は控えるべきです。掲示板やSNSなどで誹謗中傷を受けたとき、投稿者の目星がついているケースもあります。
ことの発端が仕事でのトラブルや交友関係で起こっていることも多いため、投稿者の予想がつくということも少なくありません。しかし、反撃をしてさらに事態が悪化するリスクも相当程度考えられるため、控えるべきだといえます。
反撃行為が行き過ぎると、今度は自分が「加害者」となってしまうこともあります。相手に対して不法行為をしたということで、一気に不利な立場に置かれることもあります。反撃したいという気持ちがあっても、自分で相手に制裁を加えるような行為をするべきではありません。
ネット削除の相談窓口についてのQ&A
Q1 「弁護士」と「削除業者」ではどちらが削除依頼に適していますか?
ネット記事の削除依頼は、被害者当人か、その者から依頼を受けた弁護士でなければ行うことができません。一番重要なことは、削除依頼を「弁護士が行っているか」という点です。
最近では、ネット上に書き込まれた誹謗中傷の投稿に対し「安く・早く対応する」とうたう削除業者も増えています。弁護士以外の者が報酬を得て削除依頼を行うことは、弁護士法違反として処罰の対象となってしまいます。ですので、削除依頼を「誰が対応してくれるのか」を必ず確認する必要があります。
特に、弁護士の中でもネットの誹謗中傷問題に詳しい人に相談されることが望ましいです。ネットの問題は、単に法律だけで解決できるものだけではなく、ウェブのリテラシーが求められるケースも多くあります。ネットの中のことは見えないことも多く、実践経験がとても重要です。
POINT
削除依頼で対応が難しい場合、「逆SEO」という技術的な対策方法もあります。問題解決に様々なアプローチ方法がありますので、状況に応じて最善の策を選択する必要があります。
ネット削除を弁護士に依頼するメリットについては以下の記事でも解説していますので参考にしていただければと思います。
Q2 費用のかからない相談窓口はありますか?
ネットでの誹謗中傷の問題を相談できる窓口はいくつかあります。中でも、無料で相談が受けられるところもありますので、積極的に活用してみましょう。
公益的な機関として相談を受け付けている窓口としては、次の2つが代表的です。これらは、誰でも利用することができます。ネットのトラブルに関する悩みがあれば、一度問い合わせてみましょう。
ただし公益的機関は、相談を受けている数が多いため、対応までに時間を要することがあります。急いで削除したい情報が流出している場合には法律事務所に相談しましょう。
Q3 「今から家に行くぞ」などの脅迫めいた投稿があった場合はどうすればいいですか?
「家に行って火をつける」「家族にも危害を加える」など、身に危険を感じるような投稿もありえます。そのときには、最寄りの「警察署」までご相談されるとよいでしょう。緊急性が高い事案として警察に訴えることが重要です。
脅迫ではなく、名誉毀損の問題であれば、警察署への相談はあらかじめ電話で担当者に内容を伝えて、アポをとることが大切です。事前に担当者に事情を伝えておくことで、スムーズに警察で相談を行うことができます。アポなしでの相談では、ネット問題に詳しい警察の方に対応してもらえないこともあります。
被害届、刑事告訴に関しては以下の記事でも解説していますので参考にしていただければと思います。
投稿者の特定についてのQ&A
Q1 3年前の投稿でも相手を特定することはできますか?
掲示板の投稿で、3年前に投稿されたコメントの場合、投稿者を特定することは難しいと考えられます。掲示板の投稿は、接続情報の痕跡が3ヶ月程度しか保存されないことが多く、3年も前のデータはすでに残っていない可能性が高いといえます。掲示板への接続情報を「アクセスログ」といいます。直近3ヶ月程度までであれば、アクセスログをもとに発信者情報までさかのぼることができると考えられます。
投稿者の特定は、どのような投稿でもできるというわけではありません。「誰の」「どのような権利が侵害されているか」が説明できるということが前提となります。これは法律上の判断が必要になりますので、弁護士に相談していただくことをおすすめします。
発信者情報開示請求については、以下の記事でも解説していますので参考にしていただければと思います。
Q2 投稿者への「損害賠償請求」と「刑事告訴」は両方できますか?
「損害賠償請求」と「刑事告訴」は両方行うことができます。投稿者を特定すれば、投稿者の名前や住所が判明します。民事事件として、相手に損害賠償を求める方法もありますし、刑事事件として相手に責任追及する方法もあります。両者は別次元の問題ですので、どちらかを選択すれば他方ができなくなる、というものではありません。
刑事事件として告訴をする場合は、捜査機関が捜査を進めてくれます。民事事件として相手に損害賠償を求める場合は、求める金額の算定や何を根拠に請求するかを整理する必要があるため、弁護士に相談されることをおすすめします。
Q3 投稿者の特定と削除は同時にすすめるべき?
投稿者の特定と投稿の削除は同時にすすめるべきではありません。たとえば、刑事責任を追及したい場合、削除したい対象が刑事事件の証拠となるからです。もし、削除請求を先にしてしまい、投稿が削除されると名誉毀損などの誹謗中傷があったことを証明できなくなります。その結果、投稿者を特定しても刑事責任を追及する術を失ってしまいます。これは、民事責任を追及する場面においても同様です。
投稿者の特定と削除の両方を行いたい場合、投稿者の特定を先にすべきといえます。投稿者を特定し、証拠を保全して刑事責任・民事責任が追及できる段階になったあとに、削除をするようにしましょう。
ネットの誹謗中傷に関しては、何をどうすればよいのか、わからないことが多いと思います。初めて風評被害を受けたというときには、どこに相談にいけばよいのかもわからないものです。そんなときは、ネットでの誹謗中傷に詳しい専門家に相談することが大切です。インターネットに詳しい弁護士への相談も検討してみてください。
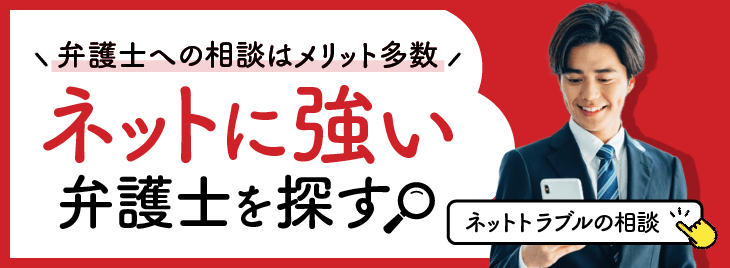

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了