専業主婦の離婚後の生活は成り立つ?貯金なしでも使える公的支援と収入確保
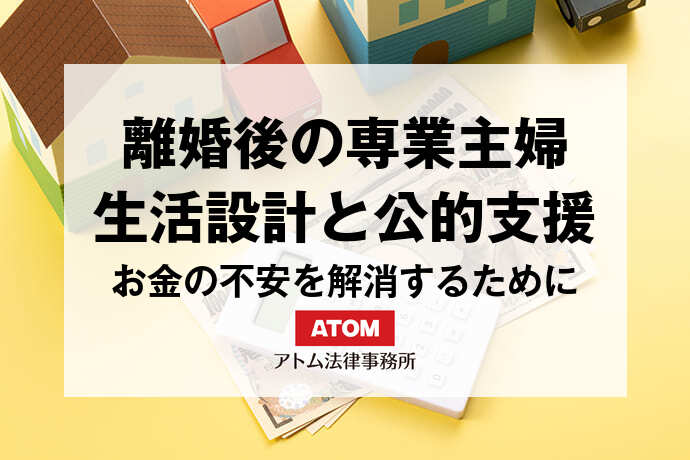
専業主婦が離婚後に必要な生活費は、子持ちの場合で月約26万円、単身の場合は月約18万円が目安です。この金額は、離婚時に請求できる財産分与や養育費、国や自治体の公的支援、そしてご自身の就労収入の3つを組み合わせることで確保できます。
貯金がない、お金がない、特別なスキルがないという状況でも、適切な準備と制度活用により、離婚後の生活を成り立たせることは十分に可能です。本記事では、専業主婦が離婚後の生活への不安を解消するために知っておくべき生活費の目安と収入を確保する3つの方法、利用できる支援制度の申請先と手続きについて解説します。
目次
専業主婦の離婚後に必要な生活費の目安
離婚後の生活を設計する第一歩は、毎月いくら必要かを把握することです。
離婚後の生活費をシミュレーションする
総務省統計局の2025年の家計調査報告によると、女性の一人暮らしやシングルマザー世帯の1か月の消費支出(生活費)は、以下が目安となります。
| 世帯構成 | 消費支出 |
|---|---|
| 母親と18歳未満の子どもの世帯 | 263,111円 |
| 34歳以下の一人暮らし女性 | 188,449円 |
| 35歳〜59歳の一人暮らし女性 | 183,805円 |
| 60歳以上の一人暮らし女性 | 154,695円 |
女性の一人暮らしはおよそ18万円、未成年の子どもをもつシングルマザーはおよそ26万円が生活費の平均となっています。
この平均は住居費を含んだ目安ですが、家賃は地域によって大きく変動します。また、子どもの教育費や習い事代なども、状況に応じて考慮する必要があります。
まずは自身の状況で、月々いくら必要か具体的に試算することが重要です。
離婚後の生活費は3つの収入源で確保する
専業主婦が離婚後の生活を設計するには、主に3つの収入源を組み合わせて考えます。
離婚時に請求できるお金
専業主婦であっても、離婚に際して法的に請求できる権利があります。これらは生活再建の基盤となる重要なお金です。
- 婚姻費用(離婚成立前)
離婚が成立するまでの間の生活費です。別居中に請求できます。 - 財産分与(離婚時)
婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を公平に分ける制度です。専業主婦でも原則として2分の1の権利が認められます。 - 年金分割(離婚時)
婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度です。 - 養育費(離婚後)
子どもが未成年の場合、子どもを監護していない親から受け取れる生活費・教育費です。 - 慰謝料(該当する場合)
相手の不貞行為やDVなどが原因で離婚する場合に請求できる精神的苦痛に対する賠償金です。
実務上、専業主婦が財産分与で不利になるケースとして、「相手名義の財産だから請求できない」と誤解して権利を放棄してしまうことがあります。
名義にかかわらず、婚姻期間中に形成された財産は実質的に夫婦の共有財産となるので、分与対象の財産を正確に把握しておくことが重要です。
関連記事
・専業主婦も離婚で財産分与は可能!熟年離婚は1000万が相場?
・子どもがいるときの財産分与|子ども名義の預貯金や学資保険はどうなる?
・専業主婦の年金分割は離婚後2年以内?条件・手続き・注意点を解説!
・離婚後の生活費はもらえる?支払い義務の解説と請求のための交渉術
国や自治体からの公的支援
「離婚時のお金だけで暮らしていけるか心配」という場合でも、生活を支えてくれる公的支援制度があります。具体的には次章で説明しますが、このような制度の活用は生活安定の鍵となります。
公的支援の多くは申請が必要であるため、離婚届提出の前後で、利用できる制度を市区町村窓口で確認しておきましょう。
関連記事
・離婚後住む場所がない!お金がなくても住むところを確保する公的支援
働くことによる収入
経済的自立のためには、ご自身の収入を得ることが最も安定した基盤となります。
特にシングルマザーは、仕事の面で厳しい現実に直面することも少なくありません。内閣府の「男女共同参画白書 令和4年版」によると、40代でシングルマザーになった人のうち、非正規雇用は46.9%と最も多く、短時間勤務も28.6%と高い割合を占めています。
また、ひとり親を対象にした調査では、就労年収が100万円未満の人が20.7%で最多となり、100〜150万円未満も20%と、収入は全体的に低い傾向が見られました(法制審議会家族法制部会第18回会議資料「離婚後等の子どもの養育に関するアンケート調査」より)。
こうした状況から、離婚前から準備を進めるとともに、公的支援や就労支援制度を積極的に活用することが、生活の安定につながります。
専業主婦の離婚後の生活を支える公的支援制度
財産分与や養育費など、離婚時に受け取るお金だけでは生活が不安な場合、公的支援制度を活用することで生活の安定を図れます。
これらは申請しなければ受けられないため、知っていることが重要です。
ひとり親家庭が受けられる支援制度
ひとり親家庭が申請によって受けられる公的支援制度として、児童扶養手当や医療費助成、児童育成手当等があります。
児童扶養手当
児童扶養手当は、子どもを養育するひとり親家庭に支給される手当です。
「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者を言います。
児童扶養手当 | 内閣府男女共同参画局
申請は市区町村役場で行います。支給額は所得に応じて変動します。
ひとり親家庭等医療費助成制度
一定の所得要件の下で、ひとり親家庭の親と子どもの医療費を一部または全部助成する制度もあります。
ひとり親家庭等医療費助成制度の申請を市区町村役場で行い、交付を受けた医療証を医療機関で提示することで助成が受けられます。
児童育成手当
自治体独自の制度として、児童育成手当が児童扶養手当に上乗せ、または別途支給される場合があります。
児童扶養手当の申請時に市区町村役場で確認しましょう。
住まいに関する支援制度
住まいに関する支援制度として、住居確保給付金や公営住宅・母子生活支援施設があります。
住居確保給付金
経済的に困窮し、住居を失うおそれがある場合、都道府県等が家賃相当額を支給します。
申請には収入や資産の要件があり、申請先は自立相談支援機関となります。
支給期間は原則3か月ですが、最大9か月まで延長できます。
公営住宅
公営住宅は、自治体が主体となり、経済的な理由で住まい探しが難しい方のために、相場より安い家賃で提供している制度です。
申請先は都道府県・市区町村役場で、申込方法や選考方法は自治体ごとに異なります。
DV被害者世帯やひとり親世帯など、特定の世帯に優先入居枠が設けられている場合もあります。
母子生活支援施設
母子生活支援施設は、母子家庭等を対象に、安い家賃で入居できる施設であり、生活全般の支援や相談、職業自立の支援も行っています。
申請先は都道府県・市区町村役場や福祉事務所です。
利用期間に制限がある場合もあるため、事前に確認が必要です。
教育・保育に関する支援制度
子どもの教育や保育に関する支援として、就学援助制度と保育料の無償化や減免があります。
就学援助制度
就学援助制度は、経済的理由で就学が困難な世帯に対し、小中学校の学用品費、給食費、修学旅行費等を援助する制度です。
学校や市区町村の教育委員会等から申請書類が配布されます。
援助内容や支給額、所得要件は自治体ごとに異なります。
保育料の無償化・減免
3歳〜5歳児は所得にかかわらず保育料が無償となります。
0歳〜2歳児については、住民税非課税世帯が無償化の対象です。
保育料の減免や無償化の具体的な条件や運用は自治体ごとに異なり、自治体独自の補助や減免制度が設けられている場合もあります。
税金や保険料の減免・猶予制度
収入や家庭の状況に応じて、税金の軽減や保険料の免除、猶予を受けられる場合があります。
国民年金と国民健康保険料の減免・猶予
失業や低所得など経済的理由により、国民年金や国民健康保険料の減免や猶予を受けられます。
前年所得が一定額以下の場合、年金事務所に申請すると、国民年金保険料の全額または一部の納付が免除されます。納付猶予や学生納付特例もあります。
国民健康保険料も減免や猶予制度があります。申請先は市区町村役場で、具体的な基準や手続きは自治体ごとに異なります。
寡婦控除・ひとり親控除
寡婦控除・ひとり親控除は、所得税や住民税の負担を軽減するための制度です。
寡婦控除は夫と死別または離婚した後に婚姻していない女性が対象、ひとり親控除は子を扶養するひとり親が対象です。
どちらも一定の要件を満たす場合に適用されます。
緊急時に利用できる支援制度
他の支援制度を活用しても生活が困難な場合のセーフティネットとして、生活保護があります。
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
生活保護制度 |厚生労働省
生活保護の申請・相談窓口は、居住地の福祉事務所です。
また、都道府県の社会福祉協議会が実施する公的な貸付制度もあります。
生活福祉資金貸付制度は、低所得者、高齢者、障害者などが、安定した生活を送れるよう、都道府県の社会福祉協議会が資金の貸付けと必要な相談や支援を行う制度です。
政府広報オンライン
生活福祉資金貸付制度のひとつである緊急小口資金は、緊急かつ一時的に生活費が必要な場合に原則無利子で少額の貸付を受けられます。
申請窓口は市区町村の社会福祉協議会です。
専業主婦のブランクを支援する無料の相談窓口
離婚後の生活を安定させるためには、仕事を見つけることが大切です。しかし、専業主婦の期間が長いと、スキルや職歴がないと不安になるのは無理もありません。
だからこそ、国や自治体の再就職支援制度を積極的に活用することが重要です。
ハローワーク(公共職業安定所)
ハローワークは全国に設置されている国の機関です。
求職相談や職業紹介、求人情報の提供、履歴書・面接指導、各種セミナーなど、仕事探しに関する幅広い無料サービスを提供しています。
企業への紹介状の発行や、就職活動に必要なアドバイスも受けられます。
マザーズハローワーク
子育て中の女性の仕事探しをサポートするマザーズハローワークもあります。
子連れで来所しやすい環境や、保育情報の提供、担当者制によるきめ細かな支援など、子育てと就職活動の両立を支援する体制が整っています。
一般のハローワーク内に、マザーズコーナーが設置されている場合もあります。
公的職業訓練(ハロートレーニング)
国や地方自治体が実施する職業訓練制度で、PCの操作や医療事務、介護など再就職に必要な知識や技能を無料または一部教材費のみで学ぶことができます。
ハロートレーニングは、希望する仕事に就くために必要な職業スキルや知識などを習得することができる公的制度です。
ハロートレーニング|厚生労働省
訓練期間や内容はさまざまで、訓練中に手当が支給される場合もあります。
自治体の就労支援窓口
多くの市区町村が、女性向けやひとり親向けの就労支援センター、就労相談窓口を独自に設けており、地域の実情に応じたきめ細かな支援を行っています。
これらの窓口では、職業相談、求人情報の提供、職業訓練の案内、履歴書作成や面接指導、各種セミナーの開催など、再就職に向けたサポートを受けられます。
専業主婦が離婚前に準備すべきこと
お金がない状態での離婚を避けるため、離婚前であれば以下の準備を進めておくようにしましょう。
- 当面の生活費の確保
離婚後すぐの生活費として、最低でも3か月分、できれば半年分の生活費を貯蓄として確保しておくことが望ましいです。 - 離婚後の生活シミュレーション
必要な生活費、養育費や公的支援で得られる収入、不足分を補う仕事の収入など、具体的な収支計画を立てます。 - 利用できる支援制度の事前リサーチ
ご自身の状況で利用できそうな公的支援を、事前に役所などで確認しておきます。 - 弁護士への無料相談
財産分与や養育費などを適正な条件で受け取るため、離婚問題に詳しい弁護士へ事前に相談し、法的な見通しを立てておくことが重要です。 - 子どもの預け先の確保
子どもがいる場合は仕事探しの前に保育所や学童保育の確保が必要となるため、市区町村役場の保育課に相談しておきます。
専業主婦の離婚は、経済的な不安が先行しがちです。
しかし、離婚時に請求できる法的な権利と、利用可能な公的支援制度を正しく理解し、活用することで生活を立て直すための見通しが立ってくるはずです。
「お金がない」「貯金がない」「なんの取り柄もない」と一人で抱え込まず、まずは弁護士などの専門家に相談し、ご自身の状況でどのような選択肢があるかを確認することから始めてください。
専業主婦の離婚後の生活に関するよくある質問
Q. 貯金なしの専業主婦でも離婚して生活できますか?
貯金がないまま離婚する場合、まず確保すべきなのは離婚成立までの生活費(婚姻費用)です。別居中であれば配偶者に法的に請求できます。あわせて、財産分与や養育費を確実に取り決め、初期資金を確保しましょう。
離婚直後は、児童扶養手当や住居確保給付金など即効性のある公的支援を優先的に申請することで、当面の生活費を補えます。
Q. 専業主婦でも財産分与はもらえる?
専業主婦であっても、財産分与を受ける権利があります。財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産について、名義にかかわらず原則として2分の1ずつ分けることが認められています。
Q. なんの取り柄も資格もないですが仕事は見つかる?
ハローワークやマザーズハローワークでは、無料で求職相談や職業紹介、履歴書添削、面接指導などの支援を受けることができます。
公的職業訓練を利用すれば、パソコンスキルや医療事務など再就職に必要な資格を無料または低額で取得することも可能です。
子育て中の女性向けに特化した支援窓口も多く設けられているため、まずは相談してみることをおすすめします。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
