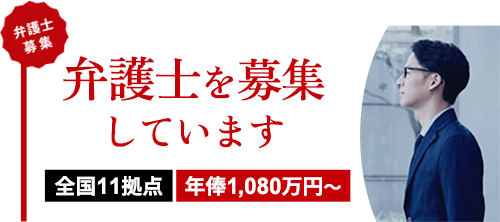介護職の腰痛は労災保険により補償される?認定のポイントを解説
更新日:

介護職は、重労働かつ不自然な体勢で行う作業も多く、腰痛になりやすい職種といえます。
腰痛を発症させてしまった場合、労災認定されることで労災保険による補償を受けることが出来ます。とはいえ、労災保険の適用にはさまざまな要件があり、常に労災保険が適用されるというものではありません。
本記事では、介護職をはじめとする職場での腰痛における労災認定のポイントについて解説を行います。
目次
腰痛で労災認定される要件について
まずは、腰痛において、いかなる場合に労災認定されるかについて解説します。労災認定されるためには、ポイントをおさえた資料や記載が不可欠です。これから解説する点をしっかりと認識して、資料の作成等を行いましょう。
腰痛は2種類に区分される
腰痛について、労災認定の判断では厚労省のHPのうち「腰痛の労災認定」についての記載内容がとても参考になります。この基準によると、腰痛について以下のように区分されております。
- 災害性の原因による腰痛
- 災害性の原因によらない腰痛
まずは、ご自身の腰痛が、いずれの腰痛に当てはまるのか検討しましょう。
災害性の原因による腰痛の場合
災害性の原因による腰痛とは、以下の(a)と(b)のいずれも満たし、治療の必要性があるものをいいます。
(a)腰の負傷又はその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
(b)腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと学的に認められること
このような要件を満たせば、労災保険より補償を受けることができます
たとえば、介護職の場合であれば、利用者をベッドに移乗させる際などに突発的に腰を痛めてしまったケースが考えられるでしょう。
災害性の原因によらない腰痛の場合
災害性の原因によらない腰痛とは、日々の業務による腰部への負荷が徐々に蓄積して発症した腰痛をいい、発症原因により、さらに以下の二つに区分されています。
(ア)筋肉等の疲労を原因とした腰痛
次のような業務に約3ヶ月以上従事したことによ筋肉等の疲労を原因とした腰痛になった場合には、労災認定されます。
- 約20キロ以上の重量物又は重量の異なる物品を繰り返し中腰の体勢で取り扱う業務(港湾荷役など)
- 毎日数時間程度、腰にとって極めて不自然な姿勢を保持して行う業務(配電工など)
- 長時間立ち上がることも出来ず、同一の姿勢を保持して行う業務(長距離トラックの運転手など)
- 腰に著しく大きな振動を受ける作業(車両系建設用機械の運転業務)
(イ)骨の変化を原因とした腰痛
次のような重量物を取り扱う業務に相当長期間(約10年以上)にわたり、継続したことによる骨の変化を原因として発症した腰痛は労災認定されます。
- 約30キロ以上の重量物を、労働時間の3分の1程度以上に及んで取り扱う業務
- 約20キロ以上の重量物を、労働時間の約半分程度以上に及んで取り扱う業務
- 上記(ア)の業務に約10年以上にわたって従事した後、骨の変化を原因とする腰痛が生じた場合
災害性の原因によらない腰痛である場合、㋐㋑に挙げた要件に該当するかを検討することになります。
そして、労災申請をする際には、上記で挙げた認定基準に沿うような資料や医師の意見などを収集することが必要となります。
介護職の場合は、勤務内容や勤労期間、腰痛の症状等を詳しく記載した書面や診断書を提出することになるでしょう。
腰痛の関連記事
介護により腰痛になりやすい作業とは
介護業務において、腰痛発生の要因となりやすい作業について紹介します。
- 移乗介助
利用者のベッドから車いす、または、車いすからベッドなどへと移動させる介助をいいます - 入浴介助
入浴のために利用者を浴槽へと移動させる際に腰を痛めやすいといえます - トイレ介助・おむつ交換
トイレへの移動や着衣の上げ下げ、おむつ交換の際に前傾姿勢になることなどから腰痛が発生しやすいでしょう - 体位交換
前傾姿勢や中腰になって体位を変えるため、腰への負担が大きい作業です - 更衣介助
着衣の上げ下げのために中腰になったり、寝たきりの利用者では前傾姿勢を維持する必要があるため、腰痛の要因になりやすいといえます
労災による腰痛における補償内容
腰痛を悪化させてしまい、欠勤や退職をしてしまった場合、労災保険からどのような補償を受けることが出来るでしょうか。
ここでは、腰痛により労災認定された場合に受給できる給付内容の説明をします。
労災保険給付の種類について
労災保険給付には、主なものとして以下の種類の補償があります。
- 療養(補償)給付:治療費の支払
- 休業(補償)給付:休業療養中の生活補償
- 障害(補償)給付:後遺障害に対する給付
- 傷病(補償)給付:受傷から1年6ヶ月を経過した重篤な傷病に対する給付
- 介護(補償)給付:重篤な傷病によって受ける介護に対する給付
給付を受けるための要件や、具体的な給付内容について知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。
- 療養(補償)給付
労災の治療費は療養(補償)給付から|給付内容や手続きについて解説 - 休業(補償)給付
労災における休業補償の計算方法は?給付条件・期間・申請手続きを解説 - 障害(補償)給付
労災の後遺障害とは?障害等級の認定基準と金額早見表、給付の流れ
具体的な受給例
ここで、具体的なケースについて考えていきたいと思います。
介護職であるAさんは、利用者を車椅子からベッドに移乗させている際、腰に強い痛みを覚えた後、強度の腰痛・指先に痺れなどの状態が生じました。その後、約半年間治療を行いましたが、痛みは取れず、医師からはこれ以上の治療を行っても効果が出ない旨、話されました。
この事例では、Aさんは速やかに腰痛を生じさせたことについて事業主に報告しなければなりません。事業主は、申請書類に記載をして労基署に労災申請を行います。労災が認定されればAさんは半年間、療養補償給付を受給することができるため、治療費を自分で負担する必要はありません。
また、Aさんが腰痛を発症後、欠勤した場合は休業補償給付より平均賃金相当額のうち、最大で80%が支給されます。
加えて、治療が終了した時点で後遺障害が発生している場合、障害一時金の支給がされます。
なお、仮に後遺障害等級が14級であれば、障害一時金として平均賃金相当額の56日分が支給されることになるでしょう。
労災事故で損害賠償請求するための方法
労災事故が事業主の原因により生じている場合は、労災保険給付に加えて、事業主に損害賠償請求をすることができる可能性があります。
ここでは、民事上の損害賠償請求を行うための方法について解説をします。
事業主の安全配慮義務違反が必要
事業主に損害賠償請求をする場合、その根拠として考えられるのは、職場の安全配慮義務違反にもとづく損害賠償請求となります。
事業主は、労働者が安全に勤務することができるように配慮する安全配慮義務があるとされており、そのような義務に反した場合は安全配慮義務違反といえます。
事業主の安全配慮義務違反が原因で腰痛となった場合には、事情主に対する損害賠償請求が可能となるのです。安全配慮義務違反の有無を判断する基準については、関連記事を参考にしてください。
安全配慮義務違反の関連記事
厚労省の指針等を参考に資料の収集を行う
労災というものは、いかなる労働環境でも起こりうるものといえます。
しかし、安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求をする場面では、事業主のどのような義務があり、それに違反していたかということを具体的に考える必要があります。
その際に、役に立つのが厚労省から発表されている「職場における腰痛予防対策指針」です。
この指針では、福祉、医療分野等における介護・介護作業についても取り上げられております。
たとえば、移乗介助等における対象者の抱上げについて、労働者の腰部に著しく負担がかかることから、リフト等を積極的に使用することとし、原則として人力による人の抱上げは行わせないことという記載もあります。
この指針に従っていないからといって直ちに違法性があるとはいえませんが、事業主の安全配慮義務違反の有無を考える上で、参考になる記載です。
具体的には、以下のような腰痛対策を行えていたのかという点に注目することになります。
- 利用者の身体状態に応じた適切な福祉用具を活用していたのか
- 腰への負担を軽減できる介助動作や方法の指導を行っていたのか
- 介護職員の健康状態を定期的にチェックしていたのか
- 介護職員に過度の負担が生じないよう適切に休暇や休憩を与えていたのか
損害賠償請求を考える際には、上記指針等を参考にし、客観的に事業主に安全配慮義務違反があったのかを検討しましょう。
労災が起こった原因次第では弁護士相談も必要
腰痛が労災として認定されることで、治療にかかる費用や休業時の補償を受けられる点は安心につながるポイントです。
しかし、労災保険と損害賠償請求は別物だということには留意しましょう。事業主に対する損害賠償請求が認められるのは、安全配慮義務違反など落ち度がある時に限られます。
会社の落ち度を証明することは、専門知識が欠かせず容易ではありません。どんな法的根拠に基づいて損害賠償を請求できるのかは、法律の専門家である弁護士への相談を検討しましょう。
- 事業主に安全配慮義務違反があったといえそうか
- 損害賠償請求するべき慰謝料の相場はいくらなのか
- 事業主から提示された損害賠償金は妥当なのか
たとえばこうした疑問や不安は、一人で悩むよりも、弁護士に相談するほうが解決に近づく可能性があります。
また、弁護士に正式に依頼すれば、慰謝料を含む損害賠償請求を代理してもらえるため、仕事や家事などの日常生活への復帰もしやすいでしょう。
労災の損害賠償請求に関して弁護士に相談・依頼するメリットは、関連記事『労災に強い弁護士に相談するメリットと探し方|労災事故の無料相談はできる?』で紹介しているとおり、多数あります。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了