離婚の引越しはいつが正解?タイミングの判断基準と手続きの流れを解説
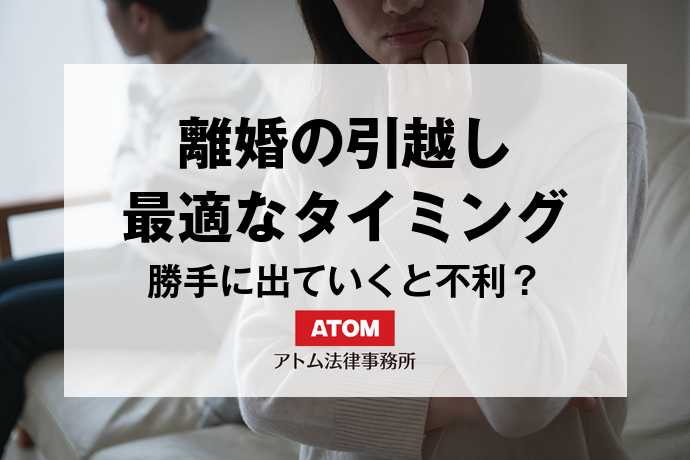
離婚に伴う引越しでは、「離婚届を出す前に引っ越すべきか、それとも離婚成立後か」で悩む方が多くいます。
DVやモラハラがある場合や、相手が離婚に応じない場合は、身の安全を守るために離婚前に別居することが有効です。一方、話し合いが円満に進んでおり、財産分与で引越し費用を確保したい場合は、離婚成立後に引っ越す方がスムーズです。
ただし、正当な理由なく離婚前に家を出ると、「悪意の遺棄」と判断されるおそれや、手続きが二度手間になる可能性もあります。そのため、状況に応じた慎重な判断が必要です。
本記事では、引越しの適切なタイミングの考え方から、役所手続きの流れ、不利にならないための注意点、費用面の対処法までを分かりやすく解説します。
目次
別居先行の引越し?離婚成立後の引越し?
離婚届の提出と引越し、どちらを先に行うかで手続きの流れやメリットは大きく変わります。
自身の状況に合わせて、どちらが適しているかを確認してください。
| 判断軸 | 別居先行 | 離婚成立後 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 安全確保・精神的平穏 | 費用の節約・手間の削減 |
| 費用面 | 婚姻費用を請求できる | 財産分与を費用に充てられる |
| 手続き | 住所変更と氏名変更が別々 | 住所と氏名の変更を同時処理 |
別居や引越しを先行させた方がよいケース
以下の項目に当てはまる場合は、離婚届を出す前に別居を開始することを検討します。
- DVやモラハラを受けており身の危険がある
- 相手が離婚に反対しており、別居の実績を作って婚姻関係の破綻を証明したい
- 同居のストレスが限界に達している
- 別居中の生活費である婚姻費用を請求し、経済的な基盤を確保したい
別居を先行させるメリット
離婚前に別居を始める最大のメリットは、精神的な平穏を早期に確保できる点です。
相手と物理的な距離を置くことで、冷静に離婚協議を進めることが可能になります。
また、法的な観点からも意味があります。別居期間が長期化すれば、夫婦関係が破綻している客観的な証拠となり、裁判などで離婚が認められやすくなるからです。
さらに、別居中は収入の多い配偶者に対して婚姻費用つまり生活費を請求できる権利が生じるため、当面の生活基盤を確保しやすいという利点もあります。
別居を先行させるデメリット
離婚届を出す前に住所を変えるため、住民票の異動や世帯主の手続きが一時的なものになる可能性があります。
離婚成立後に再び氏名の変更や戸籍の手続きが必要となり、役所へ行く回数が増えるなど事務的な手間がかかります。
また、財産分与が決まる前に動くため、初期費用を一時的に自分で負担しなければならないケースが多くなります。
離婚成立後の引越しが向いているケース
以下の項目に当てはまる場合は、同居したまま離婚条件を決め、離婚届提出と同時またはその後に引っ越すのがスムーズです。
- 財産分与や親権について話し合いが円満に進んでいる
- 財産分与で得たお金を引越し費用に充てたい
- 子どもの転校手続きなどを一度に済ませたい
- 相手が協力的で、急いで家を出る必要がない
離婚成立後に引っ越すメリット
離婚届を出してから、あるいは同時に引越しをする最大のメリットは、手続きの効率良さです。
離婚による氏名の変更と住所変更を一度のタイミングで行えるため、運転免許証や銀行口座の名義変更といった煩雑な作業を最小限に抑えることができます。
また、離婚協議で決まった財産分与や解決金を引越し費用に充てることができるため、資金計画が立てやすいという経済的なメリットもあります。
離婚成立後に引っ越すデメリット
離婚条件が合意に至るまで同居を続けなければならないのは大きなデメリットです。
関係が悪化した相手と同じ空間で生活するストレスは計り知れず、精神的に消耗してしまうリスクがあります。
相手が話し合いを引き延ばした場合、いつまでも新生活を始められないという閉塞感を感じることもあるでしょう。
勝手に出ていくと不利?引越し前に知っておくべきリスク
別居を検討する際、勝手に家を出ると不利になるのではないかと不安に感じる人がいます。
ここでは、よくある誤解と正しい対処法を解説します。
悪意の遺棄とは何か
民法には夫婦の同居義務がありますが、単に別居しただけでは直ちに法律違反にはなりません。
問題となるのは悪意の遺棄に該当する場合です。
悪意の遺棄とは、正当な理由なく同居を拒否し、相手の生活費を渡さないなど、夫婦としての協力義務を放棄して相手を見捨てる行為を指します。
性格の不一致やDVからの避難など、正当な理由があって別居する場合は、悪意の遺棄には当たりません。
不利にならずに別居を始めるためのポイント
同居義務違反と主張されないためには、可能な限り、離婚を前提とした別居であることを相手に伝え、合意を得てから家を出ます。
話し合いが難しい場合でも、行き先や連絡先、離婚を前提とした別居である旨を置き手紙やメールで残します。これにより、勝手な家出ではないという証拠になります。
ただし、身の危険がある場合は、何も告げずに直ちに避難してください。この場合、法律上の非難を浴びることはありません。
DVやモラハラから身を守るための住所保護
DVやモラハラの被害者が新居の住所を加害者に知られると危険な場合、住民基本台帳の閲覧制限(支援措置)を利用して住所を非公開にする公的な制度があります。
利用するには、警察や支援センター等でDVの事実を証明する書類を取得し、市区町村役所で申出を行うことで、加害者からの追跡を防ぐことができます。
離婚に伴う引越しでやることリスト
離婚に伴う引越しは、通常よりも手続きが多く複雑です。時期ごとにやるべきことをまとめました。
物件探しと準備|引越し1ヶ月前から2ヶ月前
離婚の話し合いと並行して、新生活の基盤を整える時期です。この時期に進めておくべき主な準備は次のとおりです。
- 新居の物件探しと契約
- 引越し業者の見積もりと手配
- 子どもの転校相談
- 別居の準備
定職がない場合やパート勤務の場合、賃貸審査が厳しくなることがあるため、保証会社の利用や親族の代理契約が必要か確認します。
子どもがいる場合は現在の学校と引越し先の学校、または教育委員会へ連絡を入れましょう。
荷造りのコツや相手に気づかれずに準備する具体的な手順については、関連記事『離婚のための別居準備|こっそり進める手順と不利にならない別居の仕方』を参照してください。
転出とライフラインの手続き|引越し1週間前から2週間前
引越し直前は以下の手続きを行いましょう。
- 転出届の提出
- ライフラインの手続き
- 郵便物の転送届
転出届は現住所の市区町村役所に提出し、転出証明書を受け取ります。マイナンバーカードを持っている場合は、転出証明書の提出が不要になることもあります。
新居では、電気・ガス・水道・インターネットなどの開始手続きを行います。立ち会いが必要な場合もあるので、あらかじめ日程を調整しておきましょう。状況に応じて、旧居の契約の解約手続きも進めます。
また、郵便局には転送届を出します。新住所を相手に知られたくない場合は、転送届を出さずに局留めを利用するといった対策も検討します。
転入届と住民票の手続き|引越し当日以降14日以内
引越しを終えたら、速やかに行政の手続きを行います。
- 転入届の提出
- 世帯主の設定
- マイナンバーカードの住所変更
- 国民健康保険と国民年金の住所変更
転入届は、引越しから14日以内に新住所の役所へ提出します。
離婚届提出前の別居の場合、住民票の世帯主をどうするか決める必要があります。自分を世帯主にしておくと、その後の児童手当や各種手当の申請がスムーズに進むことが多いです。
氏の変更と名義変更|離婚届提出後
生活が落ち着いた段階、または協議が整った段階で離婚届を提出し、氏名の変更に伴う手続きを行います。
- 離婚届の提出
- 氏(名字)の変更手続き
- 各所への名義変更
旧姓に戻る場合は、離婚届の提出と同時に処理されることが多いですが、子どもの氏を変更するには家庭裁判所の許可が必要です。
子どもがいる場合の引越しと転校手続きの注意点
子どもの環境変化を最小限にするため、学校や手当の手続きは慎重に行います。
公立小中学校の転校手続きの流れ
まず、現在在籍している学校の担任へ転校する旨を伝え、在学証明書と教科用図書給与証明書を受け取ります。
次に、新住所の役所で転入届を提出する際、学校から受け取ったそれらの書類を窓口で提示し、入学通知書の発行を受けます。
最後に、指定された転校先の学校へ行き、手元にある在学証明書、教科用図書給与証明書、入学通知書の3点を提出することで手続きが完了します。
なお、離婚成立まで現在の学校に通わせたい場合などは、学区外通学が認められることがあるため、教育委員会へ相談してください。
児童手当と児童扶養手当の手続き
児童手当の受給者が夫になっている場合でも、妻が子どもと同居していれば、離婚後に受給者を妻へ変更できます。
また、別居中であっても、妻が子どもを実際に監護しているのであれば、受給者を変更することが可能です。
児童扶養手当は原則として離婚後の申請ですが、離婚協議中であっても、別居して子どもを監護している場合には申請できるケースがあります。
引越し費用がない場合はどうする?
まとまったお金が必要な引越し費用をどう捻出するかは切実な問題です。
別居中であっても、夫婦である以上、収入の多い側が少ない側の生活費を分担する婚姻費用分担義務があります。
別居時に持ち出した財産や、引越し費用などの一時的な支出は、財産分与で調整、精算されることが一般的です。
引越し費用の具体的な相場や、相手に請求するための詳しい手順については、関連記事『離婚の引っ越し費用はいくら?相場と夫に請求する方法』をご覧ください。
手元の資金が乏しく賃貸契約自体が難しい場合や、DVやモラハラなど緊急に避難場所を確保する必要がある場合は、関連記事『離婚後住む場所がない!お金がなくても住むところを確保する公的支援』をご確認ください。
離婚の引越しでよくある質問
Q. 離婚前に引っ越すと不利になる?
正当な理由があれば、別居しても直ちに不利になることはありません。DVや虐待からの避難、すでに婚姻関係が破綻している場合などは「正当な理由」にあたり、悪意の遺棄には該当しません。一方で、配偶者に居場所を知らせず、連絡も取らない状態が続くと、悪意の遺棄と判断される要因になることがあります。
なお、共有財産を無断で持ち出した場合は、後の財産分与で清算が必要になる点には注意が必要です。
Q. 引越しと離婚届はどちらを先に出すべき?
離婚届と引越しを同じ時期に行うと、氏名変更と住所変更を一度に処理でき、運転免許証や銀行口座などの手続きの負担を減らせます。
一方で、DVや同居による強いストレスがある場合は、安全と心身の安定を最優先し、離婚前に引っ越すことをおすすめします。
Q. 別居中でも婚姻費用は請求できる?
別居中であっても、離婚が成立するまでは婚姻費用を請求できます。収入の多い配偶者には、収入の少ない側の生活費を分担する法的な義務があります。相手が支払いに応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることで、支払いを求めることができます。
Q. 子どもの住民票を移すと親権で不利?
住民票を移すこと自体で不利になることはありませんが、引越し後も子どもの監護を継続していることが重要です。日常の世話や学校行事への参加など、主に子どもを育てていることが分かる行動は、記録に残しておきましょう。
ただし、相手に無断で遠方へ連れ去った場合は、問題とされる可能性があるため注意が必要です。
Q. 引越し費用を相手に請求できる?
別居に伴う引越し費用は、財産分与の際に精算されるのが一般的です。DVからの避難など緊急性が高い場合には、引越し費用が例外的に公的な支援の対象となったり、婚姻費用の一部として請求できることもあります。いずれの場合も、領収書や見積書は必ず保管し、後の話し合いで提示できるようにしておきましょう。
自分に合ったタイミングで新しい生活への一歩を
離婚に伴う引越しは、人生の再出発に向けた重要なステップです。
手続きは多岐にわたりますが、ひとつずつ確実に進めていけば無事に新しい生活を迎えられます。
まずは、自身の状況において離婚と引越しのどちらを優先すべきかを判断し、計画を立てることから始めてください。
法的な判断に迷う場合や、相手との交渉が難航する場合は、弁護士への相談も検討することをおすすめします。
専門家の助けを借りることで、不利な条件を回避し、安心して新生活をスタートさせることができます。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
