離婚後住む場所がない!お金がなくても住むところを確保する公的支援
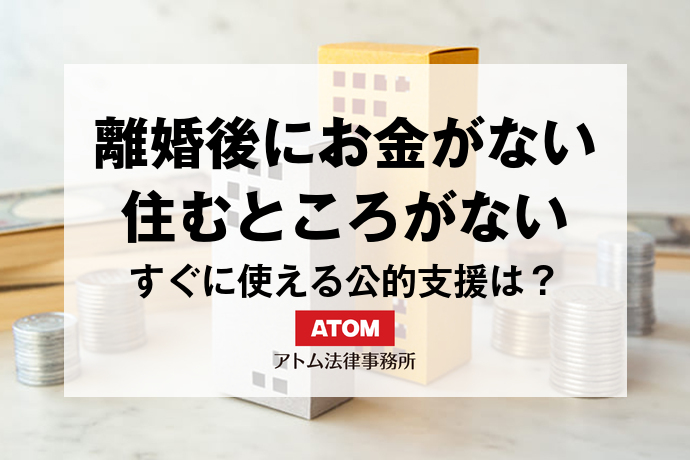
離婚によって住む場所を失う状況は、人生において最も不安を感じる瞬間の一つです。
しかし、手元に資金がない場合や保証人がいない場合でも、生活を立て直す方法は存在します。
国や自治体は、住まいに困っている人のためのセーフティネットを用意しています。
この記事では、離婚後にお金がない、住むところがないと悩む方に向けて、緊急度に応じた避難先や公的な支援制度、低予算で入居できる住まいの選択肢を解説します。
まずは自身の状況に合わせて、安全を確保することから始めましょう。
目次
今すぐ住む場所を確保するための行動手順
住む場所がないという悩みは、その緊急度によって取るべき行動が異なります。
身体的な危険が迫っている場合と、経済的に行き詰まっている場合では相談先が違うため、自身の状況に適した窓口へ直ちに連絡することが重要です。
暴力の危険がある場合はシェルターや支援センターへ
配偶者からの暴力やモラハラによって身の危険を感じている場合は、何よりもまず安全な場所へ避難することを最優先してください。
所持金がなくても、着の身着のままであっても受け入れてくれる場所があります。
最寄りの配偶者暴力相談支援センターや警察署の生活安全課へ連絡することで、公的なシェルターや一時保護施設を紹介してもらえる可能性があります。
これらの施設は場所が非公開となっており、加害者が追跡できないように配慮されています。
相談は匿名で行うことも可能であり、まずは電話で状況を伝えることが命を守る第一歩となります。
暴力はないが所持金がない場合は福祉事務所へ
暴力の被害はないものの、所持金が尽きてしまい、今夜寝る場所やネットカフェ代すら払えないという場合は、現在地を管轄する自治体の福祉事務所へ向かってください。
福祉事務所では、生活に困窮している人に対し、無料または低額で宿泊できる緊急一時宿泊施設や、更生施設を紹介する対応を行っています。
また、自治体によってはビジネスホテルを一時的な避難先として提供するケースもあります。
住む場所がない状態は行政による保護の対象となるため、遠慮せずに窓口で、今夜泊まる場所がない事実を伝えてください。
実家や知人を頼れる場合の一時避難
実家や友人を頼ることができる場合は、一時的な避難先として協力を仰ぐことも有効な手段です。
ただし、長期間の滞在は相手の生活に負担をかけ、新たなトラブルの火種となるリスクがあります。
あくまで次の住居が決まるまでの短期間の滞在と割り切り、滞在させてもらう間に公的支援の申請や新居探しを並行して進める計画性が必要です。
離婚後にお金がない住むところがない時に使える公的支援
住む場所が見つからない最大の要因は、初期費用や家賃を支払う資金不足にあることが大半です。
しかし、経済的に困窮している人を支えるための公的な制度が日本には複数用意されています。
これらの制度は国民の権利であり、利用することにためらいを感じる必要はありません。
家賃相当額が支給される住居確保給付金
離職や廃業、または個人の責任によらない理由で収入が減少し、住居を失うおそれがある人に対して、自治体が家賃相当額を支給する制度が住居確保給付金です。
この制度を利用することで、原則として3ヶ月間、最大で9ヶ月間、家賃相当額が家主へ直接支払われます。
離婚に伴って世帯収入が激減した場合も相談の対象となり得ます。
申請窓口は自立相談支援機関となっており、多くの場合は福祉事務所や社会福祉協議会の中に設置されています。
ハローワークでの求職活動が要件となる場合が多いため、まずは窓口で要件を確認することをお勧めします。
最低限の生活を保障する生活保護制度
離婚直後で職もなく、病気や育児で働くことが難しい状況であれば、生活保護の申請を検討してください。
生活保護は、憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活を営むための制度です。
生活保護には生活扶助だけでなく、アパートの家賃を補助する住宅扶助も含まれています。
これにより、敷金や礼金などの初期費用も含めて行政が負担してくれる場合があります。
離婚が成立する前であっても、実質的に世帯が分かれており困窮していれば申請は可能です。申請先は現在住んでいる、あるいは避難している地域の福祉事務所です。
親族への照会を心配する方もいますが、虐待などの事情があれば照会を控えてもらうことも可能です。
ひとり親家庭が利用できる母子父子寡婦福祉資金貸付金
ひとり親家庭、またはこれからひとり親になる人が利用できる公的な貸付制度として、母子父子寡婦福祉資金貸付金があります。
この制度の中には、転宅資金という項目があり、引っ越しに必要な敷金、礼金、運送代などを有利子または無利子で借りることができます。
民間のローンよりも圧倒的に低い金利、あるいは無利子で利用できる点が大きなメリットです。
申請から貸付決定までには時間がかかる場合があるため、早めに市区町村の福祉担当窓口へ相談することが重要です。
保証人なしや低予算でも借りられる住まいの選択肢
資金面での目処が立ったとしても、保証人がいない、あるいは審査が通るか不安という壁にぶつかることがあります。
しかし、民間の賃貸物件以外にも目を向けることで、住居確保のハードルは下がります。
家賃が安く優先入居枠がある公営住宅
都道府県や市区町村が運営する公営住宅は、民間の相場よりも家賃が安く設定されています。礼金や仲介手数料、更新料が不要である点も大きな魅力です。
多くの自治体では、ひとり親世帯に対して当選確率を優遇したり、別枠での募集を行ったりする措置をとっています。
収入が低いことが入居の条件となっているため、経済的な不安がある方こそ利用しやすい住宅です。
募集時期が限られていることが多いため、役所の住宅課で最新の募集状況を確認してください。
初期費用を抑えられるUR賃貸住宅
UR都市機構が管理するUR賃貸住宅は、礼金、仲介手数料、更新料、保証人がすべて不要という特徴があります。
保証人を頼める親族がいない場合でも、本人の身分証明と収入証明があれば契約が可能です。
初期費用を大幅に抑えられるため、手持ちの資金が少ない場合の有力な選択肢となります。
家賃は周辺相場と同程度ですが、退去時の原状回復負担区分が明確であり、安心して長く住み続けられる環境が整っています。
NPO法人が運営する母子ハウスやシェアハウス
民間のNPO法人などが、住む場所に困っているシングルマザー向けに運営している母子ハウスやシェアハウスがあります。
これらは低廉な家賃で提供されており、同じような境遇の入居者同士で情報交換や助け合いができる点がメリットです。
保証人が不要なケースも多く、生活再建までの足がかりとして活用できます。
地域の支援団体やインターネットを通じて、近隣にそのような施設がないか探してみることも一つの方法です。
新生活の資金を確保するため配偶者に請求すべきお金
新しい住居での生活を維持し続けるためには、継続的な収入の確保が不可欠です。
ご自身の就労収入だけでなく、配偶者へ法的に請求できるお金を確実に受け取ることが生活の安定につながります。
別居中の生活費をまかなう婚姻費用
離婚が成立するまでの間、収入の少ない側は収入の多い配偶者に対して生活費を請求する権利があります。これを婚姻費用といいます。
別居中であっても、夫婦である以上は互いに生活レベルを維持する義務があります。
家賃や光熱費、食費などがこれに含まれます。相手が支払いに応じない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることで、支払いを求めることが可能です。
夫婦の収入に応じた具体的な請求金額の計算方法や相場については、関連記事『婚姻費用の請求方法|弁護士なしで自分で進める手順と注意点』をあわせてご覧ください。
子どもとの生活を守るための養育費
未成年の子どもがいる場合、離婚後の子どもの生活費や教育費として養育費を請求できます。
これは親としての義務であり、特殊な事情がない限り、免れることはできません。
口約束だけで終わらせず、公正証書を作成するか、調停を通じて取り決めを行うことで、不払いが発生した際に強制執行などの手続きを取りやすくなります。
夫婦で築いた資産を分ける財産分与
結婚期間中に夫婦で協力して築いた財産は、名義にかかわらず共有財産とみなされ、離婚時に原則として半分ずつ分けることができます。
これを財産分与といいます。
預貯金だけでなく、保険の解約返戻金、不動産、将来受け取る退職金なども対象となる可能性があります。
当面の生活資金として、これらを正当に請求することは非常に重要です。
財産分与について対象となる財産や請求する手続きを説明した関連記事『離婚の財産分与とは?割合はどうなる?夫婦の財産の分け方を解説』をあわせてご覧ください。
住む場所やお金の不安は弁護士や自治体に相談を
離婚後に住む場所がないという問題は、物理的な住居の確保と、それを維持するための経済的な基盤、そして法的な権利主張が複雑に絡み合っています。
これらをすべて一人で解決しようと抱え込む必要はありません。
まずは緊急の寝場所や当面の生活費について、自治体の福祉事務所へ相談してください。
そして、配偶者からの適切な金銭支払いを確保するために、弁護士への相談を検討してください。
法テラスを利用すれば、お金がない方でも弁護士費用の立替制度や無料法律相談を利用できる場合があります。
専門家の力を借りることで、安全な住まいと安心できる生活を取り戻す道筋は必ず見えてきます。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
