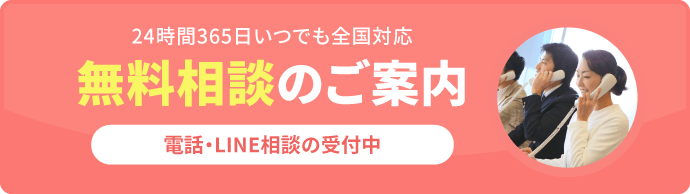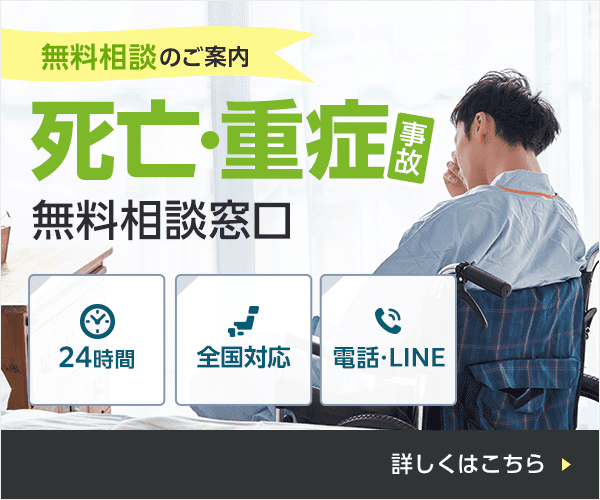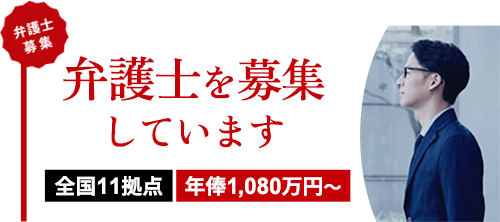通学中の事故でも保険が利用できる場合を解説
更新日:
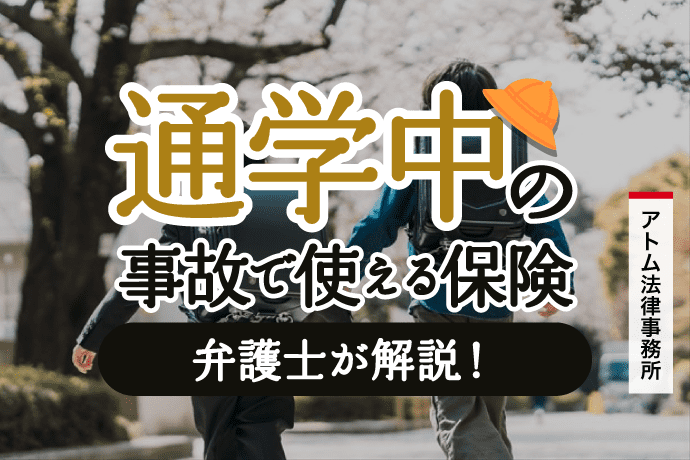
通学中に起きた事故について、学校に法的責任を追及することが可能でしょうか。もし学校に対して責任を追及できない場合は、他に補償を受けることはできないのでしょうか。
本記事では、通学中に起きた事故について、被害者やその家族がどのような補償を受けることができるのかということを解説していきます。
目次
通学中の事故について
まずは、通学中の事故にはどのようなタイプが多いのか解説していきます。
通学中の事故は圧倒的に交通事故が多い
日本スポーツ振興センターでは通学中の事故の傾向を発表しています。
同センターが平成11年度から平成24年度の14年間に保険金を給付した通学中の事例の中で、小学校・中学校・高等学校の外因による死亡事故877件の分析結果が公表されています。
この877件の内訳としては、以下の通りです。
| 件数 | |
|---|---|
| 交通事故 | 701件 |
| 地震・津波 | 78件 |
| 転倒・転落 | 33件 |
| 犯罪被害 | 16件 |
| 鉄道事故 | 15件 |
| 水面への転落 | 15件 |
| 大雨 | 9件 |
| 物体との衝突 | 7件 |
| 遊具 | 1件 |
| 落雷 | 1件 |
| 落雪 | 1件 |
想像に難くありませんが、やはり通学中の事故は交通事故が圧倒的に多く、全体の約8割を占めています。
通学中の交通事故の特徴
交通事故の通学方法で一番多いのは自転車です。
次いで徒歩、二輪車(自動二輪車、原動機付自転車)の順番で多くなっています。
通学方法としては、この3つの手段での交通事故がほぼすべてです。
特殊な例として、電車を利用した際の事故で駅のホームから転落して電車に轢かれてしまうというケースもありました。
通学中の事故でも利用できる保険
通学中の事故にも適用される保険がありますので解説していきます。
学校事故には災害共済給付が利用できる
義務教育諸学校や高等学校、幼稚園、幼稚連携型認定こども園、高等専修学校および保育所等の管理下における災害に対しては、日本スポーツ振興センターが整備している災害共済給付制度を利用できます。
災害共済給付の対象となる災害の範囲や支給内容については、以下のように規定されています。
負傷した場合
負傷については、「その原因である事由が学校の管理下で生じたもの」で、療養に要する費用が5,000円以上のものが対象となります。
国民健康保険を利用しない場合の自己負担額の4割分が給付されます。
疾病が発生した場合
疾病については、「その原因である事由が学校の管理下で生じたもの」で、療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち、文部科学省令で定めている以下の疾病を対象とします。
- 学校給食等による中毒
- ガス等による中毒
- 熱中症
- 溺水
- 異物の嚥下又は迷入による疾病
- 漆等による皮膚炎
- 外部衝撃等による疾病
- 負傷による疾病
国民健康保険を利用しない場合の自己負担額の4割分が給付されます。
完治せずに後遺症が残った場合
「学校の管理下の負傷又は疾病」が完治せず、後遺症が残ることもあります。
日本スポーツ振興センターから、後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けた場合には、障害見舞金支給の対象となります。
後遺障害に該当する症状は、症状の程度に応じて1級から14級に区分されており、『日本スポーツ振興センターのホームページ』で確認できます。
認定された等級に応じて、44万円から2,000万円の障害見舞金が給付されます。
死亡した場合
「学校の管理下において発生した」事故に起因する死亡および疾病に直接起因する死亡を対象として、1,500万円の死亡見舞金が支給されます。
ただし、事故の発生が「学校の管理下」といえるか否かという点が重要な要件となることに注意してください。
通学中の事故も災害共済給付の対象となる
学校の管理下となる範囲についての詳細は、「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に関する規程」に明記されています。
規定によると「通常の経路及び方法により通学する場合」には、学校の管理下に該当すると規定されているのです。つまり、災害共済給付の対象となります。
重要
通常の経路・通常の通学方法で通学していて事故にあった場合には、災害共済給付の対象となる
通学とは何か
「通学」とは、学校教育を受けるために、児童生徒等が住居・職場と学校との間を往復する行為です。
通学中に認められる行為には、単純な遊戯やいたずら、自身の怪我を治療するための通院も含まれます。
さらに、学校周辺・通学路の乗降車駅周辺・自宅周辺で学用品等を購入するのと同程度の行動範囲であれば、短時間の寄り道・回り道は通学中における行為として認められています。
一方で、程度態様が著しく突飛な行為や、通院先の病院で治療を受けているときに事故が起こって負傷した場合は、通学中の事故とは認められず、災害共済給付を受けることはできません。
通常の経路とは何か
「通常の経路」とは、児童生徒が通学のために平常通っている通学路をいいます。
ただし、それ以外にも社会通念上、通常の経路と認められる経路がある場合や一定の寄り道や回り道をする場合にも含むとされていますので、学校側が指定する通学路と多少異なるルートをとっていたとしても「通常のルート」と認められる可能性があります。
「通常の方法」による通学と認められないものとは
通学が学校の管理下として認められるためには、「通常の方法」による通学である必要があります。
通常の方法としては、徒歩や自転車、自動車(原動機付自転車、自動二輪車を含む。)、バス、鉄道などが例示されています。
また、天候や身体の状況を含め、その他やむを得ない事情により普段の通学方法以外の方法をとった場合についても、「通常の方法」とみなされる可能性があります。
たとえば、以下のような場合です。
- 学用品を忘れて取りに帰った際に、遅刻を避けるために徒歩から自転車等に変えた
- 悪天候や身体の障害のため徒歩・自転車からバス等に変更した
ただし、原則として自転車等への便乗は通常の方法とは認められませんので注意してください。
さらに、自転車・原動機付自転車・自動二輪車への二人乗りについては、原則として乗せた方も乗った方も通常の方法による通学とは認められていません。
通学中の事故に関する法的責任
最後に、通学中の事故について法的な責任の所在はどこにあるのかということを説明します。
通学中の事故に学校の責任が問えるか
通学中の事故についても災害共済給付制度の保険が適用されることを説明しました。
しかし、保険の適用があるか否かということと、通学路の安全確保について学校側に法的責任があるか否かは分けて考える必要があります。
法律では以下のように規定されています。
学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため(略)通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
学校保健安全法第27条
学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、(略)警察署その他(略)との連携を図るよう努めるものとする。
学校保健安全法第30条
このような法律の規定からすると、学校には交通ルールの基本的指導を実施する責務はありますが、児童生徒の安全確保のために保護者・警察等と連携を図ることは努力義務でしかないことがわかります。
地域の道路の安全や交通安全を守ることについての一義的責務は警察にあるのです。
そして、子どもに対する監督義務はその親権者が有しているため、登下校中の子どもの行為は保護者の責務であると考えることもできます。
以上から、学校としては交通安全に関する指導を実施していればその責務を果たしていると判断される可能性が高く、登下校中の全面的な安全確保の責務までは負わされていないと考えられます。
通学事故の予見可能性があった場合には責任が認められる可能性がある
児童生徒が通学中に負傷することを教師が予見できる場合には、負傷という結果を回避する義務を怠った点に過失があるとして、学校側に損害賠償を請求できる可能性があります。
具体的には、登下校中に日常的に特定の児童生徒から子どもの安全が脅かされている状況を教員が認識しているような場合です。
このような場合には、学校外といえども、学校側は何らかの対処をとるべきだったと評価できる可能性があります。
教師は生徒が危険な目にあうことのないよう、安全な学生生活を過ごせるように配慮すべき「安全配慮義務」を負っているのです。安全配慮義務についてもっと詳しく知りたい方は、関連記事『学校事故における安全配慮義務とは?教師が負う2つの責任』も併せてお役立てください。
他の生徒が法的責任を負う場合があるのか
では、登下校中の事故に関して他の生徒が法的責任を負うことはあるのでしょうか。
事故の原因が他の生徒による場合は?
他の生徒の故意や過失が原因で事故が発生した場合には、民法上の不法行為責任を追及することが可能です。
ただし、民法では、年齢の幼い子どもが「責任無能力者」に該当するため、損害賠償責任を負わないとしています。
もっとも、「責任無能力者」の監督義務を負うものに対して、代わりに損害賠償請求を行うことが可能です。
子どもの保護者は「責任無能力者」の監督義務を負っているため、保護者に対して損害賠償請求が可能となります。
加害生徒の年齢が12歳前後を超える場合は、「責任無能力者」とならないことがあり、加害生徒に対する損害賠償請求が可能となりえます。
もっとも、加害生徒に支払い能力がないことが大半であるため、保護者に対する請求を行うことになるでしょう。
この場合、保護者には加害生徒が不法行為を行わないように監督する義務があるにもかかわらず、その義務を行ったために損害が生じたとして、保護者に対して損害賠償請求を行うことが可能です。
登校班でトラブルが起こった場合は?
通学中の事故に関して登校班が絡む場合も考えられます。
もし、低学年のお子さんを通学させている方なら、年上の児童が一緒に学校まで連れて行ってくれる方が安心だと思うのではないでしょうか。
ただ、登校班での登校中に事故が発生した場合、その責任問題はどうなるのでしょうか。
登校班の班長は大きくても12歳程度ということになります。
そのため、「責任無能力者」に該当することが多く、登校班の班長が賠償責任を問われる可能性は低いといえるでしょう。
通学中の事故による損害賠償請求は弁護士に相談しよう
法的責任が絡む問題は弁護士に相談する
通学中の事故を含め学校事故にはさまざまなタイプがあります。
法的な責任が複雑に絡むような問題もありえますので、お子さんが学校への通学中で事故に遭った場合は、一度法律の専門家である弁護士にご相談ください。
関連記事『学校事故は弁護士に相談・依頼!メリットと無料法律相談の窓口を紹介』でも解説しているとおり、損害賠償請求において弁護士が果たす役割は多数あります。
まずは無料の法律相談を利用して、疑問点や弁護士に依頼すべきかどうかについて聞いてみるとよいでしょう。
アトム法律事務所の無料相談
通学中の事故でお子さまが重い後遺症を負ってしまったり、亡くなられてしまった場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。
法律相談の予約受付は24時間体制で行っているので、一度気軽にご連絡ください。
無料法律相談ご希望される方はこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了