M&Aの価格相場は?いくらで売れる?価格の決定要因と目安について
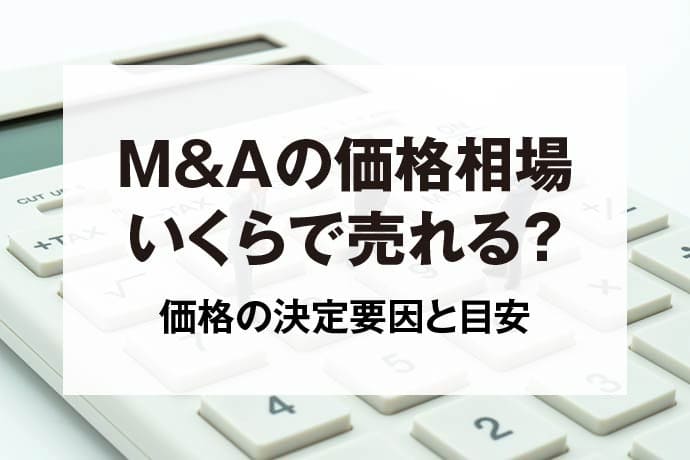
- M&Aの価格相場はある?
- 自分の会社はいくらで売れる?目安は?
- 価格は何で決まる?相場を動かす要因は?
M&Aの価格相場は、売り手、買い手の双方が重大な関心を寄せるものです。
買い手には「M&Aの買収価格をおさえたい」という思惑がある一方、売り手側は「相場価格を上回る高額で売却したい」と思うものでしょう。
M&Aの価格相場の算出方法は一律ではありません。いくらで売れるのか、その目安を知るには、様々な観点から検討する必要があります。
いまやM&Aは中小企業の事業承継における一つの重要な選択肢となっています。
この記事では、M&Aの価格相場の算出方法や、相場価格に影響する要素などについて解説していきますので、事業承継をご検討中の経営者の方など、ぜひ最後までご覧ください。
目次
M&Aの価格相場は?価格の決め方は?
M&Aの価格相場とは?
M&Aとは、「Mergers and Acquisitions」(合併と買収)の略語です。
M&Aが成立すれば、買い手側は、売り手側に対して、対価を渡すことになります。このM&Aの対価が、譲渡価格、買収価格などといわれるものです。
M&Aの価格相場を求めるには、様々な要素を考慮しなければなりません。
いくらで売れるのかは、一概には言えませんが、数ある要素や計算方法を組み合わせることで、一定の目安を知ることはできるでしょう。
M&Aの価格の決まり方は?
M&Aの譲渡価格は、最終的には、売り手側と買い手側の交渉によって決まります。
ただ、最終的な価格決定までの道のりは長いものです。
たとえば、仲介会社をとおしてM&Aをおこなう場合は通常、まずは売り手側がノンネームシートにおいて、名前をふせつつ、企業の概要や希望の売却価格を提示します。
買収を検討中の企業は、その情報を参考にしながら、M&Aの交渉に応じるか検討します。この段階で、買い手側としても希望の買収価額(譲渡価格)があるものでしょう。
そして、企業の経営陣同士の顔合わせをおこない(トップ面談)、買い手側がM&Aを前向きに考えていることを示すために、希望の買収価格などを明示して意向表明をおこないます。
買い手と売り手で意気投合できたら、その時点でのおおよその条件(M&A価格を含む)などについて合意をしておきます(基本合意)。
その後、買収監査の結果も踏まえて、最終的なM&Aの価格を双方合意の上で決定し、晴れて成約となります。
関連記事
売り手と買い手の価格相場はズレる?
売り手側から提示するM&Aの価格は、高額になる傾向があります。
一方で、買い手側には買収価格をおさえたいという思惑があるため、おさえた価格を対案として提示してくるものでしょう。
ですが通常、両者ともに、まったく根拠がないM&A価格を提示していることは考え難いものです。
売り手側のM&A価格も、買い手側の対案としての買収価格も、一般的に考慮される要素や、計算方法にのっとっていなければ、話し合いの俎上にのせることができないからです。
売り手と買い手の相場の見立てに違いがあるとすれば、重点を置く要素の違いといえるでしょう。
売り手側の対応としては、根拠にもとづく適切な反論の準備と、譲歩できるラインの設定が必要です。
関連記事
M&Aの価格相場の計算方法
M&Aの売却価格の目安を知るには、実務で用いられている売却価格の算定方法により、計算をおこなう必要があります。
一般に代表的なアプローチは以下の3つになります。
M&A価格の評価方法
- コストアプローチ
企業の資産価値に基づいて企業価値を算出する方法
(例)時価純資産法など - インカムアプローチ
将来の収益性に基づいて企業価値を算出する方法
(例)DCF法など - マーケットアプローチ
類似企業の市場価値に基づいて企業価値を算出する方法。
(例)類似上場会社比較法・EBITDAマルチプル法
時価純資産法
コストアプローチの一種に、時価純資産法があります。簿価純資産法もありますが、実務では、時価純資産法のほうが用いられる機会が多いでしょう。
時価純資産法とは、企業価値評価の算定方法の一種で、企業が保有する資産の時価総額から負債の時価総額を差し引いた額(純資産額)を企業価値とみなす方法です。
資産の時価総額-負債の時価総額=時価純資産額
DCF法
インカムアプローチの一種に、DCF法があります。
DCF法は、将来のフリーキャッシュフロー(FCF)を現在価値に割り引くことで、企業価値を算出する方法です。M&Aにおける企業価値評価で最もポピュラーな手法の一つです。
関連記事
EBITDAマルチプル法
マーケットアプローチの一種に、類似上場会社比較法があります。その中でも種類はいくつかあり、実務では、EBITDAマルチプル法が用いられることが多いでしょう。
類似上場会社比較法は、類似する上場企業の財務指標を用いて、評価対象企業の企業価値を推測する方法です。
類似企業の選定には、業種、規模、成長性、収益性など様々な要素を考慮する必要があります。また、評価指標は、企業の特性に合わせて適切なものを選択する必要があります。
年倍法(年買法)
中小企業のM&A実務で多用されている計算方法として、年倍法(年買法)という企業価値の評価方法もあります。
年倍法は、M&A価格相場を知るための簡易な計算方法です。
過去の実績に基づき、売上高や利益に一定の倍率をかけることで、企業価値を算出します。
時価純資産額+営業利益の数年分程度=年倍法によるM&A価格
M&A価格相場は、業種や企業規模、成長性によって大きく異なりますが、年倍法を用いることで、資産価値を評価しながら事業の将来性も加味して、M&A価格の目安を把握することができます。
なお、年倍法は将来のリスクなどを評価できていないため、買収監査などによって将来のリスクが顕在化した場合は、買い手側からシビアな値引き交渉を求められることもあるでしょう。
各手法のメリット・デメリット
これらのM&A価格の評価方法はどれも一長一短があります。
そのため、いずれの評価方法を採用するかよりも、複数のアプローチを組み合わせて、いかに交渉相手が納得できる金額を提示できるかがポイントです。
企業価値評価の方法
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 時価純資産法 | 資産価値を評価できる 客観性がある | 将来の収益性を評価できない 無形資産の評価が難しい |
| DCF法 | 将来の収益性を評価できる 理論的な根拠がある | 客観性が担保できない 計算が複雑で手間がかかる |
| 類似上場会社比較法 | 実例を参考にできるので交渉しやすい | 比較対象が見つからない時に困る |
| 年倍法 | 資産・収益性の両方を考慮 | リスクを評価できない |
関連記事
M&Aの価格相場を動かす要因
M&A価格相場を動かす要因としては、以下のような事情があげられます。
価格相場に影響する要因
- 売り手側の資産や収益性
- M&Aスキームの違い
- 需要と供給のバランス
- 買収側のシナジー効果への期待度
売り手側の資産や収益性
M&A価格の算定では、資産や将来の収益性に着目することになります。年倍法やDCF法などの計算方法を見ればわかるように、これらの要素は必要です。
譲渡企業が保有する資産価値が高ければ高いほど、企業の価値も高くなるものでしょう。
売り手側の純資産額や、営業利益の大きさなどの指標も、M&Aの価格相場を動かす要因になります。
資産・収益性のポイント
- 純資産額はM&A価格の下限の目安になる
- 無形資産(ブランド、特許、ノウハウetc.)の評価をあげ、のれん代を高額に見積もる
- 有形資産(土地・建物・設備etc.)を有効活用して、企業価値を高める
- 営業利益の大きさは、将来の収益力を示す指標になる
M&Aスキームの違い
M&Aの価格相場には、スキームの違いも影響を与えます。
中小企業のM&Aにおいて、よく採用されるスキームは株式譲渡や、事業譲渡でしょう。
株式譲渡は会社全体の売却になるのに対し、事業譲渡は事業の一部のみ譲渡することができます。
買い手としては、事業譲渡の場合、譲渡対象となる資産を選ぶことができるので、負債を負うリスクを低減させることができます。売り手としては、リスクが低減する分、価値が上がるため、M&A価格をより高額に設定できる可能性があります。
このように、M&Aスキームの違いによっても、価格相場は変動するものです。
ただし、スキームは目的に合うものを選択すべきであり、手続きの難易度も変わってくるので、スキームを選択する際は十分な検討を要します。
M&Aスキームのポイント
- 中小企業のM&Aスキーム
株式譲渡、事業譲渡が選択されることが多い - M&A価格の傾向
株式譲渡よりも、M&A価格が高額になる傾向がある - 注意点
目的にあったスキームを選択することが重要
関連記事
需要と供給
M&Aの価格相場には、需要と供給のバランスも影響を与えます。
同種同業の売り手が多い場合は、売り手の供給過剰となります。この場合、売り手側が他社にない強みを有しないときは、M&A価格は下がる傾向にあるでしょう。
一方、景気の良い時期や、特定の業種で成長が見込まれる場合などは売り手市場となります。売り手が優位な状況では、買収側は競争に勝ち抜くために、より高い価格を提示する必要が生じます。
複数の買い手候補と交渉することで、競争を促し、より高額な売却価格を実現するという戦略も考えられるでしょう。
買収側のシナジー効果への期待度
シナジー効果への期待度も、M&A 価格相場を動かす要因となります。
シナジー効果とは、企業同士が合併や買収によって統合することで、単独で運営していた場合よりも大きな価値を生み出す効果のことです。
買収側が、M&Aによって大きなシナジー効果を期待できる場合、高い価格を支払ってもメリットがあると判断します。
逆に、シナジー効果が期待できない場合は、価格を下げて交渉する可能性が高くなります。
売り手側としては、複数の買い手候補を見比べることで、もっともwin-winな関係を築けると思える相手を見極めることが大切です。
関連記事
より高額なM&A価格を目指すには?
より高額なM&Aを目指すには、以下の3点が重要です。
売り手側が高額売却を目指すには
- 企業価値向上を図る
- 強みをアピールする
- 買い手探しを慎重におこなう
企業価値向上を図る
M&Aの価格は、企業価値をベースに決定されます。そのため、M&Aを検討する前に、企業価値向上に向けた取り組みを行うことが重要です。
企業価値の向上を図るためには、以下のような取り組みが考えられます。
- 収益性の向上
- 財務体質の改善
- 成長戦略の明確化
- ガバナンスの強化
これらの取り組みを通じて、企業の魅力を高め、より高額な売却価格を実現する可能性を高めていきましょう。
関連記事
強みをアピールする
M&Aでは、自社の強みを効果的にアピールすることが重要です。
売り手企業の強みとしては、以下のようなものが考えられます。
- 独自の技術やノウハウ
- 優秀な人材
- 豊富な顧客基盤
- 強固なブランド力
これらの強みを明確に伝えることで、買収側の興味を引き出し、より高額な価格を引き出すことができます。
買い手探しを慎重に…M&A仲介会社の価格相場は?
M&Aでは、自社の価値を理解し、適切な価格を提示してくれる買い手を見つけることが重要です。
行政の相談窓口や、M&A仲介会社を活用すると、買い手探しを比較的スムーズにおこなうことができるでしょう。
M&A仲介会社の価格相場
民間のM&A仲介会社の利用手数料は、会社ごとに異なります。
一般的には、M&A仲介会社の利用価格については、以下のような費用が問題になるでしょう。
- 相談料
- 着手金
- 中間報酬
- 成功報酬
- 月額報酬
たとえば、相談料は無料、成功報酬は少なくともM&A価格の5%程度かかるのが相場で、その他オプションを依頼するとその分、利用価格が上がっていくというパターンも多いでしょう。
また、着手金や中間報酬の要否も、会社によって異なります。
M&A仲介会社を利用する場合は、事前に料金体系をよく確認して、予算に合わせて上手に活用することがポイントです。
関連記事
まとめ
売り手側が、M&Aで高額売却を実現するには、企業価値を高め、強みを効果的にアピールすることが重要です。
また、買い手探しを慎重に行い、競争入札を検討するなど、戦略的な交渉も必要となります。
M&A価格相場でお悩みの際は、M&A仲介会社の無料相談なども活用してみましょう。

