派遣社員でも退職代行は利用できる!注意点を解説
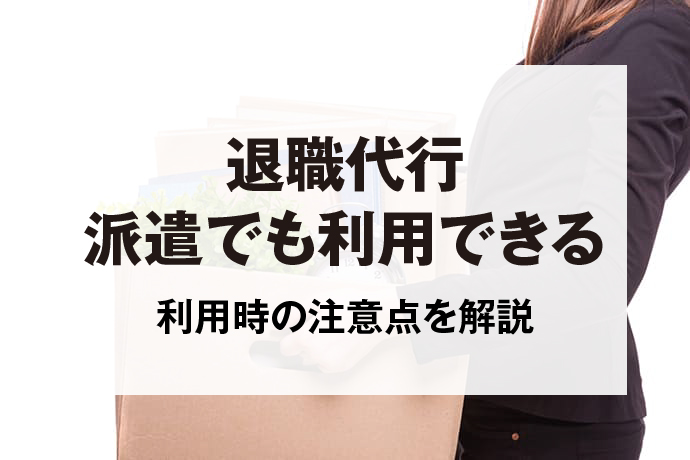
「派遣社員として働いている会社が合わない」
「派遣社員だけど退職代行を使って辞めたい」
派遣社員として勤めている会社が合わず、派遣会社に言いづらいことから、退職代行を利用して辞めることを考えている方もいるでしょう。
結論から言えば、派遣社員であっても退職代行は利用できます。
しかし、雇用形態によっては、退職代行業者選びを慎重に行う必要があります。
この記事では、派遣社員の雇用形態における退職条件の違い、退職代行を利用するときの注意点を詳しく解説していきます。
目次
派遣社員でも退職代行は利用できる
派遣社員には「常用型派遣(無期雇用契約)」と「登録型派遣(有期雇用契約)」があり、雇用形態によって退職の条件が異なります。
どちらの派遣社員でも退職代行を利用して退職することは可能です。しかし、常用型よりも登録型の方が、利用できる退職代行サービスが限られるので、探す際には注意が必要です。
ご自身がどちらの雇用形態に該当するか確認したうえで、退職代行サービスを利用しましょう。
常用型派遣(無期雇用契約)の場合
常用型派遣は、派遣社員と派遣元(派遣会社)が無期雇用契約を結んでいる雇用形態です。
常用型派遣の場合は、正社員と同様に民法627条の退職ルールが適用されます。
つまり、2週間前に退職の意思を伝えれば、基本的にいつでも辞めることができます。
登録型派遣(有期雇用契約)の場合
登録型派遣は、派遣先に就業している契約期間のみ、派遣元と雇用契約を結んでいる雇用契約のことです。派遣先での契約が終了すれば、派遣元との契約も終了します。
登録型派遣の場合は、原則として、雇用契約で定められた期間働かなければなりません。
契約期間満了前でも退職代行を利用して退職できますが、やむを得ない事由が必要となります。
民法628条では、「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」とあります。
やむを得な事由は、以下のようなものが挙げられます。
やむを得ない事由の例
- パワハラやセクハラを受けている
- 身内の介護が必要となった
- ケガや病気などで仕事に支障をきたした
なお、やむを得ない事由がなくても、会社と労働者との間で両者の合意があれば退職できます。
実務上、退職の際にやむを得ない事由の有無について争われることは少ないです。会社との合意のもと、退職を認めてもらえるケースが多いでしょう。
退職代行を利用する場合には、退職代行業者から会社に合意を求めるように働きかけてもらう必要があります。
そのため、登録型派遣の場合はとくに、退職代行業者選びを慎重に行う必要があるといえるでしょう。
登録型派遣でも契約開始から1年以上経過していれば退職できる
契約開始から1年以上経過している派遣社員は、いつでも退職可能です。
期間の定めのある労働契約を締結した労働者は、契約の初日から1年が経過すれば、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職できると定められています(労働基準法137条)。
正社員のように退職を申し出てから2週間といった期間の決まりもありません。
もっとも、業務の引き継ぎを行わずに即日退職すると、会社から損害賠償請求されるおそれもあるので、退職時には注意が必要です。
派遣社員が退職代行を利用するときの注意点
派遣社員も利用できる退職代行事業者を選ぶ
そもそも退職代行事業者によっては、派遣社員からの依頼を受け付けていないこともあります。
また、退職代行業者によっては、常用型派遣は対応しているものの、登録型派遣は対応していないケースも多いです。
退職代行を利用する際には、自身が常用型・登録型の派遣社員であることを告げ、利用できる退職代行事業者を選ぶようにしましょう。
派遣社員が利用できるかどうかは、ホームページや口コミなどで確認してください。もし記載がなければ、退職代行事業者に事前に相談するといいでしょう。
関連記事
退職代行を利用した派遣会社は使えなくなる
退職代行を利用して退職すると、契約していた派遣会社は使えなくなる可能性が高いです。
退職代行を利用すると、派遣会社との関係性が悪化し、再雇用のリスクが非常に大きくなるためです。
なお、退職代行を利用しても、新たにほかの派遣会社で働くことはできます。
「退職代行を利用したことで派遣会社全体のブラックリストに載る」などと噂されることもありますが、派遣会社同士で個人情報を共有することは、個人情報保護法違反にあたります。
ほかの派遣会社で働けなくなることは、心配する必要はないでしょう。
派遣社員が退職代行業者を選ぶときのポイント
非弁行為のリスクがない弁護士に依頼する
退職代行を行う事業者は、「一般の退職代行業者」「労働組合」「弁護士」の3種類に区別できます。
どの事業者に依頼するか迷ったときには、弁護士に依頼することがおすすめです。
一般の退職代行業者が代行できるのはあくまで「退職の意思を告げること」だけです。
そのため、それ以上に何らかの法的な交渉をおこなうと、非弁行為(弁護士資格をもたない者が、報酬を目的に弁護士業務をおこなう違法行為)に該当するリスクが大きくなります。
派遣社員が退職代行を利用した場合は、会社に合意を得るといった会社との交渉が必要になることが多いです。
とくに登録型の派遣社員の方は会社との交渉が可能な労働組合や弁護士に依頼すべきと言えます。
また、弁護士であれば会社との交渉ができるうえ、未払い残業代や給与、退職金の請求も可能です。
さらに、労働組合が訴訟といった法的な手続きに発展すると対処が難しくなるデメリットがある一方、弁護士は法的な手続きにもスムーズに移行できるメリットがあります。
関連記事
・退職代行を弁護士に依頼するメリットは?費用・代行業者との違いまで完全解説!
退職代行の料金やサービス内容も確認しておく
利用する退職代行サービスによって、かかる費用は異なります。
依頼費用や追加料金の発生の有無、万が一退職が失敗してしまった場合の返金保証が付いているかなどは確認しておくべきでしょう。
退職代行サービスを依頼するからには、当然失敗は避けたいものです。返金保証が付いていないサービスは、お金を払って損することも考えられるので、選ぶときには注意が必要です。
また、退職は成功したものの、追加料金が発生し、想像以上の費用がかかってしまうこともあります。
相場よりも極端に費用が低い退職代行サービスは、追加料金を設定している可能性もあります。相談する際には、追加料金の条件などを確認しておきましょう。
関連記事
・退職代行サービスの金額相場はいくら?3つの相談先と対応の違いを解説
まとめ
この記事では、派遣社員が退職代行が利用可能かどうかについて詳しく解説しました。
派遣社員であっても、退職代行を利用して退職可能です。
退職代行の利用を検討している方は、トラブルを防いで安心して退職するためにも、退職代行事業者の違いや退職代行の流れをしっかりと理解したうえで利用するようにしましょう。
また、失業保険や国民健康保険の切り替え手続きなど、具体的に退職代行をした後にやるべきことを把握しておけば、安心して退職代行を利用できると思います。
退職代行の流れや退職代行利用後の手続きに関して詳しく知りたい方は、『退職代行の流れは?手順を弁護士が徹底解説』の記事もご覧ください。
以下の記事でも、派遣社員での退職代行利用について詳しく解説しておりますので、是非とも合わせてご確認ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了