セクハラで労災認定を受けることはできる!認定されるための条件と申請の流れ
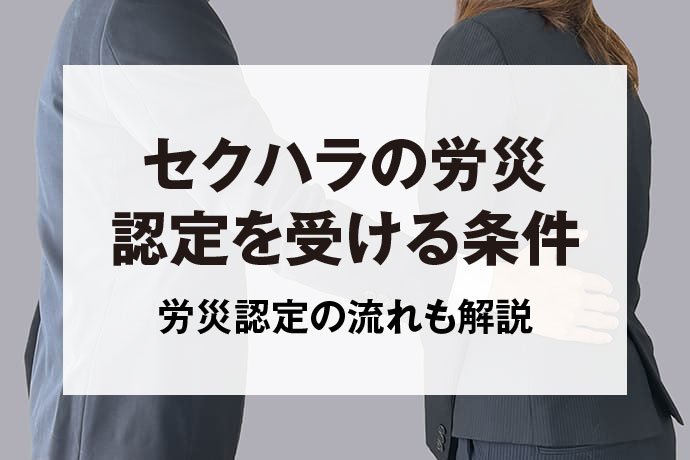
「上司の執拗なセクハラで適応障害になった」
「セクハラ被害で休職を検討している。労災認定は可能?」
セクハラ被害が原因でうつ病や適応障害などの精神疾患になった場合、労災認定されれば、労災保険によって補償を受けることができます。
ただし、セクハラ被害で労災認定を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
この記事では、セクハラで労災認定を受けるための条件や労災申請を行う流れを解説します。
セクハラで労災認定を受けるための条件
セクハラで労災認定を受けるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
セクハラで労災認定されるための条件
- 労災認定の対象となる精神疾患を患うこと
- 発病前の約6か月間に、セクハラによる強い心理的負荷が認められること
- セクハラ以外、もしくは個体要因による発病でないこと
それぞれ詳しく解説していきます。そもそもセクハラがどういったものか詳しく知りたい方は『どこからがセクハラになる?結局セクハラの基準は?職場のセクハラ発言一覧』の記事もあわせてご覧ください。
(1)労災認定の対象となる精神疾患を患うこと
まず、労災認定を受けるためには、厚生労働省が定める「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」に該当する精神疾患を患っていることが必要です。
対象となる精神疾患の代表的なものは、うつ病や適応障害、急性ストレス反応などです。
参考:「ICD-10(国際疾病分類)第5章 精神および行動の障害」厚生労働省
(2)発症前の約6か月間に、セクハラによる強い心理的負荷が認められること
セクハラで労災認定されるためには、発病前の約6か月間に、業務上のセクハラ被害による強い心理的負荷が認められることが重要です。
心理的負荷の強度は負荷の種類ごとに「弱」「中」「強」の3段階で評価され、心理的負荷が「強」と評価されれば、原則労災と認められます。
(3)セクハラ以外、もしくは個体要因による発病でないこと
セクハラで労災認定を受けるためには、業務上のセクハラ被害で精神疾患を患っている必要があります。
そのため、精神疾患を患った原因が、「離婚した」「多額の借金を負った」など、業務とは関係ないものであるときは労災認定されません。
また、過去にセクハラとは無関係に精神疾患を患っていたり、アルコールや薬物依存があったりした場合には精神疾患の要因がセクハラ以外にある可能性を慎重に判断されます。
ここまで紹介した3つの条件が揃ってはじめて、セクハラの労災と認定されます。
心理的負荷が「強」と判断される例
心理的負荷の認定は、「特別な出来事」がある場合とない場合に分類できます。
特別な出来事がある場合
まず、不同意性交や本人の意思を抑圧してわいせつ行為が行われた場合は、心理的負荷が「強」となります。
1度だけでも被害者の尊厳を大きく傷つける行為です。
特別な出来事がない場合
特別な出来事がない場合は、「セクハラの内容や程度、継続する状況」「セクハラ後の会社の対応や改善状況、人間関係」などを総合的に評価されます。
中でも、心理的負荷が「強」と判断されるようなケースは以下の通りです。
身体接触を含むケース
- 胸や腰などへの身体接触を継続して行われた
- 会社にセクハラ被害を訴えたものの適切な対応がされなかった
身体接触を含まないケース
- セクハラ発言の中に人格を否定するものが含まれており、継続して発言された
- 性的な発言が継続し、会社が把握しても適切な対応や改善が見られなかった
一方、セクハラ行為が一度きりだった、会社にセクハラ被害を訴えたら適切な対応が取られ改善されたなどのケースでは、心理的負荷が「中」となり、労災認定されないこともあります。
参考:セクシュアルハラスメントによる精神障害の労災認定について|厚生労働省
セクハラで労災申請を行う流れ
(1)医師の診断を受けて診断書をもらう
精神疾患を証明するためには、医師による診察が必要になります。
精神疾患は他人から見ても判断がつきにくいことが多いので、専門の医師による診察と適切な治療を受けているかが重要です。
また、これらの精神疾患を患っていることを証明するために、診断書が必要となります。診断書のみならず、診察時のカルテが労災認定の判断に用いられる場合もあります。
(2)会社に「事業主証明」を書いてもらう
診断を受けたら、労働基準監督署に請求書を提出しましょう。請求書の様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
請求書には、会社が労災の証明を記載する「事業主証明欄」があり、この部分は会社側に記載してもらうことが必要です。
しかし、会社側が労災の保険料負担増加を懸念することなどから、事業主証明の記載を拒否することもあります。
会社が労災を認めない・いわゆる労災隠しを行う理由については『会社に労災隠しをされてしまった!労災隠しの対処法を解説』の記事で詳しく解説しています。
なお、会社に事業主証明を拒否された場合でも労災保険の請求はできるため、労働基準監督署に相談しましょう。
(3)請求書を労働基準監督署に提出する
請求書に記入できたら、労働基準監督署に提出しましょう。
給付金の種類ごとに申請期限が設けられているので、注意が必要です。
参考:「労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか。」|厚生労働省
労働基準監督署への請求が認められれば、労災認定となり、労災保険の受給が可能になります。
労災の請求をしてから実際に労災保険を受給するまではおおむね1か月程度かかります。内容によっては数か月間かかる場合もあります。労災の被害に遭った際には速やかに手続きを進めましょう。
セクハラによる労災認定で受け取れる金額
セクハラで労災認定を受けた場合、労働者は労災保険から給付金を受け取れます。ここではセクハラで労災認定された際に受け取れる主な給付金を紹介します。
療養(補償)給付:全額
療養(補償)給付とは、労災による病気の治療費を補償するものです。
労働者の治療費や通院料、入院料に至るまでが全額労災保険で支払われます。
休業(補償)給付:8割
休業(補償)給付とは、労災で負った病気によって休業した場合に認められる給付です。
休業(補償)給付は、以下の条件を満たせば支給されます。
- 業務上の負傷や傷病による療養であること
- 労働できないこと
- 賃金の支払いがないこと
休業(補償)給付は、仕事を4日以上休業した場合に限り、給付基礎日額の80%(保険給付60%+特別支給金20%)を支給してもらえます。
給付基礎日額は、「3か月間の賃金総額÷3か月間の暦日数」で計算されます。
休業給付が支給される期間に制限はなく、休業開始から4日目から休業が終了するまで支払われます。
なお、休業開始1日~3日間は「待期期間」といわれ、休業給付は支払われません。ただし、待期期間中は会社から労働者に給付基礎日額の60%が支払われます。
関連記事
・労災の休業補償を受けるための手続きは?医師の証明が必要な理由
セクハラは慰謝料請求も検討すべき
慰謝料請求は労災認定の有無に関係なくできる
セクハラで労災が認定されれば、治療費の全額や休業した場合の賃金は8割給付されます。しかし、労災給付はあくまで生活を守るための賃金です。
セクハラで精神疾患を患った場合は、慰謝料請求も検討しましょう。
セクハラ行為自体が労働者に対する不法行為となるため、労災認定の有無にかかわらず慰謝料請求可能です。
セクハラにあって、精神的な苦痛を受けた場合、セクハラ行為者や会社に対して慰謝料を請求することができます。
セクハラで慰謝料請求する場合は、会社と労働者の両方に請求することが一般的です。
セクハラの慰謝料は加害者の地位が高く、被害者にとって拒むことが難しい状態でのセクハラであれば、高額になる傾向があります。
セクハラの慰謝料の事例を詳しく知りたい方は、『セクハラで慰謝料を請求したい!慰謝料の相場や用意すべき証拠を解説』の記事をご覧ください。
セクハラの慰謝料請求は弁護士に相談
セクハラで慰謝料を請求したい方は、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談することで、そもそも自分が受けている行為がセクハラに該当するのか、過去の判例などから慰謝料がいくら受け取れる可能性があるのかなどを知ることができます。
また、セクハラで慰謝料請求するための証拠の収集方法についてもアドバイスをもらうことができます。
弁護士に相談した際には、セクハラの期間や態様などを聞かれることになるので、事前にある程度情報を整理してからいくと、より適切な回答をうけられるでしょう。
関連記事
・セクハラを弁護士に相談する|費用・準備するもの・注意点を確認!
まとめ
セクハラ被害が原因でうつ病や適応障害などの精神疾患になった場合、労災認定される場合があります。
労災が認定されれば、労災保険の療養(補償)給付で治療費用が全額、休業(補償)給付により給与の約8割が支払われます。
セクハラ被害で悩んでいる方は、労災申請を行う流れを確認し、請求しましょう。
労災は労働基準監督署に請求するため、労災に関して分からない点があれば労働基準監督署への相談がおすすめです。
なお、労災の相談窓口については『労災の相談はどこでできる?困ったときの相談先を紹介!無料の窓口も!』の記事で相談先ごとの特徴を解説しています。
セクハラで慰謝料請求を検討している方は弁護士への相談がおすすめです。
無料の相談を受け付けている弁護士事務所や、女性弁護士が相談に乗ってくれる事務所もあるので、抱え込まずに相談してみてください。
「これはセクハラじゃないのかも」「周りの人も我慢している」などの理由で自身でセクハラ被害を抱え込む必要はありません。
専門家への相談がセクハラ被害解決の一歩となります。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了