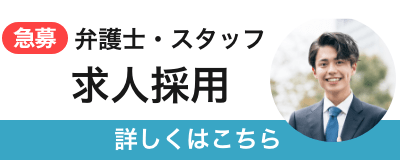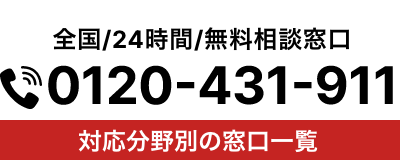毎年、夏や冬になると「エアコンを使わずに体調を崩し、命を落とした高齢者」のニュースが相次ぎます。 「電気代が高いから」「身体に悪そうだから」──そんな理由でエアコンを使わず、室内で熱中症や低体温症に陥るケースが少なくありません。
しかし、適切に使用していれば防げた健康被害である以上、場合によっては家族や周囲の法的責任が問われることもあります。
本記事では、実際の事例やデータ、法的な視点を交えながら、高齢者のエアコン未使用によるリスクと対策について考えてみます。
高齢者がエアコンを使わない理由と実態

高齢者がエアコンを敬遠する理由には、いくつか共通するものがあります。
- 電気代の不安
「年金生活でこれ以上出費は増やせない」という思いから、極力エアコンをつけずに過ごそうとする方が多いです。 - 健康への思い込み
「冷えすぎると体に悪い」「自然の風のほうが健康的」という先入観が根強く、暑さや寒さに耐えてしまうケースも少なくありません。 - 操作の難しさ
小さなボタンや複雑なリモコン表示に戸惑い、正しい使い方が分からず結局使わなくなる、というUX上の問題もあります。
実際に、消防庁の2022年の統計では、熱中症で救急搬送された人の約半数が65歳以上の高齢者です。冬季には低体温による事故も報告されています。
例えば、東京都内で真夏にエアコンを使わず過ごしていた90代の女性が室内で意識を失い、命を落としたケースや、冬に毛布だけで過ごしていた男性が低体温で搬送された事例もあり、毎年繰り返されています。
家族や周囲が「なぜ使わないのか」を知り、その壁を取り除くことが重要です。
健康被害が起きた場合の法的責任はどこまで及ぶ?

高齢者が一人暮らしの場合、基本的には本人の意思による結果として自己責任とされることが多いです。
ただし、以下のようなケースでは第三者の法的責任が問われる場合もあります。
- 成年後見人がいる場合
成年後見人がついていながら、明らかに危険な状態を放置していた場合は、監督義務違反とみなされる可能性があります。 - 扶養義務者の配慮義務違反
法的な扶養義務を負う家族が、明らかに危険な状況を知りながら適切な対応を怠った場合に問題視されることがあります。 - 介護サービス事業者の対応
グループホームや訪問介護のスタッフが、危険な環境を見逃した場合、契約上の義務違反を問われることもあります。
実際の裁判例では、成年後見人の不作為を厳しく問われた例がある一方、「助言や配慮はしていた」と認められ、責任を免れた事例もあります。
いずれにしても、周囲の行動が問われる可能性があると認識し、事前の予防と配慮を行うことが大切です。
エアコンの正しい使い方で防げる健康リスク

エアコンは適切に使えば、命を守る「安全装置」です。近年は高齢者向けに設計された機種も登場しています。
例えば:
- 誰でも使いやすい簡単リモコン
- 部屋や体温に応じて自動で調整する温度センサー
- 過度な冷暖房を防ぐ24時間タイマー
こうした機能を備えた製品を選び、正しく使うことで健康被害のリスクを大幅に減らせます。どのような機種を選び、どう使うべきかについては、 エアコン研究所 の記事が参考になります。
高齢者におすすめのエアコン機能や冷やしすぎを防ぐ工夫など、図解や具体例が豊富で、初めての方にも分かりやすく解説しているので、一度目を通してみるのがおすすめです。
※本記事は特定のサービスを推奨するものではなく、情報提供を目的としています。
家族・地域ができる見守りと予防策

高齢者が安心してエアコンを使えるよう、家族や地域ができることもあります。
- 日々の声かけや、設定のサポート
- 「見守り機能付きエアコン」などの導入
- 地域包括支援センターや見守りサービスとの連携
- センサーやLINE通知などの簡易な見守りツール
最近は、民間サービスやIT技術の進化で「無理のない見守り」がしやすくなっています。
身近なところからできる工夫を考えてみましょう。
命を守る設備は、正しく使うことが大切

エアコンの未使用による健康被害や法的トラブルは、防ぐことができるリスクです。
法的責任を追及される前に、生活者としてできる備えをしておくことが大切です。
家族、地域、支援者がそれぞれの立場でできることを少しずつ積み重ねることで、悲しい事故を防げます。
不安や疑問がある場合は、エアコン研究所のような中立的な情報サイトで知識を得るところから始めてみてください。正しい理解と準備で、あなたや大切な人の命を守りましょう。