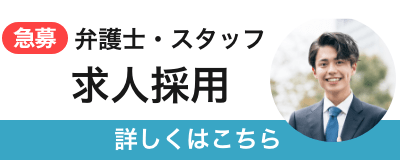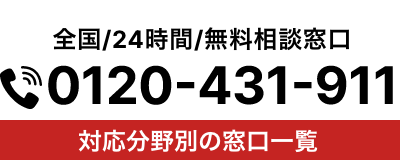「正社員として採用されたはずなのに、実際には業務委託契約だった」
このように、求人情報や面接での説明と実際の雇用形態が異なる“ギャップ”に関する相談が近年増えています。特に社会経験が浅い若手の方の場合、企業側の説明をうのみにしてしまい、雇用契約の詳細をきちんと確認しないまま就業を始めるケースも少なくありません。
結果として、思っていた雇用条件と大きく異なる待遇に気づき、トラブルへと発展してしまうこともあります。
この記事では、転職時に注意したい雇用契約の確認ポイントと、トラブルを未然に防ぐためにできる情報収集の方法について解説します。
よくある「雇用形態のギャップ」とは?

まずは、よくあるギャップをご紹介します。
想定と違った雇用形態に戸惑うケース
近年、特に以下のようなトラブルが多くみられます。
- 正社員として採用されたはずが、実際は業務委託だった
→社会保険に加入できず、安定性がないことに不安を抱く人が多いです。 - 契約社員だと説明されたのに、日雇い派遣だった
→勤務先や条件が日ごとに変わり、将来設計が立てにくいという声もあります。 - 社会保険未加入・労働条件通知書が交付されていない
→入社後に保険の加入手続きが進まないことで「話が違う」と発覚する例が散見されます。
ギャップに気づくきっかけ
就業後に違和感を覚えるきっかけは、次のようなタイミングが多いです。
- 給与明細や社会保険の加入有無を確認したとき
- 同僚との待遇の差に気づいたとき
- そもそも契約書の控えがないと後から気づいたとき
書面がないと証拠が残らず、のちのち「言った・言わない」の争いに発展しやすい点にも注意が必要です。
なぜ雇用形態の食い違いが起こるのか?

次に、なぜ食い違いが起こってしまうのか、その理由を見ていきましょう。
口頭説明だけでの入社決定が原因に
雇用形態の認識違いが生まれる背景には、求人票や面接での説明が不十分だったり、あいまいだったりするケースがあります。「正社員登用あり」とだけ書かれていて、具体的な契約条件の説明を十分に行わない企業も少なくありません。
また、内定通知書に詳細条件が明記されないまま、流れで入社してしまう人もいます。このような場合、実際に働き始めてから「思っていた条件と違う」と感じるリスクが高くなります。
確認不足は求職者側の落ち度になることも
「正社員で当たり前だろう」と思い込みで判断し、きちんと確認をしなかった結果、求職者自身にも責任を問われる場合があります。特に若手層は、面接時に条件を尋ねにくい雰囲気に飲まれてしまい、疑問を持っても聞けないまま入社してしまう傾向があります。
しかし、契約は双方の合意で成り立つものである以上、確認の努力を怠ると不利な立場に立たされかねません。
雇用契約で確認すべき5つのポイント

転職先を選ぶ際は、以下の5つの項目を必ず書面で確認しましょう。
① 雇用形態(正社員・契約社員・業務委託など)
② 労働時間・休日・残業の取り扱い
③ 賃金や各種手当の明記
④ 社会保険や福利厚生の有無
⑤ 試用期間の有無と条件
どの立場で雇われるのかは、最も重要なポイントです。社会保険や雇用保険の適用も変わるため、あいまいな説明では了承しないことが大切です。
労働時間においてはシフト制か固定制か、残業代は支給されるのかなど、勤務時間に関する条件を明確にしましょう。基本給・賞与・交通費などの取り決めは、契約書で具体的に確認するとトラブルを防ぎやすくなります。
加入条件や手続きについても口頭説明だけでなく、必ず文書でも確認してください。「いつまで試用期間か」「その後にどう切り替わるのか」なども見逃せないポイントです。
雇用形態トラブルに直面したらどうする?

実際にトラブルに直面したらどうすれば良いのか、以下を参考にしながら冷静に対応することを心がけましょう。
まずは書面を確認し、雇用契約の有無を整理
最初に行うべきは、契約書の確認です。
どのような条件で契約したのかを客観的に証明できる書面の有無が、問題解決の出発点になります。
労働基準監督署や労働相談窓口に相談する
もし企業側との話し合いで解決できない場合は、労働基準監督署や各地の労働相談窓口に相談しましょう。
行政のサポートを受けることで、相手方に改善を促すことも可能です。
状況に応じて法的措置を検討(みなし労働契約など)
場合によっては、実態として雇用関係が成立しているとみなされる「みなし労働契約」の主張など、法的なアプローチが有効です。
一人で抱え込まず、専門家へ相談することも検討してください。
トラブル回避の鍵は「働く前の情報収集」

次に、トラブルを回避するためのポイントを見ていきましょう。
「知らなかった」では済まされない初期トラブル
特に20代や初めての転職者に多いのが、「なんとなく」で転職を決めてしまい、職種や働き方の理解が浅いまま入社するケースです。
結果として、入社後に後悔する例が後を絶ちません。「知らなかった」では済まされないのが社会の厳しさでもあります。
職種理解に役立つ情報源の活用を

職種や業界の特徴を事前に把握しておくことで、トラブルを回避しやすくなります。転職前に働き方や業界の特徴を理解することで、トラブルの予防につながります。
転職活動を成功させるためには、応募先企業や業界についての事前情報が欠かせません。
特に若手層や初めての転職を検討している方にとっては、「どのような質問がされるのか」「どんな傾向があるのか」を把握しておくことが面接対策に役立ちます。
面接情報特化型口コミメディア|転職アカホン では、実際の面接を受けた人の体験談や質問内容が共有されており、企業ごとの傾向を効率よく掴むことができます。
また、コラム「転職アカホン講座」では、職種別の転職事情や業界の特徴についても解説されています。
情報収集の一助として活用してみてはいかがでしょうか。
まとめ
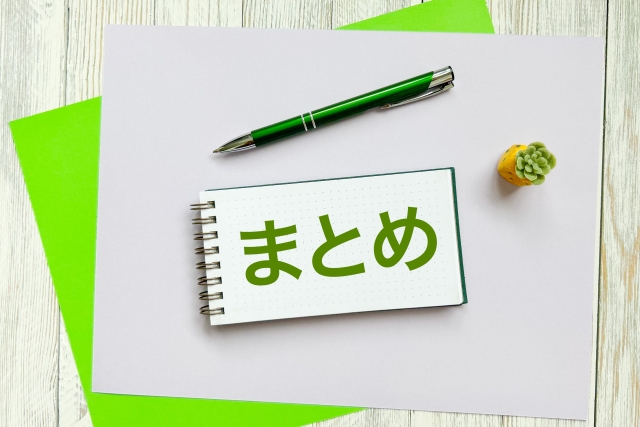
雇用形態のギャップは、誰にでも起こり得る身近なトラブルです。
しかし、入社前にしっかりと契約書を確認し、必要な情報を集めておくことで防げるケースが大半を占めます。万が一、説明と異なる雇用条件で働くことになってしまった場合でも、書面を整理したうえで労働基準監督署や相談窓口に早めに相談することで、解決の糸口を見つけられるはずです。
雇用契約は、働く人の人生に大きく影響する大事な土台です。「なんとなく」や「大丈夫だろう」という気持ちに流されず、自ら確認し、納得してから働き始める意識を持つことが、安心して働ける職場を選ぶための第一歩になるでしょう。