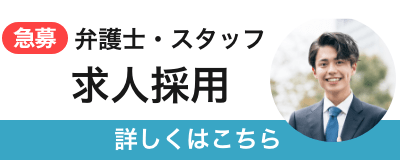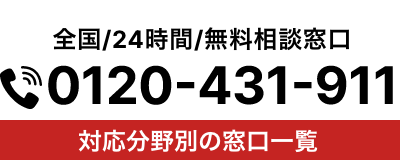不動産賃貸業を営むオーナーにとって、確定申告や日々の経費処理は避けて通れない業務です。物件管理や賃料回収と並行して、修繕費、減価償却費、借入金利息などの経費を適切に計上することが求められます。
しかしながら、これらの費目は判断が難しく、特に副業として不動産投資を行っている方にとっては「どこまでが経費にできるのか」「どのタイミングで計上すべきか」といった基準が曖昧なまま申告をしてしまうケースも少なくありません。
本記事では、不動産オーナーが陥りがちな経費処理のミスと、それが招く税務調査のリスク、そしてその防止策について解説します。
不動産オーナーがやりがちな経費処理ミスとそのリスク

不動産経営において「少しぐらいなら大丈夫」と軽く考えてしまった処理が、後々税務署から厳しく指摘されることがあります。以下に、代表的な失敗事例を紹介します。
事例① 自宅兼事務所の家賃を全額経費にしてしまった
不動産管理の業務を自宅で行っているからといって、家賃の全額を経費にしてしまったケースです。実際には生活スペースと業務スペースを明確に分け、業務に使用した割合のみを按分して計上しなければなりません。
この按分を行わずに全額を経費としたことで、税務調査で指摘を受け、結果として追徴課税と延滞税が課された例もあります。
事例② 業務と関係の薄い接待費を計上
不動産管理業務に関連する打ち合わせや営業活動の飲食費は経費になり得ますが、家族や親しい友人との食事を「接待交際費」として計上してしまったケースでは、経費として認められないばかりか、意図的な脱税と見なされかねません。
「誰と」「何の目的で」行ったのかという記録がない場合は、説明責任を果たせず否認されるリスクが高まります。
事例③ 帳簿の不備・領収書紛失による調査
日々の記帳を後回しにし、領収書が散逸してしまったり、帳簿と実態が一致していなかったりすると、税務署から「不明瞭な経営」と判断され調査の対象になります。経費自体に問題がなくても、証拠書類がないと認められません。
「小さなミスの積み重ね」が大きなトラブルへとつながる代表例です。
なぜ不動産特化の税理士が必要なのか?
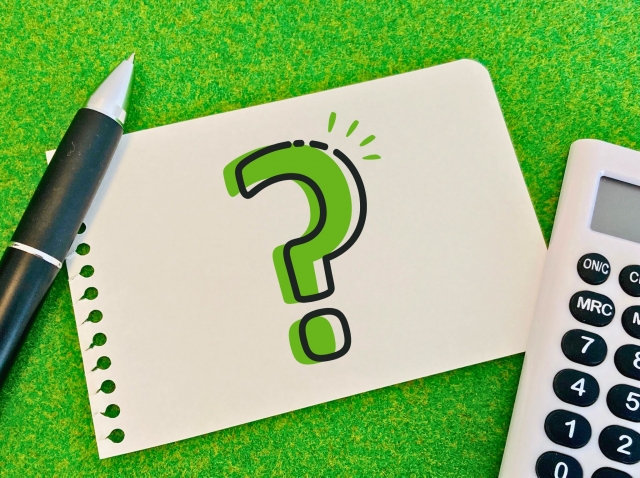
不動産業は他の業種に比べて、税務上の判断が難しい項目が多く存在します。
たとえば、修繕費と資本的支出の線引き。屋根の塗り替えなどは「修繕費」として一括経費にできる場合もありますが、構造を改善するリフォームになると「資本的支出」となり、減価償却で数年に分けて経費にする必要があります。
また、物件ごとの減価償却資産の区分や管理会社との契約費用の処理など、判断が分かれる“グレーゾーン”が非常に多いのが現実です。
こうした判断を自己流で行うのではなく、不動産業に精通した税理士に相談することで、税務リスクを未然に防ぐことが可能になります。
文京区本駒込を拠点に不動産オーナーを支える|飯田哲久税理士事務所
不動産投資家や賃貸オーナーにとって心強い存在が、東京都文京区本駒込にある「飯田哲久税理士事務所」です。
同事務所では、不動産特化型のサービスとして、確定申告・経費処理・減価償却・帳簿記帳・税務調査の対応までをワンストップで支援。不動産経営におけるあらゆる税務課題に対応しています。
「これは経費にできるのか?」「税務署から指摘されないか?」といった不安にも、的確なアドバイスが受けられるため、不動産オーナーにとっては日々の経営判断に安心感が生まれます。
▶不動産投資・賃貸業をベースに、各種フリーランス含め約90件のお客さまを幅広く支援している税理士事務所です。
※本記事は特定の税理士を推奨するものではなく、情報提供を目的としています。
不動産オーナーこそ経費管理を見直そう
不動産賃貸業では、日常的な業務に加えて、経費処理という重要なタスクがあります。その処理を自己判断で行うことにより、意図せぬ税務調査や追徴課税のリスクを抱えることになります。
「これくらい大丈夫だろう」と油断せず、専門知識を持つ税理士と連携することが、不動産経営を安定させるための鍵です。
経費処理ルールを見直し、透明性のある経営を目指していきましょう。