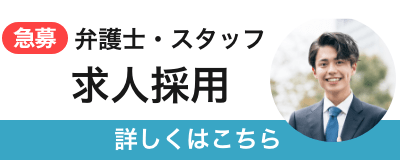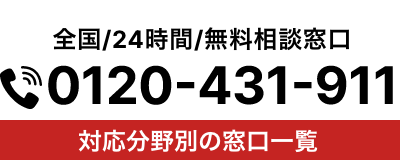介護施設の運営には、日々の現場対応や行政手続きだけでなく、「職員との関係」や「労務管理」など、多岐にわたるマネジメントが求められます。特に昨今では、職員の定着率の低下や労働環境をめぐる問題から、労務トラブルが顕在化するケースが増えてきました。
本記事では、介護業界で起こりがちな労務トラブルの事例と、その対策、そして専門家に相談すべきタイミングについて解説します。
介護業界で起きやすい労務トラブルとは

まずは、実際に介護業界で起こりやすい労務トラブルを紹介します。
1. 長時間労働・サービス残業問題
介護施設では慢性的な人手不足から、職員が長時間労働を強いられたり、定時を超えても記録業務が終わらない「サービス残業」が常態化している施設もあります。
これにより、職員の疲弊が進み、最終的に離職や労基署への申告につながるケースも少なくありません。
2. ハラスメントや指導体制の不備
利用者対応のプレッシャーが大きい現場では、管理者や先輩職員による厳しい指導が「パワハラ」と捉えられてしまうこともあり、注意が必要です。
新人職員が定着しない背景には、こうした職場内コミュニケーションの問題があるケースも見受けられます。
3. 雇用契約・処遇改善加算制度をめぐる誤解
厚生労働省の処遇改善加算制度に関して、「加算分が給与に反映されていない」として職員とのトラブルに発展する事例もあります。
これは雇用契約の内容や説明不足が原因となっている場合が多く、法的トラブルに発展するリスクをはらんでいます。
実際にあった介護施設での労務トラブル事例

続いて、実際にあったトラブル事例を紹介します。
職員の過労による労基署からの是正勧告
定時を超えた業務が常態化していた施設では、元職員からの通報により労働基準監督署が調査を実施しました。
結果的に是正勧告を受け、労働環境の抜本的見直しが求められた事例です。
利用者対応に関する職員間の衝突と退職騒動
夜勤時の対応方針を巡って意見が対立し、職員間で口論に発展しました。その後、チーム内の信頼関係が崩れ、複数名の退職につながったケースもあります。
最初は、ささいなことでしたが、結果的には大きなトラブルになってしまった事例です。
勤務実態と契約内容の相違が発覚し、損害賠償請求に
雇用契約に記載されていた業務内容と実際の業務内容に大きな差異があり、職員が精神的苦痛を理由に損害賠償を求める裁判を起こした例もあります。
労務トラブルを防ぐために介護施設が取るべき対策
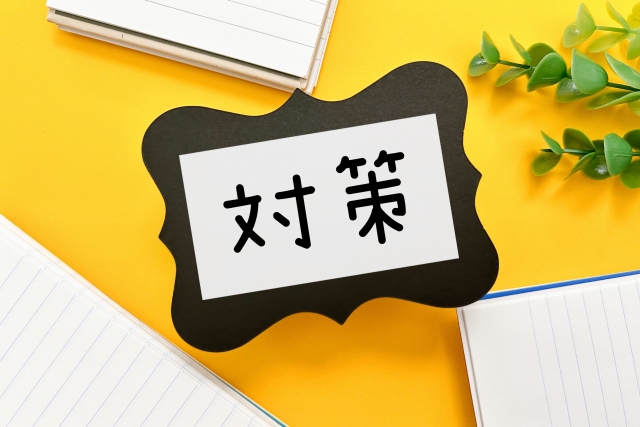
続いて、労務トラブルを防ぐために介護施設が取るべき対策を紹介します。
労働環境とシフトの「見える化」
ICTの活用による勤怠管理システムの導入で、職員の労働時間を正確に把握する体制を整えることが重要です。
また、月次の勤務実績を可視化することで、管理職も無理のないシフト組みが可能になります。
雇用契約書・就業規則の見直し
契約内容に曖昧な点がないかを定期的にチェックし、必要に応じて社会保険労務士や税理士と連携して文書の整備を進めましょう。
処遇改善加算に関する説明文書の添付なども有効です。
教育・指導体制の構築と外部研修の活用
新任職員への教育・指導は属人的に行われることが多く、トラブルの原因になります。
研修マニュアルやOJTの標準化、外部講師を招いたハラスメント研修などを導入することで、職場全体の意識改革が可能です。
トラブル発生前に「専門家」に相談すべきタイミングとは

次に、専門家に相談すべき適切なタイミングを見ていきましょう。
職員の不満が“表面化”する前段階
定期的な面談やアンケートで職員の声を拾い、制度改善につなげる前に、外部の目から見たアドバイスが必要な場合もあります。
早い段階で対処をすれば、大きなトラブルには発展しません。
厚労省の監査・指導の予告が届いたとき
厚労省の監査・指導の予告が届いたときも、早めの相談が必要です。監査前に労務や経理体制を整備しておくことで、指摘リスクを最小限に抑えられます。
何にせよ、早い段階での対処が最も大切です。
新規採用や法人化など組織変化のタイミング
事業拡大や法人成りの際は、契約・労務・税務など幅広い見直しが必要になるため、専門家への相談が効果的です。
無理に自分たちだけで対処しようとせず、プロに頼りましょう。
経営・労務の両面から支援する「介護事業者専門」の会計事務所という選択肢

介護事業に特化した経営支援・労務対策を行う会計事務所の一例として、クールジャパン会計事務所をご紹介します。
訪問介護・看護・デイサービス事業者の支援実績が豊富で、就業規則や助成金活用、帳簿整備など、実務に直結するサポートが受けられるのが特長です。
職員が安心して働ける環境づくりは、リスク対策の第一歩
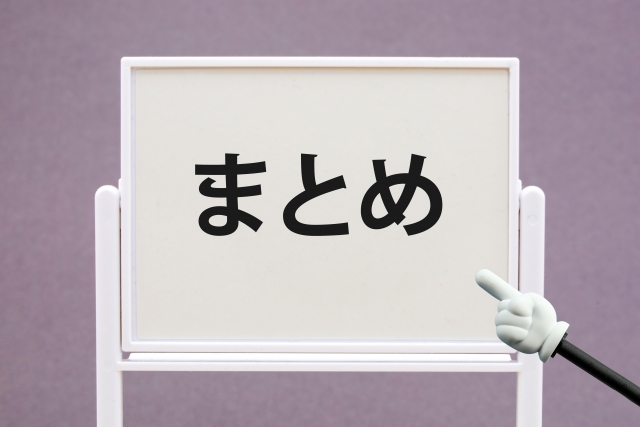
介護施設における労務トラブルは、職員の働きやすさと事業の安定性の両方に影響を与えます。
後手に回る前に専門家と連携し、トラブルの芽を早期に摘み取る体制を整えましょう。早めの対策をとることで、トラブルを最小限に抑えられます。